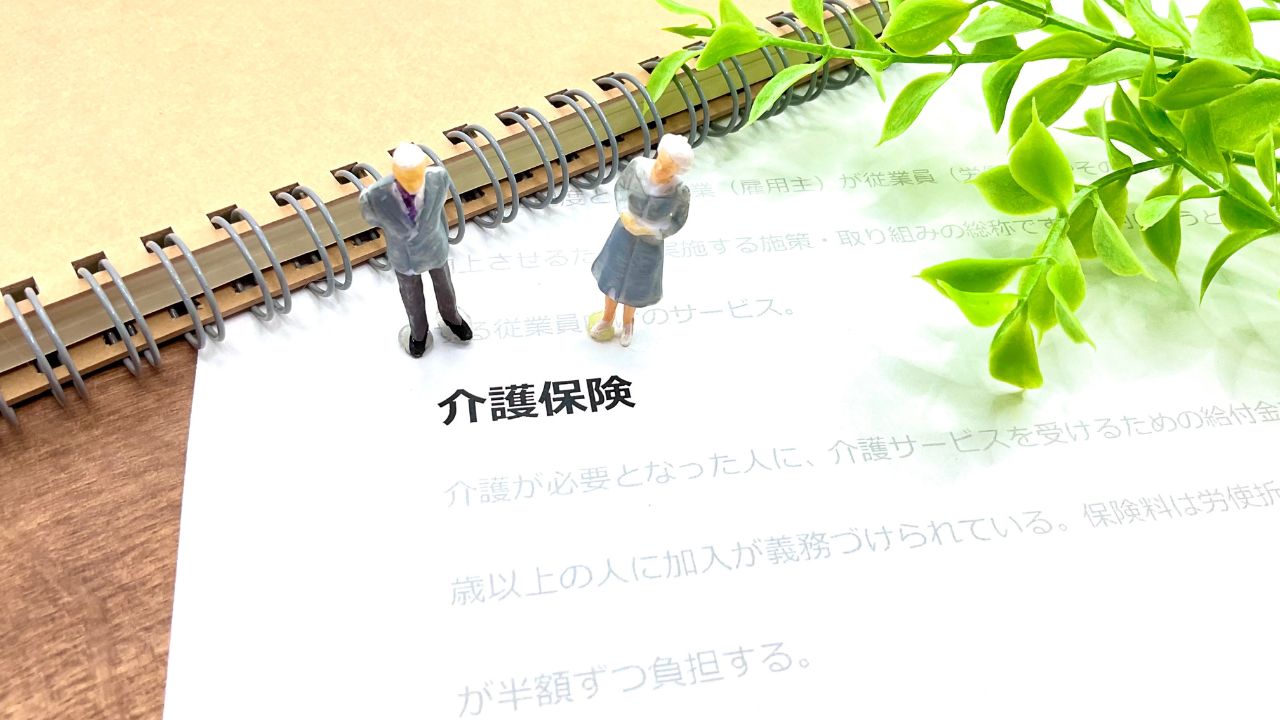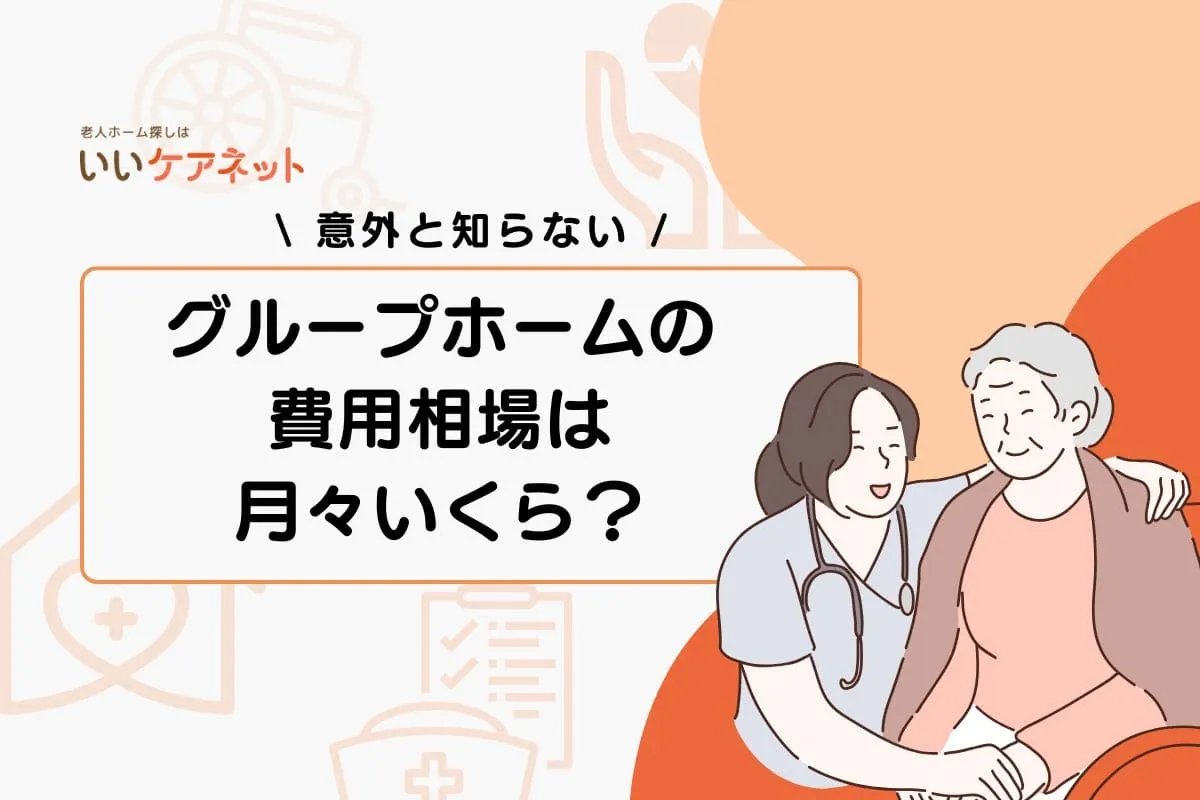介護が必要な状況に直面したとき、要介護2とはどのような状態なのかを理解することは非常に重要です。適切な知識を持って入れば、家族の介護をよりスムーズに進められるからです。
この記事では、要介護2の具体的な状態や要介護1や要介護3との違い、要介護2の方が利用できるサービスや入居可能な施設を解説します。
要介護2に関する正確な知識を得れば、本人の状況を適切に理解し、最適な介護サービスを選択できるようになります。記事を参考に、本人の生活の質を維持しながら、自身の負担も軽減する方法を知っていきましょう。
要介護2とは|要介護1と要介護3の違いも解説

要介護2とはどんな状態か、その特徴を詳しく見ていきましょう。
- 要介護2とはどんな状態か
- 要介護1との違い
- 要介護3との違い
それぞれ解説します。
要介護2とはどんな状態か
要介護2は、日常生活を送る上で部分的な介助が必要な状態を指します。食事や排せつなどの基本的な動作に加え、家事や買い物といった日常的な活動にも見守りや手助けが必要です。
具体的には、以下のような状態です。
- 立ち上がりや歩行の際に支えが必要
- 簡単な調理や掃除などの家事を行う際に介助が必要
- 認知機能の低下も見られ判断や記憶が必要な場面でサポートが必要
要介護2の方は、介護保険制度に基づいて「要介護認定等基準時間」が50分以上70分未満と定められています。これは、1日の中で介護に必要とされる時間の目安です。
要介護2の方々は、自立した生活を送るための支援を受けながら、できる限り自分の力で日常生活を送る意識が大切です。介護サービスを上手に活用して、生活の質を維持・向上させていきましょう。
関連記事:介護保険申請のタイミングはいつ?失敗しないための手続きガイド
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
参考:厚生労働省『要介護認定はどのように行われるか』
要介護1との違い
要介護1と要介護2の違いは、主に自立度の差にあります。要介護2では、身の回りのことを自分で行うのが難しくなります。
要介護1と要介護2の違いを以下の表にまとめました。
| 要介護1 | 要介護2 | |
| 日常生活(食事・トイレ・入浴) | 一部サポートが必要 | 多くの場面で部分的なサポートが必要 |
| 歩行 | 杖や手すりを使えば自分で歩行が可能 | 他者の支えが必要 |
| 認知機能 | 軽度の認知機能低下 | 顕著な理解力や判断力の低下 |
| 介護にかかる時間(1日あたり) | 32分以上50分未満 | 50分以上70分未満 |
要介護度が上がったからといって落胆せず、新たな状況に適した支援を受けながら、できる限り自立した生活を送るよう心がけましょう。
関連記事:要介護1の状態を徹底解説|利用できるサービスや要支援2・要介護2との違いまで
要介護3との違い
要介護3は、要介護2よりもさらに介助が必要な状態です。要介護3では、日常生活のほとんどを自分一人で行うことができません。
要介護3と要介護2の違いを以下の表にまとめました。
| 要介護3 | 要介護2 | |
| 日常生活(食事・トイレ・入浴) | 全面的な介助が必要 | 多くの場面で部分的なサポートが必要 |
| 歩行 | 自力での立ち上がりや歩行が困難 | 他者の支えが必要 |
| 認知機能 | 判断や決定に全面的な介助が必要 | 判断や決定に部分的な介助が必要 |
| 介護にかかる時間(1日あたり) | 70分以上90分未満 | 50分以上70分未満 |
要介護3になったとしても、適切なサポートを受けながら、その人らしい生活を送る姿勢が大切です。状態に合わせた介護サービスを積極的に活用しましょう。
関連記事:要介護3に見られる状況とは?状態や他の要介護との差
要介護2で受けられるサービス

要介護2で利用できるサービスは以下の6つがあります。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- 短期入所型サービス
- 施設入所サービス
- 地域密着型サービス
- 福祉用具・住宅改修
- その他のサービス
それぞれ解説します。
訪問型サービス
ご自宅で専門的なサービスを受けられる「訪問型サービス」には、以下の7種類があります。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護では、ホームヘルパーと呼ばれる介護の専門家がご自宅に来て、食事や入浴、排せつのお手伝いといった身体介護や、掃除や洗濯、調理といった生活援助をしてくれます。毎日の生活で少しお手伝いが必要になった時に、心強い味方になってくれるサービスです。
訪問看護では、医師の指示に基づいて、看護師や保健師がご自宅を訪問し、健康管理や医療処置のサポートをしてくれます。病状の観察や点滴、床ずれの処置など、医療的なケアが必要な時に安心です。
関連記事:訪問看護を利用するには?相談先や利用の流れについて
通所型サービス
施設に通ってサービスを受けられる「通所型サービス」には、主に以下の6種類があります。
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅サービス
通所介護(デイサービス)は、日帰りで施設に通い、入浴や食事の提供、レクリエーションや機能訓練などを受けられるサービスです。他の利用者の方との交流を通して、社会とのつながりを維持するのに役立ちます。
通所リハビリテーション(デイケア)は、医療機関や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士などによる専門的なリハビリテーションを受けられるサービスです。要介護2の方で、身体機能の回復や維持を目的とする場合に適しています。
関連記事:デイサービスは送迎OK!費用や利用条件など気になるポイントを解説
関連記事:デイサービスは健康な人も利用可能?費用やデイケアの違いも解説
短期入所型サービス
一時的に宿泊してサービスを受けられる「短期入所型サービス」は、主に以下の2種類です。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)は、短期間施設に宿泊し、入浴や排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けられるサービスです。ご家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合や、介護される方の気分転換を目的として利用できます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、医療的なケアが必要な要介護2の方向けに、介護老人保健施設などに短期間宿泊し、看護や機能訓練などを受けられるサービスです。
これらのサービスは、最長30日まで利用可能なので、状況に合わせて利用期間を調整できます。ご家族の都合や介護される方の状態に合わせて、上手に活用しましょう。
施設入所サービス
施設に入所して24時間体制のケアを受けられる「施設入所サービス」は、主に以下の6種類です。
| 施設の種類 | 施設の特徴 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指し、介護・看護・リハビリを提供。原則3〜6か月で退所が必要です |
| ケアハウス(介護型) | 自立が難しい高齢者向け。少ない費用で介護や生活援助を受けられます |
| 介護医療院 | 医療と介護の両方を提供。生活援助にも力を入れています |
| 有料老人ホーム | 24時間介護サービスを受けられる「介護型」生活援助を中心とした「住宅型」など多様な施設があります |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | バリアフリー対応で「安否確認」や「生活相談」などのサービスを提供しています |
| グループホーム | 認知症の方を対象。少人数での共同生活を行います |
有料老人ホーム、サ高住、グループホームは民間施設で、これら以外は公的施設です。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。介護保険や介護サービスの情報は「いいケアジャーナル」で随時更新中!
関連記事:サービス付き高齢者向け住宅とは|メリット・デメリットから他施設との違いまで解説
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を支える「地域密着型サービス」には、以下の4種類があります。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の要介護2の方向けに、少人数で共同生活を送る場を提供するサービスです。家庭的な雰囲気の中で、日常生活の支援や機能訓練を受けられます。
小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心として、必要に応じて「訪問」や「宿泊」を組み合わせたサービスを提供します。住み慣れた地域で、柔軟なケアを受けたい方に適しています。
関連記事:小規模多機能型居宅介護でずっと泊まりは可能?30日ルールやメリット・デメリットもわかりやすく解説!
地域密着型サービスは、地域とのつながりを大切にしながら、利用者の方の生活を支えるサービスです。それぞれのサービスの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったサービスを選択しましょう。
福祉用具・住宅改修
生活をより快適にするための「福祉用具・住宅改修」には、介護保険が適用されるものがあります。
以下は要介護2の方が利用できるサービスです。
- ベッドや車椅子、歩行器などのレンタル
- 手すりの設置や段差解消など住宅改修
福祉用具や住宅改修を利用すれば、自宅での生活をより安全で快適なものにできます。介護保険の適用範囲や手続きについては、ケアマネジャーに相談してみましょう。
関連記事:「福祉用具」について
その他のサービス
施設に入居して利用できるサービスとして、「特定施設入居者生活介護」があります。
特定施設入居者生活介護は、介護付有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している要介護2の方が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けられるサービスです。
有料老人ホームにはさまざまな種類があり、提供されるサービス内容や費用も異なります。ご自身の希望や状況に合った施設を選ぶ意識が大切です。
特定施設入居者生活介護を利用すれば、施設で安心して生活を送りやすくなります。施設選びの際は、見学や体験入居などを活用し、ご自身に合った施設を見つけるようにしましょう。
関連ページ:失敗しない!初めての老人ホーム選びの法則
要介護2でもらえるお金「区分支給限度額」

区分支給限度基準額とは、介護保険制度が定める介護サービスの月々の利用上限額を示すものです。
介護が必要な方の状態(要支援・要介護)に応じて7段階に分かれており、各区分で利用できる金額が異なります。
以下は区分支給限度基準額の一覧です。
| 区分 | 介護サービス利用の上限額(月額) |
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
参考:厚生労働省『サービス利用者の費用負担等』
※1単位当たり10円として計算した場合
※自己負担1割の場合
要介護2の方の上限額は、19万7,050円です。この上限額の範囲内であれば、個々の状況や必要性に応じてサービスを組み合わせることができます。
実際の支払額は利用者の所得に応じて異なります。一般的な所得の方は1割負担となり、月額上限までサービスを利用した場合の自己負担額は1万9,705円です。
所得が高い場合は2割(年金収入280万円以上340万円未満)または3割(年金収入340万円以上)となり、その場合は2割負担の方はおよそ3万9,410円、3割負担の方は約5万9,115円の支払いとなります。
要介護2のケアプラン例と料金の目安

先ほど解説した区分支給限度基準額をもとに、要介護2における具体的なケアプラン例と料金の目安を見ていきましょう。
以下2パターンのケースを紹介します。
- 自宅に住む場合
- 施設入所の場合
なお、ケアプランはケアマネジャーと相談しながら作成するのが一般的です。利用者や家族の要望を踏まえて作成されるため、事前に希望するサービス内容について考えておくと良いでしょう。
自宅に住む場合
以下は、要介護2の上限額19万7,050円の範囲内で利用可能なケアプラン例です。
| 利用するサービス | 利用回数 | 料金/回・日 |
| 訪問介護 | 月3回 | 3,370円 |
| 訪問入浴介護 | 月4回 | 14,250円 |
| 訪問看護 | 月2回 | 5,150円 |
| 訪問リハビリテーション | 月4回 | 3,340円 |
| 短期入所生活介護 | 2日間 | 8,620円 |
| 通所リハビリテーション | – | 75,030円(月額) |
| 福祉用具貸与 | – | 13,770円(月額) |
| 合計の料金 | 196,810円 | |
| 自己負担額(1割負担の場合) | 19,681円 | |
※参考:厚生労働省『介護サービス概算料金の試算』
在宅で介護を受ける場合、看護・介護の専門家が定期的に自宅を訪問してケアを行います。また、介護施設に短期宿泊するサービスとの組み合わせも可能です。
ベットや車椅子といった福祉用具のレンタルも利用して、安全な生活環境を整える取り組みもできます。
施設入所の場合
要介護2では、有料老人ホームや養護老人ホームを含むさまざまな種類の介護施設への入所を選択できます。ただし、施設での入所費用は区分支給限度基準額の対象外となるため、別途費用が必要です。
区分支給限度基準額の対象となるサービスであれば、施設生活をしながら追加で利用できます。以下は、施設入所を想定したケアプラン例です。
| 利用するサービス | 利用回数 | 料金/回 |
| 訪問看護 | 月4回 | 5,150円 |
| 通所リハビリテーション | – | 75,030円(月額) |
| 福祉用具貸与 | – | 7,260円(定額) |
| 合計の料金 | 10万9,400円 | |
| 自己負担額(1割負担の場合) | 1万940円 | |
※参考:厚生労働省『介護サービス概算料金の試算』
施設での生活は24時間体制の支援環境が整っています。しかし、必要に応じて訪問看護や福祉用具の貸与といった追加のサービスを選択できるため、よりきめ細かなケアを受けられます。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。介護保険や介護サービスの情報は「いいケアジャーナル」で随時更新中!
要介護2で受けられるサービスやもらえる支給金を把握して介護の負担を減らそう【まとめ】

要介護2は、日常生活の多くの場面で部分的な介助が必要な状態を指します。
立ち上がりや歩行時に支えが必要で、家事や買い物などの日常活動にも見守りや手助けが求められます。認知機能の低下も見られ、判断力や理解力に一部支障が出始める段階です。
要介護2の方は、介護保険制度を活用してさまざまなサービスを利用できます。訪問介護や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などのサービスを組み合わせれば、在宅生活を続けることも可能です。また、グループホームや有料老人ホームなどの施設入居も選択肢となります。
適切な介護サービスを利用すれば、要介護2の方でも生活の質を維持し、できる限り自立した生活を送ることができます。ご本人の希望や家族の状況に合わせて、ケアマネジャーと相談しながら最適なケアプランを作成していきましょう。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
要介護2に関するよくある質問

要介護2に関して、皆さまからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご両親の介護についてお悩みの方々に、少しでもお役に立てれば幸いです。
- 要介護2で一人暮らしは可能ですか?
- 認知症でどの程度の症状が見られると要介護2になりますか?
- 要介護2でもらえるお金は月いくらですか?
- 特別養護老人ホームは利用できますか?
これらの項目について、詳しく見ていきましょう。
要介護2で一人暮らしは可能ですか?
要介護2の状態では、一般的には一人暮らしが難しいといわれていますが、適切な介護サービスを利用すれば、不可能ではありません。
要介護2になると、足腰が弱くなり、立ち上がりや歩行に支えが必要になります。日常生活や身の回りのことにも、手伝いや見守りが必要となってきます。
しかし、訪問介護などの介護保険サービスを上手に利用すれば、一人暮らしを続けられるケースもあるでしょう。ホームヘルパーに来てもらって、掃除や食事の準備を手伝ってもらう選択肢もあります。また、デイサービスを利用すれば、日中は施設で過ごし、夜は自宅で休むという生活スタイルも可能です。
福祉用具の利用も大切なポイントです。要介護2になると、杖や歩行器、手すりなどの福祉用具が介護保険でレンタルできるようになります。これらを上手に活用すれば、自宅での生活がより安全で快適になるでしょう。
一人暮らしを続けるかどうかは、ご本人の希望や家族の状況、住んでいる地域の介護サービスの充実度などによって変わってきます。ケアマネジャーと相談しながら、最適な生活環境を整えていきましょう。
関連記事:高齢者一人暮らしの限界と対策|自治体の支援や施設入居を活用しよう
認知症でどの程度の症状が見られると要介護2になりますか?
要介護2は、日常生活を送る上で部分的な介助が必要な状態です。そのため、認知機能の低下において以下のような症状が見られる場合、要介護2と認定される可能性が高くなります。
- 薬の種類や服用時間の管理が困難
- お金の管理や支払いの判断が自力では難しい
- 基本的な身の回りの自己ケア(歯磨き・爪切りなど)が十分にできない
ただし、最終的な要介護度は、身体機能や生活環境などを含めた総合的な調査結果に基づいて決定されます。
関連記事:【認知症の正しい接し方】間違った接し方は症状を悪化させることも
要介護2でもらえるお金は月いくらですか?
要介護2では直接お金がもらえる制度はありませんが、介護保険制度により、介護サービスの利用料が軽減されます。
介護保険制度では、利用する介護サービスの自己負担が1〜3割で済みます。この割合は、所得などの条件によって変わってきます。たとえば、年金収入が低い方は1割負担、比較的高い方は2割または3割負担となります。
要介護2の方が利用できる介護サービスの上限額(区分支給限度基準額)は、月額約197,050円です。1割負担の場合、最大で月額19,705円の自己負担で、約197,050円分のサービスを利用できるということになります。
ただし、注意点もあります。この金額は地域によって異なる場合があるため、上限額の確認は必要です。ケアマネージャーや地域包括支援センターに確認をしましょう。また、区分支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分が全額自己負担になります。介護保険外のサービスを利用する場合も、全額自己負担です。
介護にかかる費用を抑えるためには、介護保険サービスを上手に組み合わせることが大切です。ケアマネジャーと相談しながら、ご家族の状況に合ったケアプランを作成しましょう。
特別養護老人ホームは利用できますか?
特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方が入所対象となりますが、要介護2の方でも特別な事情がある場合は入所できる可能性があります。
特養の入所条件は、一般的に以下のようになっています。
- 65歳以上で要介護3以上の方
- 40〜64歳で特定疾病があり要介護3以上の方
ただし、要介護1〜2の方でも、以下のような特別な事情がある場合は入所対象となる可能性があります。
- 認知症により日常生活に支障がある
- 知的障がいや精神障がいにより意思疎通が難しい
- 深刻な虐待を受けている疑いがある
- 家族の支援が得られず、地域の介護サービスも不十分
特養への入所順番は、各施設で毎月開催される「入所判定委員会」で決められます。介護度が重い方や緊急性が高い方が優先されやすい傾向にあります。
要介護2の方が特養に入所できない場合でも、他の選択肢があります。たとえば、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、要介護2の方でも入居できる施設があります。また、在宅での介護サービスを充実させることで、自宅での生活を続けることも可能です。
特養への入所を検討する際は、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
関連記事:特養に早く入れる方法【9選】施設選びのポイントから入居待ちの対処法まで解説
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。