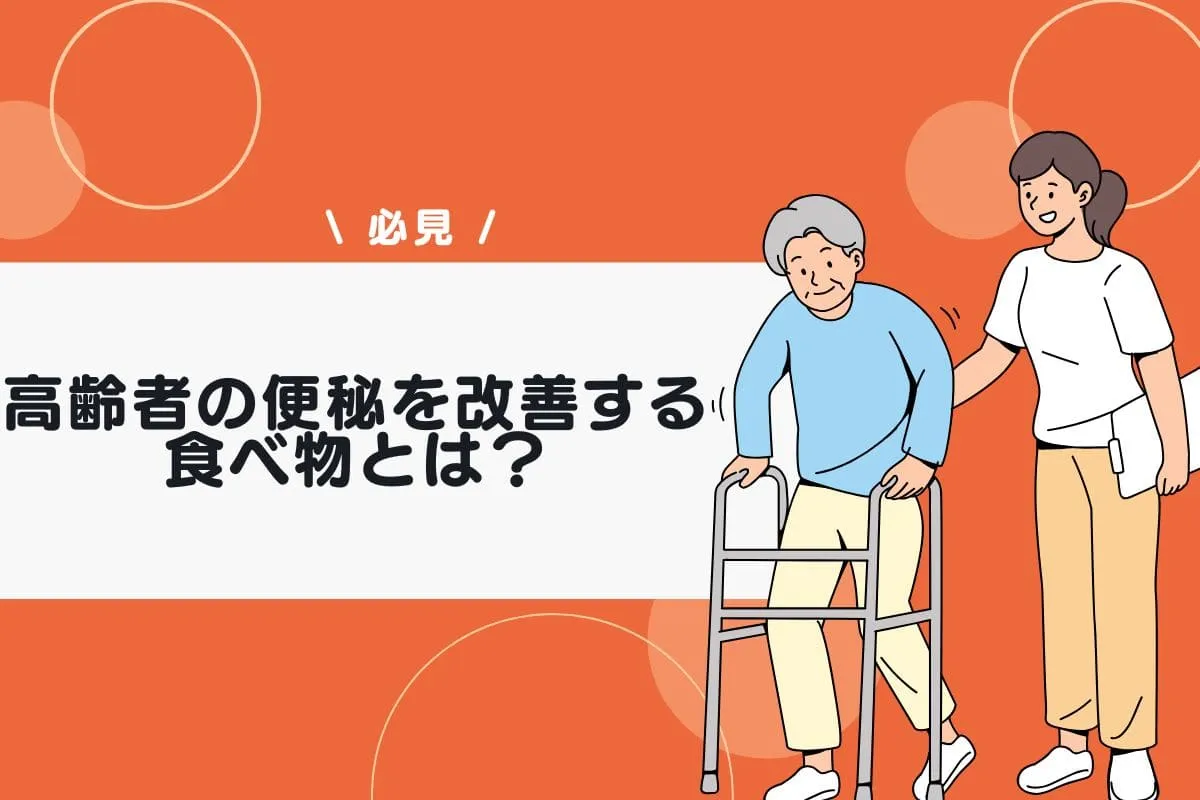地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために重要な介護サービスです。介護が必要になったとき、将来的にどのようなサービスを利用できるのかを知っておくことは、大切です。
この記事では、地域密着型サービスの基本から、9種類の具体的なサービス内容までを詳しく解説します。訪問サービスや通所サービス、施設サービス、複合型サービスの利用条件や特徴を知っておけば、介護の選択肢を広げられます。
地域密着型サービスを活用して介護負担を減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
地域密着型サービスとは

地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい生活を長く続けられるように支援する、心強いサービスです。
地域密着型サービスは2006年の介護保険法改正により創設され、市町村が指定した事業者が提供しています。住んでいる市町村がサービスを提供するため、地域の実情に合わせた介護を受けられるのが特徴です。
たとえば、世田谷区は東京の中でも高齢者が多い地域であり、訪問介護や通所介護を組み合わせたサービスに力を入れています。
地域密着型サービスを利用できる方は、以下条件を満たす方です。
- 要介護認定を受けた65歳以上
- 特定疾病により介護が必要と認められた40歳から64歳
- サービスを提供する事業所がある市区町村に住民票がある方
ただし、要支援の方は介護予防目的のサービスのみであれば利用できます。
地域密着型サービスを利用する場合には、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談すると、具体的なアドバイスがもらえるでしょう。
地域包括支援センターは、高齢者の生活を包括的にサポートする機関です。専門知識を持った職員が、利用者一人ひとりの状況に合わせた、丁寧な助言をしてくれるでしょう。
なお、将来的に施設への入居を視野に入れている場合は、老人ホーム探しの専門家に相談するのも一つの選択肢です。
「いいケアネット」では、経験豊富な相談員が親身にお話を聞き、ご希望にぴったりの施設をご紹介します。地域密着型サービスだけでなく、さまざまな選択肢の中から最適な施設を探しましょう。
地域密着型サービス9種類の一覧

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように設計された9種類のサービスです。訪問、通所、施設、複合型の4つの形態に分かれており、それぞれの特徴を詳しく解説します。
訪問サービス
訪問サービスは、自宅での生活を支援するために提供されるサービスです。夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の2種類があります。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護は、夜間の不安を解消し、安心して在宅生活を送れるようにするサービスです。夜間帯(午後10時から翌朝6時)を中心に、定期的な巡回訪問と緊急時の随時対応を組み合わせて提供します。
定期巡回では、排せつの介助や体位変換、就寝時の見守りなどを行います。また、利用者には緊急通報用の端末が渡され、体調不良時やトイレで困ったときなど、必要に応じて随時訪問を受けられます。
たとえば、夜中にベッドから転落して起き上がれなくなった場合でも、すぐに介護スタッフが駆けつけて対応してくれるため、一人暮らしの高齢者も安心して生活を送れます。サービスの選択時には、ご自身の生活リズムに合わせて、巡回の時間帯や頻度を相談しましょう。
関連記事:高齢者一人暮らしの限界と対策|自治体の支援や施設入居を活用しよう
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間365日、介護と看護の両方のサービスを必要なタイミングで受けられる在宅介護の形です。介護職員による定期的な訪問と、緊急時の随時対応に加えて、看護師による医療的なケアも一体的に提供されます。
1回の訪問は10~20分程度で、食事、排せつ、服薬確認などの短時間の身体介護を中心に行います。看護師との連携により、体調管理や医療処置も可能なため、医療ニーズの高い方でも在宅生活を継続できます。
たとえば、糖尿病の方の場合、介護職員が食事介助や服薬確認を行い、看護師が血糖値の測定や投薬管理を担当するといった、きめ細かなケアを受けられます。在宅での介護に不安がある場合は、このサービスの利用を検討しましょう。
通所サービス
通所サービスは、施設に通って日帰りで介護を受けるサービスです。地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護の2種類があります。
地域密着型通所介護
19名未満の少人数制で運営される小規模なデイサービスです。家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴などの日常生活の支援や、体操、リハビリなどの機能訓練を受けられます。
利用者一人ひとりに合わせたきめ細かなケアが特徴で、スタッフとの密な関係づくりが可能です。自宅から施設までの送迎サービスも提供されるため、移動の心配もありません。
要介護1から5の方が対象となりますので、ご自身の状態に合わせたサービス内容を相談しましょう。
関連記事:デイサービスは送迎OK!費用や利用条件など気になるポイントを解説
関連記事:【デイサービス】介護認定なしの人は料金いくら?減額のポイントなどを解説
認知症対応型通所介護
認知症の方に特化した12名以下の小規模デイサービスです。要支援・要介護どちらでも利用できます。認知症の症状や状態に応じた専門的なケアと、その方の得意なことを活かしたプログラムを提供します。
家庭的な環境で、少人数ならではの手厚い支援を受けられます。日常生活動作の維持・改善を目指した活動や、脳の活性化を促すレクリエーションなど、認知症状の進行を緩やかにする取り組みを行います。
たとえば、料理が得意な方には調理の準備を手伝っていただいたり、園芸が好きな方には植物の世話をしていただいたりと、その方の特性を活かした活動を取り入れています。認知症の方でも安心して過ごせる環境を整えましょう。
施設サービス
施設サービスは、入居して生活支援を受けるサービスです。以下の3種類に分けられます。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
30名未満の小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームで提供される介護サービスです。住み慣れた地域での生活を継続しながら、必要な介護サービスを受けられます。
常駐の介護スタッフによる24時間の見守りがあり、食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援から、機能訓練まで幅広いサービスを提供します。多くの施設では看護師も配置されているため、健康管理も充実しています。
たとえば、自室での生活を基本としながら、施設内でのレクリエーションや地域との交流活動にも参加できます。要介護1から5の方が対象となりますので、施設の特徴や料金体系をよく確認して選びましょう。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員29名以下の小規模な特別養護老人ホームです。常に介護が必要な方に対して、地域や家族とのつながりを大切にしながら、きめ細かな介護サービスを提供します。
原則として要介護3以上の方が対象ですが、特別な事情がある場合は要介護1・2の方も入所できます。食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援に加え、機能訓練や療養上の世話も行います。
たとえば、地域の行事に参加したり、ボランティアとの交流を持ったりすることで、入所者の生活に潤いを持たせています。地域との関係を保ちながら生活したい方は、このサービスの利用を検討しましょう。
認知症対応型共同生活介護
認知症の方が5~9名の小規模な単位で共同生活を送る、いわゆるグループホームです。家庭的な環境の中で、できる限り自立した生活を送れるよう支援します。
入居者は介護スタッフと一緒に、調理や掃除などの日常生活動作を行いながら、残存能力の維持・向上を図ります。共同生活を通じて、他の入居者との交流も自然に生まれます。
たとえば、野菜の下ごしらえや洗濯物たたみなど、それぞれができることを担当すると、生活への意欲を保てます。要支援2または要介護1から5で認知症と診断された方が対象となります。
関連記事:グループホームとは?入居条件や老人ホームとの違いを簡単に解説
複合型サービス
複合型サービスは、複数のサービスを組み合わせて提供するものです。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の2種類があります。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、「泊まり」と「訪問」を組み合わせた柔軟なサービスです。登録定員は29名以下で、顔なじみの職員による一貫したケアを受けられます。
利用者の状態や希望に応じて、デイサービス的な通いを基本としながら、必要に応じて自宅への訪問介護や施設での宿泊を組み合わせられます。馴染みの関係の中でサービスを受けられるため、環境の変化に敏感な方にも適しています。
たとえば、普段は日中に通所して過ごし、家族の用事があるときは宿泊を利用するなど、柔軟な対応が可能です。要支援・要介護の方で、さまざまなサービスを組み合わせて利用したい場合は、このサービスの利用を検討しましょう。
関連記事:小規模多機能型居宅介護でずっと泊まりは可能?費用や30日ルールの制限など解説
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護のサービスに、看護師による訪問看護を加えた総合的なサービスです。医療ニーズの高い要介護者でも、住み慣れた地域での生活を続けられます。
「通い」「泊まり」「訪問」のサービスに加えて、看護師による医療的ケアを提供します。介護と看護が一体となったサービスにより、医療処置が必要な方でも安心して在宅生活を送れるでしょう。
たとえば、点滴や喀痰吸引が必要な方でも、看護師による医療的ケアと介護スタッフによる生活支援を組み合わせて受けられます。医療的ケアが必要な要介護者の方は、このサービスが適しているでしょう。
地域密着型サービスの利用開始までの流れ

地域密着型サービスは、以下の5ステップでサービスを開始できます。
- 担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
- 利用したいサービスの事業所を検索し、空き状況を確認する
- 事業所と契約する
- ケアプランを作成する
- サービスを利用開始する
まず、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに相談し、利用したいサービスや、自身の希望を伝えます。次に、利用したい地域密着型サービスの事業所を探し、空き状況を確認しましょう。
その後、利用したいサービスを提供している事業所と契約を締結します。ケアプランを作成しますが、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、施設を利用する場合は、その事業所のケアマネジャーが担当となり、新たにケアプランを作成します。
ケアプランを作成したら、サービスの利用開始です。
利用開始後も定期的にケアプランは見直しされ、必要に応じてサービス内容が調整されます。
地域密着型サービスについてよくある質問と回答
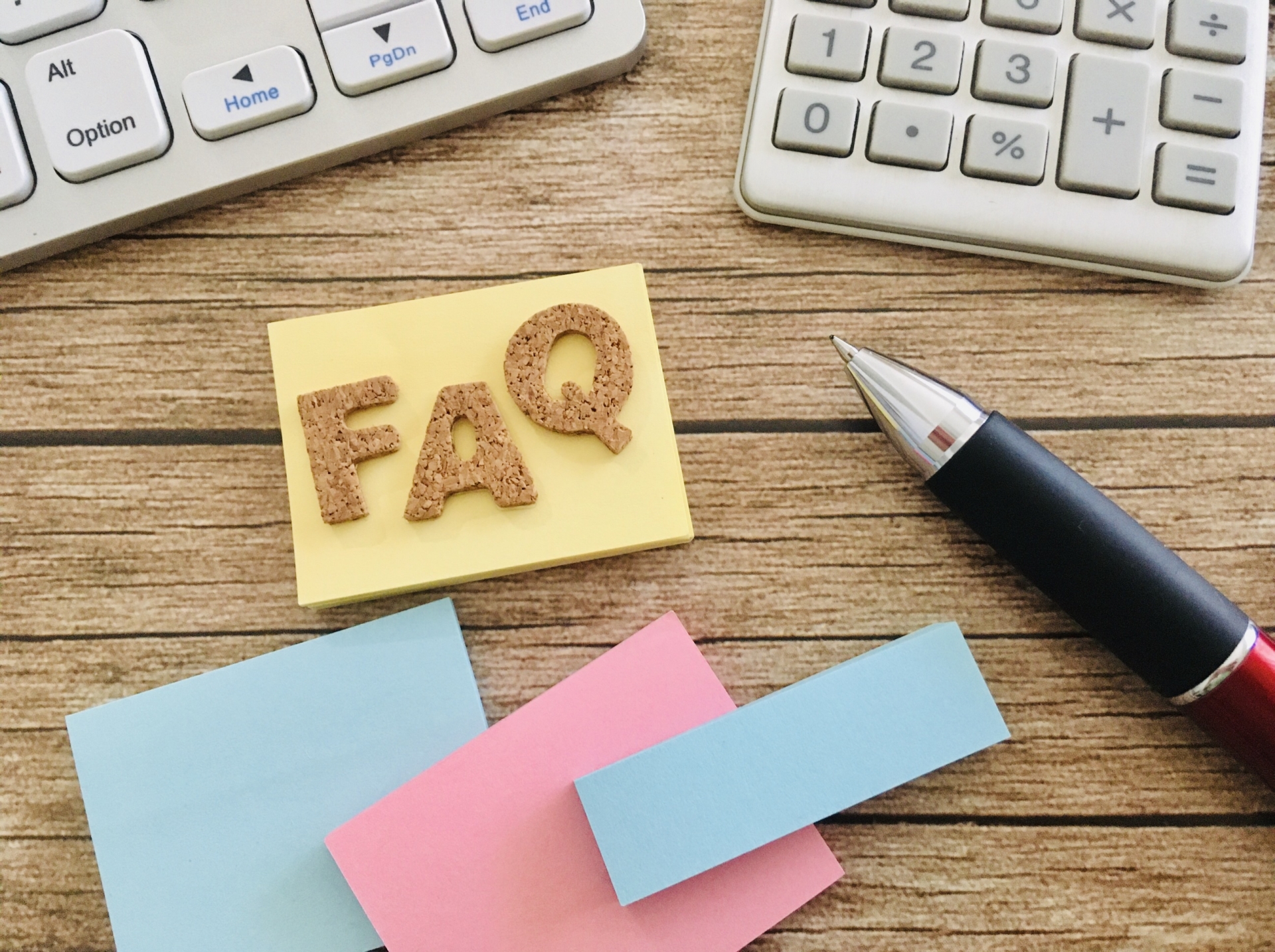
地域密着型サービスについて、よくある質問とその回答をまとめました。これらを参考に、サービスへの理解を深めましょう。
地域密着型サービスと居宅サービスの違いは?
最大の違いは、サービスを利用できる範囲と規模にあります。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域でより細やかな介護サービスを受けられる制度です。対象の市町村に住んでいる方のみがサービスを受けられます。
一方、居宅サービスは、都道府県が指定する事業者が提供しており、どの地域に住んでいても利用できます。
お住まいの地域で利用できるサービスを確認し、ご家族の状況に合ったものを選びましょう。
デイサービスと地域密着型デイサービスの違いは?
定員数と利用できる地域が大きく異なるのが、この2つのデイサービスの特徴です。
通常のデイサービスは定員が19名以上で、お住まいの地域に関係なく利用できます。それに対し、地域密着型デイサービスは定員18名以下の小規模な施設で、その地域に住む方のみが利用可能です。
たとえば、通常のデイサービスなら、隣の市町村の施設でも利用できますが、地域密着型は原則として市町村をまたいでの利用はできません。また、料金面では地域密着型のほうが若干高めに設定されているケースもあります
少人数でアットホームな雰囲気を好む方は、地域密着型を検討しましょう。
住所地特例者は地域密着型サービスを利用できる?
住所地特例とは、他の市区町村の介護保険施設などに入所し、施設所在地に住民票を移した場合でも、元の市区町村が保険者であり続ける制度です。
住民票を異動させていても、居住している市町村の地域密着型サービスを、例外的に利用できる場合があります。
住所地特例者が地域密着型サービスを例外的に利用するためには、事前に元の保険者である市町村と現在居住している市区町村に利用の申し出をします。その申し出を受けて、両市区町村が協議を行い、利用する許可を双方から得なければなりません。
詳細は、元の市区町村(保険者)と現在居住している市区町村の介護保険担当窓口にそれぞれ確認してみましょう。
地域密着型サービスを活用して豊かな生活を実現しよう

地域密着型サービスでは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、さまざまなサービスが提供されています。市町村が指定する事業者が提供しており、地域の特性に応じたきめ細やかなサービスを受けられるのが特徴です。
訪問、通所、施設、複合型の4つの形態に分かれた9種類のサービスがあり、それぞれの特徴を理解すると、介護の選択肢を広げられます。
介護が必要になったときのために、お住まいの地域でどのような地域密着型サービスが利用できるのか、地域包括支援センターに相談してみましょう。
一方で、地域密着型サービスについて調べている中で、将来的に老人ホームへの入居を視野に入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、いざ探すとなると、種類が豊富でどこが最適か判断に迷います。そのようなときは、老人ホーム探しの専門家「いいケアネット」にご相談ください。
経験豊富な相談員が親身にお話を伺い、ご希望にぴったりの施設をご紹介します。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。