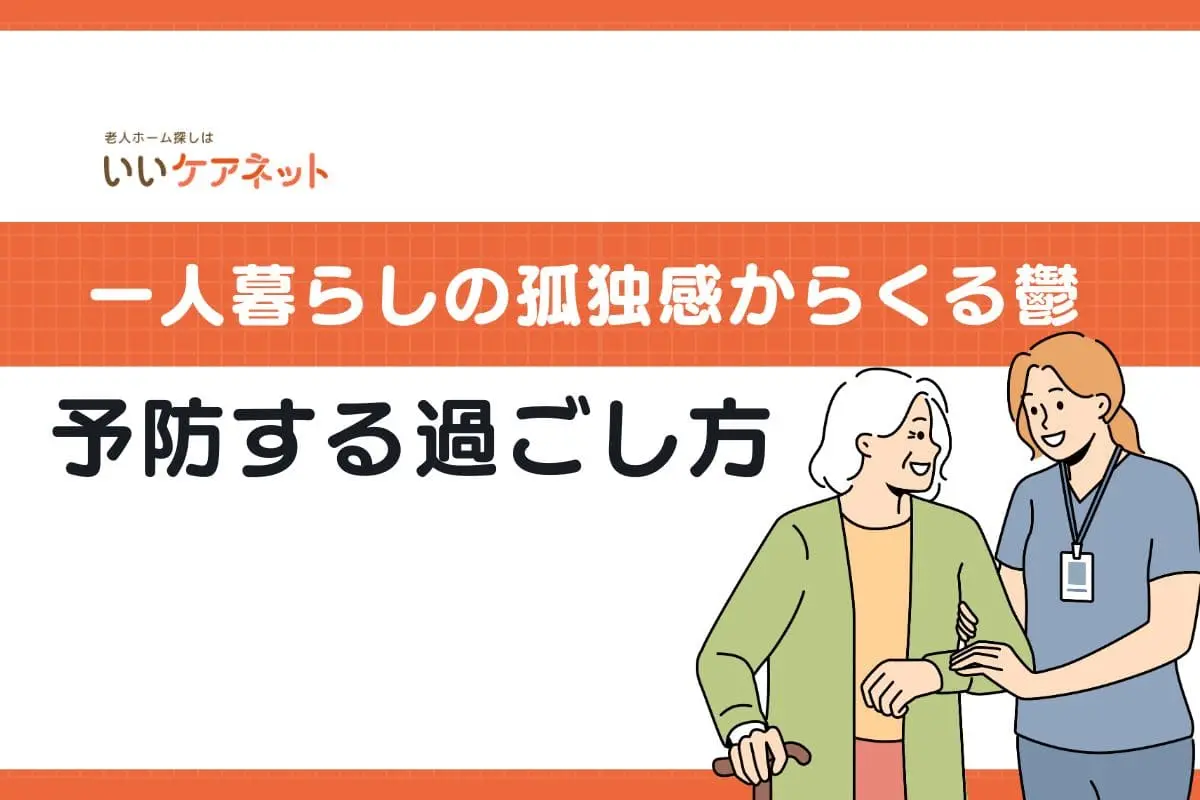在宅介護は、住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるメリットがありますが、家族にとっては負担が大きくなるデメリットも無視できません。
本記事では、在宅介護のメリットとデメリットを詳しく解説し、家族の負担を軽減するためのポイントや介護サービスの利用方法について紹介します。
仕事と介護の両立が難しいと感じている方や、急な体調不良への対応に不安を抱えている方に向け、おすすめの介護サービスを網羅的にまとめました。
在宅介護のデメリットを乗り越えるための具体的な解決策を知りたい方は、ぜひ読み進めてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
在宅介護のメリット

在宅介護のメリットは、主に以下の通りです。
- 本人にとって住み慣れた自宅での生活が続く
- 施設入居と比べて介護費用が節約できる
- 介護サービスの選択肢が広がる
1つずつ解説していきます。
本人にとって住み慣れた自宅での生活が続く
在宅介護を継続するメリットは、自宅での生活を続けられる点です。
ほとんどの方が、自宅を安らぎの場所だと感じており、馴染みのある自宅で暮らしたいと思うものです。
たとえば好きな時間に起床し、慣れ親しんだ家具に囲まれた環境で過ごすのは、精神的な健康に大きく寄与します。
自分のペースで生活できるため、介護を受ける側の自主性やプライバシーが尊重されやすいのも在宅介護のメリットです。
施設入居と比べて介護費用が節約できる
在宅介護を継続すると、介護費用が節約できるのもメリットです。
必要最低限の介護サービスを選択すれば、施設介護ほど高額な費用はかかりません。
介護のほとんどを家族が負担する分、介護にかかる費用が節約できます。
そもそも介護施設にかかる費用は、施設の種類にもよりますが公的施設で約7万〜20万円、民間施設で約13万〜30万円かかります。
居住費を抑えた分、食費や本人の趣味などにあてられるのが在宅介護のメリットです。
また、介護保険を利用すれば福祉用具を含めて自己負担を1〜3割に節約でき、経済的な負担が軽減します。
関連記事:障がい者が入れる老人ホームとは?費用・種類・選び方を紹介
介護サービスの選択肢が広がる
在宅介護にすると、介護サービスの選択肢が広がるのも魅力に感じられます。
介護サービスも多様化しており、利用者や家族のニーズにあわせたサポートが受けられます。
自宅で受けられたり通いで受けられたりする介護サービスの種類や概要をそれぞれ表でまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
自宅で受けられる介護サービス
自宅にいながら在宅介護として受けられる介護サービスの一例は以下の通りです。
| サービス名 | 内容 | 訪問する専門家 |
| 訪問入浴介護 | 介護スタッフが自宅を訪れて入浴の介護を行う | 介護スタッフ |
| 訪問看護 | 医療従事者が医師の指示のもとで医療ケアを行う | 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
| 訪問リハビリテーション | リハビリの専門職が医師の指示のもとでリハビリを行う | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
| 居宅療養管理指導 | 医療従事者が管理や指導を行う | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士 |
| 夜間対応型訪問介護 | 介護スタッフが定期的に訪問し介護や生活支援を行う | 介護スタッフ |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・看護スタッフが定期的に訪問し、介護・生活支援・医療ケアを行う | 介護スタッフ、看護スタッフ |
通いで受けられる介護サービス
介護施設に入居せず、通って受けられる介護サービスの一例は以下の通りです。
| サービス名 | 内容 |
| デイサービス(通所介護) | 日帰りで介護施設に通って介護サービスを受けられる |
| デイケア(通所リハビリテーション) | 日帰りで医療機関や介護施設に通って、医師の指示のもとでリハビリが受けられる |
| 地域密着型通所介護 | 施設と同じ市区町村に住む方のみが対象となるデイサービス |
| 認知症対応型通所介護 | 施設と同じ市区町村に住む、認知症の方のみが対象となるデイサービス |
一時的な宿泊や生活環境の整備ができる介護サービス
介護サービスは、一時的な宿泊ができたり生活環境の整備ができたりするため、組み合わせの自由度が高いのも魅力です。
| サービス名 | 内容 |
| ショートステイ(短期入所生活介護) | 数日~1週間程度の短期間にわたった介護施設の入所 |
| 医療型ショートステイ(短期入所療養介護) | 短期間にわたり介護施設に入所し、医学や介護的なケアが受けられる |
| 福祉用具のレンタルや購入 | 介護保険の適用価格で福祉用具をレンタル、または購入できる |
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
在宅介護のデメリット

在宅介護は、本人にとって住み慣れた環境であり、節約ができるなどのメリットがある一方で、デメリットもあります。
在宅介護におけるデメリットは以下の通りです。
- 家族の負担が大きくなる
- 仕事と介護の両立が難しい
- 急な体調不良や不測の事態に対応しにくい
1つずつ解説していきます。
家族の負担が大きくなる
在宅介護のデメリットは、必要とする介護が多い場合、家族の負担が大きくなる点です。
とくに在宅介護では、時間的・肉体的・精神的な負担が大きくなります。
介護により拘束される時間が長くなり、自分の時間が取れない精神的なストレスが増加していくからです。
また、在宅介護は24時間365日の対応が必要なため、休みがありません。
夜間に徘徊があったり、トイレ介助が必要だったりすると、介護する家族の睡眠にも影響します。
必要な介護が増えていくにつれ、いつ終わるかもわからない介護生活を続けることに不安を抱くようになります。
介護度が高い場合は、家族の負担が大きくなる点には注意が必要です。
仕事と介護の両立が難しい
在宅介護をする家庭の多くが、仕事と介護の両立が難しいと感じるのもデメリットです。
仕事中でも要介護者の緊急対応が原因で、仕事を休む事態になるケースもあります。
取引先との商談や会議など、休みを取りにくい日に対応せざるを得ない可能性もあり、ストレスに感じてしまうでしょう。
在宅介護に集中するために離職するケースも珍しくありません。
総務省が2022年に発表した調査結果によると、年間で約10万人の方が介護を理由に離職している結果が出ています。
在宅介護に集中するためにも、仕事と介護の両立ができるよう、職場からの理解が得られるよう交渉できるかも大切なポイントです。
急な体調不良や不測の事態に対応しにくい
在宅介護では、急な体調不良や不測の事態に直面した際、迅速かつ適切に対応するのが難しい点もデメリットとして挙げられます。
介護をしている家族が専門的な医療知識を持たない場合、状況を見極めて適切な行動を取るのは容易ではありません。
たとえば、介護を必要とする方が夜間に体調が悪くなった場合、夜間に診療してもらえる医療機関を探さなければいけません。
訪問介護を利用していたとしても、サービス提供の時間外に不測な事態が起こると、すべての対応を家族でおこなう必要があります。
在宅介護の場合、医療機器がそろっていないため、十分に対応できず症状を悪化する可能性もある点がデメリットです。
在宅介護で受けられるおすすめの介護サービス

ここからは、在宅介護で受けられる介護サービスについて解説していきます。
先述で紹介した介護サービスのうち、中でもおすすめの介護サービスは以下の通りです。
- 訪問介護
- デイサービス
- ショートステイ
- 福祉用具のレンタル・購入
それぞれ、より詳しく解説していくので、介護サービス選びの参考にしてください。
訪問介護
訪問介護は、介護が必要な方が住み慣れた自宅で生活を続けるために、介護スタッフが定期的に家庭を訪問し、日常生活のサポートを行うサービスです。
たとえば、食事の準備や掃除、洗濯などの家事援助から、入浴や排泄のような身体介助まで、幅広いサポートが提供されます。
また、訪問介護では、利用者の健康状態や生活スタイルに基づいて、個別のケアプランが作成されるため、より個人のニーズにあわせた支援が可能です。
介護スタッフが利用者の生活の一部となるため、孤立感を減らし、社会参加の機会を広げられるのもメリットです。
関連記事:訪問介護ってどんなサービスをしてくれるの?利用方法は?
デイサービス
デイサービスは、高齢者や介護が必要な方が日中の一定時間施設を利用し、必要なケアやリハビリを受けられるサービスです。
利用者は、自宅から施設までの送迎を含めたサービスを受けるため、家族にとっても日中の間だけ介護から解放される時間が得られます。
利用者にとって日常生活の一部としてリズムを作るとともに、外出の機会を提供し、社会的な交流を促進する役割も果たしています。
食事の提供や入浴支援、レクリエーション活動などのプログラムが用意されており、利用者の健康を維持・向上させるのが施設の目的です。
要介護度に応じて、個別のケアプランに基づいた支援が行われるため、利用者は自分のペースで無理なくサービスを受けられます。
デイサービスは在宅介護における負担を軽減し、介護の質を向上させるための有力な選択肢の1つです。
関連記事:【デイサービス】介護認定なしの人は料金いくら?減額のポイントなどを解説
ショートステイ
ショートステイは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間入居し、専門のスタッフからのケアを受けられるサービスです。
介護を担う家族が一時的に介護の負担から解放されるよう支援するのを目的としています。
また、利用者にとっても、異なる環境での生活を体験するのは気分転換となります。
ほかの利用者やスタッフとの交流を通じて、社会的な刺激を得られるのがメリットです。
さらに、ショートステイは、在宅介護の限界を超えた場合の一時的な避難所として機能するケースもあります。
たとえば家庭内で急に大きな変化があったり介護者自身が体調を崩したりした場合、利用者の生活を支援できるのです。
利用者が快適に過ごせるようにリバビリやレクリエーションを実施しているため、単なる「お泊まり」ではないのがショートステイの特徴です。
関連記事:小規模多機能型居宅介護でずっと泊まりは可能?費用や30日ルールの制限など解説
福祉用具のレンタル・購入
福祉用具のレンタルや購入は、介護を受ける側の身体的負担を軽減し、日常生活をより安全で快適にするためのサポートを提供しています。
たとえば以下のような福祉用具のレンタルや購入が提供されています。
- 車椅子
- 歩行器
- ベッド
- 入浴用具など
福祉用具をレンタルした場合、初期費用を抑えられるだけでなく、必要に応じて福祉用具を変えられるのがメリットです。
短期間で使用し、機能性を確かめてから購入を検討したい方におすすめです。
また、福祉用具のレンタルや購入は介護保険制度の利用により、費用を一部補助できる可能性があります。
経済的な負担を軽減させながら福祉用具を活用したい方は、ケアマネジャーや地域の福祉相談窓口に相談しましょう。
介護サービスを受ける流れ

在宅で介護しながら、介護サービスを利用したいと思った方は、以下の流れで利用していきましょう。
- 市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行う
- 訪問調査員が自宅を訪れ、身体や生活の状況を確認する
- 介護度が審査され、要介護度が決定される
- ケアマネージャーと面談し、ケアプランを作成する
- 訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護サービスを選択し、利用を開始する
- 利用開始後も定期的にケアプランを見直し、必要に応じてサービス内容を変更する
介護サービスを受ける流れは、申請からサービス利用、見直しまで一連のステップを踏む必要があるのです。
在宅介護がデメリットに感じる方は介護サービスの利用を検討しよう!【まとめ】

在宅介護は、本人にとって住み慣れた環境で生活が続き、施設入居よりも費用を節約できるなど、多くのメリットがあります。
一方で在宅介護を続けると、家族の負担が大きくなったり仕事と介護の両立が難しく、離職につながったりするのがデメリットです。
在宅介護の限界を超えると、共倒れになってしまう可能性も考えられます。
在宅介護を続けるメリットよりもデメリットが上回っていると感じたら、すぐに老人ホームの入居を検討しましょう。
希望する老人ホームによっては、すぐに入れない可能性もあるので、早めの行動が大切です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
在宅介護がデメリットに感じる方からのよくある質問

在宅介護が限界になると起こりうるリスクとは?
在宅介護を限界に感じると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 介護に疲れた健康問題
- 介護離職
- 家庭内のコミュニケーション不足など
在宅介護は、24時間365日の介護が必要になるケースがあるため、肉体だけでなく精神的にも疲れてしまうものです。
介護を理由に離職してしまうと、経済的な基盤が不安定になるだけでなく、介護サービスの利用も難しくなってしまいます。
在宅介護におけるリスクを防止・軽減させるためにも、早いうちに介護サービスを利用しながら周囲からのサポートを受けるのがおすすめです。
在宅介護の大変なことランキングは?
在宅介護の大変さについて、2021年「リゼクリニック」が調査した結果によると、以下のようなランキングになっています。
1位:相手とのコミュニケーション(全体:51.7%、男性3位:39.8%、女性1位:59.7%)
在宅介護では本人とのコミュニケーションが難しく、認知症の方との意思疎通が困難な点から上位にランクインしています。
2位:排泄の介助(全体:46.1%、男性1位:40.9%、女性3位:49.6%)
排泄の介助は、男性が最も大変と感じる部分です。
おむつの交換やトイレへの誘導など、適切なケアが必要です。
3位:精神面(全体:42.7%、男性6位:28.0%、女性2位:52.5%)
とくに女性にとって、精神的負担が大きい結果が出ています。
介護うつを防ぐため、介護サービスを利用しリフレッシュする時間を確保しましょう。
4位:時間面(全体:41.4%、男性4位:34.4%、女性4位:46.0%)
介護は生活の中心となり、家事や仕事との両立が難しい傾向にあります。
家族の協力を得て、自分の時間を作るのが重要です。
5位:食事の介助(全体:38.4%、男性1位:40.9%、女性5位:36.7%)
男性にとっては排泄の介助と同様に大変なタスクです。
誤嚥防止に配慮し、配食サービスの利用も検討しましょう。
6位:入浴の介助(全体:32.8%、男性4位:34.4%、女性6位:31.7%)
体力を必要とし、リスクも高いため、介護保険や福祉用具を活用して安全な入浴環境を整えましょう。
7位:経済面(全体:29.7%、男性7位:26.9%、女性6位:31.7%)
介護用品や住宅改修に費用がかかります。
介護保険や介護休業制度を活用し、経済的負担を軽減するのが大切です。
8位:徘徊(全体:16.8%、男性8位:16.1%、女性8位:17.3%)
認知症による徘徊は危険を伴います。
早めに専門家に相談し、対策を講じられるかが求められます。
9位:身だしなみのケア(全体:14.7%、男性9位:14.0%、女性9位:15.1%)
認知症になると身だしなみに無頓着になるケースがあります。
自発的にケアできる環境を整え、気持ちを前向きに保つ工夫が必要です。
10位:とくにない(全体:6.9%、男性10位:9.7%、女性10位:5.0%)
現時点で介護に問題を感じていない場合でも、将来のために対策を考えておくと安心です。
在宅介護を負担に感じたら何をすべきなの?
在宅介護をしていて負担に感じたら、まずは自分の負担を軽減するための具体的な対策を考えるのが大切です。
たとえば以下の手段が選択肢になります。
- 介護サービスの利用を検討する
- ケアマネジャーや民間の紹介窓口に相談する
- 家族や親しい友人に声をかけて協力体制を整える
在宅介護は長期間にわたるため、介護者本人が疲弊するのは避けなければいけません。
趣味に時間をあてたく休日の予定を空けていたとしても、介護を必要とする方が急に体調を崩した場合、早期の対応が求められます。
在宅介護が負担に感じる前に、介護サービスを利用しながら介護環境を整えていくのがおすすめです。
なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。
「できるだけ費用を抑えた介護サービスを利用したい」と考えている方も含め、気兼ねなくご相談ください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。