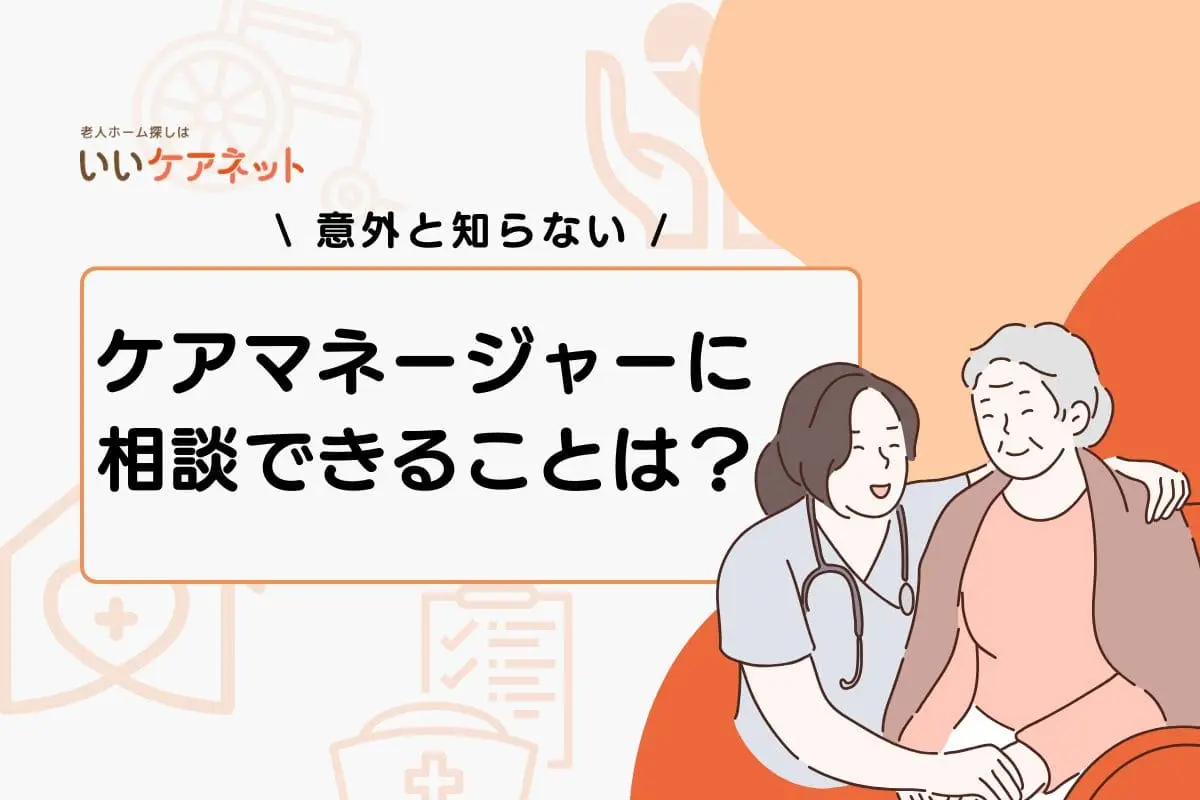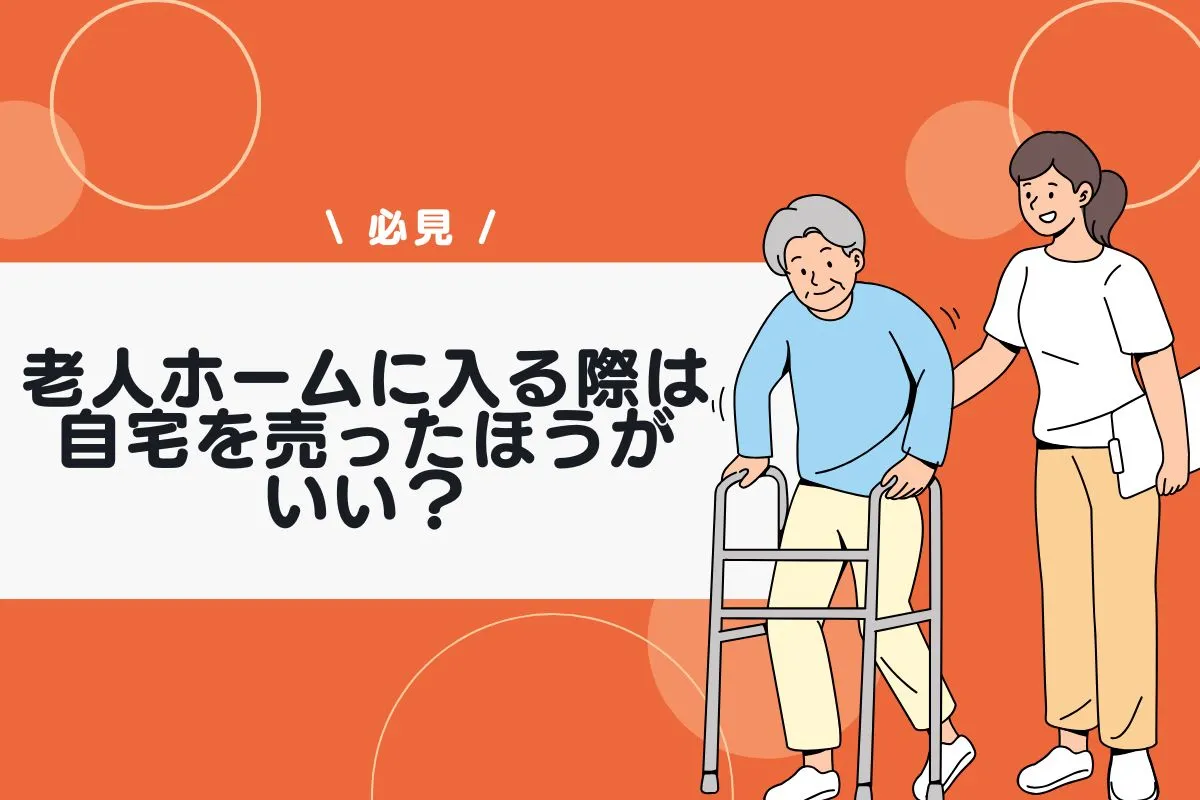認知症による徘徊行動は放置する危険性を把握されている方もいるでしょう。
一方で「共働きで忙しいから、できるなら探さないで済む方法を知りたい」と考えている方も少なくないでしょう。
本記事では、認知症による徘徊を探さないで済ませられる見込みの高い対応策を紹介します。
探さないで起こり得るリスクや行方不明になった場合の発見率、よくある発見場所なども解説しています。
家族の負担を軽減しながら認知症への支援を講じたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
認知症による徘徊を探さないで済ませるための対応策

認知症の家族が徘徊しているのを探さないで済ませるには、以下の対策を講じるのがおすすめです。
- 玄関にセンサーや補助鍵などを設置する
- GPSを杖や靴に入れておく
- 本人の生活習慣を見直す
- 徘徊につながる接し方をしない
- 福祉サービスを利用する
それぞれの徘徊対策を詳しく解説していきます。
玄関にセンサーや補助鍵などを設置する
認知症による徘徊を探さないで未然に防ぐための効果的な方法の1つとして、玄関にセンサーや補助鍵の設置がおすすめです。
センサーは、玄関を出入りする際の動きを感知し、家族にアラートを送信でき、徘徊行動をいち早く察知するので探さないで済む可能性を高めます。
とくに、夜間の無意識な外出を防ぐためには、音や光で知らせるタイプのセンサーがおすすめです。
また補助鍵は、認知症の方が無意識に玄関を開けてしまうのを防ぐための有効な手段です。
通常の鍵とは異なる操作が必要な補助鍵を取り付けると、認知症の方が自力で玄関を開けるのが難しくなります。
設置に際しては、居住する地域の防犯対策や法律に基づき適切な製品を選ぶようにしましょう。
GPSを杖や靴に入れておく
認知症の方が徘徊していても、すぐ発見できるよう対策しておくのに、徘徊対策グッズの1つであるGPSを杖や靴に組み込むのが効果的です。
GPSを入れ込むと、徘徊を未然に防ぐのが難しい場合でも、位置情報をリアルタイムで確認できるため、早期発見と対応に役立ちます。
杖を使って歩行している方は、日常的に持ち歩く可能性が高いため効果的です。
GPSデバイスの選択肢は豊富で、防水機能や長時間のバッテリー稼働など、使う方のライフスタイルに合わせた製品を選ぶのが重要です。
ただし、GPSデバイスの使用には、本人および家族の同意を得ておくのをおすすめします。プライバシーの配慮や心理的な負担を考慮しながら、適切に導入していきましょう。
関連記事:認知症の徘徊対策グッズ4選!選ぶときのポイントや対応策も解説
本人の生活習慣を見直す
認知症による徘徊を探さないで済ませるためにも、本人の生活習慣を見直すのが重要です。
徘徊の原因は多岐にわたりますが、その中でもとくに生活習慣の乱れが影響している可能性があります。
たとえば、日常のルーチンが崩れると不安感が増し、徘徊につながります。
規則正しい睡眠時間を確保し、日中は適度な運動を取り入れ、体を動かすと精神的なリラックス効果も期待できるためおすすめの方法です。
日常生活において本人がどのような行動をとるかを観察し、不安を感じる状況を把握するのも、徘徊防止には有効です。
本人が感じている不安やストレスに耳を傾け、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
徘徊につながる接し方をしない
認知症の方に対して、無意識のうちに徘徊を促してしまうような接し方を避けるのも重要な対応策です。
たとえば、以下のステップで認知症の方と接してみましょう。
- 本人の話をよく聞き、安心感を与える
- 優しく短い言葉で具体的に指示を与える
- 日々の生活で一貫性を保ち、日常のルーチンを整える
- 感情の起伏が激しい場合は穏やかに接する
- 認知症の方の視点に立ち、住環境を見直す
認知症の方が安心して過ごせる環境を作り出し、徘徊のリスクを低減が可能です。
家族や介護者が寄り添った接し方を心がけるのは、本人の安心感を高め、徘徊を未然に防ぐための大切なステップです。
認知症による徘徊を未然に防ぎ、探さないで済ませたい方はぜひ実施してみてください。
福祉サービスを利用する
福祉サービスを利用するのも、認知症による徘徊を防ぐための有効な手段の1つです。
福祉サービスの利用は、施設によっては家族の立場では探さないで済ませられる可能性もあります。
| 福祉サービス名 | 支援内容 | 期待できる効果 |
| デイサービス | 日中の活動を提供し、専門スタッフによるケアを行う | 日中の活動により認知機能を刺激し、精神的な安定を促す |
| ショートステイ | 短期間の宿泊サービスを提供し、介護者の負担を軽減させる | 介護者の休養やリフレッシュの時間を確保し、継続的なケアをサポートする |
| 認知症グループホーム | 認知症の方が少人数で共同生活を送り、日常生活をサポートする | 家庭的な環境での生活を提供し、安心感と社会的なつながりを維持する |
上記の通り、福祉サービスの利用は専門スタッフによるケアや介護者の負担軽減に寄与しますが「家族の一員」であるのを忘れてはいけません。
多様な福祉サービスの中から「どの福祉サービスを利用すれば良いのか」わからない方に向け、いいケアネットでは「入居無料相談」を受け付けています。
家族として認知症の方が徘徊するのを、どう支援すべきかお困りの方も含め、気兼ねなくご相談ください。
認知症による徘徊を探さない場合に起こり得るリスク

認知症の方が徘徊をしているにもかかわらず、積極的に探さない場合、以下のような深刻なリスクが生じる可能性があります。
| 徘徊リスクの種類 | 内容 |
| 事故や怪我のリスク | 交通量の多い道路に出たり、階段から転落したりする危険性がある |
| 健康リスク | 気候条件による体温調節の困難さが命にかかわる可能性がある |
| 精神的負担 | 迷子による混乱や不安が認知症の悪化を招く可能性がある |
| 社会的影響 | 家族や地域社会への負担が家族関係やコミュニティの絆を弱める可能性がある |
| 法的リスク | 他人の財産損壊や交通事故による法的責任を負う危険性がある |
上記のリスクを未然に防ぐためにも、適切な対策と地域社会との連携が不可欠です。
関連記事:認知症による徘徊を放置するとどうなる?理由や対策ポイントを解説!
そもそもなぜ認知症の方は徘徊をするのか
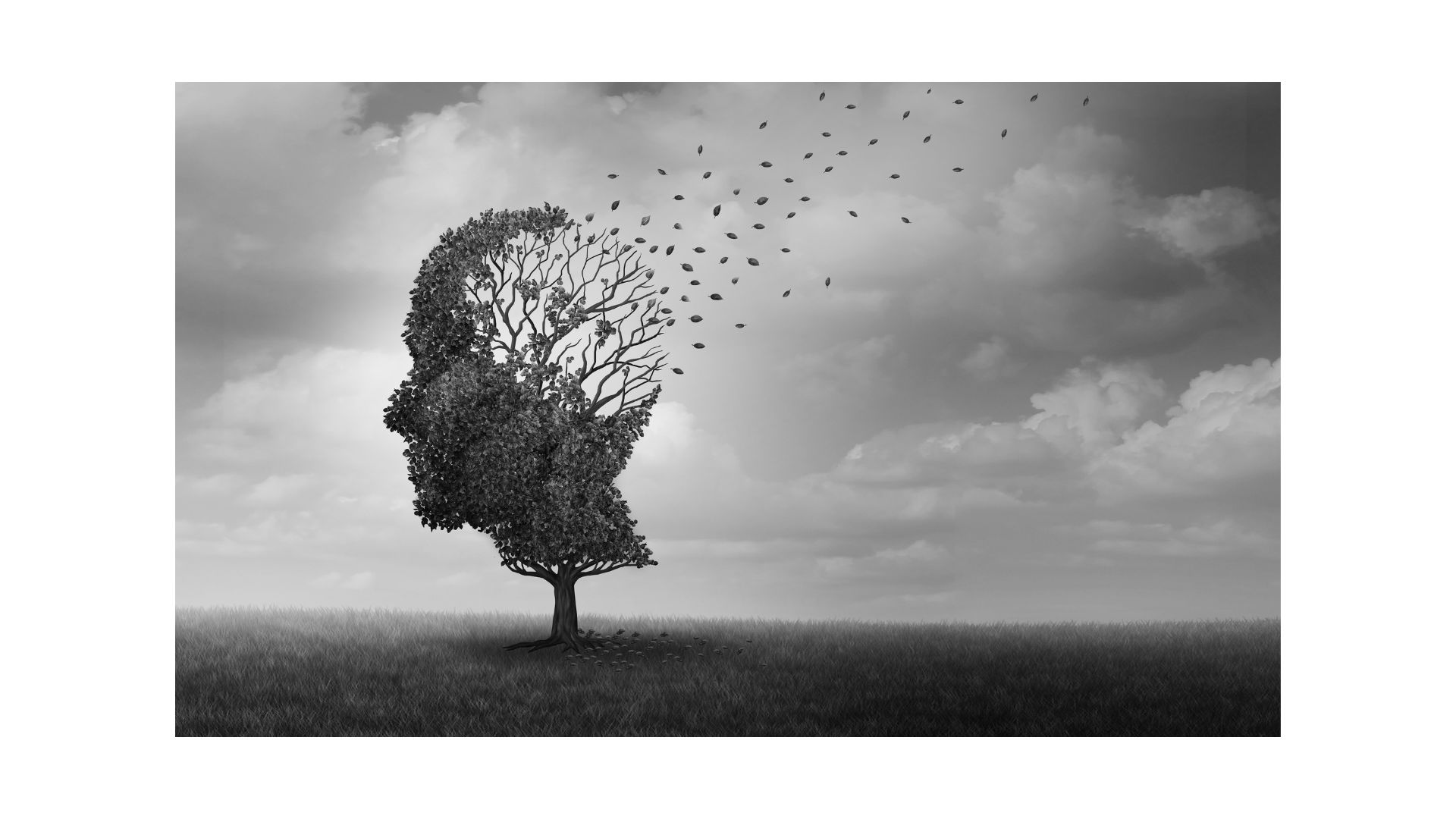
ここからは認知症の方が徘徊をしてしまう原因や症状、予防策について解説します。家族の徘徊を探さないで済ませるための対応策選びを決めるためにも、ぜひ参考にしてください。
徘徊の原因や症状
徘徊をしてしまう理由は、主に認知症による記憶障害や認識能力の低下です。自宅や周囲の環境がわからなくなり、目的地を見失ってしまう可能性があります。
また、認知症の進行に伴う不安感や混乱感が、歩き回る行動を引き起こします。
たとえば、過去の記憶に基づいてかつての仕事場へ向かおうとしたり、家に帰ろうとしたりする欲求が生じているのです。症状としては、以下の症例があるケースが大半です。
| 症状 | 内容 |
| サンセット症候群 | 夕方から夜間にかけて徘徊が増える症状 |
| 目的の曖昧さ | 歩き回る際に目的がはっきりせず、同じ場所を往復するケースが多い |
| 外出先での目的不明 | 外出先での行動に目的がなく、何をしたいかが明確でないケースが多い。 |
| 転倒や事故 | 徘徊中に転倒や交通事故に遭う可能性が高い |
上記のような症状を理解し、適切な対応策を講じるのが重要です。
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART2】~認知症の種類・症状について~
認知症の予防策
認知症の予防策は、政府広報オンラインには予防について「認知症にならないということではなく、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにする」と記載されています。
認知症による徘徊リスクを軽減させるためにも、以下の予防策を1つの参考にしてください。
| 予防策 | 具体的な活動内容 |
| 適度な運動 | ウォーキング、軽いエアロビクス |
| バランスの取れた食事 | 地中海食、和食、野菜、果物、魚 |
| 社会的活動 | サークルやボランティア活動 |
| 知的活動 | 読書、パズル、音楽 |
| ストレス管理 | リラクゼーション、十分な睡眠 |
| 健康診断 | 早期発見と対策、家族や医療機関との連携 |
社会的活動の中でも「認知症カフェ」も注目を集めています。
認知症の方や家族、介護者が集まって情報交換や交流を深められるだけでなく、専門家による相談やリラックスした環境での会話が可能です。
「施設入所は考えていない」という方は1つの選択肢にしてみてください。
関連記事:認知症カフェとは?目的・メリット・探し方について詳しく解説
認知症の方が徘徊する原因を把握して事前に対策しよう!【まとめ】

認知症の方の徘徊に対して「探さない」という選択肢を考えるには、事前の対策が必須です。
徘徊の原因を理解し環境を整えれば、探さない状況を効果的に作り出せます。
ドアに補助鍵を設置し、センサーで玄関や窓を監視、またGPSデバイスを活用すると、事前に安全を確保できます。
さらに、日常生活の改善と地域の福祉サービスを利用するのも、徘徊を未然に防ぎ、探さない状況の実現が可能です。
介護者は無理をせず、プロのサポートを活用しながら、安心して介護を続けることが大切です。
なお、大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
認知症の徘徊を探さないで良いか気になる方によくある質問
認知症の方が徘徊したときの発見率はどれくらい?
認知症の方が徘徊したとき「発見までにかかった時間」で発見率が異なり、時間別の発見率は以下の通りです。
- 3〜6時間:約25%
- 6〜9時間:約15%(※1)
警視庁の調査結果でも19,039人(前年比330人増加)の方が認知症、またはその疑いのある方が行方不明との結果を公表しています。
中でも家族からの届出があり、受理した当日の発見数は13,517人で、2〜3日になると4,471人との結果も出ています。
死亡確認数も、受理当日で118人、2〜3日で192人という結果も出ているため、社会問題化しているのも実情です(※2)。
見つかるまでにかかる時間が長くなるほど、リスクが増大する傾向があります。
とくに、夜間に徘徊した場合や天候が悪い場合などは、発見が遅れる可能性が高く、命にかかわる可能性もあります。
発見率を高めるためにも、近隣の住民や地域の商店、公共施設の職員にあらかじめ情報を共有し、協力体制を築いておくのが重要です。
※1 参考:桜美林大学老年学総合研究所「認知症高齢者の徘徊・行方不明・死亡に関する研究」
※2 参考:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和5年における行方不明者の状況」
認知症の方が徘徊したときのよくある発見場所はどこ?
認知症の方が徘徊したとき、よくある発見場所について愛知県の統計結果をもとに紹介すると、以下の通りです。
- 自宅敷地内:11.4%
- 自宅の付近よりは遠いが近所:12.3%
- 2より遠いが普段移動する範囲内:15.9%
- 3より遠い市町村内:22.0%
- 4より遠い県内:21.1%
- 県外:2.4%
- 不明:14.8%
上記の通り、認知症の方が徘徊した際の発見場所は、半数がよくある行動パターンや記憶に基づいた場所で発見されています。
自宅や周辺、玄関、庭、近隣の道端などで見つかるケースが大半です。過去に頻繁に訪れていた場所、たとえば以前の自宅や勤務先、行きつけの店なども候補に挙がります。
家族や介護者は、よくある発見場所を理解し、周辺を重点的に確認すると、徘徊した認知症の方を早期に発見する可能性が高まります。
事前に行きそうな場所を把握し、必要に応じて地域の見守りネットワークや警察に協力を依頼するのも有効です。
認知症で徘徊する方でも施設入所はできるの?
認知症の方が徘徊する場合でも、施設への入所は可能です。多くの介護施設では、認知症の症状に対応したケアを提供しています。
たとえば、認知症専門のユニットケアを提供する施設では、徘徊する方に対して安全な環境を整えているケースが大半です。
徘徊を防ぐためのセキュリティシステムや、スタッフによる24時間の見守り体制が含まれます。
また、入所前には、施設のスタッフと面談し、徘徊の頻度やパターンを共有し、最適なケアプランを策定するのがおすすめです。
施設によっては、徘徊により外出した際の迅速な対応策を持っている場合があります。
徘徊が認知症の方の安全に直接影響を与えるため、施設選びは慎重に行い、安心して過ごせる環境を提供するのが大切です。
なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための「入居無料相談」を受け付けています。
「認知症による徘徊行動がひどいけれど施設入所はできるのか心配」という方も気兼ねなくご相談ください。
関連記事:認知症でも入居可能な施設はある?【PART2】~ひどくても入れるのか~
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。