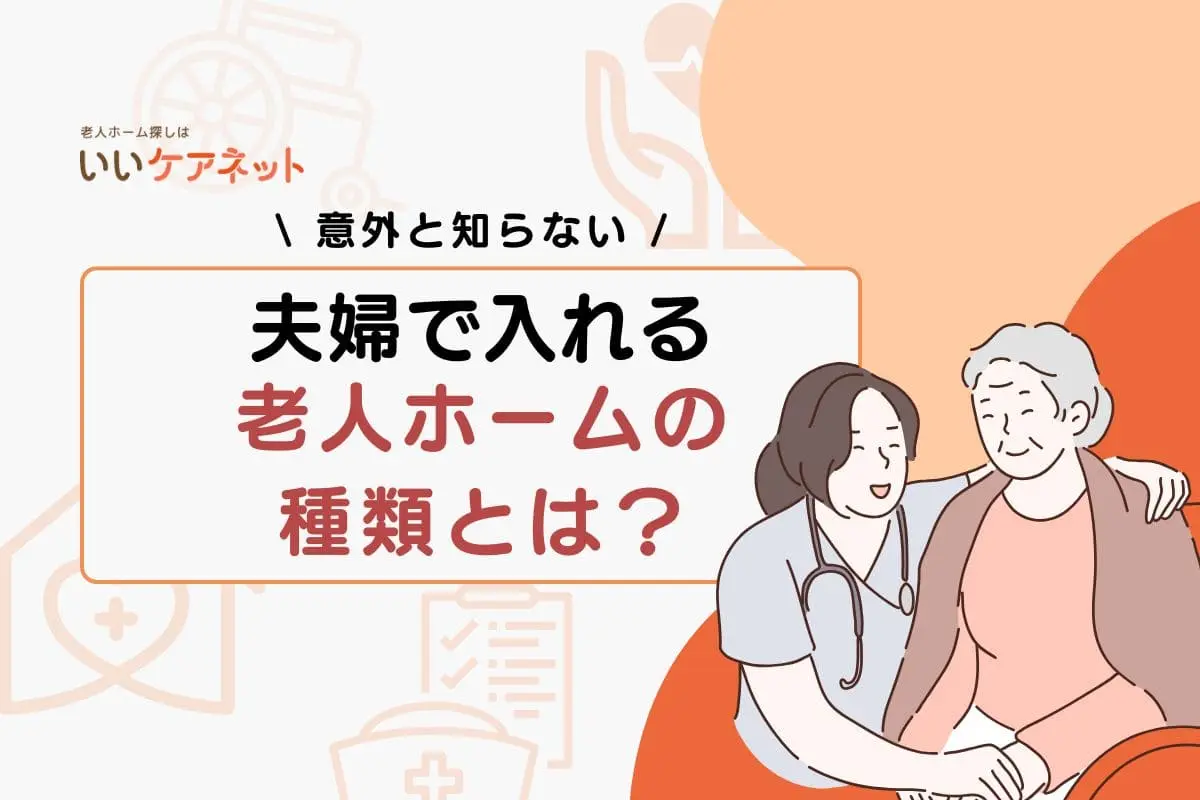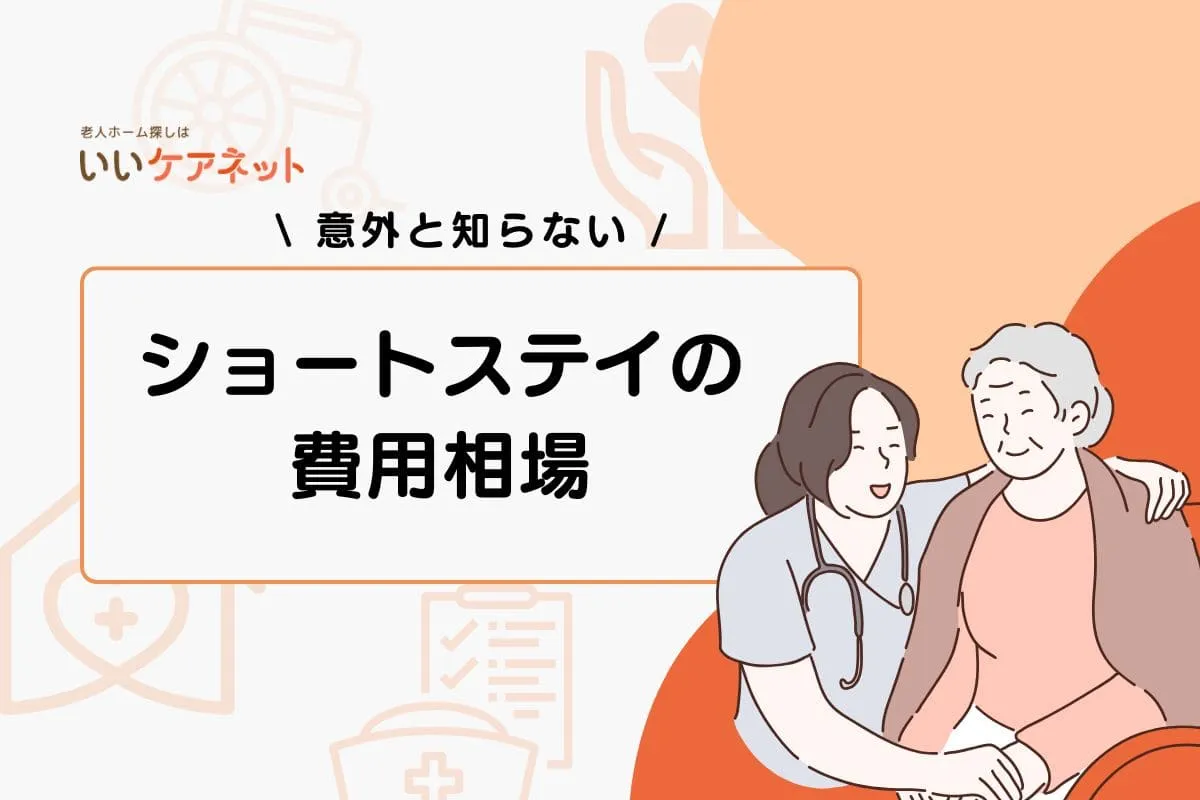「老人ホームでも訪問診療は受けられるか知りたい」「費用や手続きが複雑でよくわからない」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。施設によって利用条件が違うのか、詳しく知りたい方もいると思います。
多くの老人ホームでは訪問診療を利用できます。保険の仕組みや施設ごとの違いを正しく理解し、適切なサービス利用につなげましょう。
この記事では、老人ホームでの訪問診療の利用可否から、医療保険と介護保険による費用の仕組み、施設タイプ別の違い、そして利用開始までの手順を分かりやすく解説します。
老人ホームでの訪問診療について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧いただき、不安解消に役立ててください。
老人ホームで訪問診療は受けられるのか

老人ホームに入居していても、訪問診療を利用できる場合は多くあります。ただし、すべての施設が対応しているとは限らないので、事前に施設の利用条件を把握しておきましょう。
そもそも、訪問診療とは、医師が定期的かつ計画的に入居者の方を訪問し、診察や治療、薬の処方、健康相談などを行う医療サービスです。
通院が難しい方でもお住まいの施設で医療を受けられるため、ご本人やご家族の通院に関わる負担を軽くできるのが大きなメリットです。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です!親の介護にお悩みの方は、気になる記事をチェックしてみてください。
医療保険と介護保険による費用の違い

訪問診療の費用は主に医療保険が適用されます。しかし、サービス内容によっては、介護保険が関わることもあります。
その仕組みを以下3点から解説します。
- 医療保険でまかなわれる費用と自己負担
- 介護保険でまかなわれる費用と自己負担
- 月々の自己負担額の目安
各保険の対象や自己負担をあらかじめ知っておくと、安心してサービスを利用できます。負担軽減制度も合わせて確認していきましょう。
医療保険|在宅時医学総合管理料など
訪問診療では、主に医療保険が適用されます。費用項目には「在宅患者訪問診療料」や「在宅時医学総合管理料」、「施設入居時等医学総合管理料」などがあります。
医療保険に該当する医療行為は以下のとおりです。
- 在宅での診察・問診
- 血液検査・尿検査などの各種検査
- 点滴・注射などの医療処置
- 処方薬の調剤・服薬指導
自己負担割合は年齢や所得によって異なりますが、通常は医療費の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割を負担することになります。
介護保険|居宅療養管理指導など
介護保険を使った訪問診療は、治療ではなく指導や助言が中心です。
対象は、要介護または要支援と認定された方です。医師や薬剤師などが自宅を訪問し、健康管理や薬の説明などをおこないます。これを「居宅療養管理指導」(要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」)と呼びます。
主なサービスは以下のとおりです。
- 医師による健康や療養のアドバイス
- 薬剤師による薬の使い方の説明
- 栄養士による食事や栄養の助言
- 看護師による生活相談や助言
- 報告書の作成や管理
治療が必要な場合は医療保険が使われ、負担額は介護度や所得に応じて変わります。
月々の自己負担額の目安|医療保険と介護保険の合算
月々の自己負担額は、医療保険と介護保険それぞれの負担分を合わせて考えるのが基本です。たとえば、医療保険で月2回訪問診療と処方を受ける場合、1割負担で約7,000円、3割負担なら約20,000円が目安です。
一方、介護保険の「居宅療養管理指導」は、1割負担で月に約600円、3割で月に約1,800円が目安となります。医療費が高額になった際は、高額療養費制度を利用して負担を軽減できる可能性もあります。
施設の種類別による費用の違い

老人ホームの訪問診療は、施設の種類で利用方法や費用が異なります。主な6つの施設タイプ別にその違いを解説します。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- グループホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
各施設の特徴を把握し、ご自身の状況に合う施設を選ぶための参考にしてください。それぞれの違いを理解し、最適な施設を見つけましょう。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームでは、多くの場合、施設が提携している協力医療機関の医師が訪問診療を担当します。定期的な健康管理や診察が受けられ、緊急時の対応も比較的スムーズなのが特徴です。
訪問診療の費用は施設の料金体系によって異なり、月額利用料に一部が含まれることもあります。ただし、診察や治療、検査といった医療行為の多くは、別途自己負担となるのが一般的です。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの場合、訪問診療は基本的に外部の医療サービスを利用する形です。入居者やご家族が、施設からの紹介やご自身で探した訪問診療クリニックと個別に契約を結びます。
そのため訪問診療にかかる費用は別途個人の負担となり、利用した医療機関へ直接支払うのが一般的です。どの医療機関を選ぶかなど自由度は高いですが、契約手続きや費用管理はご自身で行う必要があります。
関連記事:住宅型有料老人ホームとは?主なサービス内容や必要な料金をわかりやすく解説!
グループホーム
グループホームには医師が常駐していないため、訪問診療は外部の医療機関を利用します。施設によっては連携している医療機関があり、そこの医師が担当することもあるでしょう。
訪問診療にかかる費用は、施設の利用料のほかに別途個人の負担となるのが一般的です。利用する医療機関やサービス内容によって費用は異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
関連記事:グループホームとは?入居条件や老人ホームとの違いを簡単に解説
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、基本的に賃貸住宅としての側面が強い施設です。そのため訪問診療の利用は、入居者自身が自由に医療機関を選んで契約する形になります。
費用についても、医療機関との個別契約に基づき別途個人の負担となるのが一般的です。どのような医療サービスが必要か、費用はどの程度かなどを事前に確認し、計画的に利用することをおすすめします。
関連記事:サービス付き高齢者向け住宅の問題点とは?失敗しない選び方も解説
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)には、法律に基づいて施設の医師(嘱託医)が配置されています。この医師が定期的かつ計画的に入居者の診察や健康管理、必要な処置などを行います。
これらの医療行為にかかる費用は、基本的に施設サービス費の中に含まれているのが特徴です。そのため、外部の医療機関による訪問診療を別途利用するケースは、比較的少ないといえます。
関連記事:特別養護老人ホームの費用は?自己負担額を軽減できる制度も解説
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰を目指すリハビリテーションを中心とした医療ケアを提供する施設です。医師が常勤しており、入所者の日々の健康管理や医療的な処置は施設内の医師が担当します。
そのため、外部の医療機関に訪問診療を依頼することは原則としてありません。常勤医による診察や必要な医療サービスの費用は、施設のサービス費に含まれているのが一般的です。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。無料で利用できるので、登録してどんな施設があるかチェックしてみてください。
関連記事:介護老人保健施設の費用が知りたい!内訳や費用の軽減方法も紹介
訪問診療を始める4ステップ

老人ホームで訪問診療を始める際の、一般的な手順について解説します。施設の種類や状況によって多少異なる場合もありますので、あくまで参考としてください。
- ケアマネジャーや入居施設の相談員に相談する
- 訪問診療を依頼する医療機関を決める
- 医師と診療方針や費用を確認する
- 納得がいったら契約して訪問診療をスタートする
これらの手順をあらかじめ理解しておくことで、スムーズに訪問診療の利用を開始できるでしょう。ご本人やご家族だけで判断せず、専門家とよく相談しながら進めてください。
ケアマネジャーや入居施設の相談員に相談する
まず、入居している老人ホームのケアマネジャーや相談員に、訪問診療の利用について相談しましょう。施設で訪問診療が利用可能か、またどのような医療機関の選択肢があるのかを確認します。
施設によっては、提携している協力医療機関がある場合や、特定の医療機関を指定されることもあります。希望する医療サービスの内容や頻度などを伝え、適切な情報を得るように心がけてください。
訪問診療を依頼する医療機関を決める
次に、相談した内容や得られた情報をもとに、訪問診療を依頼する医療機関を決めます。施設が連携している医療機関にするか、ご自身やご家族が希望する他の医療機関を探すのかを検討しましょう。
医療機関の専門分野や評判、施設からの距離なども比較検討するポイントです。最終的には、ご本人やご家族が納得でき、信頼関係を築けそうな医療機関を選ぶようにしてください。
医師と診療方針や費用を確認する
訪問診療を依頼する医療機関が決まったら、担当医師と面談の機会を持ちます。そこで、ご本人の健康状態や希望する医療内容を伝え、具体的な診療方針について話し合います。
月々の訪問回数や診療時間、緊急時の対応、そして費用の詳細(自己負担額や支払い方法など)をしっかり確認しましょう。疑問点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めるようにします。
納得がいったら契約して訪問診療をスタートする
診療方針や費用について十分に説明を受け、納得できたら医療機関と正式に契約を結びます。契約内容(訪問スケジュール、提供サービス、費用など)を改めて確認し、不明な点がないようにしましょう。
契約後は、取り決めたスケジュールに従って訪問診療が開始されます。定期的な医師の訪問により、施設にいながら必要な医療サービスを受けることが可能です。
老人ホームでも訪問診療を上手に活用しよう【まとめ】

老人ホームでの生活においても、訪問診療は心身の健康を支える選択肢の1つです。この記事では、訪問診療の基本的な仕組みから、医療保険・介護保険における費用の違い、施設タイプごとの特徴、そして利用開始までの手順を解説してきました。
訪問診療を利用できるかどうか、またどのようなサービスが受けられるかは、入居する施設の種類やご本人の健康状態によって異なります。そのため、事前に施設やケアマネジャー、医療機関へしっかりと確認し、情報を集めるようにしましょう。
「いいケアジャーナル」では、介護保険法や介護施設の特徴などコラムを掲載しています。介護について知りたいことがある方は、他の記事も読んでみてください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。