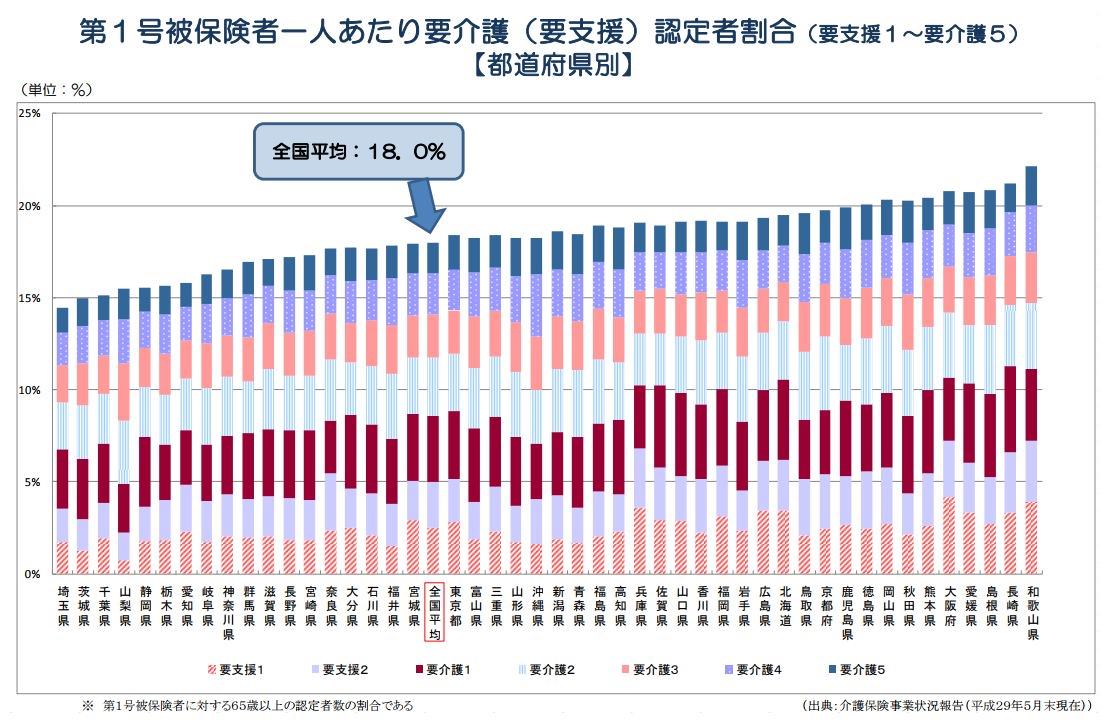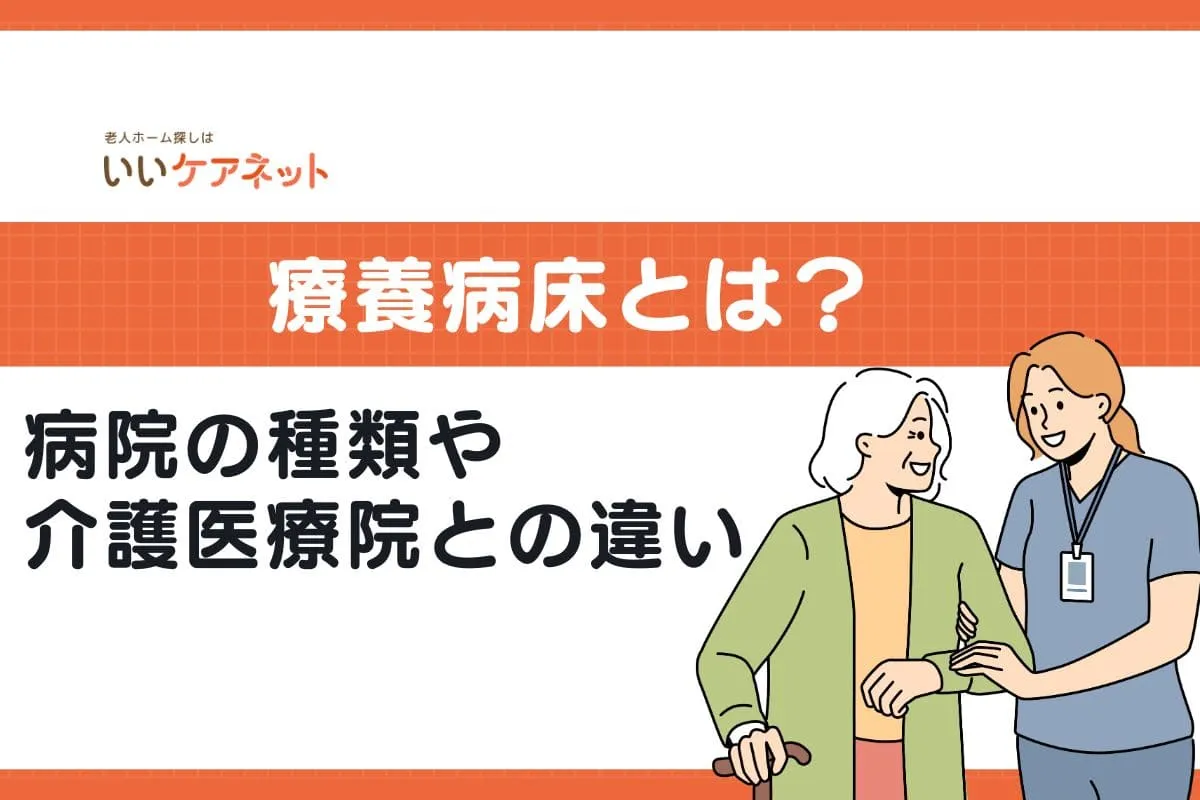ペースメーカーは、心臓の働きを助けることで高齢者の生活の質を維持する医療機器です。装着後も多くの老人は以前と変わらない日常生活を送ることが可能ですが、安全を確保するためには本人と周囲がいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
この記事では、ペースメーカーを装着した高齢者本人と、その家族や介護に携わる方が知っておくべき、日常生活や介護の場面での具体的な注意点を解説します。
そもそもペースメーカーとは?高齢者が装着する主な理由

ペースメーカーは心臓の脈が遅くなる「徐脈性不整脈」などに対し、電気刺激を送って正常な脈拍を維持する小さな医療機器です。高齢になると心臓の機能が低下し、脈が遅くなることでめまいや息切れ、失神などの症状が現れやすくなります。これらの症状を改善し、心不全の悪化や突然死のリスクを減らす目的で装着されます。
ペースメーカーが直接的に寿命を延ばすわけではありませんが、症状を緩和し、安定した心臓の働きを保つことで、QOL(生活の質)を維持するために重要な役割を果たします。
【シーン別】高齢者がペースメーカー装着後に日常生活で気をつけること

ペースメーカーを装着した後も、基本的には以前と変わらない生活を送ることが可能です。しかし、特定の機器が発する電磁波や一部の医療行為、激しい運動など、いくつかの場面では注意が求められます。
ここでは、日常生活の様々なシーンにおいて、高齢者が安全に過ごすために気をつけるべき具体的なポイントを解説します。これらの注意点を正しく理解し、過度に恐れることなく安心して生活を送りましょう。
スマートフォンやIH調理器など電磁波を出す機器に近づきすぎない
日常生活で使用する多くの家電製品は、通常の使い方であれば問題ありません。しかし、スマートフォンや携帯電話は、ペースメーカーの植え込み部分から15cm以上離して使用・携行する必要があります。通話は植え込み部位と反対側の耳で行い、胸ポケットに入れるのは避けてください。
また、IH調理器やIH炊飯器は強力な電磁波を発生させるため、使用中は機器に近づきすぎないよう注意が必要です。このほか、マッサージチェアや低周波治療器なども影響を及ぼす可能性があるため、使用前には医師に相談することが求められます。これらの機器以外でも、強い電磁波を発生させるものには注意が必要です。
空港の保安検査では金属探知機を通過しない
ペースメーカーは金属を含むため、空港の保安検査で用いられる金属探知機に反応します。また、金属探知機が発する電磁波が、ペースメーカーの作動に影響を与える可能性もゼロではありません。
そのため、保安検査を受ける際は、金属探知機のゲートを通過せず、係員にペースメーカー手帳を提示してください。手帳を見せることで、ペースメーカーを装着していることが伝わり、ゲートを通らずに手によるボディチェック(触手検査)など、別の方法で検査を受けられます。
これは国内線・国際線問わず共通の対応であり、事前に知っておくことで、慌てずにスムーズな検査を受けることができ、安心して生活の範囲を広げられます。
MRI検査を受ける前には必ず医師へ申告する
MRI検査は強力な磁場を用いるため、従来のペースメーカーを装着している場合は検査を受けられません。近年では、特定の条件下でMRI検査が可能な「MRI対応ペースメーカー」も普及していますが、その場合でも検査前には必ず医師、看護師、検査技師にペースメーカーを装着していることを伝えなければなりません。
申告する際は、使用している機種や設定を確認してもらうために、ペースメーカー手帳を提示することが不可欠です。自己判断で申告を怠ると、機器の誤作動や故障を引き起こす危険があります。
他の医療機関を受診する際も、ペースメーカーの存在を必ず伝える習慣をつけましょう。
ウォーキングなどの適度な運動は可能だが激しいスポーツは避ける
ペースメーカー装着後、退院して傷口が安定すれば、ウォーキングやラジオ体操、ゲートボールといった適度な運動は健康維持のために推奨されます。しかし、他者との接触があるラグビーや柔道、サッカーなどの激しいコンタクトスポーツは、植え込み部分への強い衝撃で本体やリード線が破損する恐れがあるため避けるべきです。
また、ゴルフのスイングのように腕を激しく、繰り返し動かす運動も、リード線に負担がかかる可能性があるため注意が必要です。どのような運動がどの程度可能なのかは、個人の状態によって異なるため、新しい運動を始める前には必ず担当の医師に相談してください。
長時間の入浴や熱すぎるお湯は心臓に負担がかかるため控える
手術後の傷口が完全に治れば、家庭での入浴は問題なく行えます。ただし、42度を超えるような熱いお湯や、肩まで長時間浸かるような入浴は、急激な血圧の変動を引き起こし、心臓に負担をかけるため避けることが望ましいです。
特に高齢者は、ぬるめのお湯で短時間のうちに済ませることを心がけてください。
また、公衆浴場や温泉施設にある「電気風呂」は、水中に電流が流れており、ペースメーカーの作動に影響を及ぼす危険性が非常に高いため、絶対に入ってはいけません。脱衣所と浴槽の温度差によるヒートショックにも注意が必要です。
旅行や外出の際はペースメーカー手帳を必ず携帯する
ペースメーカー手帳には、装着しているペースメーカーの機種や設定、手術を行った病院、担当医師などの重要な情報が記録されています。旅行中や外出先で体調が急変した際、この手帳を医療機関に提示することで、迅速かつ適切な処置を受けられます。
また、空港の保安検査やMRI検査など、ペースメーカーの装着を証明する必要がある場面でも役立ちます。日常生活においても、いつどこで不測の事態が起こるか分かりません。万が一に備え、外出する際は必ず健康保険証などと一緒にペースメーカー手帳を携帯する習慣をつけてください。
高齢者本人と周りの介護者が特に注意すべきポイント

ペースメーカーを装着した高齢者の安全な生活には、本人の自己管理だけでなく、家族や介護者による日々の見守りとサポートが欠かせません。特に認知症を合併している場合、本人からの体調変化の訴えが難しくなるため、周囲の注意深い観察や看護の視点がより重要になります。
ここでは、本人と介護者が連携して注意すべき体調管理のポイントや、緊急時の対応、介護施設を利用する際の注意点を解説します。
日々の脈拍をセルフチェックする習慣をつける
ペースメーカーは脈が設定値より遅くならないように監視・作動しますが、自身の体調を把握するために、毎日決まった時間に脈拍を測る習慣は非常に重要です。朝、起床して安静にしている時などに、手首で1分間の脈拍数を数えます。
もし、ペースメーカーで設定された脈拍数を下回る、息切れやめまい、ふらつきといった症状がある、あるいは脈が極端に速い、不規則に感じるなどの異常があれば、速やかにかかりつけの医療機関へ相談してください。
家族や介護者も定期的に脈拍を測る手伝いをしたり、本人の体調に関する訴えに注意深く耳を傾けたりする看護の視点が求められます。
植え込み部分の皮膚に赤みや腫れがないか確認する
ペースメーカー本体は、前胸部の皮膚の下に植え込まれています。この植え込み部分の皮膚に異常がないか、入浴時などに定期的に観察することが大切です。
確認するべき点は、皮膚の赤み、腫れ、熱っぽさ、痛み、膿の有無などです。これらは感染症の兆候である可能性があり、放置すると重篤な状態になりかねません。
また、皮膚が薄くなってペースメーカー本体の角が浮き出てきたり、皮膚を突き破って露出しそうになっていたりしないかもチェックします。本人だけでは確認しにくいため、家族や介護者が気にかけて観察するといった看護的なサポートが重要です。
家族や介護者はAEDの使い方を事前に把握しておく
ペースメーカーを装着している人が意識を失い、心停止状態になった場合でも、AED(自動体外式除細動器)は使用できます。AEDは心臓の状態を自動で解析し、電気ショックが必要かどうかを判断するため、ためらわずに使用してください。ただし、使用する際には一点だけ注意が必要です。
AEDの電極パッドは、ペースメーカー本体が植え込まれている部分(胸の皮膚の盛り上がり)の真上を避け、そこから3cm以上離れた位置に貼り付けます。万が一の事態に備え、家族や介護に携わる人は、消防署などが実施する救命講習に参加し、AEDの正しい使い方とこの注意点をあらかじめ学んでおくことが望ましいです。
介護施設への入所を検討する際はペースメーカーについて相談する
ペースメーカーを装着している高齢者が老人ホームなどの介護施設への入所を検討する際には、入所相談の段階で必ずその事実を施設側に伝えなければなりません。施設によって、ペースメーカー装着者の受け入れ実績や、緊急時の対応マニュアル、医療連携体制が異なるためです。
特に認知症を合併している場合、本人が体調不良を正確に伝えられないケースも想定されるため、職員による観察や定期的なチェック体制が整っているかが重要になります。定期検診への通院サポートの可否や、提携医療機関、看取りに関する方針なども含め、安心して介護を任せられる施設かどうかを事前にしっかりと確認してください。
まとめ

ペースメーカーを装着した高齢者が安全に暮らすためには、いくつかの注意点を理解し、日常生活に取り入れることが重要です。スマートフォンなどの電磁波を発する機器とは適切な距離を保ち、空港の保安検査やMRI検査では必ずペースメーカー手帳を提示してください。適度な運動は可能ですが、身体に強い衝撃が加わるスポーツは避けるべきです。
本人が日々の脈拍や植え込み部分の皮膚状態をチェックするとともに、家族や介護者もこれらの点に気を配り、サポートする体制が求められます。正しい知識を持つことで、過度に活動を制限することなく、質の高い生活を維持することが可能です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。