「要介護認定を受けるにはどのような手続きが必要?」
「要介護認定はどこに行けば受けられるの?」
このような疑問を抱えていませんか。
要介護認定を受けるには、必要書類を準備し、各市区町村の「介護保険」を担当する窓口へ申請を行いましょう。
審査は一次と二次に分かれており、申請から原則30日以内に結果通知が届きます。
この記事では、要介護認定を受けるために必要な6ステップや、認定結果の8段階、認定を受けたあとに利用できるサービスなどについて紹介します。
この記事を読むことで、要介護認定を受けるための詳しい方法がわかります。ぜひ最後までご覧ください。
要介護認定を受けるために必要な6ステップ

要介護認定を受けるにあたっては、以下の6ステップが必要です。
- 要介護認定の申請
- 調査員による訪問調査
- 主治医の意見書の準備
- 一次判定(コンピュータによる判定)
- 二次判定(審査会での判定)
- 要介護認定結果の通知
これらの項目を順番に見ていきましょう。
1.要介護認定の申請
要介護認定を申請できる方や、申請に必要なものなどを詳しく紹介します。
要介護認定を申請できる方
要介護認定を申請できるのは、以下のいずれかにあてはまる方です。
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満でかつ、「特定疾病」がある方
特定疾病(とくていしっぺい)とは、加齢によって生じる心身の変化により、要介護状態を引き起こす可能性のある病気を指します。
特定疾病に該当する16種類の病気は以下のとおりです。
| 【特定疾病に該当する 16 の疾病】
◆ がん(がん末期) |
本人ではなく、家族や親族といった代理人も申請できます。
要介護認定申請のために必要なもの
要介護認定申請に必要なものは、主に以下のとおりです。
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証もしくは健康保険被保険者証
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 身分証明書
- 主治医名、もしくは通院先がわかるもの
要介護認定申請書を入手する方法としては、申請先で受け取る、市区町村のホームページからダウンロードするなどがあります。
健康保険被保険者証は、40歳以上65歳未満の方が申請する際に必要です。
申請に必要なものは、市区町村により異なるため、事前に問い合わせておくことをおすすめします。
要介護認定の申請先
要介護認定の申請先は、本人が住む市区町村役場の介護保険担当窓口です。
窓口の名前は市区町村により異なるため、事前に問い合わせておくと申請がスムーズに進むでしょう。
2.調査員による訪問調査
市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーといった調査員が本人の自宅を訪問し、「要介護認定調査」を行います。
ケアマネジャーとは、要介護認定を受けた方の介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、介護上の相談に乗ったりする専門家のことです。
要介護認定調査の主な内容(抜粋)は以下のとおりです。
|
要介護認定調査を受けるときには、本人の状況をよく知っている家族が同席すると良いでしょう。
人によっては調査時に、自分1人では行えないことも「これはできます」「問題ありません」などと答える場合があります。
普段の状況と認定結果がずれてしまうのを避けるため、家族が同席して普段の状況を伝えましょう。
本人の前で普段の状況を伝えにくいのであれば、実際の様子や生活での困りごとなどを書いたメモを渡してもいいかもしれません。
このときは、本人のプライドを傷つけないように、「何か隠しごとをしている」と思わせない配慮が必要です。
メモを封筒に入れておき、調査員が来たときに「今日の調査資料です」といった言葉かけをして、さりげなく渡すのも良いでしょう。
3.主治医意見書の準備
要介護認定を受けるために必要なもう1つの書類が、主治医意見書です。
主治医意見書の作成依頼は、役所の介護保険担当者が行います。
要介護認定申請時に、主治医名を介護保険担当者に伝えておきましょう。
複数の医療機関に通院している場合、誰が主治医であるか判断がつきかねる可能性があります。
そのときは、「本人の状況を一番知っている医師」を主治医としましょう。
4.一次判定(コンピュータによる判定)
要介護認定調査票と主治医意見書の一部をコンピューター集計して、全国一律の方法で判定します。
これが一次判定であり、要介護認定の大事な資料になります。
5.二次判定(審査会での判定)
一次判定後に実施されるのが、要介護認定審査会における二次判定です。
要介護認定審査会の委員は、介護・医療・福祉に関する専門家5名程度で構成されます。
二次判定の資料になるものは、以下のとおりです。
- 一次判定の結果
- 主治医意見書の内容
- 要介護認定調査内の特記事項
資料をもとに審査会委員が話し合い、要介護認定結果が決まります。
6.要介護認定結果の通知
要介護認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に届きます。
以下のような書類が同封される場合もあるため、すべてに目を通してください。
- 認定期間が記入された新しい介護保険被保険者証
- 介護保険サービス利用に関する説明書類
- ケアマネジャーが所属する事業所(居宅介護支援事業所)の一覧
認定結果や同封された書類について不明な点があるときは、介護保険担当者に問い合わせましょう。
要介護認定結果は、自立を含めて8段階

要介護認定結果(要介護度)とは、「日常生活において、どのくらい介護や支援を必要とするか」の指標です。
自立(非該当)を含めると、8段階にわかれます。
要介護度別の具体的な状況と、介護サービス利用限度額は以下のとおりです。
| 要介護度 | 具体的な状況 | 介護サービス利用限度額 |
| 自立(非該当) | 日常生活全般において、介助や見守りを 必要としない状態 |
介護保険サービス対象外 |
| 要支援1 | 食事や排泄、入浴などの日常生活動作は自立
調理や洗濯などで見守りや支援が必要 |
50,320円 |
| 要支援2 | 日常生活動作はほぼ自立。
入浴や排泄などに見守りや介助が必要 立ち上がりや歩行など不安定 |
105,310円 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行などが不安定
排泄や入浴に一部介助が必要 認知症の症状が出ている場合もある |
167,650円 |
| 要介護2 | 1人で立ち上がりや起き上がりが難しい状態
排泄や入浴に一部、またはすべてに介助が必要 |
197,050円 |
| 要介護3 | 立ち上がりや起き上がり、歩行などが
1人ではできない状態 排泄や入浴、着替えなどで、全介助が必要 |
270,480円 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要
理解力の低下が見られることもある |
309,380円 |
| 要介護5 | 生活全般に介助が必要
寝たきりで意思の疎通が難しい場合もある |
362,170円 |
要介護度別の詳しい状況は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:要支援1で受けられるサービスは?要支援1に適した介護施設も解説
関連記事:要支援2で受けられるサービスは?|認定基準から施設入居のメリットまで解説
要介護認定を受けてから介護保険サービスを利用するまで

要介護認定を受けてから介護保険サービスを利用するまでの流れは、認定結果により異なります。
- 要支援認定を受けた方
- 要介護認定を受けた方
- 非該当(自立)と認定された方
順番に見ていきましょう。
要支援認定を受けた方
要支援認定を受けた方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画作成を依頼した後に、サービス利用となります。
介護予防サービス計画作成を依頼する
要支援の認定を受けて、介護保険サービスを希望される方は、近くの地域包括支援センターに連絡しましょう。
要支援の方は、介護予防サービスの対象になります。
地域包括支援センターとは介護に関する全般的な相談窓口で、基本的に以下の3職種が在籍しています。
- 保健師
- 主任ケアマネジャー
- 社会福祉士
介護予防サービス計画作成を依頼する際には、主に以下の内容を伝えましょう。
- 本人の心身の状況
- 家族の状況
- 希望するサービス
これらの情報は、地域包括支援センター職員が、本人・家族の状況に合った介護予防サービス計画を作成するために必要です。
関連記事:高齢者とその家族をサポートする地域包括支援センターとは
介護予防サービス計画に基づいたサービスを利用する
介護予防サービス計画作成後、希望する事業所と契約の上、サービス開始となります。
サービス開始後も、地域包括支援センター職員が定期的に本人・家族の状況を確認していきます。
要支援の方が利用できる、主な介護予防サービスは以下のとおりです。
| サービスの種類 | サービス名 | 具体的な内容 |
| 訪問サービス | 介護予防訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、日常の家事支援や、入浴や排泄などの介助を行う |
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護師が、主治医の指示により自宅を訪問し、身体状況の観察や必要な医療処置などを行う | |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士などリハビリ専門職が自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて必要なリハビリを行う | |
| 介護予防訪問入浴 | 簡易浴槽を積んだ車で自宅を訪問し、介護職員や看護師が入浴の介助を行う | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や看護師、薬剤師などが自宅を訪問し、医療面での指導を行う | |
| 通所サービス | 介護予防通所介護 (デイサービス) | デイサービスセンターに通い、入浴や食事、排泄といった日常生活動作の介助を受けるほか、レクリエーション活動や利用者同士の交流を楽しむ |
| 介護予防通所リハビリテーション (デイケア) | デイケアセンターに通い、本人に合ったリハビリを受ける | |
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 一時的に施設へ入所し、必要な介護や医療、リハビリを受ける |
| 介護予防短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) | 一時的に施設や医療機関へ入所し、必要な医療、リハビリ、介護などを受ける | |
| 地域密着型サービス ※事業所と同じ市区町村に住んでいる人が利用対象者 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 「訪問」「通所」「宿泊」を組み合わせたサービスを、同じ事業所内で受ける |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象にしたデイサービス。日常生活動作の介護やリハビリ、レクリエーション活動などを受ける | |
| その他のサービス | 介護予防福祉用具貸与 | 歩行器や歩行補助杖など、日常生活に必要な福祉用具の貸し出しを受ける |
| 介護予防福祉用具購入 | 入浴や排泄などを助ける福祉用具を購入する際の費用助成を受ける | |
| 介護予防住宅改修 | 手すりの取り付けや段差の解消、扉の取り換えなど生活環境を整えるために必要な改修工事の費用助成を受ける |
要介護認定を受けた方
要介護認定を受けた方は、担当ケアマネジャーを決めて、介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼した後に、サービス利用となります。
担当ケアマネジャーを決める
ケアマネジャーとは、介護サービス計画(ケアプラン)作成や、介護に関する相談の専門家です。
ケアマネジャーについては、介護保険担当者からの指定がないため、自分たちで決める必要があります。
ケアマネジャーを決めるときは、以下の点をポイントにすると良いでしょう。
- 利用者や家族の話をていねいに聞いてくれるか
- 利用者や家族の状況に合ったサービス計画を作成してくれるか
- 介護保険サービスに関して詳しい知識があるか
- 介護保険以外のサービスについても詳しいか
- 守秘義務を守ってくれるか
地域包括支援センターやかかりつけ医に相談したり、友人知人からの口コミを参考にしたりするのも1つの方法です。
介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する
ケアマネジャーが決まったら、介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼しましょう。
ケアプラン作成時に伝える情報は、主に以下のとおりです。
- 本人の心身の状況
- 家族の状況
- 希望するサービス
これらの情報は、ケアマネジャーが、本人・家族の状況に合ったケアプランを作成するために必要です。
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいたサービスを利用する
ケアプラン作成後、希望する事業所と契約の上、サービス開始となります。
サービス開始後も、ケアマネジャーが定期的に本人・家族の状況を確認していきます。
要介護の方が利用できる、主な介護サービスは以下のとおりです。
| サービスの種類 | サービス名 | 具体的な内容 |
| 訪問サービス | 介護予防訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、日常の家事支援や、入浴や排泄などの介助を行う |
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護師が、主治医の指示により自宅を訪問し、身体状況の観察や必要な医療処置などを行う | |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士などリハビリ専門職が自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて必要なリハビリを行う | |
| 介護予防訪問入浴 | 簡易浴槽を積んだ車で自宅を訪問し、介護職員や看護師が入浴の介助を行う | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や看護師、薬剤師などが自宅を訪問し、医療面での指導を行う | |
| 通所サービス | 介護予防通所介護 (デイサービス) | デイサービスセンターに通い、入浴や食事、排泄といった日常生活動作の介助を受けるほか、レクリエーション活動や利用者同士の交流を楽しむ |
| 介護予防通所リハビリテーション (デイケア) | デイケアセンターに通い、本人に合ったリハビリを受ける | |
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 一時的に施設へ入所し、必要な介護や医療、リハビリを受ける |
| 介護予防短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) | 一時的に施設や医療機関へ入所し、必要な医療、リハビリ、介護などを受ける | |
| 地域密着型サービス
※事業所と同じ市区町村に住んでいる人が利用対象者 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 「訪問」「通所」「宿泊」を組み合わせたサービスを、同じ事業所内で受ける |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象にしたデイサービス。日常生活動作の介護やリハビリ、レクリエーション活動などを受ける | |
| 介護予防地域密着型通所介護 | 定員19名未満の小規模なデイサービス。日常生活動作の介護やリハビリ、レクリエーション活動などを受ける | |
| 介護予防看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護に加えて、「訪問看護」を受けられる | |
| 夜間対応型訪問介護 | 18時から翌朝8時までの夜間に訪問介護を受けられる。「定期巡回」と「随時訪問」の2種類がある | |
| その他のサービス | 介護予防福祉用具貸与・購入 | 福祉用具の貸し出し、または購入費用の助成を受ける |
| 介護予防住宅改修 | 手すりの取り付けや段差の解消、扉の取り換えなど生活環境を整えるために必要な改修工事の費用助成を受ける |
非該当(自立)と認定された方
非該当(自立)と認定された方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画作成を依頼後に、サービス利用となります。
介護予防サービス計画作成を依頼する
要支援と認定された方と同じく、地域包括支援センター職員に、介護予防サービス計画作成を依頼します。
介護予防サービス計画作成を依頼する際には、主に以下の内容を伝えましょう。
- 本人の心身の状況
- 家族の状況
- 希望するサービス
これらの情報は、地域包括支援センター職員が、本人・家族の状況に合った介護予防サービス計画を作成するために必要です。
介護予防サービス計画に基づいたサービスを利用する
介護予防サービス計画作成後、サービスが開始されます。
主なサービスの例は以下のとおりです。
- ホームヘルパーやボランティアの訪問による日常生活上の支援
- デイサービスセンターや地域住民・ボランティアが主体となっている通いの場
- 配食サービスや緊急通報システムなど市区町村独自のサービス
- 体力作り教室
- 介護予防教室
サービス内容は、市区町村ごとに異なるため、地域包括支援センター職員に相談しましょう。
要介護認定後に入所できる施設紹介

要介護認定結果が出た後に入所できる、主な高齢者施設は以下のとおりです。
| 施設の区分 | 施設名 | 内容 |
| 公的施設 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
日常生活上の介護や健康管理、医療、リハビリを受けられる施設 やむを得ない場合を除き、要介護3以上の方が対象 |
| 介護老人保健施設 | 自宅に戻ることを前提として、必要な医療や介護、リハビリを受けられる施設 要介護1以上の方が対象 |
|
| 介護医療院 | 長期療養が必要な方向けに、医療や介護を提供する施設 要介護1以上の方が対象 |
|
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の診断を受けた方が、5~9名以内の少人数で介護職員とともに共同で暮らす施設 地域密着型サービスの1つ 要支援2以上の方が対象 |
|
| ケアハウス | 家庭での生活が難しい方を対象とした施設 自立型と介護型がある ・自立型:介護サービスが必要なときは介護保険サービス事業所と別途契約する ・介護型:施設内の介護職員による介護サービスを受けられる |
|
| 養護老人ホーム | 経済的および家庭的な事情で、自宅での生活が難しい方向けの施設 食事の提供や日常生活支援などを行うが、介護サービスは提供されない |
|
| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 介護職員や看護師が常駐して、介護や看護、リハビリなどを受けられる施設 |
| 住宅型有料老人ホーム | 常駐する職員による日常生活の見守りや食事の提供、緊急時対応などを受けられる施設 介護サービスを受けるときは、介護保険サービス事業所と別途契約する |
|
| 健康型有料老人ホーム | 健康な方が入居できる民間施設 常駐する職員による日常生活の見守りや食事の提供、緊急時対応などを受けられる レクリエーション活動や娯楽施設が充実しているところもある |
|
| サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者が暮らしやすいようにバリアフリー対応となっている賃貸住宅 専門の職員が常駐して、安否確認や生活相談などを行う 介護サービスを受けるときは、介護保険サービス事業所と別途契約する |
高齢者施設は、大きく分けると「公的施設」と「民間施設」の2種類です。
施設によっては、費用が高額なところや、入所申し込み後の待機期間が長いところもあります。
状況は施設ごとに異なるため、直接施設に問い合わせるか、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員に相談しましょう。
要介護認定を受けられなかった場合の対処法

要介護認定申請の結果、要介護や要支援といった認定を受けられなかったときの主な対処法は、下記に示した2つです。
それぞれ見ていきましょう。
結果に納得がいかないなら「区分変更申請もしくは不服申し立て」をする
要介護認定結果に納得がいかない場合の対応として、「区分変更申請」と「不服申し立て」の2つがあげられます。
区分変更申請とは、本人の要介護度と実際の状況に大きく開きがあるときや、本人の状況が著しく変化したときに行う手続きです。
区分変更の手続きは、要介護認定と同じ流れになります。
不服申し立てとは、都道府県にある「介護保険審査会」に書面を提出して、認定結果への不服を申し立てるものです。
不服申し立ての場合、決定内容を知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。
どちらの方法を取るにしても、まずは市区町村の介護保険窓口に相談しましょう。
どうしても支援を受けたいなら「介護保険外サービス」を活用する
「介護認定を受けられなかったが、どうしても支援を受けたい」
このような場合、介護保険外サービスを活用する選択肢があります。
介護保険外サービスの内容は、市区町村により異なります。
主なものは以下のとおりです。
- 配食サービス
- 緊急通報システム
- おむつ代の支給
- 訪問理美容
- ボランティアによる支援
ただし、介護保険外サービスを利用する場合、費用は基本的に全額自費になる点は注意が必要です。
またサービスの内容は地域によって差があるため、必ずしも希望の支援が受けられるとは限らない点も理解しておきましょう。介護保険外サービスの詳しい内容については、お近くの地域包括支援センターに問い合わせることをおすすめします。
要介護認定結果には有効期限がある

初めて要介護認定を受けた場合の有効期限は6か月です。
引き続きサービス利用を希望する場合は、認定の更新申請が必要になります。
更新申請は有効期限の60日前から可能です。
詳しくは、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに問い合わせましょう。
まとめ|要介護認定を受けるためには、まず申請が必要

要介護認定を受けるためには、市区町村役場の介護保険窓口での申請が必要です。
申請から認定までには、要介護認定調査や主治医意見書作成などの過程を経て、約30日かかります。
要介護認定の結果は、自立(非該当)から要介護5までの8段階にわかれており、利用できるサービスも結果により異なります。
要介護認定を受けたい方は、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
要介護認定を受けるときによくあるQ&A
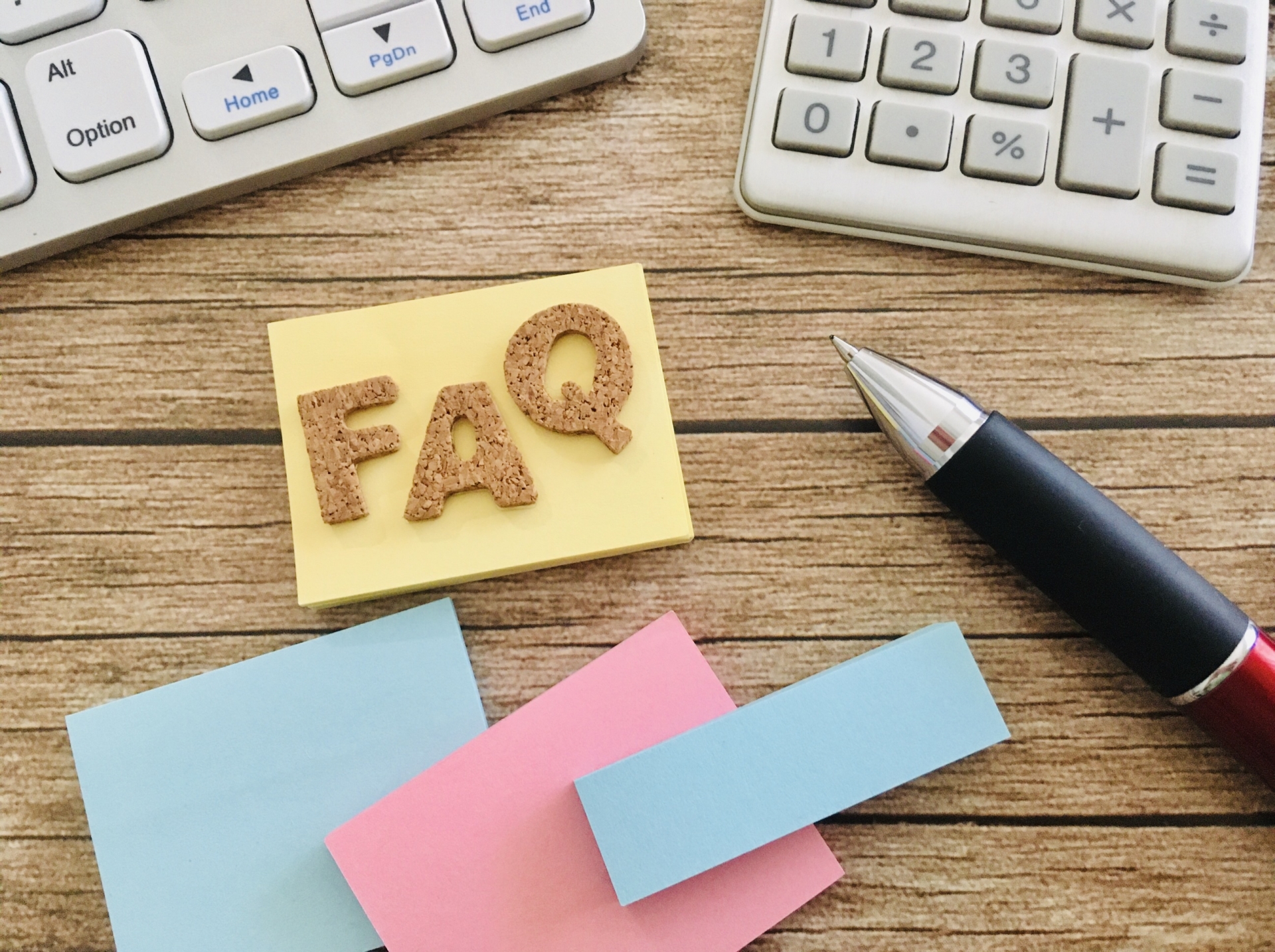
要介護認定を受けるタイミングはいつが良いでしょうか?
入浴や食事、排泄など、日常生活で介護を必要とするようになったときが、申請のタイミングです。
介護が必要となる原因としては、主に以下のようなものがあります。
- 認知症
- 転倒による骨折
- 脳血管疾患後遺症
- 加齢による筋力低下
ただし本人が「介護を受けるのは恥ずかしい」「自分にはまだ介護は必要ない」と思うケースも少なくありません。
本人とよく相談して、納得いくタイミングで申請しましょう。
関連記事:介護保険申請のベストなタイミングはいつ?流れや必要なものを紹介
入院中でも要介護認定を受けられますか?
入院中でも要介護認定は受けられます。
ただし、入院中の要介護認定申請は、「本人の病状が安定しているとき」が原則です。
入院や手術の直後、リハビリを開始して間もない時期などは、病状が不安定であるため、申請には適しません。
病状が安定している状況で、入院中に要介護認定申請を行う場合は、主治医や看護師、医療相談員などに相談しましょう。
なお、入院中に要介護認定結果が出されても、介護保険サービスは利用できません。
入院中は医療保険が優先されるためです。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。











