「親が徘徊するようになってきた……認知症かも」
「徘徊したときに、どう対応したら良いの……」
「共働きで忙しくて徘徊を放置しないかが心配……」などとお悩みの方も多いでしょう。
認知症による徘徊は、症状の特徴や徘徊の理由を知ると、事前に対策がとれるようになります。
しかし、忙しさや家族の負担を理由に、徘徊を放置してしまうと、本人の怪我や事故に遭うだけでなく、罪に問われる可能性もあるのです。
そこで本記事では、認知症による徘徊を放置したリスクだけでなく、認知症の症状や徘徊する理由、対策方法などを解説します。
仮に本人が徘徊してしまった場合の対応方法なども解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
認知症による徘徊を放置するリスク

認知症の方が徘徊をしていて放置してしまうと、以下のようなリスクが起きる可能性があります。
- 怪我や事故に遭う
- 施設を追い出される
- 罪に問われる可能性がある
リスクを防止するためにも、順番に注意すべきポイントを解説していきます。
怪我や事故に遭う
認知症の方が徘徊をしていても放置すると、本人が怪我や事故に巻き込まれるリスクが挙げられます。
とくに繁華街や交通量の多い道路、夜間など視界が悪い場所を歩いていると、車との接触事故や転倒による怪我が発生しやすくなります。
また、認知症の症状により判断力や方向感覚が低下しているため、危険を察知する能力が弱まっている点も問題点です。
たとえば、階段や段差のある場所、建設現場などでは、ちょっとした不注意が大きな事故につながるケースも珍しくありません。
さらに、悪天候時には滑りやすい路面や視界不良のため、危険度は一層増します。
認知症の方が徘徊をしているのを放置すると、目の届かないところで怪我や事故に遭う可能性がある点を見逃さないようにしましょう。
施設を追い出される
認知症の方が徘徊を繰り返す場合、施設での生活に影響を及ぼす可能性があるため、たとえ施設入所していても追い出されるリスクがあります。
施設側はほかの入居者の安全や安心を考慮しなければならず、徘徊が続くと、施設の退去勧告につながる可能性があるのです。
施設は、適切なケアを提供するための体制やリソースに制限があるため、認知症による徘徊が多い場合、施設自体が管理不可能な状況に陥ります。
徘徊を放置しすぎると、誰かに外出を制限されることにストレスを感じ、認知症の症状を悪化させる事態につながる可能性もあります。
施設の従業員が認知症による徘徊の多さにリソースが制限されるほどの症状ではないかの確認が重要です。
以下の記事では、認知症の方がグループホームを追い出される理由を詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:認知症グループホームから追い出される理由とは|確認事項・やるべき事項まとめ
罪に問われる可能性がある
認知症で徘徊している方を放置していると、最悪の場合で罪に問われる可能性があります。
たとえば徘徊で行方不明になった方を放置し、事故や溺死、凍死などで亡くなってしまった場合「保護責任者遺棄罪」に問われるので注意が必要です。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
実際にも、認知症の方が徘徊をしてしまい、行方不明になった数も年々増加しています。
警視庁の調査結果でも19,039人(前年比330人増加)の方が認知症、またはその疑いのある方が行方不明になっているのを発表しました。
行方不明者の全体を通した約20%の方が認知症による徘徊なため、未然に防げるかが重要視されているのです。
社会問題化している認知症による徘徊は、決して放置せず対策を講じられるかが重要です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
参考:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和5年における行方不明者の状況」
【基礎知識】認知症の概要
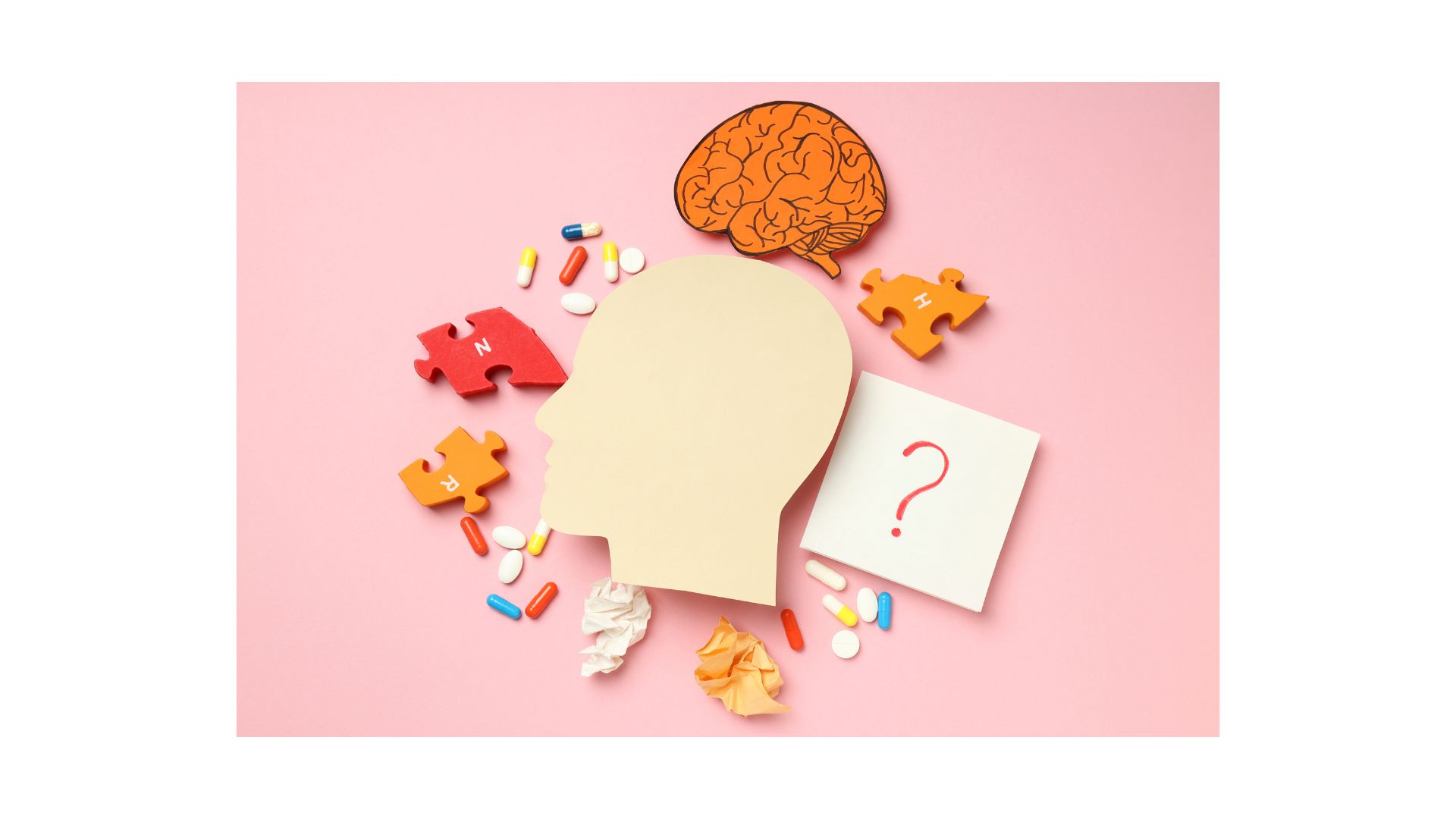
怪我や事故だけでなく施設の退去勧告、罪に問われるリスクなどがある徘徊は、そもそも目的や目的地を決めずに歩き回る行動です。
ここからはおさらいも兼ねて、認知症の症状や徘徊につながってしまう理由について深掘りしていきます。
認知症の症状
認知症の症状は多岐にわたり、記憶障害や判断力の低下、思考力の障害などが典型的です。
認知症の症状が進行すると、日常生活における基本的な行動に支障をきたし、徘徊のような行動が見られるのです。
そもそも認知症の症状は「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」に分類されています。
認知症による徘徊を放置せず適切な対応をするためにも、分類によって異なる症状について解説していきます。
中核症状
中核症状は、認知症が引き起こす脳の障害が原因となって現れる症状です。
中核症状には、以下の症状がみられます。
- 記憶障害
- 失語
- 失行
- 失認
- 見当識障害
- 実行機能障害
上記のような症状が現れると、すでに食事をしたのに食べたのを忘れたり、上手く会話ができなくなったりする日常生活の変化が典型的です。
また、場所・時間・人の認識が難しくなったり、料理や薬の管理といった一連の行動が難しくなったりする症状もあります。
認知症による徘徊は、本人だけでなく家族の負担もかかるため、放置せずに早期の理解と対応ができるかが重要です。
認知症の症状は個人差があるため、個別のケアプランが必要です。
周辺症状(BPSD)
周辺症状(BPSD)は行動・心理症状とも呼ばれており、主に以下のような症状がみられます。
- せん妄
- 抑うつ
- 睡眠障害
- 攻撃的な言動・行動
- 徘徊
徘徊のような行動での異常を引き起こす要因となるケースが多く、本人だけでなく介護者や家族にも大きな負担を与えます。
たとえば何かに怒っていたり、落ち着かない様子がみられたりするような不穏がある場合は、周辺症状(BPSD)と判断しても良いでしょう。
また、認知症の症状である周辺症状(BPSD)は、環境の改善や医療的な介入によって症状が緩和するケースもあります。
認知症の症状が軽いからと放置せず、早い段階での医療や介護サービスを取り入れるのが重要です。
認知症の方が徘徊をしてしまう理由
認知症の方が徘徊をしてしまう主な理由は以下の通りです。
- 体の不快感からくる身体的な理由
- 居心地の悪さからくる環境的な理由
- 不安やストレスからくる心理的な理由
理由を把握できていれば、徘徊を放置してしまうリスクを軽減できる見込みがあります。
後述する徘徊の対策方法で、適切な方法を選ぶためにも、ぜひ参考にしてください。
体の不快感からくる身体的な理由
徘徊は体の違和感が原因となっている可能性があります。
たとえば、以下のような違和感を感じる場合は要注意です。
- お腹が空いた
- のどが渇いた
- トイレに行きたい
認知症の方は上記のような違和感を感じても、どこへ行けば良いのか、どうすれば良いのかわからず徘徊してしまうのです。
体の不快感からくるケースでは、中核症状の「記憶障害」や「見当識障害」が関係している可能性があります。
| 項目 | 症状の特徴 |
| 記憶障害 | ・記憶がすっかりない状態
・経験した内容自体を忘れる ・食事を摂ったことを忘れるのが典型的 |
| 見当識障害 | ・自分に置かれた状況や時間、場所などの把握に障害がある
・自分がいる場所がどこなのかわからなくなるなどの症状がある |
食事を摂っていても空腹感を訴える場合は、温かい飲み物を提供してみても良いでしょう。
また、高齢者は加齢により胃腸の働きが低下するため、便秘になりがちです。
便秘の傾向がある方は、医師の指示のもとで適切なお通じになるよう調整すると、徘徊の対策になる可能性があります。
居心地の悪さからくる環境的な理由
認知症の方が徘徊を起こす背景には、居心地の悪さを感じる環境的な要因が存在します。
そもそも認知症は、環境の変化に大きく影響されやすい傾向があります。
たとえば、老人ホームに入居した直後では「今いる場所がわからない」「知らない人ばかりで落ち着かない」と感じて、徘徊に至るケースが大半です。
新しい環境は本人にとって馴染みのない空間となり、不安を引き起こし、結果として外に出て安心できる場所を探す徘徊行動につながるのです。
なるべく馴染みのある場所で、馴染みのある顔ぶれと生活できる環境を整えていきましょう。
不安やストレスからくる心理的な理由
認知症の方が徘徊する理由として、心理的な焦燥感が原因となり、徘徊に至るケースもあります。
たとえば、仕事に出かける時間だと思い込んで外出しようとするケースが典型的です。
日常生活における不安やストレスが増大する場合もあり、本人にとっては不安解決を目的にしていた行動が徘徊につながってしまうのです。
日常生活を送る中で感じる不安やストレスも認知症による徘徊へとつながる可能性があるため、本人との寄り添いが重要になります。
認知症による徘徊を対策する方法

ここまで紹介した認知症症状の特徴と徘徊の理由を踏まえて、対策方法を考える際のポイントを解説していきます。
認知症による徘徊を放置せず、事前に対策するためのポイントは以下の通りです。
- 否定的な接し方をしない
- 趣味や作業を促す
- 適度な運動をしてもらう
- 鍵やGPSなどの対策グッズを取り入れる
- h3: かかりつけ医に相談する
- 福祉サービスを利用する
1つずつ解説していきます。
否定的な接し方をしない
認知症による徘徊を防ぐためには、本人を尊重し、否定的な接し方をしないのが重要です。
徘徊には必ず理由があり、本人が何かをしようとした結果、徘徊行動につながります。
否定して抑制すればするほど不安感が高まり、さらに落ち着かなくなる傾向が多くみられます。
また、否定されたり怒られたりしたのを本人が忘れたとしても、否定されたときの気持ちは残ってしまい、ストレスを与えてしまうのです。
本人の話をよく聞きながら「どこへ行きたいのか」「何をしたいのか」などを推測して、目的の達成を手助けしましょう。
たとえば認知症の方が徘徊しそうな場合、徘徊する前に日常生活における変化を探していきます。
本人が行きたがっている場所や理由を観察し、本人の目的に寄り添えるようサポートできるかが重要です。
趣味や作業を促す
好きな趣味や作業を促して、不安感を取り除くのも認知症による徘徊を事前に防ぐ方法の1つです。
徘徊の原因となる焦燥感には、明確な目的がある場合と、理由もなくそわそわしている場合があります。
後者の場合、本人に話を聞いても目的がわからないため、どう対応して良いのかわかりません。
対応の仕方がわからないときは、本人の好きな趣味を促してみましょう。
本人に集中できる趣味がないときは、あまり難しくない軽作業をお手伝いしてもらうのも良いでしょう。
適度な運動をしてもらう
日中に少し運動をすると、徘徊が減少するケースもあります。
適度な運動をすると、運動は身体機能の維持だけでなく、精神的な安定にも寄与します。
とくに散歩やストレッチ、ラジオ体操などの軽い運動は、日常生活に取り入れやすく、無理なく継続できる点が魅力です。
また、運動を通じてリズムのある生活を送ると、昼夜逆転の防止にも役立ちます。
認知症の家族が夜間徘徊しそう、またはした経験がある場合は、日中に適度な運動をしてもらうのがおすすめです。
鍵やGPSなどの対策グッズを取り入れる
認知症による徘徊を未然に防ぐために、鍵やGPSなどの対策グッズを取り入れると、放置していても外出防止や早期発見につながる見込みがあります。
| 方法 | 効果 |
| 特殊な鍵やドアチャイムの設置 | 家から出て行く際にセンサーが反応して徘徊を防止できる |
| GPS機能を備えた靴やブレスレットの着用 | 外出先での居場所を把握し、迅速に対応できる |
徘徊対策のグッズを取り入れると、家族や介護者にとっての安心感を提供し、日常の負担を軽減する役割も果たします。
ただし、あまりにも厳重にしてしまうと、本人にとってストレスを与えてしまう可能性がある点は注意してください。
本人に対して十分な理解が得られるような説明をするためにも、丁寧さのあるコミュニケーションが重要です。
関連記事:認知症の徘徊対策グッズ4選!選ぶときのポイントや対応策も解説
かかりつけ医に相談する
認知症による徘徊は、家族にとっても不安だけでなく負担になるケースが多いため、かかりつけ医を含めた専門家に相談するのがおすすめの対策方法です。
かかりつけ医に相談すると、徘徊の背景にある認知症の進行状況を正確に把握し、適切な治療や対応策を講じられる見込みが高まります。
たとえば、適切な薬物療法で症状を軽減し、徘徊の頻度を減らせる可能性もあるでしょう。
また、かかりつけ医は、患者の生活環境や日常の行動パターンを考慮に入れた助言を提供してくれます。
家庭内での安全対策やリスク管理についての具体的なアドバイスも受けられます。
専門医の診療や地域の支援サービスを利用すると、家族の負担を軽減しながら本人にとって、より安心して生活できる環境を整えるのがメリットです。
福祉サービスを利用する
認知症による徘徊が心配である一方で、仕事が忙しく家族にとって負担となっている場合は、福祉サービスの利用を検討しましょう。
福祉サービスの利用は、徘徊のリスクを軽減できるだけでなく、本人や家族にとっての安心につながる可能性を高めてくれます。
たとえば認知症カフェやサポートグループに参加すると、社会とのつながりを持ち続けられるため、家族も介護負担を軽減できます。
地域全体での見守り体制も整うため、仕事で忙しい方にとってもおすすめの選択肢です。
なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。
「認知症の症状がひどくても入居できるのか」と不安に感じている方も含め、気兼ねなくご相談ください。
関連記事:認知症でも入居可能な施設はある?【PART2】~ひどくても入れるのか~
徘徊が起きてしまった場合の対応

ここからは認知症による徘徊が起きてしまった場合の対応について解説していきます。
徘徊が起きてしまった場合は、放置せずに以下の行動を取っていきましょう。
- 近所の方へ応援を依頼する
- 本人の馴染みがある場所を探す
- 警察や地域包括支援センターに相談する
番外編として、後半では徘徊している方を見つけた場合の対応についても触れているので、ぜひ参考にしてください。
近所の方へ応援を依頼する
認知症の方が徘徊してしまった場合、近所の方に協力を依頼するのがおすすめの対応方法です。
とくに本人の顔を把握している方からの協力が得られれば、より早く本人を見つけられる可能性が高まります。
まずは認知症の方が徘徊する前に、家族に認知症の方がいるのと、何かが起きた場合に協力をお願いするのを伝えておきましょう。
事前に伝えておけば、徘徊してしまったとしても、目撃情報を集めたり一緒に捜索してもらえたりできるため、1人で探すよりも効率的です。
認知症の家族が怪我や事故に遭う前に早期発見できるよう、地域全体で協力してもらえるような関係を構築しておきましょう。
本人の馴染みがある場所を探す
認知症の家族が徘徊して行方がわからない場合、まずは本人が行きそうな馴染みのある場所から探してみましょう。
認知症の方は、記憶に強く残っている場所を目指す傾向にあるため、引っ越し前の住居や職場に向かっている可能性があります。
よく通っていた商店や公園などがあれば、いずれも該当する場所になります。
実際にも2015年に愛知県が始めた「徘徊高齢者の効果的な捜索に関する研究等事業」でも、普段移動する範囲内での発見率が約40%と発表しました。
認知症の家族にとって馴染みのある場所を把握できていると、後述する警察や地域包括支援センターへの相談もスムーズに進みます。
参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「徘徊高齢者の効果的な捜索に関する研究等事業」
警察や地域包括支援センターに相談する
もし徘徊により行方がわからなくなった場合は、すぐに警察へ連絡すべきです。
「警察沙汰になっては皆さんに迷惑をかけてしまう……」と、警察への連絡を躊躇してしまいがちですが、遠慮は一切不要です。
生命の危機にかかわる重大な事態になったら、一刻も早く警察へ連絡しましょう。
また、地域包括支援センターへの相談もおすすめの対応方法です。
地域包括支援センターでは、認知症を含めた高齢者が直面する問題に対して支援する機関です。
認知症の家族にいる方への不安や悩みに対した寄り添い、支援さくなどの提案もしてくれるため、家族の負担軽減につながります。
【番外編】徘徊している方を見つけた場合の対応
認知症による徘徊をしているように感じる方を見つけた場合、まずは冷静に対応するのが重要です。
具体的には以下の流れで対応しておきましょう。
- 徘徊している方の様子を観察し状況把握をする
- 安全な場所へ誘導する
- 優しいトーンで話しかけ、相手の名前や住所を聞く(このとき自分の名前を名乗って安心感を与えましょう)
- 持ち物や衣服に名前や住所が記載されていないかを確認する
- 個人情報がわかる場合は、家族や近くの住人に連絡を取り、わからない場合は警察や地域包括支援センターへ連絡する
- 認知症の方の家族もしくは警察が到着するまで寄り添った対応を心がける
認知症による徘徊を見つけても放置せず、冷静で寄り添った対応を心がけましょう。
認知症による徘徊は放置せず寄り添いをお忘れなく!【まとめ】

認知症による徘徊を放置すると、本人が怪我や事故に遭うだけでなく、施設入所している方は追い出され、罪に問われるリスクがあります。
認知症の方が徘徊してしまうのも、体の不快感や居心地の悪さ、不安やストレスなどの理由からきています。
認知症の症状に応じた適切な対策を講じるためにも、前提として否定的な接し方をしないのが重要です。
寄り添った対応に重点をおいた上で、趣味や作業、適度な運動などを促し、状況に応じて補助鍵やGPSなどの徘徊対策グッズを取り入れましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。











