「父(母)が最近おかしな行動を取るようになった」
「年齢的に認知症の可能性はあるけれど、知っている症状とは違う」などと感じた経験はありませんか。
実はその症状、老人性うつの可能性があります。
今回は老人性うつの人が家族にいる場合「どうすれば良いのか」と悩んでいる人に向けて、適切なサポート法を紹介します。
老人性うつの症状や発症の原因、認知症との違いも解説するので、ぜひ参考にしてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
老人性うつの人との接し方はどうすれば良いのか

老人性うつの人と接する際、以下のポイントを押さえて接していきましょう。
- 本人の訴えに寄り添う
- ゆっくりできる環境を整える
- 適度に体を動かすサポートをする
- 本人の趣味や遊びに付き添う
それぞれの観点を詳しく解説していきます。
本人の訴えに寄り添う
老人性うつの人と接する際、家族として「どうすれば良いのか……」と思われる人も多いでしょう。
家族の接し方としては、本人の訴えに対し「辛いね」「大変だね」などと、同意するのが重要です。
あくまで共感に重点を置くよう意識して接すれば不安感が薄れます。逆に「頑張れ」と励ます発言は、プレッシャーに感じてしまいます。
また「気のせいだよ」と否定する発言も、悲観的になり病状が悪化する可能性もあるため、避けた方が良いでしょう。
ただし、老人性うつの人との接し方は、本人の性格や病状などによって異なるため、少しでも困ったら医師に相談してください。
ゆっくりできる環境を整える
老人性うつの人と接する上で大事な項目の1つに、本人がゆっくりできる環境の有無も関係しています。
引っ越し先でくつろげる環境を作ってあげるなど、本人が安心して暮らせるよう環境を調整すると効果的です。
そもそもうつ病に発症しやすい人の特徴として挙げられるのが、本人の責任感が関係しています。
体調不良でも仕事や家事をこなそうとする人がうつ病になりやすい傾向にあるため、作業を代わって本人にゆっくりしてもらうのもおすすめです。
適度に体を動かすサポートをする
老人性うつの人と散歩や体操など、体を動かすサポートをするのもおすすめの接し方です。
日々の買い物に付き合ってもらうのも1つの選択肢です。
そもそもうつ病になると、休養が大切だと思われがちですが、老人性うつに関しては、活動を促すのが大切になってきます。
外出に誘ったり、地域の活動への参加をおすすめしたりすれば、1人で何もしない時間を減らせるでしょう。
適度に体を動かすと、筋肉の衰えを抑えられるだけでなく、睡眠障害にアプローチできる傾向にあるため、積極的に取り入れたい接し方の1つです。
本人の趣味や遊びに付き添う
本人の趣味や遊びに付き添うのも、老人性うつの人との接し方でおすすめできる方法です。
高齢者にとっての趣味や遊びは、手芸、あやとり、囲碁、将棋などがあげられます。
一緒に楽しむと脳の活性化にもつながるだけでなく、前向きな気持ちに変わり、老人性うつの改善に効果的と言えます。
しかし、仕事や家事で忙しく、本人の趣味や遊びに付き添う時間が確保しにくい人もいるでしょう。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。
「普段忙しいから父(母)の趣味に付き添う時間がない」という人も含め、気兼ねなくご相談ください。
そもそも老人性うつとは
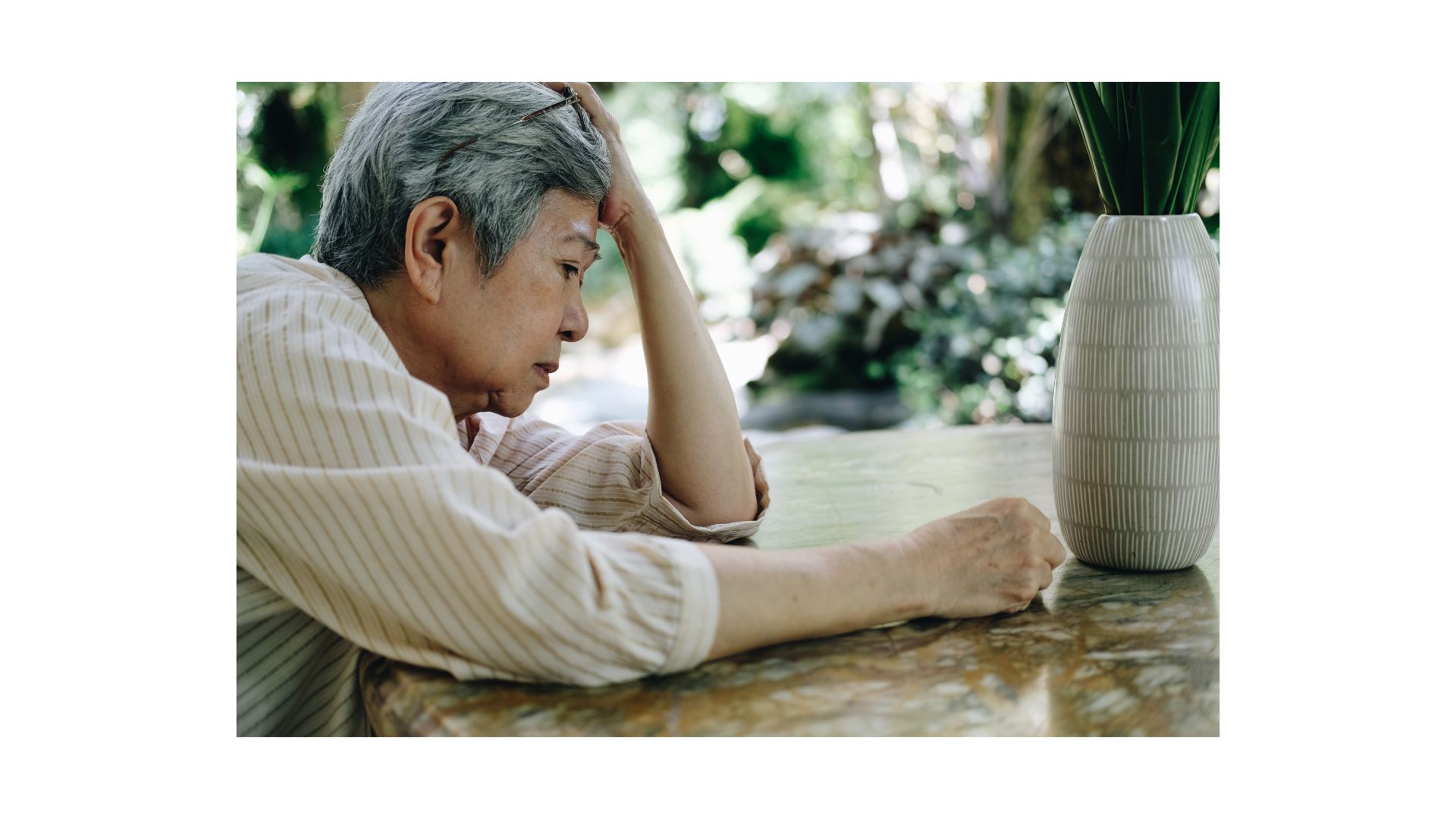
老人性うつは認知症と並んで、高齢者によく見られる病気の1つです。
老人性うつと他の年代のうつ病と本質的な違いはありませんが、高齢者として捉える65歳以上の人を指すのが老人性うつです。
「老人性うつ」という正式な病名ではなく、65歳以上の人に用いられる傾向にあります。
普段と比べてボーッとする様子が多かったり元気がなかったりするようであれば、老人性うつを伺い始める必要があります。
老人性うつの症状
老人性うつの症状は、気分が落ち込んだり食欲がなくなったりなど、人によって異なるだけでなく「年齢のせい」と捉え、治療が遅れてしまう可能性があります。
以下の表で詳しく老人性うつの症状をまとめたので、該当する症状がないかチェックしてみてください。
| 概要 | 主な症状 |
| 抑うつ | ・気分の落ち込み
・不安感や焦り ・日内変動(起床後は症状が強く午後から気分が良くなる症状) |
| 身体的な症状 | ・頭痛
・腰痛 ・胃痛 ・倦怠感 ・めまい ・食欲不振 ・睡眠障害など |
| 仮性認知症 | ・集中力や思考力の低下
・注意力散漫 |
| 妄想 | ・微小妄想(自分の過小評価)
・不安や心配ごとの増加 |
上記のように症状が多いため、つい内科や外科で受診してもらい「問題なし」という結果になった人もいるでしょう。
身体的な症状だけでなく、行動の変化で判断できるケースもあるため、早めに老人性うつを疑いましょう。
以下の記事では、関連した症状である老年症候群について、詳しく解説しているので、比較する意味でも、ぜひ参考にしてください。
関連記事:老年症候群(ろうねんしょうこうぐん)とは?具体的な症状や原因、対処法について
老人性うつが発症する原因

老人性うつが発症する原因は、厳密には解明されていません。
しかし、老人性うつが発症するのは環境的・心理的要因が関係していると言われています。
ここからは環境的・心理的要因によって発症すると言われている老人性うつの原因について深掘りしていきます。
環境的要因
老人性うつが発症する原因は、環境の変化が良くあるケースです。
以下のような環境変化が最近あった人は注意しましょう。
- 責任ある仕事や役職の退職(引退)
- 子どもの独立
- 人との交流の変化や減少
- 家族の死別
年齢を重ねれば重ねるほど、責任の重さや交流の深さがなんらかの影響により失った際の精神的な負担がかかります。
言わば「生きがい」が失われた心境から、老人性うつが発症するケースが多いのです。
心理的要因
老人性うつは、環境の変化に伴って心理的な影響で発症するケースもあります。
- 加齢に伴った心身の衰え
- 病状の悪化
- 死別による悲しみ
- 家族への介護によるストレス
慣れない地域に引っ越して、地域の人と馴染めずストレスを感じた結果、老人性うつになってしまう人もいます。
家族の死別や引っ越しなど、大きな変化があった場合は老人性うつの発症原因としてみられるため、注意しておきましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
老人性うつと認知症との違いと見分け方

ここまでお伝えしたように「老人性うつと認知症似てるような気がする」と感じた人もいるでしょう。
老人性うつと認知症は症状が重なっている部分があるため、見分けるポイントがあります。
老人性うつと認知症の違いや見分け方を表でまとめたので、ぜひ参考にしてください。
| 老人性うつ | 認知症 | |
| 初期の症状 | 身体的不調・抑うつなど | 性格の変化・記憶障害など |
| 症状の進行 | なんらかのきっかけで発症・短期間(1カ月程度)で激変する | 進行はゆっくりの場合が多い |
| 自覚の有無 | 自覚できる | 気づきにくい |
| 気分の落ち込み | 多い | 少ない |
| もの忘れ・忘れ方 | 短期記憶に支障がでる・自覚があり忘れやすいと訴える | 短期記憶に支障が出る・自覚が少なく、取り繕う傾向がある |
| 攻撃性 | なし | 出現するケースあり |
| 妄想 | 心気妄想・罪業妄想・貧困妄想など | もの盗られ妄想など |
| 日内変動 | 朝方調子が悪く、夕方になるにつれて良くなる | 比較的少ない |
| 症状の改善 | 改善の可能性あり | 進行を遅らせるのは可能 |
ただし老人性うつと認知症は併発している可能性があるため、専門家でも見分けるのは難しいのが実情です。
自身や家族だけで「認知症だ」「うつ病だ」と判断せずに、医療機関に相談してください。
以下の記事では「認知症」に特化して解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART1】~認知症と物忘れの違い・初期症状チェックリスト~
見分けるチェックポイント
ここからはさらに老人性うつと認知症を見分けられる見込みのある判断基準を紹介します。
| 概要 | チェックポイント |
| 記憶障害 | ・老人性うつは記憶障害がなく、認知症はよくある
※「わからない」と答えられると判断が難しい |
| 不安感 | ・物忘れではなく不安感が顕著に出ていたら老人性うつの可能性大 |
| 発病 | ・時間帯によって症状が変わる場合は老人性うつ |
| 睡眠 | ・睡眠障害が出ていたら老人性うつ |
| 質問に対する回答 | ・「わからない」と答えたら老人性うつの可能性の方が高い
・見当違いな回答だった場合は認知症の可能性が高い |
以下の記事では、高齢者はとくに注意が必要なセルフネグレクトについて解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:セルフネグレクトとは?原因や対策を解説【高齢者は要注意】
老人性うつかも?と思ったらどうすれば良いか
家族が老人性うつの疑いがある場合「どうすれば良いのか」と焦るものですが、以下を意識してみましょう。
- 十分な睡眠時間や食事が取れているか
- 生活環境に変化がないか
- 趣味や遊びにかける時間がなくなっていないか
- 体調不良や疲れを訴えていないか
環境的・心理的要因によって発症すると言われている老人性うつのため、上記の変化があれば早めに医療機関で相談してください。
言い換えれば、上記の変化をなるべく減らせるかが老人性うつの予防や改善につながります。
自分自身がストレスを抱えてしまうと、本人との接し方が変わってしまいます。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。
「専門的なサポートが受けられる環境にお願いしたい」という人も含め、気兼ねなくご相談ください。
老人性うつの治療法

老人性うつを疑ったら、かかりつけ医に相談、もしくは精神科、心療内科を受診してください。
うつと診断された場合、治療は主に「薬物療法」「精神療法」「環境調整」の3つが中心になってきます。
薬物療法
一般的なうつ病と同様に、抗うつ剤などを使用する薬物療法が基本の治療法となります。
ただし、老人性うつの場合は抗うつ剤の使用が難しい場合があります。
抗うつ剤には以下のような副作用があるので注意が必要です。
- 血圧が上がる
- 尿が出にくくなる
- 頻脈が生じる
その人の健康状態にあった抗うつ剤を選択する必要があるため、必ず医師に判断してもらってください。
精神療法
病院に通い、医師や看護師と話せば、症状が改善する可能性があります。
話し相手になってもらえるため、孤独感の解消につながるからです。
またカウンセリングによって不安だった将来に見通しが立ち、症状の軽減に役立ちます。
症状が緩和されれば、人との交流を増やすためにデイサービスのような福祉サービスの利用も検討できます。
以下の記事では、うつ病に似ているアパシーについても触れているので、ぜひ参考にしてください。
環境調整
老人性うつは、環境的要因が主な発症の原因になるため、環境の調整をするのがおすすめの治療法です。
本人とっての生きがいが感じられるよう、身近な家族の視点で環境を調整していきましょう。
たとえば日頃の買い出しに付き合ってもらったり、気分転換も兼ねた旅行を計画したりするのが効果的です。
人と接する機会を用意するのも効果的で、本人と家族の双方にとって刺激的な時間を設けていきましょう。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けているので、気兼ねなくご相談ください。
老人性うつの予防法
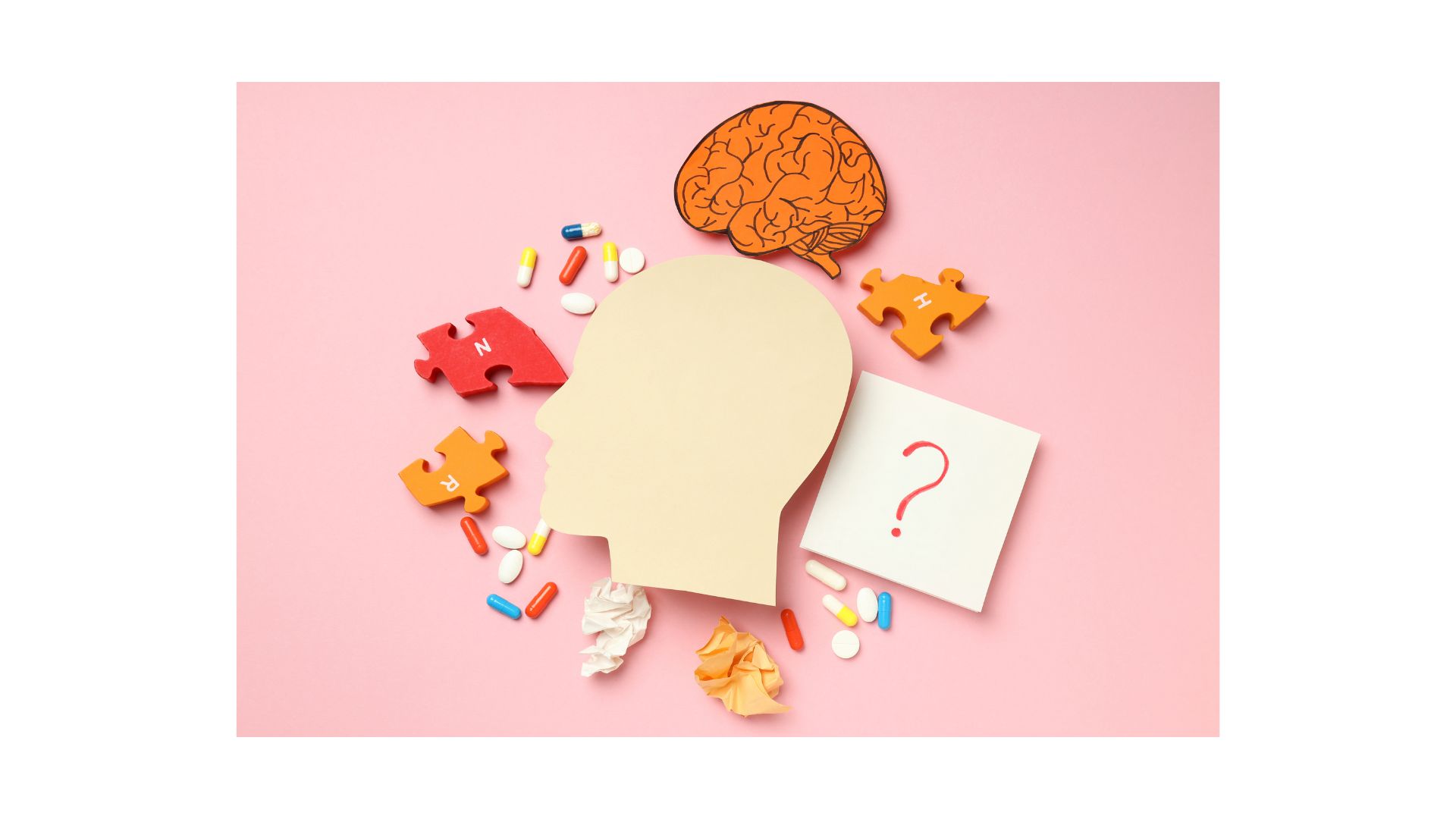
老人性うつの発症や症状の悪化を予防するには、以下の方法がおすすめです。
- 適切な運動を行う
- サークル活動に参加する
- ストレスを発散する
- バランスの良い食事を取る
それぞれの予防法を解説していきます。
適切な運動を行う
うつ病は「セロトニン」と呼ばれる精神を安定させる働きがある神経伝達物質と関係が深いと言われています。
セロトニンは太陽光を浴びたり、運動をしたりすると分泌されます。
日光を浴びながらのウォーキングや、簡単な体操を行うのを心がけてみてください。
サークル活動に参加する
家に引きこもりがちにならないよう、近所のサークル活動に参加するのも良い方法です。
友人ができるだけでなく、共通の趣味や遊びができるため、本人にとって生きがいが生まれる可能性があります。
「自分は1人ではなく社会の一員なんだ」と自覚できれば、孤独感の解消にもつながります。
ストレスを発散する
ストレスを溜め込まず、健康で穏やかな精神状態を保つのも大切です。
散歩やスポーツ、自分なりのリフレッシュ法などを見つけられるようサポートしてみてください。
また、心配ごとがあるときは誰かに相談するよう促すのも良い方法です。1人で抱え込まず、人に話すだけで心が楽になるので、積極的に実施していきましょう。
バランスの良い食事をとる
老人性うつの人にとって、バランスの良い食生活もおすすめの予防法です。
一人暮らしの方や身体的に自炊が難しい方は、コンビニ弁当や手軽にとれる炭水化物が中心の食生活になりがちです。
必要なビタミンやミネラルが不足しないように、バランスの良い食事を心がけてください。
自分で用意が難しい場合は、宅配サービスの利用を検討するのも良いでしょう。
老人性うつには早めの対処が大切!【まとめ】

今回は老人性うつの人が家族にいる場合「家族としてどうすれば」と考えている人に向けて、サポート法を解説しました。
老人性うつは本人が死に至る可能性もあり、介護している家族もうつになってしまう可能性がある恐ろしい病気です。
老人性うつは高齢者であれば誰もがかかる可能性がありますが、適切な治療を行えば改善する見込みのある病気です。
身近な高齢者に対し「なんとなく今までと様子が違うな」と感じたときは、ためらわず早めに医療機関の受診をおすすめします。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。











