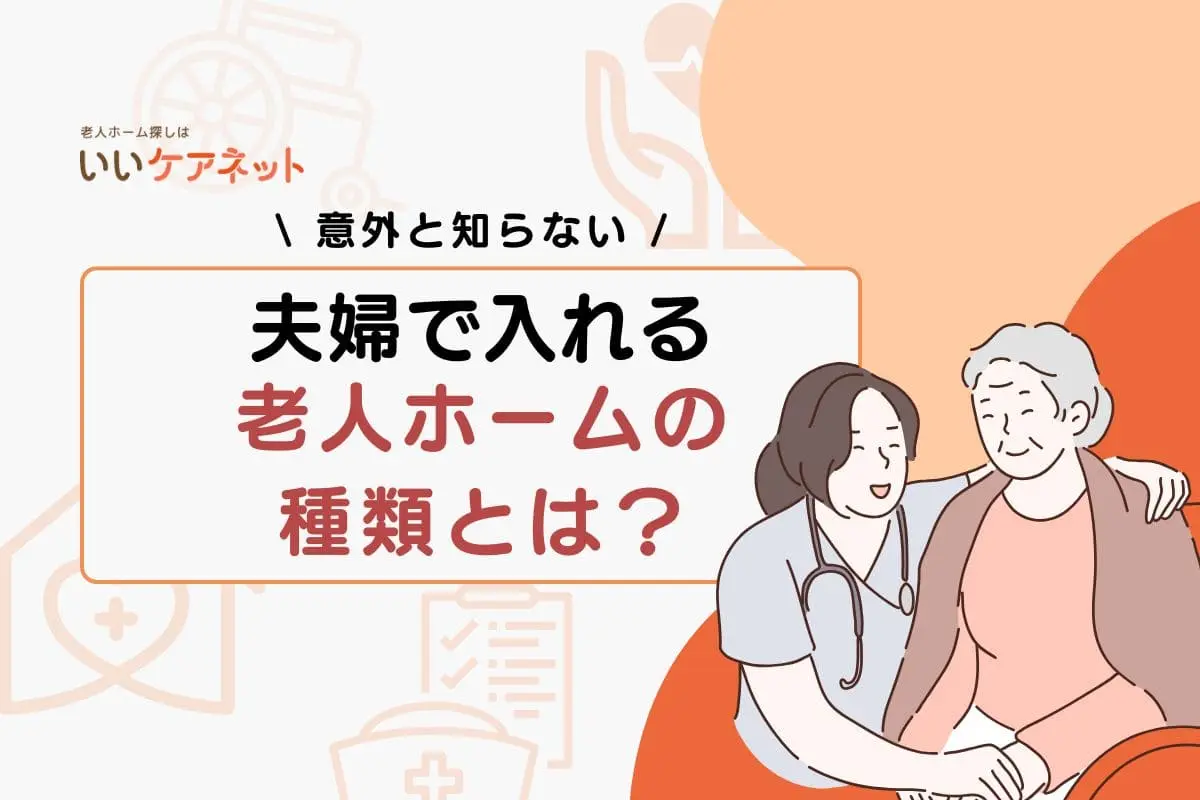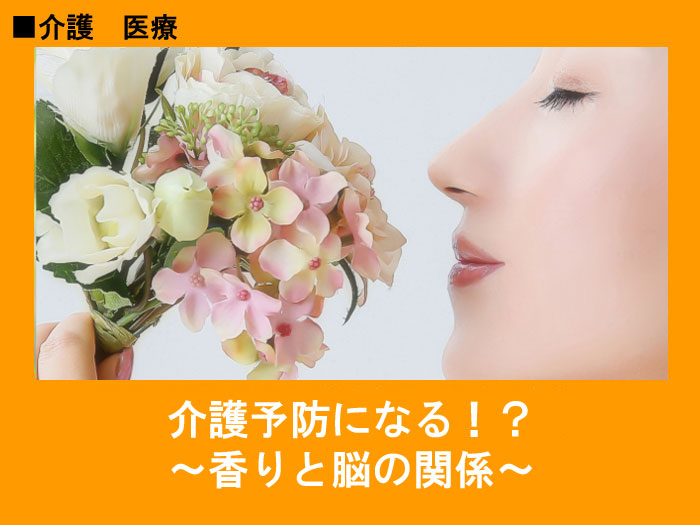「介護保険料の支払いが始まるけれど、いくらが平均なのか」と気になり始めた方もいるでしょう。
介護保険料は、40歳以上になると原則支払い義務が発生します。
しかし、住んでいる地域や所得などに応じて介護保険料が異なるため、事前に理解しておくと将来設計にも影響するでしょう。
そこで本記事では、地域ごとに異なる介護保険料について、東京都や大阪府のような都市部を例に平均値を紹介します。
年齢によって異なる計算方法や支払い方法、滞納してしまった場合のリスクなども解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
介護保険料は平均いくら?

介護保険料の平均は、以下のように年齢でまず分けてから決まります。
- 40〜64歳の平均(第2号被保険者)
- 65歳以上の平均(第1号被保険者)
それぞれの平均について、順番に解説していきます。
40〜64歳の平均(第2号被保険者)
40〜64歳の第2号被保険者に該当する方の介護保険料は、6,276円が平均見込額です(※)。
通常、会社員や公務員として働いており、健康保険と一緒に介護保険料を支払っています。40〜64歳の介護保険料は、給与所得に応じて平均が決まるため、所得によって負担額が異なります。
会社員や公務員で働いている夫(または妻)の扶養内であれば保険料を納める必要はありません。
また、自営業のように国民健康保険に加入している方は、前年の所得に応じて介護保険料も決まるため、平均は所得によって異なります。
※ 参考:厚生労働省「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」
65歳以上の平均(第1号被保険者)
介護保険料の平均納付額は地域や所得により異なりますが、2021~2023年度(令和3〜5年度)では全国平均で6,014円となっています。
65歳以上の方が納める介護保険料は、市区町村で異なると同時に、財政状況や高齢者の人口割合からも考慮されます。
たとえば東京都の平均は6,320円ですが、大阪府の平均は7,486円と、同じ都市部であっても1,000円以上の平均差が生じるのです。
インターネットで「お住まいの地域名 介護保険料 平均」と検索すると、介護保険料の基準額平均が出るので、ぜひ検索してみてください。
参考:東京都「都内区市町村の第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料について」
参考:大阪府「大阪府内の第1号被保険者の保険料基準額一覧(第9期 令和6から8年度)」
関連記事:介護保険証の交付はいつ?利用のしかたや紛失・情報変更時の手続き方法
介護保険料の計算方法

介護保険料の平均ではなく、実際に自分がいくら払うのか計算したい方に向け、具体的な計算方法を解説します。
介護保険料の計算方法も、40〜64歳・65歳以上のように年齢によって異なるため、順番に解説していきます。
40〜64歳の場合
40〜64歳の方が対象となる介護保険料は、国民健康保険に加入しているか、していないかで計算方法が異なります。
ケース1.国民健康保険に加入している
40〜64歳で、自営業のような働き方で国民健康保険に加入している方は、以下が計算式になります。
介護保険料=所得割額+均等割額+平等割額+資産割額
なお、上記それぞれの金額は以下で算出されます。
| 所得割額 | 総所得から基礎控除を引いた額に介護保険の料率を掛ける |
| 均等割額 | 加入者の人数に応じて計算される金額で、所得がなくても課される |
| 平等割額 | 世帯全体に対して平等に課される |
| 資産割額 | 所有する土地や建物などの不動産に対して課される |
しかし、すべてのケースで「介護保険料=所得割額+均等割額+平等割額+資産割額」の計算方法が採用されるわけではありません。
三重県伊勢市の場合、以下の計算方法をもとに介護保険料が決まります。
介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の2号被保険者数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯に応じて計算)
引用:伊勢市「第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料」
つまり、住んでいる地域によって介護保険料の計算方法が異なる点を把握しておきましょう。
ケース2.国民健康保険に加入していない(職場で加入している医療保険)
国民健康保険ではなく、職場で医療保険に加入している場合、介護保険料は所得によって変動します。
具体的な計算方法は以下の通りです。
介護保険料= 標準報酬月額(または標準賞与額)×介護保険料率
なお、標準報酬月額は、毎年4〜6月の通勤手当や残業代を含めた給与の平均をもとに計算されます。
標準賞与額は、給与として支給される税引前の金額から、1,000円未満を切り捨てた金額を指します。
介護保険料率は健康保険組合によって異なり、具体例をあげると、以下が天引きされる平均値です。
- 健康保険組合:1.78%(※1)
- 協会けんぽ:1.59%(※2)
上記はあくまで毎年見直されるため、気になる方は都度確認しておきましょう。
※1 参考:健康保険組合連合会「令和6年度健康保険組合予算編成状況について-令和6年度予算早期集計結果報告-」
※2 参考:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
65歳以上の場合
65歳以上の介護保険料は、市区町村が設定する以下の基準で計算されます。
- 基準額:第1号被保険者の負担分を市町村に住む65歳以上の住民数で割った額
- 基準額に対する割合:個々の被保険者の所得に応じて9〜16段階に分けられた割合
たとえば、東京都新宿区に住むAさんのケースを考えてみましょう。
- 年間所得が200万円
- 東京都の基準額は月額6,600円
- 割合が第7段階である1.2倍
【Aさんのケースの計算式】
6,600円(東京都新宿区の基準額)×1.2(基準額に対する割合)=7,920円
介護保険料は月額7,920円、年額にして95,040円となります。
ただし、地域や所得により変動するため、詳細は住んでいる市区町村の役所やホームページなどで確認しましょう。
参考:厚生労働省「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」
介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法は、40〜64歳の場合給与からの天引きですが、65歳以上の方は以下で異なります。
- 特別徴収(年金から天引き)
- 普通徴収(口座振替や納付書)
それぞれの支払い方法の違いについて、順番に解説していきます。
特別徴収(年金から天引き)
特別徴収とは、65歳以上の方が受給する年金から介護保険料を直接差し引く方法です。
特別徴収では、年金受給者が支払いを忘れる心配もなく納付の手間を省けるため、多くの方にとって便利な方法とされています。
特別徴収が適用されるのは、年金の受給額が18万円以上で、なおかつ市区町村が年金からの天引きを実施している場合のみです。
ただし、新たに65歳になった方やほかの市区町村から転入してきた方は、最初の数カ月間は普通徴収(口座振替や納付書による支払い)になるケースもあります。
また、年金額が18万円未満の方や複数の年金を受給している場合には、特別徴収が適用されないケースもあるため注意が必要です。
年金受給者は、毎年の介護保険料の通知を確認し、支払いが適正におこなわれているかどうかを確認しておきましょう。
普通徴収(口座振替や納付書)
普通徴収は、介護保険料の支払い方法の1つで、主に口座振替や納付書を利用して支払う方法です。
普通徴収では、年金からの天引きではないため、納付忘れには注意しなければいけません。
以下の状況にある方は普通徴収に該当するケースが多いため、忘れずに支払いましょう。
- 年金を受給していない方
- 受給額が少なく年金からの天引きが困難な方
- 転居や転職などで住所や収入状況が変わり、特別徴収に該当しなくなった場合
納付忘れを防止したい方は口座振替で支払うのがおすすめです。
指定した銀行口座から自動的に保険料が引き落とされるため、支払い忘れを防ぐのに便利です。
支払いを怠ると滞納となり、延滞金が発生する可能性もあるので注意してください。
介護保険料を滞納した場合の影響
介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて以下の影響が起きてしまいます。
| 滞納期間 | 影響 |
| 1年未満 | 延滞金が発生(1カ月未満4.3~14.6%、1カ月以上14.6%) |
| 1年以上 | 給付制限が適用される可能性(保険カバー部分の全額自己負担) |
| 1年半以上 | 介護サービス費が全額自己負担、7〜9割戻らない |
| 2年以上 | 未納確定、3~4割の自己負担に引き上げ |
それぞれの対策も兼ねて、詳しく解説していきます。
1年未満の滞納
1年未満の介護保険料の滞納は深刻な影響を及ぼすわけではありませんが、早めの対処がおすすめです。
滞納が発生すると、まず市区町村から滞納者へ支払いの催促がおこなわれます。
督促状が発行されるケースが多く、納付期限から20日以内に延滞金と督促手数料が合算されて請求されます。
延滞金は市区町村により異なりますが、一般的には1カ月未満で保険料の4.3~14.6%、1カ月を超えると14.6%が上乗せされます。
たとえば、滞納額が10万円の場合、1年間で14,600円の延滞金が発生するので注意しましょう。
1年以上の滞納
1年以上の介護保険料滞納は、大きな問題を引き起こす可能性があります。
滞納を続けると介護サービスを受ける際にペナルティが課されるケースがあるため、注意が必要です。
具体的には、1年以上保険料の滞納が続いた場合「給付制限」が適用されます。
介護サービスを受けた際、通常ならば保険がカバーできるため、自己負担1〜3割で済みます。
しかし1年以上介護保険料の支払いを滞納すると全額自己負担になるのです。
ただし、1年以上滞納した段階であれば滞納分を納付すれば7〜9割は戻ってくるため、早期に納付すれば影響は少なく済むでしょう。
給付制限による高額な医療費や介護費用は、経済的な負担を倍増させるだけでなく、精神的なストレスも引き起こす可能性があります。
滞納せずしっかりと対策を立てておくと、将来的なリスクを軽減できます。
1年半以上の滞納
1年半以上の介護保険料の滞納は、さらに深刻な問題を引き起こします。
1年半以上の滞納が続くと、介護サービス費が全額自己負担となり、あとから滞納分を納付しても7〜9割は戻ってこなくなるため注意しましょう。
つまり、介護サービスを利用する際に、すべての費用を自己負担しなければならない状況になるのです。
介護サービスを受けること自体が困難になる場合があるため、1年半以上の滞納はしないよう心がけましょう。
可能な限り早急に未払いを解消し、日常生活や必要な介護サービスの安定を確保するのが重要です。
2年以上の滞納
2年以上滞納すると、未納が確定するため、延滞分の保険料をあとから納めることすらできなくなってしまいます。
延滞分を納付できないと、通常1〜3割の介護保険サービス自己負担額が3~4割へ引き上げられます。
言い換えれば長期的に介護保険サービスを利用する際、経済的負担が大きくなるのを意味するのです。
とくに施設入所は費用が多くかかるため、相当な費用負担を強いられるでしょう。
介護保険料の滞納は、経済的な負担を大幅に増加させるため、市区町村の窓口で相談し分割払いなどの対応を検討してもらいましょう。
関連記事:介護保険制度はいつから始まった?目的や背景、歴史まで徹底解説
介護保険料を払う平均額を把握しておこう!【まとめ】

介護保険料の支払額は、年齢や住んでいる地域、所得によって平均値が異なります。
介護保険料の平均が異なる一方で、40〜64歳の方はとくに将来の負担を事前に把握でき、早めの計画も立てられます。
本記事でお伝えしたように、介護保険料の滞納は多くのペナルティが課せられるため注意が必要です。
期日を守るのが前提ですが、支払いに困ってしまうケースもあります。
自分で解決するのが難しいと判断した場合、すぐに市区町村の窓口に相談しましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
介護保険料の平均に関するよくある質問

介護保険料を払わず済むケースはないの?
介護保険料は、原則として40歳以上のすべての国民が支払う義務があります。
しかし、以下のような特定の条件を満たす場合には例外も存在します。
| 国内に住所がない方 | 支払い義務なし |
| 適用除外施設に入所しているの方 | 免除の対象 |
| 短期滞在の外国人の方 | 3カ月未満であれば支払い義務なし |
| 生活保護を受給している方 | 実質負担なし |
上記の通り、基本的には支払い義務があると把握しておくのが重要です。
介護保険料の支払いを減らす方法はないの?
介護保険料は法律で定められた社会保険料の一部であり、原則として支払いを免除はできません。
しかし、以下のようなケースでは負担の軽減が可能です。
| ケース | 対策 |
| 所得が非常に低い場合や生活が困窮している場合 | 自治体に相談し、減免措置や分割払いを受ける |
| 自治体の制度 | 「介護保険料減免制度」の確認 |
| 扶養家族の状況や住民税の非課税世帯 | 特定の条件を満たすと保険料が軽減される |
| 介護保険サービスの利用 | サービスの種類や量を調整し、自己負担額を抑える |
上記対策だけでなく、日々の節約も心がけ、無理のない範囲で介護保険料を支払いに余裕を持たせるのが大切です。
介護保険料は無職の場合いくら払う必要があるの?
無職の方が支払う介護保険料も、住んでいる市区町村の基準額に応じて決められます。
「支払わずに済む」自体は基本的になく、あくまで減免の対象になると把握しておきましょう。減免される金額は4分の1〜2分の1になります。
なお、無職の方で生活保護を受給している場合であれば、介護保険料の支払い負担なく済むため、状況に応じて市区町村の窓口に相談しましょう。
関連記事:介護保険法をわかりやすく解説|目的や制度の仕組み、最新の改正まで
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。