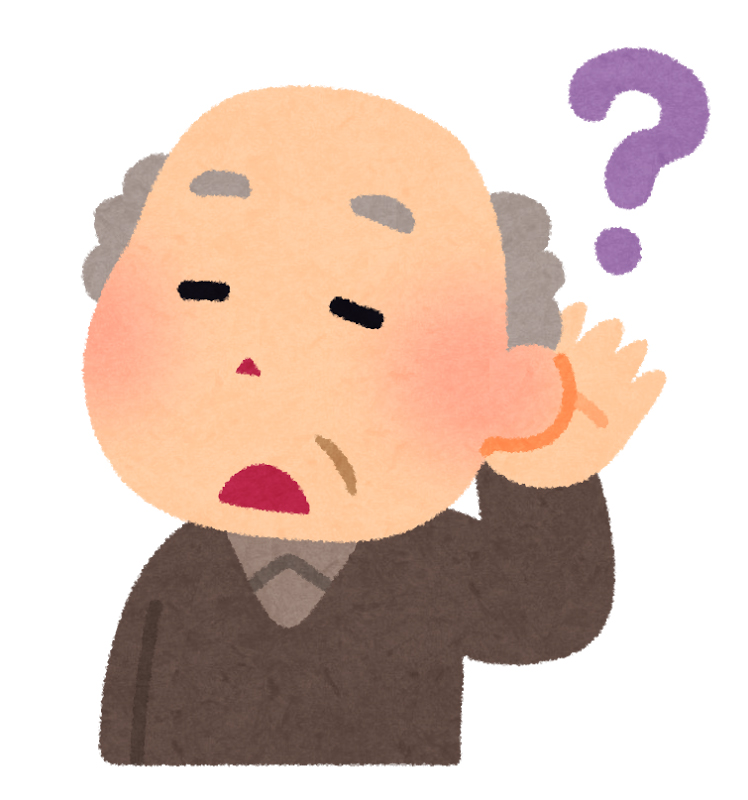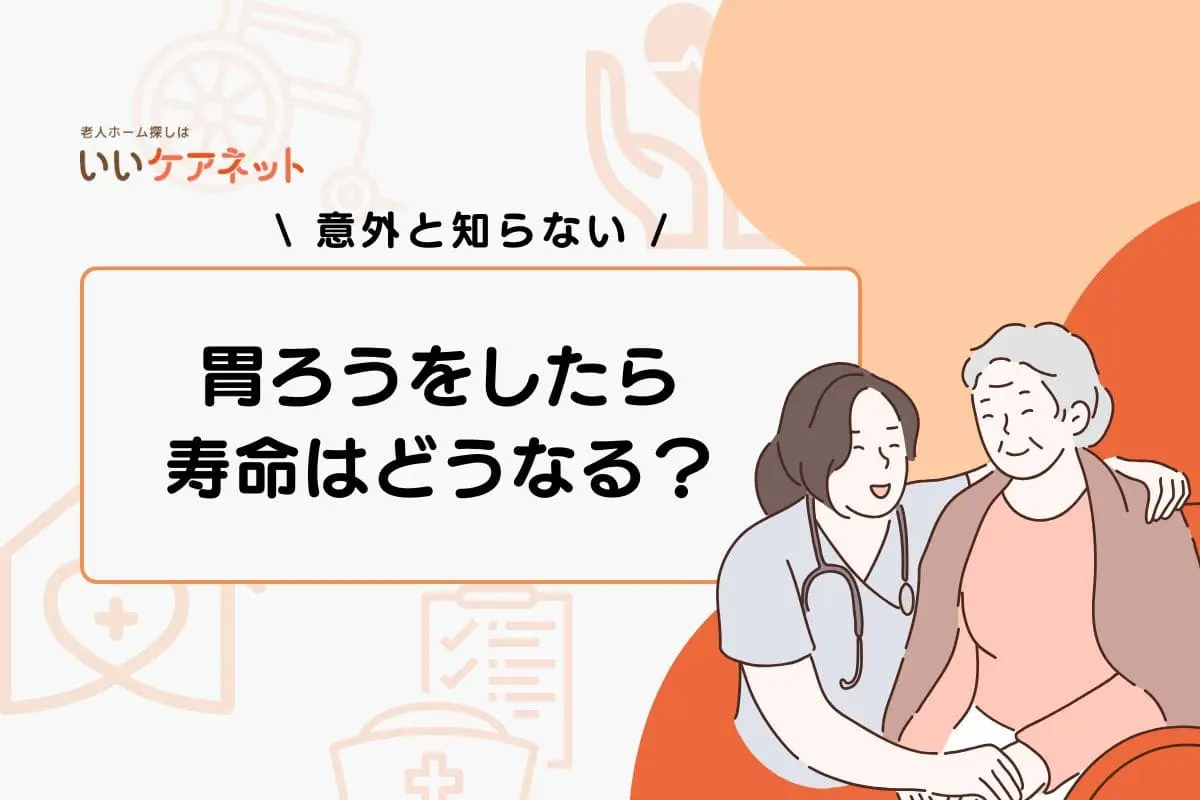高齢になるとさまざまな理由から寝たきりになるリスクが高まります。脳卒中や認知症などの病気が原因になるケースもあれば、加齢による筋力低下など原因はさまざまです。
本記事では、高齢者が寝たきりの要介護状態になる原因を紹介します。寝たきりの高齢者が発症しやすい「廃用症候群」の原因や症状、治療法も解説しています。
「両親が寝たきりになったらどうしよう」「寝たきりを防ぐ方法を知りたい」と考えている方は、ぜひご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
高齢者の寝たきりとは

寝たきりといった言葉に明確な定義はありませんが、一般的には、以下のいずれか、もしくは複数の条件に当てはまることを「寝たきり」と表現しています。
- 自力での日常生活が困難になり、ベッド上での寝起きが生活の中心になっている
- 何らかの病気やケガをきかっけに、6カ月以上ベッドに寝ている状態が続いている
- 基本的に1日中ベッドの上で過ごし、排泄や食事、着替えなどに介助を必要とする
高齢者が寝たきりの要介護状態になる原因

高齢者が寝たきりの要介助状態になる原因は、脳卒中や認知症、筋力低下などがあげられます。病気で麻痺が残ると、思うように体が動かせなくなるようになり、寝たきりになるケースも少なくありません。
ここからは、高齢者が寝たきりの要介護状態になる原因を4つ紹介します。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
関連記事:高齢者に多い病気ランキング5選!病気になりやすい理由も解説
脳卒中・認知症
高齢者が寝たきりの要介護状態になる大きな原因に、脳卒中や認知症があげられます。厚生労働省が行った「国民生活基礎調査(2022年度)」によると、65歳以上の要介護状態になった方の直接原因は、1位が脳卒中、2位が認知症と結果が出ています。
脳卒中は、脳の血管が破れたり詰まったりし、血流が阻害されて脳の機能が低下する病気です。脳の機能が低下すると、手足に麻痺が生じるため、寝たきり状態になりやすい傾向があります。
一方で認知症は、脳の機能が低下し、物ごとの判断能力が低下した結果、今まで通りの生活動作をするのが難しくなりやすい傾向にあります。認知症によって体を動かすのが難しくなり、筋力低下によって寝たきりになるケースも少なくありません。
参考:厚生労働省「国民生活基礎調査(2022年度)」
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART1】~認知症と物忘れの違い・初期症状チェックリスト~
関節・筋力低下
加齢によって関節や筋力が低下し、寝たきりになるケースもあります。変形性膝関節症で膝に痛みが生じたり、関節リウマチによって痺れが出たりなど、病気が間接的に関係している可能性もあるのです。
病気による痛みをかばうため、体を動かさなくなり、筋力が低下して寝たきりになるケースもあります。関節や筋力低下による寝たきりを防ぐには、日頃から体を動かしたり、膝や関節が痛い場合は、速やかに医療機関を受診したりするのが大切です。
転倒・怪我
高齢者は、転倒や怪我が原因で寝たきりになる可能性もあります。若い方であれば、転倒や怪我でも比較的短期間で回復できますが、高齢者は回復に時間がかかります。高齢者に多い大腿骨の骨折は、歩けるようになるまで時間がかかるため、筋力や身体能力の悪化を招き、寝たきりになるケースも少なくありません。
たとえ、転倒による怪我が治ったとしても「また転倒したらどうしよう」と不安を抱き、体を動かさなくなる方もいます。体を動かさなくなると、身体能力が衰え、寝たきりの原因につながる可能性もあります。
骨粗しょう症
骨粗しょう症も高齢者が寝たきりになる原因です。骨粗しょう症とは、骨の強度が低下し、骨折しやすくなる骨の病気です。
わずかな衝撃で骨折してしまうリスクもあります。骨粗しょう症によって骨折した場合は、回復するまで安静に過ごさなくてはなりません。
高齢者が長期間安静に過ごしていると、筋力や関節が衰え、寝たきり生活のリスクを高めます。寝たきりになり、要介護状態になる方も多くいます。骨粗しょう症や寝たきりを防ぐためにも、バランスの良い食事と、適度な運動を心がけましょう。
高齢者の寝たきりは「廃用症候群」を引き起こす

高齢者の寝たきりは「廃用症候群」を引き起こすリスクがあります。廃用症候群は、生活不発病とも呼ばれており、心身のさまざまな機能が低下してしまう病気です。筋肉や関節だけでなく、内臓の機能低下も招く可能性があります。
ここからは、高齢者の寝たきりが招く、廃用症候群の原因や症状を紹介します。
原因
廃用症候群を発症する原因は以下があげられます。
- 安静状態が長期間続く
- 運動量が低下する
- 生活環境に問題がある
転倒による怪我や、病気の治療を目的とした長期の安静は、廃用症候群の発症につながります。高齢者は、骨折や脳卒中によって入院し、ベッド上での生活が続くと筋力低下や関節が固まる拘縮(こうしゅく)が進行しやすくなります。
加齢によって体を動かす機会が減ると筋肉が衰え、寝たきりになり、廃用症候群を発症するケースも少なくありません。自宅や施設内での移動が制限されたり、家族が過度に介護をしたりすると、体を動かす意欲が低下し、寝たきりになる方もいます。
症状
廃用症候群の症状は、人によって異なり、身体的・精神面な症状などさまざまです。代表的な廃用症候群の症状は以下の通りです。
- 運動器障害
- 循環・呼吸器障害
- 自律神経・精神障害
- 泌尿器障害
- 皮膚障害
- 消化器障害
- 代謝障害
廃用症候群の特徴は、筋力や骨の強度低下だけでなく、内臓機能や精神面にも影響を及ぼす点です。人によっては、気分が落ち込む「うつ状態」になったり、認知症を発症したりするケースもある点にも留意しておきましょう。
また、廃用症候群は高齢になるにつれて、糖尿病を発症しやすくなります。「耐糖能異常」と呼ばれる糖尿病予備軍状態を放置していると、糖尿病の進行確率が高くなります。寝たきり状態で心身に異常を感じた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
治療方法
廃用症候群は、症状によって治療法が異なりますが、主に薬物治療とリハビリテーションが行われます。症状が多岐にわたるため、一概にいえませんが、発症後できるだけ早い段階からリハビリテーションをすると、効果的です。
しかし、廃用症候群は、一度発症すると回復が困難になりやすい傾向にあります。回復のために必要な時間は、廃用症候群にかかっていた期間の数倍必要ともいわれています。できるだけ発症を防ぐためにも、できるだけ寝たきり期間が続かないよう、体を動かしたり、人と関わったりするのが大切です。
高齢者が寝たきりにならないための予防対策

高齢者が寝たきりにならたいために、下記の予防策を実施することが大切です。
詳しく解説するので、まずはできることから始めていきましょう。
栄養バランスの良い食事をしっかり摂る
低栄養になると筋力が低下しやすくなるため、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。栄養が不足すると筋肉量が減少し、転倒や骨折のリスクが高まります。
とくに、体作りに欠かせないたんぱく質を積極的にとるのがおすすめです。たんぱく質は、肉や魚、卵、大豆製品などから手軽に摂取できます。他にもビタミンや食物繊維などもバランスよく摂取するのが大切です。
あまり食欲がなかったり、食事量が偏りやすかったりする方は、栄養補助食品を活用して栄養バランスを整えてみましょう。
噛む力を維持する
噛む力を維持するのも、寝たきりを防ぐのに大切なポイントです。噛む力が低下すると、食事の摂取量が減り、栄養不足に陥りやすくなります。さらに噛む動作は、脳への刺激にもなり、認知機能の低下を防ぐ効果も期待できます。
歯が抜けたり噛み合わせが悪くなったりすると、食事がしづらくなるため、定期的な歯科検診を受け、クリーニングや義歯の調整を行いましょう。噛む力を維持するため、硬めの食品やガムを取り入れるのも効果的です。
口腔ケアを行う
誤嚥性肺炎を防いだり、噛む力を維持したりするためにも、口腔ケアをしましょう。口腔内の衛生状態が悪化すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。誤嚥性肺炎は、高齢者が発症しやすい病気のため、日頃から大切しておくと予防に効果的です。
毎日の歯磨きや、うがいはもちろん、口腔内の乾燥を防ぐために、水分補給をこまめに行うのも大切です。さらに歯科での定期的なクリーニングや、口腔リハビリを受けることで、口腔内の健康を保てます。
関連記事:知らないと怖い!?正しい口腔ケアの方法をご存知ですか?
適度な運動をする
適度な運動を取り入れると、筋力低下や関節の拘縮などを防げます。病気にかかっていなくても、関節や筋力低下によって寝たきりの原因になる方も少なくありません。
ウォーキングやストレッチ、軽い筋力トレーニングを日常生活に取り入れ、体を動かすと筋力低下を防げます。
ただし、運動によって転倒や怪我をするリスクもあるため注意が必要です。高齢者が安全に運動習慣を身につけるには、家族と一緒にウォーキングをしたり、体を動かせるデイケアに通ったりするのがおすすめです。安全を確保した上で、体を動かし寝たきりを予防しましょう。
関連記事:高齢者こそ有酸素運動をすべき!メリットやウォーキングの注意点
人と触れ合う機会を作る
認知症による寝たきりを防ぐためにも、人と触れ合う機会を作りましょう。
人との交流が減ると、脳への刺激が少なくなり、認知機能が低下しやすくなります。孤独感が精神的な落ち込みを招き、活動意欲の低下につながるケースもあります。
定期的に家族や友人と会話したり、地域の集まりに参加したりなど人と集まる機会を増やしましょう。家族と離れて暮らしている場合は、オンライン通話を活用するのもおすすめです。ストレスにならない範囲で人との交流を増やし、認知機能の低下を防ぎましょう。
関連記事:高齢者におすすめテレビ電話!孫とのコミュニケーションをいつでも手軽に楽しもう
まとめ
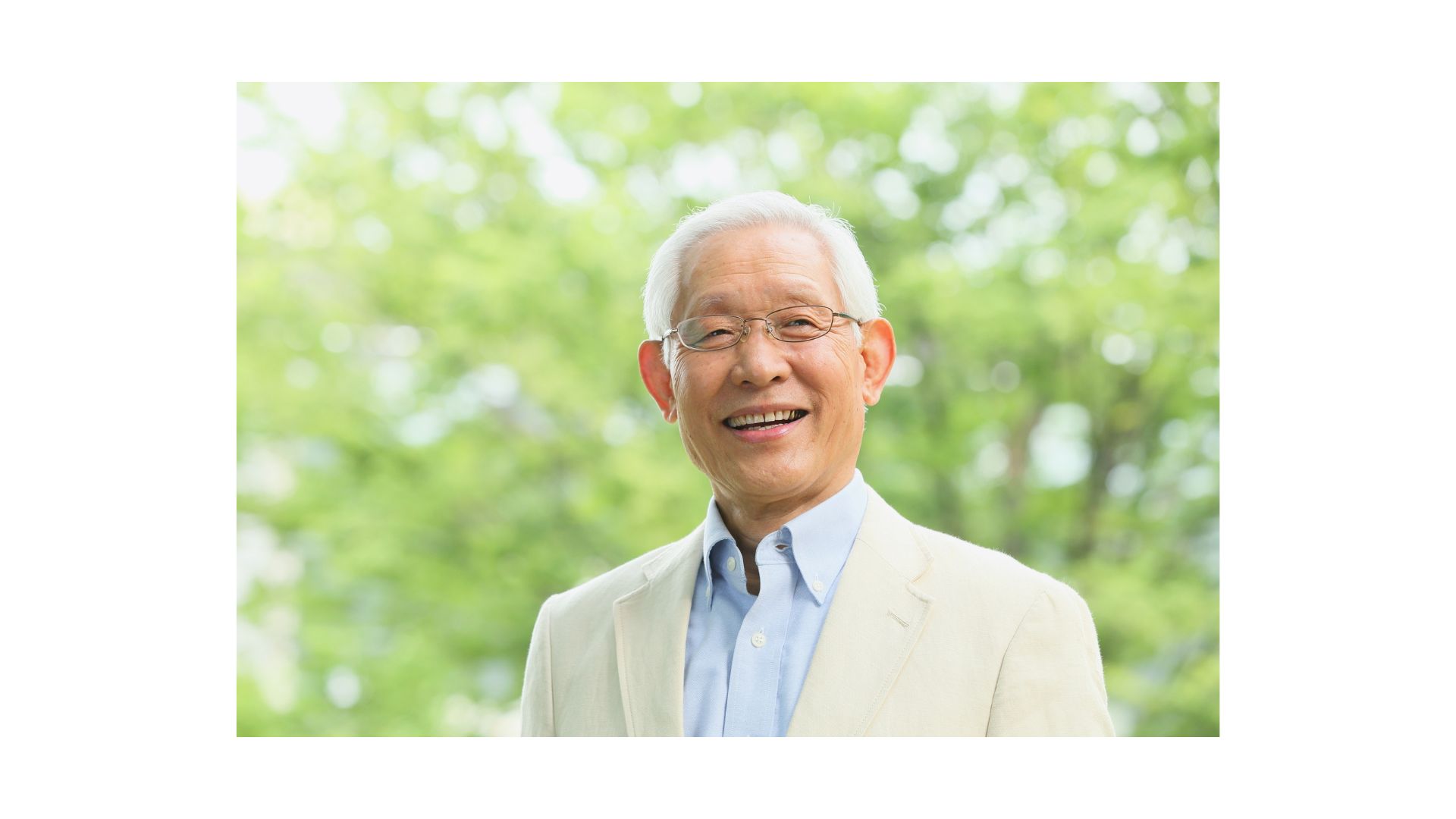
高齢者が寝たきりになる原因は、脳卒中や認知症、骨粗しょう症などがあげられます。病気になっていなくても、転倒や怪我、筋力低下によって寝たきりになるケースもあるため、注意が必要です。
長期間寝たきりの状態が続くと、廃用症候群と呼ばれる病気を発症する可能性があります。廃用症候群は、一度発症すると治りにくい傾向にあります。
寝たきりを防ぐためには、運動をしたり、人と触れ合ったりして心身ともに刺激を与えるのが重要です。転倒や怪我のリスクを抑えつつ、できることからはじめましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。