在宅介護でよく使われるポータブルトイレは、足腰が弱くなった方や夜間のトイレ移動が難しい方をサポートする便利な福祉用具です。
しかし、いざ使おうと思ってもどこに設置すれば良いのかわからなかったり、使い方の手順や汚物の処理や掃除が不安だったりする方は少なくありません。
本記事では、ポータブルトイレの設置場所や使い方の基本から、無理なく使える工夫まで、はじめての方にもわかりやすく紹介します。
介護する側も、される側も、安心して快適に使えるポイントをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
ポータブルトイレとは?

ポータブルトイレは、ベッドルームなど日常的に過ごす部屋へ設置しやすい携帯式のトイレです。介護現場でよく導入されており、夜間や緊急時の移動を短縮できるメリットがあります。
足腰が弱くなった高齢者は、トイレまで歩く途中で転倒する心配もあるため、安全面からポータブルトイレが選ばれるケースは多くなっています。
ただし、使ったあとに排せつ物が部屋に残る場合もあるので、きちんと処理して、こまめに掃除や消臭が大切です。設置後は、清潔に保つ工夫を忘れずにおこないましょう。
基本的なポータブルトイレの使い方

ポータブルトイレは、自分で動ける人と介助が必要な人とでは、使い方やサポートのしかたが変わってきます。
大切なのは、安全と衛生をしっかり守りながら、無理のない範囲での手助けです。
以下では、まずポータブルトイレの基本的な使い方を紹介します。
基本的な使い方7ステップ
ポータブルトイレを使用する際は、基本的に以下の7ステップに沿って使います。
- バケツに少し水を入れておく:汚物がこびりつきにくくなり、後の掃除が楽になります。
- ポータブルトイレまで移動する:転倒しないように、周囲の安全を確認しながら移動します。
- 手すりやひじ掛けをしっかりもつ:体を安定させて、安心して座れるようにします。
- ズボンと下着を足元まで下ろし、座面にしっかり座る:バランスを崩さないように、ゆっくりと腰を下ろしましょう。
- 排せつ後、陰部を拭きズボンと下着を上げる:清潔を保ち、快適に過ごせるようにします。
- フタや便座をしっかり閉める:臭いの広がりや衛生面への配慮のために必要です。
- バケツの中身を処理する:排せつ物はトイレに流し、すぐに処理できない場合はフタをしておきます。清潔を保つためにも、なるべく早めに後始末をおこないましょう。
可能な限りこまめに手入れや後始末するのが、ータブルトイレの基本的な使い方です。
自力で動ける場合:普通のトイレと同じ使い方
自分で動ける方は、ポータブルトイレも普段のトイレとほとんど同じ使い方ができます。ズボンと下着を下げて座り、排せつ後に陰部を拭いて終わりです。
ただし、立ち上がるときや夜間など、転倒のリスクがある時間帯には注意が必要です。必要に応じて声をかけたり、そっと見守ったりして、安全に使えるようにサポートしましょう。
移動に介助が必要な場合:手すりやひじ掛けが必要
一人で移動や立ち上がりが難しい方には、手すりやひじ掛けのサポートが欠かせません。
しっかりと体を支えながら移動し、ズボンや下着の着脱もスムーズにおこなえるようにします。
恥ずかしさを感じやすい場面なので、できるだけ露出を少なく、丁寧で素早い動作を心がけましょう。排せつ中は姿勢が崩れないように、背中に軽く手を添えるなどして、安定させてください。
終わった後は汚物の処理を本人から見えないところでおこない、プライバシーと自尊心を守れるように意識しましょう。
また、自分でできる対応はできるだけ見守り、手を出しすぎないことも大切です。
そして、排せつの様子に普段との違和感がないかを確認し、流れをパターンとして把握しておくと、よりスムーズに介助しやすくなります。
関連記事:「手すり」が介護保険適用?保険の概要や支給条件について
ポータブルトイレの汚物処理方法と掃除の手順

ポータブルトイレは、足腰が弱くなった方や、夜間にトイレまで行くのが大変な方の負担を軽くする便利な福祉用具です。
ただし、使い方や掃除のしかたを間違えると、臭いや衛生面でトラブルが起きる場合もあります。
水洗式ではないポータブルトイレの場合、便座の下にバケツがついていて、そこに排せつ物がたまります。排せつ後は、バケツを取り外して中身を水洗トイレに流しましょう。
とくに尿は、時間がたつと臭いが広がりやすくなるため、できるだけ早めの処理が大切です。
ジェル状に固める凝固剤を使っている場合は、お住まいの地域のルールに従って、きちんと処分してください。
バケツの中身の捨て方や、洗い方を正しく理解し、いつでも衛生面を清潔に保つポイントです。
ポータブルトイレの掃除が楽になる方法は「使い捨て製品」の活用
ポータブルトイレを清潔に保つためには、こまめな掃除が大切です。
ただし、毎回バケツを洗うのは手間がかかります。そのような場合に便利なのが、使い捨ての介護用品です。以下のような製品を上手に活用すれば、掃除の手間をぐっと減らせます。
- 専用の使い捨てバッグ:バケツにセットしておけば、汚物がたまったら袋ごと処理できるため、バケツを洗う必要がありません
- 吸水シート:バケツの底に敷いておくと、液体の飛び散りを防ぎ、後片づけが簡単になります
- 介護用おむつの吸収材:少し入れておけば尿をすぐに固められ、臭い消しや処理がしやすいです
- 使い捨ての便器カバー:たとえば便座部分の汚れを防ぎ、洗浄の回数を減らせます
- 消臭機能つきの使い捨てシート:臭いを抑えながら掃除もしやすくなります
こうした使い捨てアイテムを取り入れれば、介護する人の負担を軽くし、いつでも気持ち良く使える環境を整備できます。
快適なポータブルトイレの使い方3選

ポータブルトイレを快適に使うためには、使いやすさだけでなく、安全性や気持ちの面にも配慮が大切です。
快適にポータブルトイレを使ううえで意識したいのは、以下3つのポイントです。
- 設置場所を意識して安全性を確保する
- 感染症やケガにつながらないよう衛生管理を徹底する
- 本人の意志を尊重しつつ声掛けと見守りをおこなう
それぞれ、どのように使えば良いのか解説します。
設置場所を意識して安全性を確保する
ポータブルトイレは、なるべくベッドの近くや移動距離が短い場所に設置しましょう。
ただし、部屋のドアの開閉や家具の動きの邪魔にならない位置を選ぶのがポイントです。
床に段差がある場合はマットを敷いてフラットにして、つまずきを防ぎます。
夜間は小さな照明を置き、暗がりでの動作を支えます。こうした対策が転倒防止に有効です。
感染症やケガにつながらないよう衛生管理を徹底する
使ったあとは、バケツや便座をしっかり掃除しましょう。
汚物を放置すると細菌や臭いが広がるため、排せつのたびに処理するのが衛生管理の基本です。
便座やフタを除菌シートでふき取る習慣を付けると、清潔な状態を保ちやすくなります。
また、除菌シートや消臭剤、防水マットなどを活用すると、臭いや菌の繁殖の予防につながります。
汚物を放置すると細菌や臭いが広がるため、排せつのたびに処理するのが快適なポータブルトイレ利用のポイントです。
定期的な換気も忘れずにおこない、清潔な環境を保ちましょう。
本人の意志を尊重しつつ声掛けと見守りをおこなう
排せつは、プライベートでデリケートな行為です。
本人の気持ちに寄り添い、できることは本人に任せ、難しいところだけやさしくサポートするようにしましょう。
声かけのタイミングや言葉の選び方にも気を配るとより安心して利用できます。
高齢になると感覚が鈍る方も多いため、定期的に排せつの促しが必要です。バランス崩しが怖い方は背中を支え、付き添いで安心感を与えてください。
ポータブルトイレの使い方を押さえて安全で快適な介護生活を送ろう【まとめ】

ポータブルトイレは、高齢者や介助が必要な方の暮らしを支える、便利な福祉用具です。
自分でトイレに行く負担を減らせるうえ、夜間の転倒などの事故リスクも少なくなります。
ただし、掃除や臭い対策をおろそかにすると、部屋の環境に悪い影響を与える場合があります。
快適に使い続けるためには、設置場所をしっかり考えたり、使い捨てグッズを上手に活用したりする工夫が必要です。
今後、ポータブルトイレを使う予定の方は本記事を参考に、配置場所や捨て方などをシミュレーションしてみてください。
ポータブルトイレの使い方に関してよくある質問
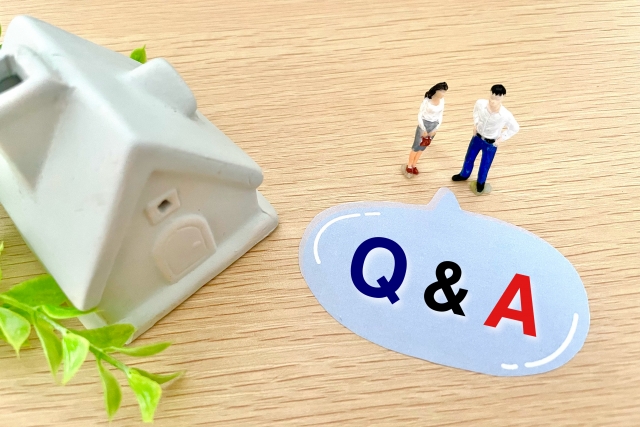
最後に、ポータブルトイレの使い方に関してよくある質問に回答します。
ポータブルトイレの中身はそのまま捨てても良い?
そのまま捨てるのはNGです。
とくに大便の場合は、自治体によって「燃えるごみ」として出せるかどうかが異なります。一般的には、処理袋や消臭シートを使って密封した状態で廃棄するのが望ましい方法です。
自治体によって分別方法や処理のルールが違うため、ごみ収集のルールがわからない場合は、お住まいの市区町村の窓口に相談しましょう。
不適切な処理を避けるためにも、正しい分別・処理の徹底が大切です。
バケツに入れる水の量はどのくらいが適切?
バケツの底が隠れるくらいの少量で十分です。
水を入れすぎると重くなったり、もち運ぶときに中身がこぼれやすくなったりする場合があります。水の量は、こびりつき防止になる程度が適量です。
なお、バケツに目安の水量ラインがある製品も増えてきています。心配なときは、取扱説明書で確認すると安心です。
ポータブルトイレは保険適用になりますか?
条件を満たせば、介護保険の対象になる場合があります。
要支援・要介護の認定を受けている方は、ポータブルトイレが福祉用具貸与(レンタル)や特定福祉用具販売の対象になるケースがあります。
保険が適用されると自己負担が軽くなる可能性はありますが、制度や条件は自治体ごとに異なるので、最新情報を確認しましょう。
確認する際には、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談するのが効率的です。
関連記事:「福祉用具」について
監修者 日本介護福祉教育学会 城田 忠
大阪青山大学介護福祉別科准教授。介護教育と介護留学を専門とし、外国人留学生の介護福祉士国家試験の合格率向上や日本語教育に関する研究を行い、介護福祉業界の発展に貢献。











