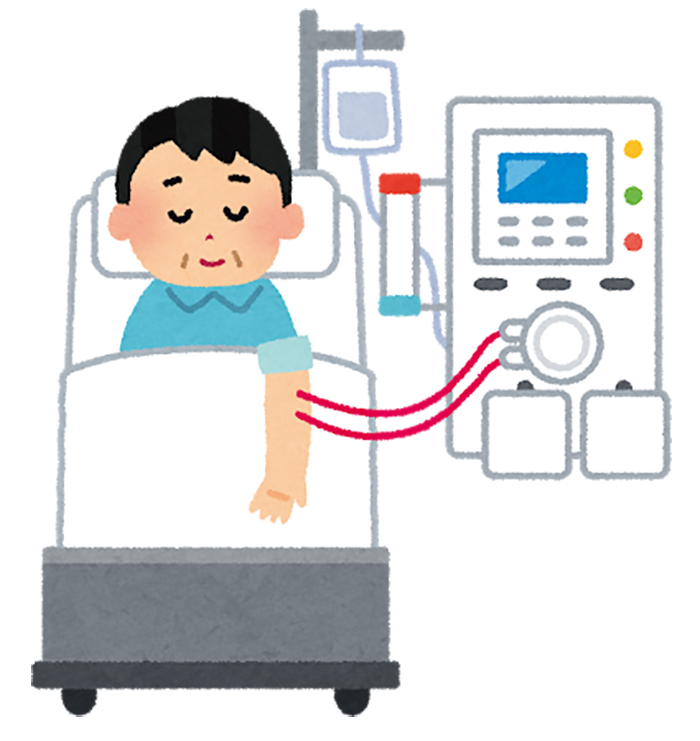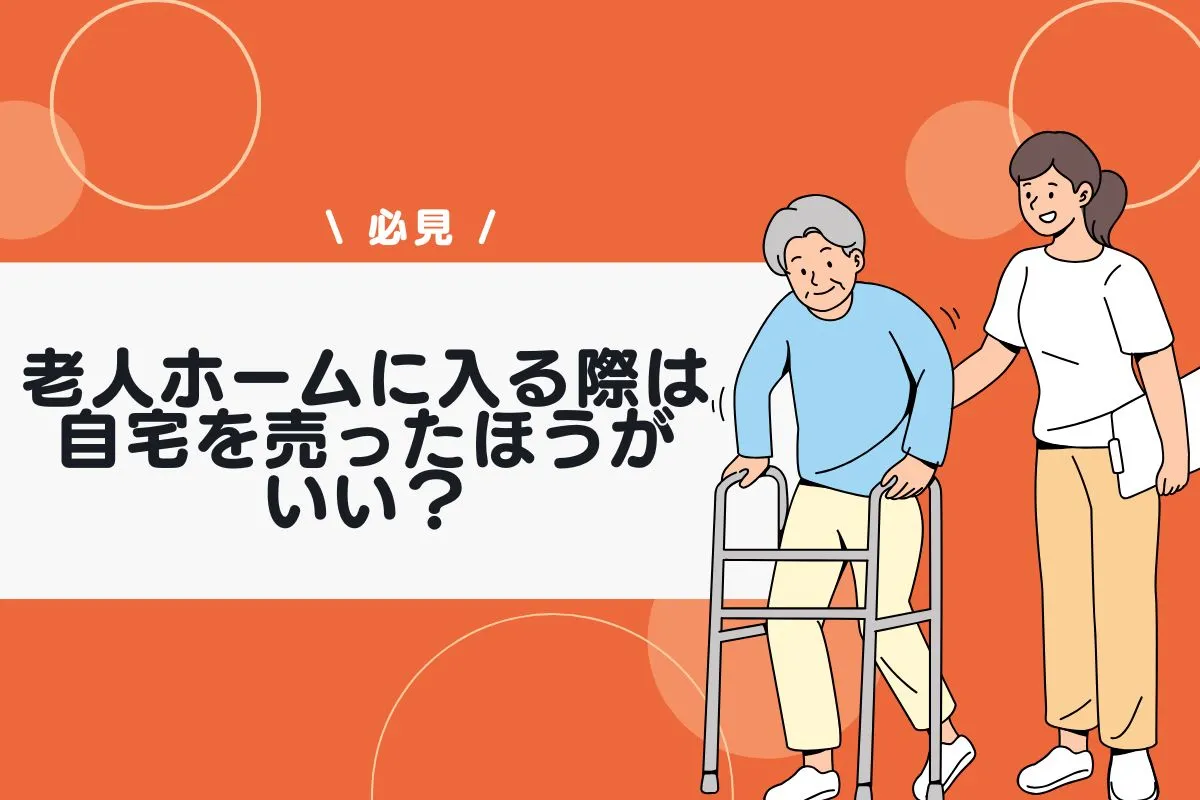老人ホームなどの介護施設に入所する際、万が一に備えて「身元引受人」を求められる場合があります。
しかし、身元引受人とは具体的にどのような役割を担うものなのでしょうか。
本記事では、家族の介護施設入所を検討中の方が知っておきたい身元引受人の概要や、もし引き受け手がいない場合の方法について解説します。
今後家族が介護施設に入所する可能性がある方は、ぜひ事前にチェックしておいてください。
介護における身元引受人とは

介護施設を利用する際に、多くの老人ホームでは「保証人」や「身元引受人」の指定を求めます。
施設側が対処しきれない事態が起きた際は、身元引受人に残務処理や入所者のサポート、あるいは連絡・相談先として対応してもらえる体制を整えるのが目的です。
以下では、身元引受人がどのような役割を担うのかを解説します。
身元引受人はトラブル対応時の対応をおこなう
身元引受人とは、簡単に言えば施設が対処しきれない事態が起こった際に連絡を受け、必要な手続きや対応をおこなう人です。
老人ホーム入所時に保証人や身元引受人を求められる理由は、料金支払いがストップした場合やトラブルが発生した場合に対応できる体制を整えるのが目的です。
高齢者をケアする場ではいつ何が起こるかわからないため、リスク管理が欠かせません。
とくに、入所者が施設で亡くなったときの連絡調整や、遺体引き取りなどは施設だけでは処理しきれないのが一般的です。
関連記事:老人ホームの費用が払えない!原因から対処法まで解説
老人ホーム入所の身元引受人と保証人は違う
身元引受人とよく混同されがちなのが「保証人」です。
保証人は契約者(入所者)の支払いが滞ったとき、施設側から費用を請求される連帯保証人として、契約者の支払い債務を肩代わりする役割を担います。
もし施設利用料が滞納された場合は、保証人が金銭トラブルを解決しなければいけません。
一方、身元引受人の役割は、入所者が亡くなった場合の対応や施設内でのトラブル時の窓口など、主に連絡・事務的な手続きの対応です。
なお、施設によっては両者を同一人物にする場合もあり、それぞれ別々で必要とされるケースもあります。
身元引受人のデメリットは手続きの多さ
身元引受人を引き受けると、さまざまな手続きが負担として押し寄せてくる可能性があります。
入所者本人が認知症などで意思判断ができない場合には、医療方針やケアプランへの同意も代理でおこなう必要があります。
さらに、亡くなった際の遺体の引き取りや葬儀の手配、施設利用料や医療費の清算など、多岐にわたる業務を負うのも、身元引受人を担当するデメリットと言えるでしょう。
また、施設と連帯保証契約を合わせて求められる場合には、利用料の支払い責任まで背負うケースは珍しくありません。
こうした負担を正しく理解した上で、身元引受人を引き受けるのが、今後のトラブルを回避するポイントです。
老人ホーム入所時の身元引受人になれる人

誰が身元引受人になれるかは、入所する老人ホームごとに条件が異なります。
多くの場合は、入所者と近い関係にある家族や親族が身元引受人とされるのが一般的です。
以下では、身元引受人になれる人の特徴や、求められる要件について解説します。
基本的には入所者の親族が身元引受人になる
多くの場合、入所者と近い関係にある家族や親族が身元引受人として求められるのが一般的です。
身元引受人には、入所者が突発的に入院する事態や、施設でのトラブル時にも連絡を取りやすい点が求められます。
ただし、施設によってはそのためすぐに駆けつけられる距離に住んでいる条件を優先する施設も少なくありません。
親族が多忙や遠方暮らしで難しい場合は、知人や友人でも身元引受人になれる場合もあります。
もし「自分以外でも大丈夫なのか」「離れて暮らす自分より近所に住む家族のほうが適任なのでは」と悩んでいるのであれば、まずは施設に相談して要件を確認してみましょう。
身元引受人自身にも一定以上の収入を求められることもある
施設のなかには、身元引受人自身に一定水準以上の収入や支払い能力を求める場合もあります。
年収や支払い能力を求めるのは、金銭保証を含む契約を結ぶ場合、連帯保証人としての責任を果たせるかどうかを確認するためです。
老人ホームの利用は長期的な契約になりやすいため、施設側は万が一の金銭的リスクを考慮しなければいけません。
ただし、求められる収入は施設によって異なります。「年収○○万円以上」といった明確なラインを設けているところもあれば、ざっくりと収入証明を提示すれば良い施設も存在するため、具体的にいくらという基準は定まっていません。
事前に収入に関する要件を施設に確認しておくと、家族内で誰が身元引受人になるべきか検討しやすくなります。
身元引受人は高齢では断られることもある
高齢の方が身元引受人として登録を希望しても断られる場合があります。
たとえば入所者よりも高齢だったり、65歳を超えていたりする場合は、逆に身元引受人側の体調リスクが考慮されるためです。
施設側としても、連絡したら確実に対応してもらえる人を求めるため、年齢制限を設けるところも珍しくありません。
最終的には施設の方針や独自基準によりますが、家族内で協力できる人がいるのであれば、年齢や体力的な余裕がある方を選びましょう。
関連記事:老老介護とは?知っておくべき原因や問題点、解決策について
身元引受人がいないときでも入所できる3つの方法

入所者本人の状況や家庭事情によっては、身元引受人を用意できないケースもあります。
しかし、身元引受人を立てられない方でも、老人ホームに入所可能です。
以下では、身元引受人がいない場合も介護施設に入所できる、3つの方法をお伝えします。
それぞれメリットや費用負担などが異なるため、自分に合った方法を選ぶ参考にしてください。
身元引受人が不要の老人ホームを探す
身元引受人を立てなくても入所できる介護施設は、一定数存在します。
一部の施設では、事前に一定額の保証料や預り金を支払えば、保証人を立てなくても身元引受人を立てずに入所可能です。
ただし全国的にも身元引受人不要の介護施設は少ないため、近隣で見つかるとは限りません。
身元引受人を立てずに老人ホームに入所したい場合は、インターネットや地域包括支援センター、ケアマネジャーなどに相談しながら、条件に合った施設を探すのが現実的です。
成年後見制度を利用して後見人を立てる
入所予定者自身の判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用を検討するのもひとつの方法です。
法定後見制度は家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や契約手続きを代わりにおこなう仕組みです。法定後見人が付けば金銭管理や契約行為などを代理してもらえるため、身元引受人の役割を一部は対応してもらえます。
後見制度は任意後見制度と成年後見制度のふたつがあり、任意後見制度は、本人が十分に判断能力があるうちに自分で後見人を選任する仕組みです。
本人の意思抜きで定められた成年後見人の場合は、医療方針や看取り対応など、すべての場面で身元引受人の役割を代行できない点に注意しましょう。
後見人制度を利用する際は、事前にどこまで対応可能かを確認してから制度の利用を進めてください。
身元引受人の代行保証会社を利用する
身元引受人や保証人が見つからない場合には、保証会社に依頼する方法もあります。
賃貸契約で目にする機会が多い保証会社ですが、老人ホーム入所時の身元引受人代行をおこなうサービスを提供している企業も存在します。
対応範囲は保証会社によってさまざまであり、支払い保証だけでなく、施設とのやり取りや書類手続き、入院・死亡時の対応など、幅広くサポートしてくれるプランまで対応している保証会社も少なくありません。
もちろん一定の費用はかかりますが、どうしても身近に頼れる人がいない場合の選択肢として有力候補になるでしょう。
身元引受人は任される役割を把握してから引き受けよう

老人ホームに入所する際、身元引受人の選定は多くの施設で必須とされています。
ただし、実際に身元引受人になる人は、多くの手続きや負担を一手に担わなければいけません。
もし依頼された場合は、責任の範囲や施設側から求められる対応の内容をしっかりと確認した上で慎重に引き受けるのも、身元引受人の役割です。
身元引受人を立てられない場合も諦めず、身元引受人不要の施設や成年後見制度、代行保証会社などの利用を検討してください。最終的に「誰がどの役割を担うのか」を家族間でよく話し合い、困ったときは早めに専門機関や施設へ相談するようにしましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。