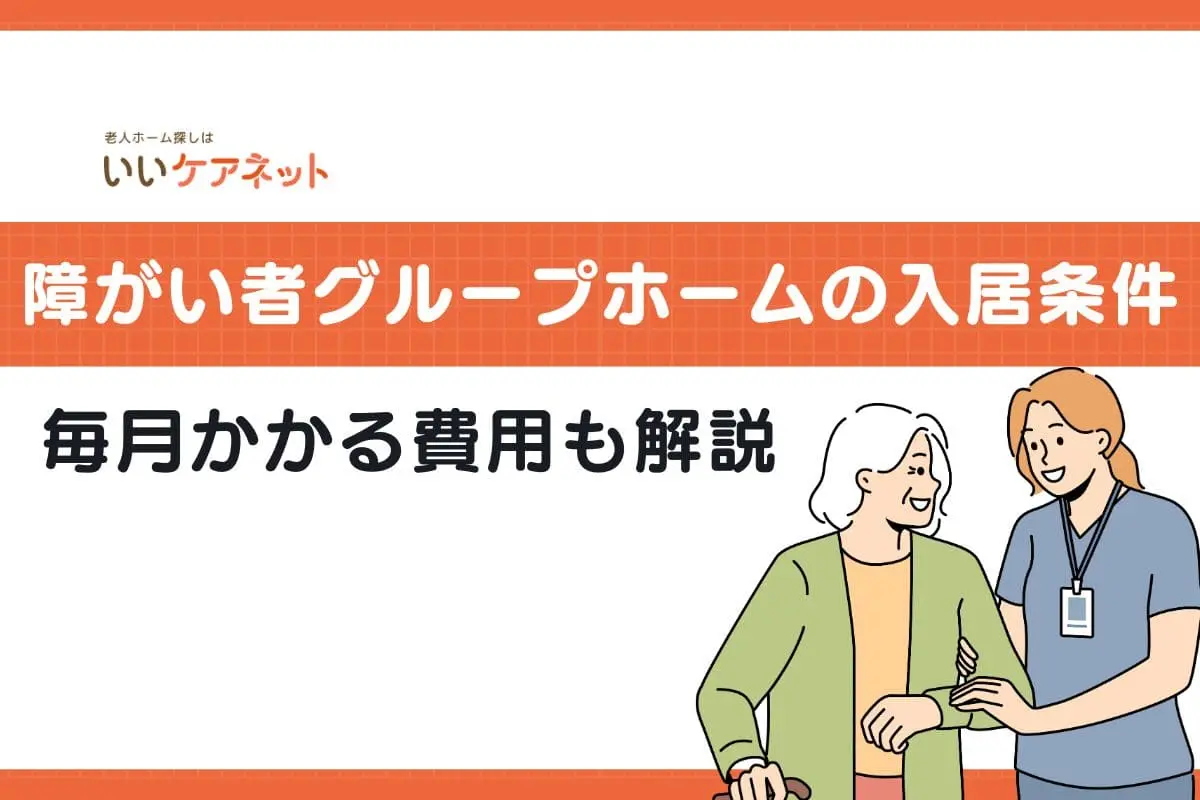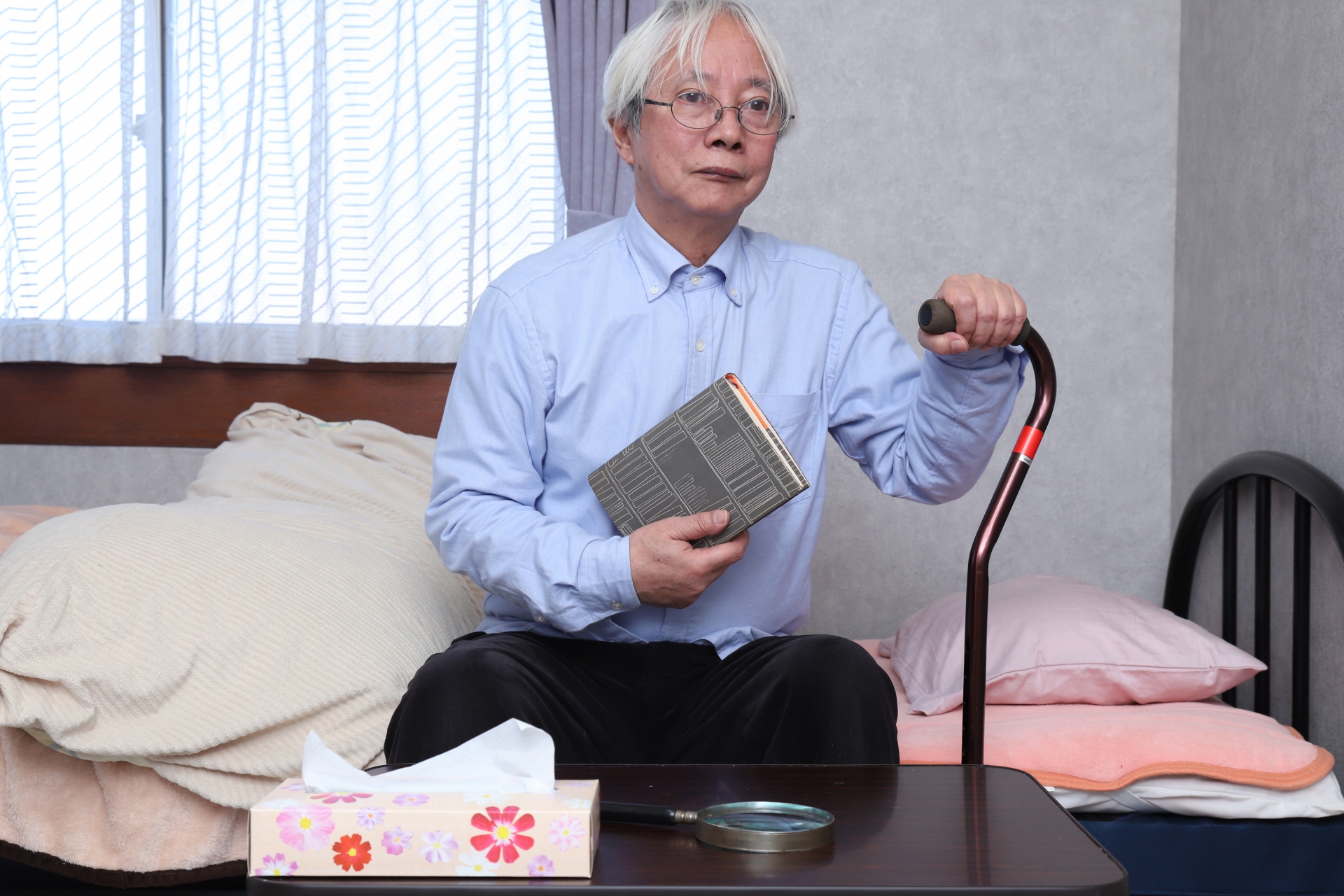「親が施設に入るときにすることを知りたい」「空き家になる実家はどうするべき?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
親が施設に入ったらすることは、実家をどうするか決める・相続対策を始めるなどさまざまです。
空き家の実家があると、固定資産税や管理費がかかり金銭的な負担になります。
この記事では、親が施設に入ったらすることや、実家の売却方法やメリット・注意点を解説します。
親が施設に入ることになり、なにをしたら良いかわからないと悩んでいる方は読んでみてください。
親が施設に入ったらすることは主に5つ

親が施設に入ったらすることは、下記の5つです。
- 実家をどうするか決める
- 住民票の異動を検討する
- 施設にかかる費用の支払いができるか確認する
- ケアマネジャーに連絡する
- 相続対策を始める
この章を参考にして、一つずつ準備を始めましょう。
実家をどうするか決める
親が施設に入る場合は、実家をどうするのか決めましょう。主な選択肢は以下のとおりです。
- そのままにしておく
- 家族が住む
- 売却する
- 賃貸や駐車場として運用する
実家をそのままにしておくと、思い出の場所としていつでも帰れます。
しかし、実家を利用する機会が少ないと空き家問題や空き巣被害のリスクがあるのです。(文献1)
警察庁によると、令和5年の空き巣被害は1日あたり約48件起こっていると報告されており、被害に遭うリスクは少なくないといえるでしょう。(文献2)
空き家問題や空き巣被害を予防する方法には、家族が住む手段があります。家族が住むと家が傷まずに済むメリットもあるのです。
家族が実家に住まない、遠方で管理が難しい場合は、売却や賃貸・駐車場運用などの方法も一つの手段です。
売却する場合は、親が認知症を発症すると、簡単に手続きできなくなります。親が施設に入ることになったら、家族で実家をどうするのか話し合っておきましょう。
住民票の異動を検討する
親が施設に入ったときは、住民票を異動するか検討しましょう。住民票に記載されている住所に自宅がある場合は、必ず異動する必要はありません。
また、介護老人保健施設やショートステイで老人ホームを利用する場合は、一時的な住まいのため、住民票を異動できない点には注意してください。
住民票の異動には、メリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|
|
介護保険料については、自治体によって保険料が異なります。
自宅から介護施設に住民票を異動するケースでは、今まで住んでいた市町村が引き続き保険者となる「住所地特例制度」を利用できるため、保険料は変わりません。(文献3)
家族の自宅に住民票を異動するケースでは、保険料が変わる可能性があるため、気になる方は自治体に問い合わせましょう。
施設にかかる費用の支払いができるか確認する
施設にかかる費用は、老人ホームの種類によって異なります。たとえば、特別養護老人ホームの場合は月に約10万円です。
有料老人ホームでは、施設によって費用が異なり、月に約15~30万円程度かかります。親の資産によっては、施設の費用が払えず家族の負担になることもあるでしょう。
厚生労働省によると、平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳と報告されています。(文献4)
平均寿命をもとに、今後どれくらいの期間を施設で生活するのかできる限り予測し、費用の目安を逆算しておきましょう。
施設ごとの費用については、下記で解説しているため、気になる方は参考にしてください。
関連記事:介護費用や介護報酬、本人負担額について
ケアマネジャーに連絡する
要介護認定を取得している方が、自宅から特別養護老人ホームなどの施設に入居する際は、担当のケアマネジャーに連絡しましょう。
ケアマネジャーは、要介護認定者が介護サービスを利用するための「ケアプラン」を作成しています。
よって自宅から施設に入居するときは、ケアマネジャーと連携し、ケアプランの変更を進める必要があります。
もし親の施設入居にあたり不安なことや疑問点がある場合は、このタイミングでケアマネジャーへ相談しておくと安心です。
相続対策を始める
親が施設に入ったときは、相続対策も始めましょう。
万が一があったときの対策が不十分の場合、親族が揉める原因になる可能性があります。
実際に、令和5年に遺産トラブルで裁判に発展した件数は、約1万4,000件と報告されています。(文献5)
金額にかかわらず、親が遺したお金や資産をどう配分するのか、家族で事前に話し合っておくと、良好な関係性を保てるでしょう。
実家の売却方法は3種類

実家の売却方法は、下記の3種類です。
- 本人が不動産業者と連絡を取る
- 子どもが代理で手続きをおこなう
- 成年後見制度を利用する
実家を売却するにあたって、「どのように売却すれば良いのか分からない…」と悩んでいる方は少なくありません。実家の売却方法について見ていきましょう。
本人が不動産業者と連絡を取る
実家の所有者が親の場合は、本人が不動産業者と連絡を取り、売却の手続きをおこなう方法があります。
親自身が手続きをおこなえると、本人の意思を不動産業者へ明確に伝えられたり、売却する相手を自分で選べたりと、納得できる売却につながります。
家族に売却を委任して「本当は売却したくなかった」など、売却後の家族トラブル予防にもつながるでしょう。
子どもが代理で手続きをおこなう
親が施設に入居しても子どもが代理で売却手続きをおこなう方法があります。
しかし、子どもが手続きを進めても、親に実家を売却する意思がなければ、売れません。
代理で手続きを始める前に親と相談して、売却の意思があるか聞いておきましょう。代理で売却手続きをする場合は、下記の準備が必要です。
- 委任状
- 印鑑証明書
- 親および子どもの本人確認書類
委任状には、物件の詳細や売却価格、代理人の権限について記載が必要です。委任状は不動産に用意してもらえるケースがほとんどです。
代理人の権限が記載されていない場合、売却時や売却後のトラブルを招く原因になるため注意しましょう。
成年後見制度を利用する
親が認知症であったり、なんらかの障害によってコミュニケーションを図れなかったりする場合は、成年後見制度を利用します。
親が認知症などで正常な判断ができないケースでは、委任状を作成して売却手続きをしても無効になるからです。成年後見人は家庭裁判所で選定してもらえます。
近くの家庭裁判所に申し立てをおこない、選任されてから売却の手続きを進めましょう。
しかし、成年後見制度の選任から売却するまでには、6カ月程度かかる点には注意しましょう。
実家を売却するメリット

実家を売却するメリットは、以下のとおりです。
- 施設の費用に充てられる
- 実家を管理する手間がなくなる
- 固定資産税や管理費の負担がなくなる
実家を売却しようか悩んでいる方は参考にしてみてください。
施設の費用に充てられる
実家を売却できると、老人ホームの費用に充てられます。親が施設の費用を事前に準備できているとは限りません。
入居する老人ホームによっては、費用が高額になるケースもあるのです。実家を売却すると、家族の金銭的な負担なく入居を続けられるでしょう。
実家を管理する手間がなくなる
実家を売却すると、建物や土地・郵便物を管理する手間や時間が不要になります。
遠方に住んでいたり、働いていたりすると、定期的に実家を尋ねて管理するのは負担になる可能性があります。
管理の負担を減らしたいと考える方は、実家の売却を親に相談してみましょう。
固定資産税や維持費の負担がなくなる
実家を売却できると、固定資産税や管理費の負担がなくなります。固定資産税は、実家に誰も住んでいなくても支払わなければいけません。
家族が実家に住んでいない場合、誰もいない家の固定資産税を支払うのは負担になるでしょう。
また、実家の管理を業者に任せたり、築年数が経過していると修繕のためにお金がかかったりするケースも少なくありません。
固定資産税や管理費は家計に負担となる可能性が高いため、親が老人ホームに入居する場合は売却しないか相談してみましょう。
実家を売却するときの注意点

実家を売却するときの注意点は、下記のとおりです。
- 親が施設を退去する可能性を考える
- 売却時にかかる税金や利用できる制度を調べる
実家を売却してから「家を売るんじゃなかった」と後悔したり、家族関係でトラブルになったりしないように参考にしてください。
親が施設を退去する可能性を考える
親が老人ホームに入居したことをきっかけに、実家を売却しようと検討している方は、親が施設を退去する可能性がないか考えましょう。
老人ホームに入居しても、さまざまな理由から退去するケースがあるのです。
たとえば「施設が合わなかった」「家族が介護できる状況になった(退職など)」「自宅でホームヘルパーを利用しながら生活するほうが合っていた」などの理由があります。
親が自宅に帰る方針になっても、実家を売却していると、新しく住む場所を探さなければいけません。
住み慣れた家でなければ「帰りたくない」とトラブルになる可能性もあります。
実家を売却する際は、退去する可能性がないか考えてから、手続きを進めましょう。
売却時にかかる税金や利用できる制度を調べる
実家を売るときは、売却時に発生する税金を理解しておきましょう。
不動産の売却では税金が発生する可能性がありますが、マイホーム特例を利用できると、3,000万円の利益までは税金がかかりません。(文献6)
実家を売却するときにかかる税金や利用できる制度を知っておくと、安心して手続きを進められるでしょう。
まとめ|親が施設に入ったらすることを理解して早めに行動しよう

親が施設に入ったらすることには、実家をどうするのか、相続対策を始めるなどさまざまです。
相続対策は家族で話し合いの機会が少ないと、いざというときにトラブルの原因になる可能性が高いです。
今回解説した内容を参考に、一つずつ取り組んでみてください。
いいケアネットでは、条件に合う施設を無料で探すサポートをしています。「親の施設を決めたけど、もう一度探したい」と悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
親が施設に入ったらすることについてよくある質問

特養の1カ月の費用はどれくらいですか?
厚生労働省によると特養の1カ月の費用は、約10~15万円です。費用は、入居する方の要介護度や、施設の環境により異なるため、入居前に確認しましょう。(文献7)
親を施設に入れる目安はありますか?
親を施設に入れる目安は、自宅での介護が難しくなった、認知症で徘徊や火の不始末などの症状が見られるようになったなど、家庭によりさまざまです。
無理をして親の介護を続ける必要はありません。「介護が負担になってきた、しんどい」と感じたときは、いいケアネットにご相談ください。
実家の片付けはいつから始めたらいいですか?
親が施設に入った実家の片付けは、売却すると決まってから始めましょう。施設に入ったときに始めると、外泊や退去したときにトラブルになるかもしれません。
実家の片付けについては、下記の記事で詳しく解説しているため、参考にしてください。
関連記事:老人ホーム入居時の不用品はどうする?買取・処分のススメ
施設に入ったら住所変更・世帯分離は必要ですか?
施設に入っても、住所変更や世帯分離は必ずおこなう必要はありません。
しかし、施設入居により、住民票の所在地の家を売却・賃貸運用する場合は、住民票の異動が必要です。
世帯分離をすると、介護にかかる費用が安くなるケースがあります。世帯分離については下記の記事で詳しく解説しているため、合わせて読んでみてください。
関連記事:世帯分離とは?メリット・デメリット、手続き方法をわかりやすく解説
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。