「前はこのような性格ではなかったのに」「何を言っても理解してもらえず、どうすれば良いのか」など、家族に認知症の方がいると不安を感じることも多いのではないでしょうか。
家族が以前と別人のようになったと感じると、どのように接したら良いかわからなくなるでしょう。認知症の方のなかには、「まだらボケ」と呼ばれるように、症状に波があるケースがあります。認知症の方が感じている世界を正しく理解し、思いやりのある接し方を心がけることで、お互いが安心して生活できるようになります。
今回は、まだらボケの方への正しい接し方や、具体的な状況別に対応の仕方などを説明するので、認知症の家族を持つ方はぜひ参考にしてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
まだらボケ(認知症)とは

まだらボケ(認知症)とは、名前の通り、認知症の症状がまだらに現れることです。まだらボケとは、血管性認知症やアルツハイマー型認知症のような認知症の種類ではなく、あくまで症状を表す言葉の一つです。
まだらボケの原因
まだらボケの原因として、以下のような身体の状態があげられます。
- 血管性認知症による脳へのダメージ
- 脳への血流の変化
- 自律神経の乱れ
- 体調不良
まだらボケの症状は、血圧が下がって脳への血流が低下するときに顕著に現れます。たとえば、起床直後や食後、寒い場所から暖かい場所への移動などは、血圧が下がって血流が変化するタイミングです。
ほかにも、自律神経の乱れによる意識の覚醒で認知症が一時的に悪化する場合もあれば、体調不良に関連して症状に波が出るケースもあります。
まだらボケの主な症状
まだらボケの場合、一日のなかで部分的に症状が現れるため、周囲を混乱させてしまうケースも少なくありません。まだらボケの主な症状は、以下の通りです。
- タイミングによって症状の程度に差がある
- 同じことができたりできなかったりする
- 短期記憶が低下する
たとえば、「朝は着替えていたのに夕方にはできなくなっている」「物忘れが増えたのに、判断力には低下が見られない」といった場合には、まだらボケが疑われます。
こうしたチグハグな様子は、認知症であるのか、単なる老化なのか家族の判断を遅らせる原因になります。
まだらボケの進行
連続的に進行するアルツハイマー型認知症と異なり、まだらボケの原因の一つである血管性認知症は、階段状に症状が進行するのが特徴です。
まだらボケの場合は、症状が急に悪化したり、改善したりするように感じられるため、患者本人や家族にとって予測がつきにくく、認知症が進行する過程がわかりにくい場合もあります。
認知症の種類と特徴について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART2】~認知症の種類・症状について~
まだらボケ(認知症)の方に対する接し方のポイント

まだらボケ(認知症)の方との接し方において、、何とかしてあげたい気持ちが強くなるほど、厳しく接してしまうことは誰にでもあります。
しかし、認知症の方が傷ついたり不快な気持ちになってしまったりしては意味がありません。接し方次第では、認知症の方が介護している家族を信頼できなくなってしまいます。
ここでは、まだらボケの方に対する接し方のポイントを解説するので、間違った対応で家族を傷つけてはいないか、確認してみてください。
1.きつい言葉かけを避ける
まだらボケの方を叱ることは、基本的にNGです。
認知症は、記憶などの知的機能が衰えても、感情の機能は衰えていません。認知症の方はなぜ叱られているのか原因がわからなくても、叱られていることだけは理解しています。
もし、理由もわからず急に大声で怒鳴られたら、誰でも嫌な気持ちになるのではないでしょうか。そして、何に対して怒られたのかの記憶は忘れても、不快な気持ちにさせられたことは覚えています。
まだらボケの方のなかで、このような嫌な気持ちが蓄積してしまうと、行動異常や妄想などが悪化して悪循環に陥ってしまいます。
2.放置しない
まだらボケの方にストレスを与えたり、放置したりするのもNGです。孤独感を感じてストレスが溜まってしまうと、大きな声を出して暴力的になるなど、不満が表面化します。認知症の方が孤独感や無力感を感じるようになると、まだらボケの症状が進行してしまう可能性もあるため、無視や放置は良くありません。
しかし、介護する側もストレスや疲れを感じている場合もあります。そっと手を握ったり、少しの声かけだけでも安心感を与えられるため、放置してしまわないよう心がけましょう。
3.機能の低下を理解する
まだらボケの方と接する際には、機能の低下に配慮が必要です。とくに、「脱水」と「便秘」の2つは、まだらボケの症状を悪化させる原因にもなります。脱水状態になると、身体の機能が正常に働かず、認知力や集中力が低下してしまいます。
そのため、まだらボケの方と接する場合は、こまめな水分補給と排便管理が大切です。認知症の方は水を飲むことを忘れがちなので、積極的に声をかけて水分補給を促し、定期的に便秘になっていないか確認しましょう。
4.本人の気持ちを理解して受け入れる
まだらボケの方が理解しがたい言動をするのは、何かしらの不安を抱えているためです。そのため、まずは本人が抱えている不安な気持ちを理解し、受け入れるようにしましょう。
認知症が進行すると、記憶が曖昧になり、日々の出来事や周りの人たちに対して混乱するようになります。このような不安を感じている認知症の方に対し、否定的な態度を示したり内容を訂正したりするのは逆効果です。
まだらボケの方の言動は、否定せずに共感することが大切です。相手の気持ちを理解し、穏やかに受け入れることで、信頼関係が築かれて安心感を与えられます。
5.本人のペースに合わせる
まだらボケの方に対する接し方のポイントとして、本人のペースに合わせることは非常に重要です。たとえば、無理に訓練させたり、部屋を模様替えしたりするなど、無理強いや急な環境変化はストレスの原因になります。
まだらボケの方と接する際は、まず認知症の方がリラックスして過ごせるよう、できるだけ本人のペースに合わせてください。また、普段から家族を含めて周囲の人間関係を良くしておくと、安心できます。
6.スキンシップやアイコンタクトを増やす
まだらボケの方と接するときは、言葉以外のコミュニケーション(バリデーション)も積極的に使用するのがポイントです。スキンシップ(肌の触れ合い)やアイコンタクト(目を合わせる)によって、認知症の方は安心感を覚えて、心を穏やかに過ごせるようになります。
会話をするときは、目線を合わせるようにして、優しく微笑みながら話をしましょう。また、手を握ったり肩に手を置いたりすると、温かさを伝えられます。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。認知症の方の介護でお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。
【状況別】まだらボケ(認知症)による行動異常への対処法
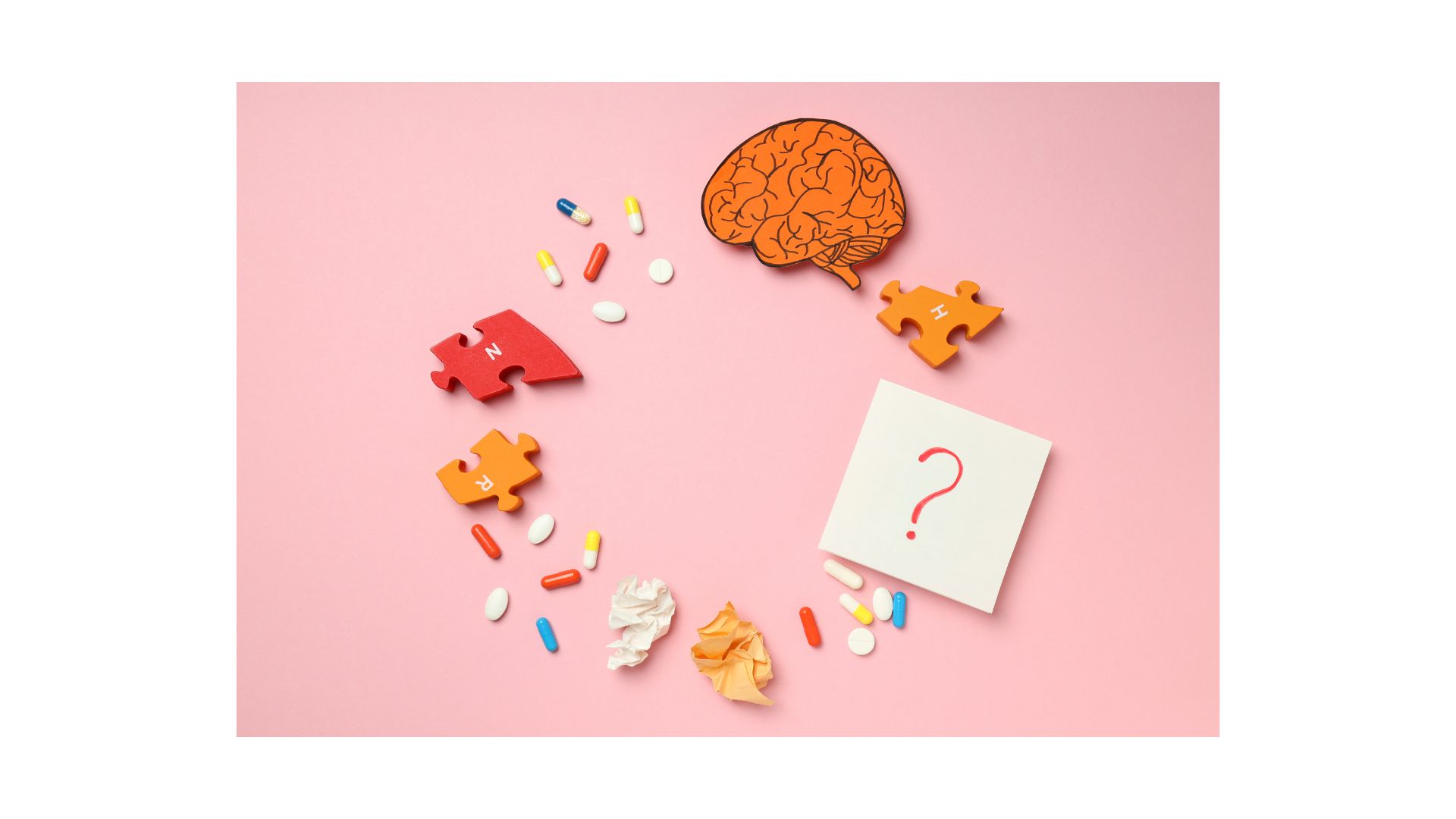
認知症の症状として、まだらボケの方には以下のような行動が見受けられます。
- 同じことを繰り返し何度も話す
- 物盗られ妄想や人物誤認をする
- 徘徊する
- 攻撃的になる
以下で、状況別の対処法を解説するので、ぜひ参考にしてください。
同じことを繰り返し何度も話す場合
まだらボケの方が同じ話を繰り返すのは、話したこと自体を忘れているためです。本人は、同じ話を繰り返しているつもりはまったくありません。
この場合は、話題を変えたり、一度言っていることを受け入れてから話をそらすようにしてみましょう。たとえば、ご飯を食べたばかりなのに、「ご飯はまだか」と何度も尋ねてきたときは、「さっき食べたでしょ」と否定してはいけません。「今支度しているから待ってね」と一度受け入れ、温かい飲み物やおやつなどを渡すと効果的です。
物盗られ妄想や人物誤認をする場合
身近な家族に「物を盗られた」と妄想してしまうのは、「頼りたいけれど頼りたくない」といった相反する気持ちの表れであるといわれています。この場合も、もちろん否定や叱ることはNGです。「物がないのであれば、一緒に探そうね」と、本人が納得するような対応をして、心を落ち着かせることが大事です。
一方、「人を間違える」といった人物誤認は、叱られたことがきっかけで起こりやすく、叱ってきた相手を知らない人にしたい思いがあるからだと考えられます。親しい人に「あなたは誰」と尋ねられるのはつらいですが、あまり真に受けず、違う話題を振ったり、距離を置いてみたりしましょう。しばらくすると、突然名前を思い出す場合があります。
徘徊する場合
まだらボケの方が目的もなく外で歩き回ってしまうのは、自分の居場所がわからなくなったり、外出した目的自体を忘れてしまったりするためです。認知症による徘徊がみられる場合は、衣服や帽子など身に着けているものに名前や連絡先を記入しておきましょう。
また、近所の人と良い関係性を築いておくと、認知症の方が徘徊しているのに気づいたタイミングで声をかけてもらえるなど、本人が状況を理解する助けになります。なかには、普段から近所の人に声をかけてもらっているうちに安心し、徘徊しなくなったケースもあります。
認知症による徘徊の対処法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:認知症による徘徊の理由とは?認知症の症状から対策まで解説!
攻撃的になる場合
まだらボケの方が攻撃的になるのは、介護者のおこないによって攻められているように感じたり、気持ちをうまく言葉で表せなかったりするためです。自分が攻められていると感じ、抵抗するため、攻撃に出てしまうのです。
この場合も、認知症の方を叱ったりはせずに、気持ちを落ち着かせるようにしましょう。それでも興奮が収まらない場合は、何を言っても逆効果になりかねません。一旦距離を置き、危険な行動をしないか見守るようにしてください。
まだらボケ(認知症)の方への接し方に悩んだら専門家への相談がおすすめ

まだらボケの方に対する接し方において思いやりは大切ですが、どれほど工夫していてもうまくいかない場合があります。無理に気持ちを押し殺して我慢したり、自分を責めたりしてはいけません。
介護者の心身が壊れてしまったら、認知症の方にとっても幸せなことではありません。家族だけで限界を感じたときは、介護疲れや介護うつになる前に、第三者や専門家に頼ることが大事です。
認知症に関する悩みは「地域包括支援センター」へ相談してみましょう。地域包括支援センターは介護や福祉に関する総合相談窓口で、保健師や看護師、ケアマネジャー、社会福祉士などの専門職が在籍しており、適切なアドバイスをもらえます。
病院にかかっている場合は、医療ソーシャルワーカーが相談に乗ってくれる場合もあるので、主治医や看護師に尋ねてみてください。ほかにも、「認知症サポーター」と呼ばれる認知症を正しく理解し支援してくれる地域ボランティアの方、ご近所の方、家族会などを頼ってみてください。
認知症に関する相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART3】~認知症に関する相談先まとめ~
老人ホームでの認知症ケアでまだらボケが改善する場合もある

まだらボケの家族を介護する時間がない方は、老人ホームへの入居を検討するのも一つの方法です。老人ホームでは、ほかの入居者の方や施設スタッフなど、多くの方と交流できるため、人間関係が広がり活き活きと生活しやすくなります。
また、老人ホームでは、以下のような認知症ケアも受けられます。
- 昔のことを思い出させる「回想法」
- 植物や野菜を育てながら心身の機能の衰えを防ぐ「園芸療法」
- みんなで歌を歌ったり、音楽を聴いたりしてストレスを軽減させる「音楽療法」
老人ホームでは、認知症に用いられる療法を、普段の生活にも取り入れています。また、老人ホームなら24時間体制で見守ってもらえるため、徘徊などの心配もなく安心です。
なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。老人ホームへの入居を検討している方は、ぜひ気軽にご相談ください。
認知症ケアについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:認知症ケアで大切な4原則とは?基礎とパーソンセンタードケアの考え方
まだらボケ(認知症)の方の気持ちを想像して適切に対応しよう【まとめ】

大切な家族が認知症になると心配ですが、最も不安を感じているのは認知症を発症した本人です。何をやっても今までのようにうまくいかず、焦りや不安を感じています。
周囲はまだらボケは病気だと理解し、手を差し伸べることが必要です。不安な気持ちを受け入れ、心に寄り添うようにしましょう。
ただし、甘やかしすぎも良くありません。基本的な接し方として叱るのはNGですが、本人や周囲の人の命に係わるような危険な行動をしてしまったときは、厳しく伝えることも必要です。認知症の方に対して思いやりを持ち、臨機応変な対応をしましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。











