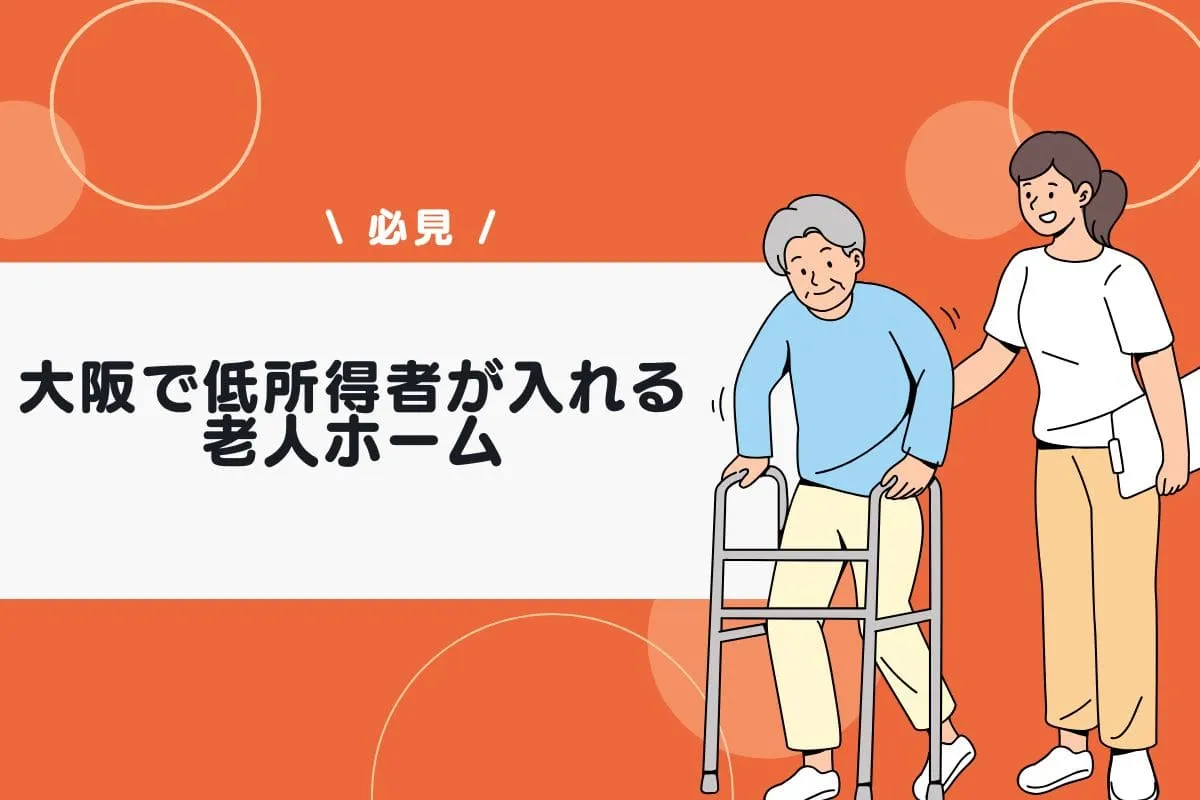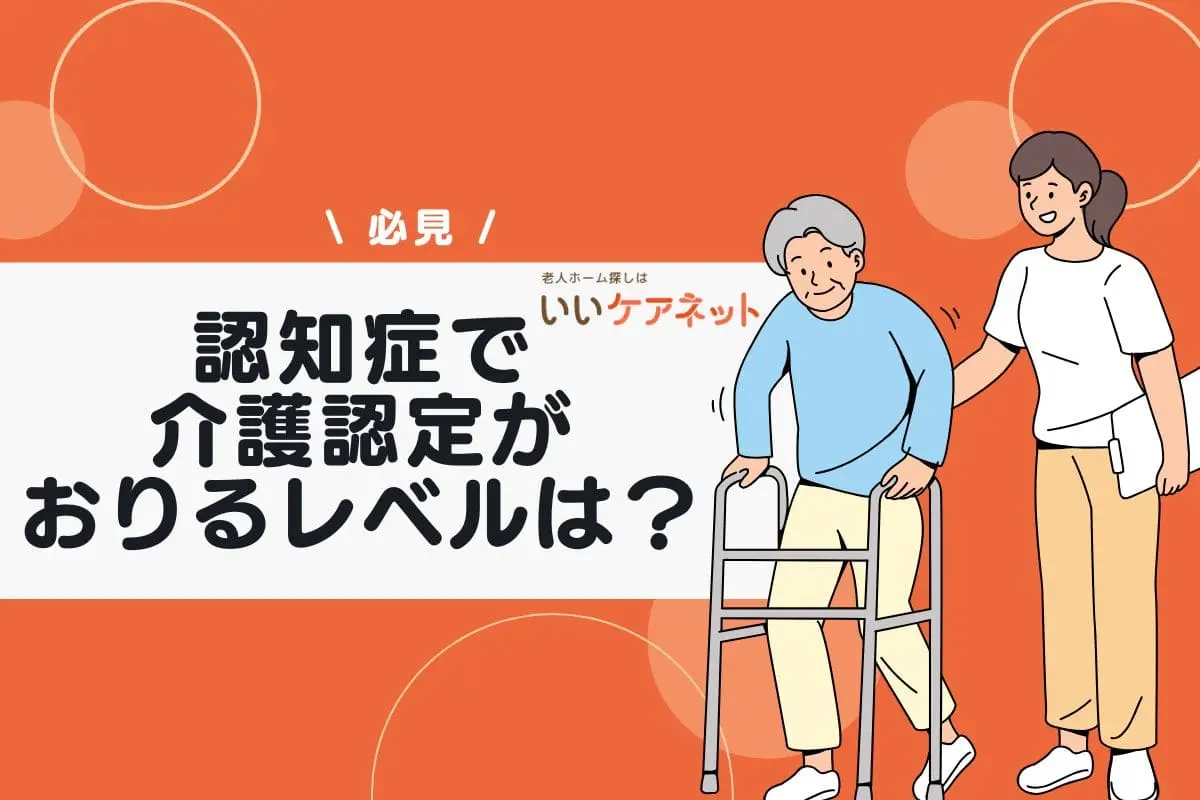「親の介護と仕事の両立が限界……」
「経済的な不安はあるけど退職すべき?」
親の介護でこのように悩む方は多いのではないでしょうか。
親の介護で退職するかを迷っているなら、まず支援制度を確認しましょう。
実は介護休業制度や介護休暇を活用すれば、収入を確保しながら介護に取り組める可能性があります。
本記事では介護離職のメリット・デメリットから支援制度、失業保険の受給方法まで解説します。
親の介護のためとはいえ、退職に後悔しないようにポイントを押さえましょう。
親の介護で退職している人の現状

親の介護を理由に離職する方が年々増えています。厚生労働省の調査によると、介護・看護を理由に離職した人は年間約10万人です。
介護離職の代表的な理由には「介護と仕事の両立が保ちにくい職場環境」や「介護と仕事の両立は精神的な負担」などが挙げられます。
また、総務省統計局の調査結果によると、介護を理由に離職した方の約8割は女性です。しかし近年は、男性の介護離職も増加傾向にあります。
総務省統計局の「令和4年就業構造基本調査」をベースにした「介護離職の社会的損失研究」によると、介護離職後は前職が正規雇用だった介護離職者のうち就業を再開した方のうち、正規雇用として就業を再開できた割合は45.6%にとどまり、半数以下でした。正規雇用から正規雇用以外として就業を再開した場合の賃金下落率は6割以上に達しています。
年齢が高くなるほど賃金の減少率は大きくなり、55-64歳の場合は55.1%もの収入減少していると明らかになりました。
このように、介護離職後は咳雇用、非正規雇用を問わず、再就職の難しさを感じる現実に直面しやすいです。
親の介護で退職するメリット

親の介護のための退職により、得られるメリットがいくつかあります。
主なメリットは以下の3つです。
- 介護に集中し、より質の高いケア・対応を提供できる
- 仕事と介護の両立から解放され、精神的ストレスが軽減する
- 委託していた外部サービスの介護費用を削減できる
まず、介護に集中できる時間的余裕が生まれ、親の状態に合わせた柔軟なケアが可能になります。病院への付き添いや緊急時の対応もスムーズになり、より質の高い介護を提供できるでしょう。
また、仕事と介護における二重の負担がなくなり、精神的・身体的ストレスが軽減します。常に仕事と介護の板挟みになっていた状態から解放され、自分自身の健康を維持しやすくなります。
さらに、介護施設やヘルパー利用などの外部サービスへの依存度が下がり、介護費用を一部削減可能なケースが多いです。親の希望に沿った在宅介護を実現しやすくなるメリットも考えられます。
親の介護で退職するデメリット

介護のために退職する場合、そのデメリットも理解しておきましょう。
主なデメリットは以下の3つです。
- 収入がなくなる
- 再就職が困難になる
- 介護の悩みを一人で抱えやすくなる
最大のデメリットは収入がなくなり、経済的な不安が生まれる点です。
また、長期的なキャリアにも影響し、介護が終わった後に再就職するのが難しくなる可能性があります。
とくに40代以降では年齢的なハンディもあり、元の職場や同条件での再就職は困難となるケースが多いです。
さらに、社会とのつながりが減り、介護の悩みを一人で抱え込みやすくなり、孤立や介護うつのリスクも高まります。
職場での人間関係が精神的な支えになっていた人も少なくありません。
また、介護サービスを使わずに一人で介護を担うと、自分の時間がなくなり、介護者と被介護者が共依存状態になって、共倒れに陥る危険性もあります。
親の介護で退職する前に知っておくと良い制度
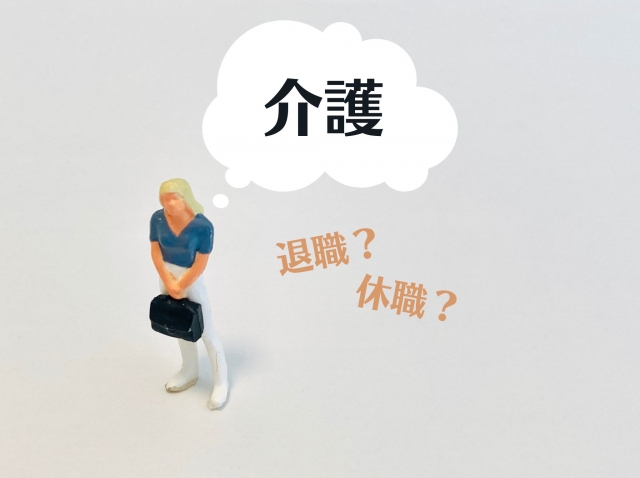
介護と仕事を両立するための制度が3つあります。
- 介護休業制度
- 介護休暇制度
- 短時間勤務制度
親の介護で退職する前に自分の状況に合った制度を把握し、退職せずに済む可能性を広げましょう。
介護休業制度
介護休業制度は、要介護状態の家族を介護するために一定期間仕事を休める制度です。
対象家族1人につき通算93日まで取得でき、3回まで分けて取得できます。
休業中は「介護休業給付金」として、休業開始時賃金の67%が支給されるため、大きな収入減を避けながら介護に集中可能です。
さらに、雇用関係を保ったまま介護に取り組める点や、原則として元の職場に復帰できる点も大きなメリットといえます。
介護が必要になった初期段階や、一時的に集中的なケアが必要な時期などに有効な制度です。
基本的に申請は休業開始の2週間前までに会社へ申し出る必要がありますが、詳細は自社の就業規則を確認しましょう。
参考:厚生労働省『介護休業とは』
介護休暇制度
介護休暇制度は、要介護状態の家族の通院付き添いや手続きなど、短期間の介護に使える制度です。
家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得できます。
2021年の法改正で時間単位での取得ができるようになり、半日だけ休みたい場合などにも柔軟に対応可能です。
原則として無給ですが、企業によっては有給になるケースもあります。事前に就業規則を確認しましょう。
介護休業とあわせて使うと、状況に応じた介護がしやすくなります。短時間の対応が必要な場面でとくに役立つ制度です。
参考:厚生労働省『介護休暇とは』
短時間勤務制度
短時間勤務制度は、要介護の家族がいる場合に1日の勤務時間を短縮でき、介護の時間を確保しやすくなる制度です。
フレックスタイム制度を使えば、始業・終業時間を自由に決められるため、家族の状況に合わせた働き方を実現可能です。
時差出勤制度では勤務時間は変えず、出勤・退勤時間だけを調整できます。
また、在宅勤務制度を活用すれば通勤時間を削減でき、その時間を介護に充てられるのも利点です。
これらの制度は介護が必要な期間中、上限なく利用できるため、長期的に介護と仕事を両立したい人にとって大きな支えになるでしょう。
参考:厚生労働省『短時間勤務等の措置とは』
親の介護による退職を後悔しないために

親の介護のためとはいえ、退職して後悔するケースは少なくありません。
少しでも後悔のない退職をめざすためには、3つの対策を事前におこなうのがポイントです。
- 介護サービスの利用を検討してみる
- 悩みを周囲の人に打ち明ける
- 第三者に相談する
具体的に、どのような点を意識すべきかを見ていきましょう。
介護サービスの利用を検討してみる
退職を決断する前に、介護サービスの利用を検討してみましょう。
訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護保険サービスを利用すれば、介護の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
家族を介護施設に入居させるのも選択肢のひとつです。このとき、家族を施設に預ける考えに罪悪感を抱く方もいるでしょう。
施設に預けることは、決して「見捨てること」ではありません。「プロと共に支える」という介護の形です。
介護施設への入所を検討したい方は、大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」をぜひご活用ください。あなたやご家族の希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。
関連記事:親を施設に入れる罪悪感がある方必見!葛藤や後悔を払拭する方法を解説
悩みを周囲の人に打ち明ける
介護の悩みを一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人、職場の同僚や上司へ事前に相談しておくのも退職を後悔しないためのポイントです。
悩みを共有すれば精神的な負担が軽くなるだけでなく、思わぬアドバイスや協力を得られる場合があります。
とくに家族間ではよく話し合って介護の分担を決めれば、一人への過度な負担を防止可能です。
また、職場に事情を伝えて理解を得れば、介護休業などの制度も利用しやすくなり、仕事との両立がしやすくなります。
第三者に相談する
介護に関する悩みは、専門家に相談するのが一番です。
相談できる専門家の種類としては、以下のような相談先があります。
- 地域包括支援センター
- ケアマネジャー
- 市区町村の介護保険窓口
- 社会福祉協議会
地域包括支援センターでは、介護に関する総合的な相談を無料で受け付けており、誰でも気軽に利用できます。
また、ケアマネジャーに相談すれば、介護保険の申請や適切なサービスの紹介など、実践的なサポートも利用可能です。
専門家の意見を聞けば、仕事と介護を両立するための具体的な方法や、安心して介護に取り組むためのヒントが見つかる可能性が高まります。
親の介護で退職する方は特定理由離職者としての失業保険が適用される

親の介護を理由に退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給可能です。
具体的には、親の介護が理由で退職した場合に「特定理由離職者」として認められる必要があります。
特定理由離職者と認められたら、通常の自己都合退職と異なり、失業給付の待機期間が7日間のみとなるのが特徴です。特定理由離職者として認定されれば、退職後の経済的リスクが大幅に下がります。
また、給付日数も自己都合退職よりも長くなり、被保険者期間や年齢に応じて90日〜330日の範囲で受給可能です。
特定理由離職者として認定されるには、親の要介護状態を証明する複数の書類を準備し、ハローワークで手続きをする必要があります。
これらの準備には時間がかかる場合もあるため、退職を考え始めたら早めに情報収集を始めておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要』
親の介護で退職する前に利用できる制度は細かく調べて活用しよう【まとめ】

親の介護で退職を考える前に、介護休業や介護休暇、短時間勤務制度などの両立支援制度をぜひ検討してみてください。これらの制度を活用すれば、退職せずに介護と両立できる可能性があります。
介護保険サービスもうまく利用すれば、介護の負担を軽減可能です。悩みを一人で抱え込まず、家族や専門家に相談するようにしましょう。
やむを得ず退職する場合でも、特定理由離職者として認められれば、通常より少ない待機期間で失業手当を受給できます。
また、自力での介護に少しでも限界を感じたら、介護施設の利用を視野に入れるのも1つの手です。
介護施設について情報集めをしたい際は、大阪を中心とした高齢者向け施設情報を掲載する「いいケアネット」をご利用ください。
無料でさまざまな施設をチェックできますので、検討し始めたらどのような施設があるかを見てみましょう。
親の介護での介護に関してよくある質問

最後に、親の介護での介護に関してよくある質問の回答をまとめました。
親の介護で退職するときの会社への伝え方は?
親の介護を理由に退職する際は、まず直属の上司に相談し、その後、人事部門へ正式に退職願を提出するのが一般的な流れです。
面談では、親の病状や介護の必要性について説明し、退職を希望する理由として具体的に「親の介護のため」と明確に伝えてください。
また、これまでの感謝の気持ちを伝え、業務の引継ぎ期間やスケジュールについて提案し、会社への配慮を示すのも、円満に退職するポイントです。
可能であれば、周囲への負担を最小限に抑えられるよう、繁忙期を避けて退職のタイミングを調整しましょう。
親の介護で退職する際に診断書は必要ですか?
退職自体には診断書は不要ですが、失業手当を「特定理由離職者」として受けるには、医師の診断書を用意しなければいけません。
診断書には、親の要介護状態の内容や介護の必要性、期間の見通しなどが明記され、発行日は申請日から1ヶ月以内が望ましいです。
また、ハローワークに申請する際に介護保険の認定結果通知書や介護保険被保険者証、戸籍謄本も提出するとスムーズに手続きが進みます。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。