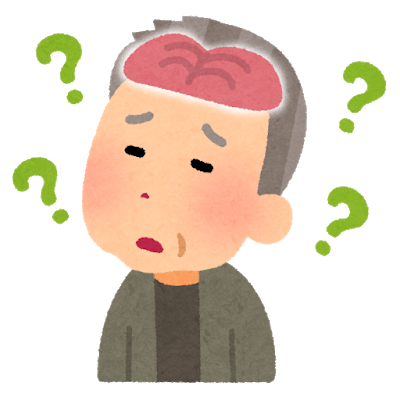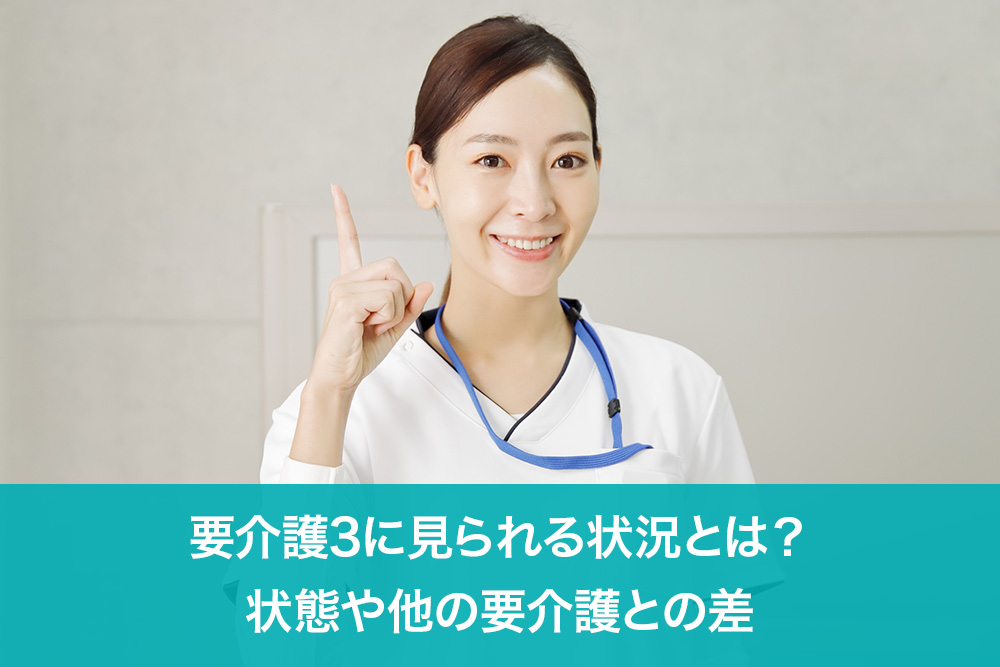近年、介護福祉業界でも最新テクノロジーの活用が進んでいます。
VR(バーチャルリアリティー)は、専用のゴーグルやヘッドセットを装着することでコンピューターが作り出した3D空間を体験できる技術です。
現在、認知症の理解促進から仮想旅行、スタッフ教育までVRは幅広く介護現場に取り入れられています。
本ページでは、介護現場でのVR活用方法や注意点などを詳しく解説します。
具体的な導入事例も紹介しているので、参考にしてみてください。
介護現場でのVR活用方法と効果

VR技術を介護現場に導入すると、要介護者や介護スタッフの支援に役立つ多くの活用方法があり、現場に良い効果をもたらします。
主な活用方法は以下の3つです。
- 要介護者の感覚・視点を疑似体験できる
- 教育や研修の教材ツールとして活用できる
- リハビリやレクリエーションに役立てられる
それぞれの効果について詳しく見ていきましょう。
要介護者の感覚・視点を実体験する
VRを装着すれば、介護を受ける側の視点や感覚を直接体験できます。
認知症の方が体験できる内容は以下のとおりです。
- 不安や混乱
- 視界の変化
- 聴覚の低下
言葉だけでは伝わりにくい感覚が疑似体験で可能になります。
介護スタッフがVRにより要介護者の感覚・視点を実体験できれば「なぜ利用者がこのような行動をとるのか」という理解が深まり、より丁寧なケアにつながっています。
教育や研修の教材ツールとして利用する
VRは介護の質を高める研修ツールとして大きな効果を発揮します。
人手不足が深刻な介護現場では、熟練スタッフが新人に指導する時間を確保することが難しいのが現状です。
こうした課題に対して、VRを教育・研修用の教材として活用すれば、実践的な学びの機会を効率的に提供できるようになります。
以下は、VRを活用した研修内容の一例です。
| 活用内容 | 学べること・体験できること |
| 基本介助技術の習得 | 移乗介助・入浴介助などをリアルな映像で学習 |
| 危険予測・緊急時対応訓練 | 転倒や急変など、現場で再現しづらい状況を体験 |
| スピーチロック体験 | 利用者視点で、職員の言葉が与える影響を体感 |
| 実践的研修による定着率向上 | 体験型で記憶に残る学習が可能 |
| 新人育成への活用 | 短期間で幅広い場面を疑似体験 |
体験を通じた学びが新人教育にも役立つと期待されています。
リハビリやレクリエーションで活用する
VRは、リハビリやレクリエーションの現場でも活用が可能です。
たとえば、バーチャル空間でボールを投げる動作や、景色の中を歩く体験を通じて、上肢や下肢のリハビリに取り組めます。
遊び感覚で取り組めるため、単調になりやすい訓練も楽しく継続しやすいです。
また、ゲーム要素のあるレクリエーションでは、利用者同士が自然に交流し、会話も生まれやすくなります。興味や好みに応じたプログラムを用意できるため、心身の活性化にもつながります。
VRを導入している介護施設をお探しの方は、大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」をご活用ください。無料登録にて、あなたの希望にあった施設を探すお手伝いをいたします。
関連記事:
リハビリができる介護施設はある?介護施設と医療施設のリハビリの違いを解説
特養(特別養護老人ホーム)のレクリエーションネタ大全|目的別で紹介
介護現場でVRを活用する注意点
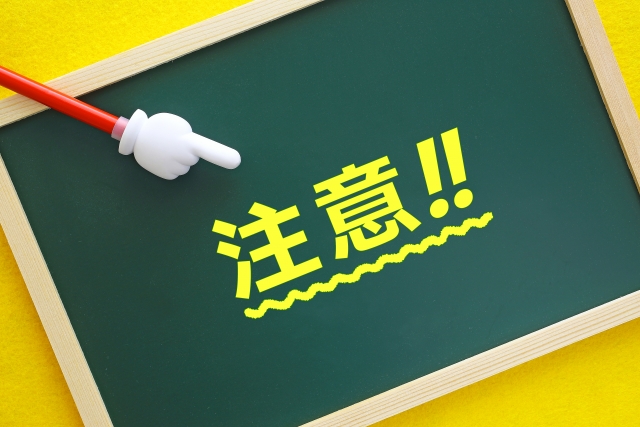
VRは介護現場で多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては注意すべき点もあります。
主な注意点は以下の3つです。
- 導入費用がかかる
- 使いこなせるまでに時間がかかる
- VRを使いたがらない高齢者もいる
これらの点を踏まえた上で、無理のない導入計画とサポート体制を整えることが大切です。
導入費用がかかる
VR機器の導入には一定の初期投資が必要です。
以下は導入費用の目安です。
| 費用項目 | 概要 | 参考価格帯 |
| VRゴーグル(HMD) | 基本機材となるヘッドマウントディスプレイ | 1台あたり約3万~15万円 |
| 専用コンテンツ費用 | 既製VR教材の購入・自社開発 | 数万円~数十万円 |
| メンテナンス費用 | ソフト・ハードの保守管理 | 年間契約・保守費が別途必要な場合あり |
| オーダーメイドVR (例:帰宅体験VR) |
撮影・編集を含むカスタム制作 | 約数十万円~100万円以上 |
VRゴーグルは1台あたり3万〜15万円程度で、施設によっては複数台が必要です。
専用コンテンツやメンテナンス費、帰宅体験VRなどのオーダーメイドでは100万円以上かかる場合もあります。
ただし、研修コストや人件費の削減につながる可能性もあり、費用対効果の見極めが重要です。
使いこなせるまでに時間がかかる
VR機器は最新のデジタル機器であるため、とくに年配のスタッフにとっては操作方法の習得に時間がかかります。
起動方法や基本操作、トラブル対応などを習得するまでには、練習期間が必要です。
新しいスタッフが入職するたびに操作方法を教えなければならず、人員の入れ替わりが多い職場では継続的な教育コストもかかります。
VRシステムのアップデートやメンテナンスにも定期的な時間を要するため、担当者の配置も検討すべきでしょう。
VRを使いたがらない高齢者もいる
介護施設の利用者の中には、VR機器に対して抵抗感を示す方も少なくありません。
とくに高齢者は「機械は苦手」という先入観から使用を躊躇したり、VRゴーグルの装着感に違和感を訴えたりします。
また、VR酔い(3D酔いに似た症状)で体調不良につながるケースもあります。
こうした課題に対しては、短時間の体験から始め、信頼関係のあるスタッフが一緒に体験して、不安をやわらげていくと良いでしょう。
無理に全員に使ってもらおうとするのではなく、個々の希望や体調に合わせた柔軟な対応が重要です。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。無料で利用できるので、登録してどんな施設があるかチェックしてみてください。
介護現場でのVR導入事例4選

介護の現場では、職員の研修や利用者の体験支援など、さまざまな場面でVRの活用が進んでいます。
ここでは、実際に導入されている4つの活用事例をご紹介します。
- 介護従事者に向けた介護技能研修用VR
- VRを活用した認知症体験
- VRを活用した介助訓練
- 「家に帰る」を擬似体験できるVR
どのようにVRが介護の現場で役立っているのか、具体的な取り組みを見ていきましょう。
①介護従事者に向けた介護技能研修用VR
介護スタッフの教育研修にVR技術を導入することで、従来の座学では伝わりにくい「現場感覚」をリアルに体験できるようになりました。
とくに注目されているのは、利用者視点を体験できる研修プログラムです。VRを活用して行う介護技能研修は以下の2点です。
・スピーチロック
介護の現場でしばしば話題にあがることのある「スピーチロック」をVRによって、老人ホームの利用者目線で体験するという研修です。
スピーチロックとは、介護の現場で介護職員やご家族の声かけによって、利用者の行動や気持ちに影響を与え、結果として動きを制限することです。
たとえば、利用者の方の安全を気遣った介護職員の安全を気遣った「やめてください」という声かけが、利用者にとっては「何も行動できない」という不快感につながります。
介護する人・される人、両方の気持ちを体験することで、自分の言葉が相手に与える印象を深く考えられます。
・介護の現場での危機の察知
VRの360度視野を活かした「危険予知訓練」では介護現場に潜む危険を察知する能力を養えます。
施設内を巡回することで、通路の狭さや物の置き方などの改善点が多く見つけられます。
介護現場の人材育成を支える有効な手段として、今後も活用が広がっていくでしょう。
②VRを活用した認知症体験
認知症の方の視点を一人称で体験できるVRプログラムは、介護現場や家族の理解を深める画期的なツールとして注目されています。
株式会社シルバーウッドが開発した「VR認知症」は、すでに14万人以上が体験し、教育機関や医療施設、一般企業まで幅広く活用されています。
見当識障害で場所がわからなくなる不安や、レビー小体型認知症の幻視体験など、さまざまな症状を本人視点で体験可能です。
認知症の方の行動が「問題行動」ではなく、周囲の理解やコミュニケーションによって大きく変わることを実感できます。
一人称の視点で体験することで、思い込みを排除し、利用者との真摯なコミュニケーションを心がける意識が深まります。
③VRを活用した介助訓練
介護現場での介助技術の習得において、VR技術を活用した新しい訓練方法が注目されています。
株式会社スリーディーと豊橋技術科学大学の共同開発による介護VRシステムは、「力の強さ」や「体の動かし方」など、感覚的なスキルを効率よく学べる革新的な研修ツールです。
このシステムは、モーションキャプチャとセンサーを組み合わせることで、介助者の接触力を計算し、仮想空間内で被介助者に触れた感覚をフィードバックします。
現在は肘部の力覚情報に限られていますが、将来的には手掌部や胸部、腰部にまで拡充され、より実践的な「持ち上げた感じ」をリアルに再現する予定です。
高齢化社会においてますます重要となる介護技術の習得を、VR技術が効率的かつ効果的にサポートする時代が到来しています。
④「家に帰る」を擬似体験できるVR
介護施設や病院に入所している高齢者の「家に帰りたい」という願いをVR技術で叶える取り組みが広がっています。
代表的な「家に帰る」を擬似体験できるVRは以下のとおりです。
| 企業名・サービス | 特徴 |
| 株式会社フロリット(おもいで眼鏡) | ・自宅を360度カメラで撮影し、VRゴーグルで体験可能 ・匂いや触感なども特殊機材で再現 |
| ディチャーム株式会社(VR帰宅) | ・駅から自宅までの道のりを360度映像で体験可能 ・商店街やお寺を通るなど、街の風景も再現 |
帰れない高齢者にとって、VRによる疑似体験は心のケアや認知機能の維持に有効とされています。
新しい高齢者とITを繋ぐコミュニケーションツールとなるでしょう。
介護現場におけるVRの効果を知って導入を検討しよう【まとめ】

本ページでは、介護現場におけるVR技術の活用方法と効果について解説しました。
VRは、要介護者の理解促進やスタッフ教育、リハビリの質向上などに効果が期待され、すでに多くの介護施設で導入が進んでいます。
コストや操作習得、高齢者の受け入れといった課題はありますが、段階的な導入とサポート体制により対応可能です。
高齢化が進む中、VRは介護の質を高める有効な手段といえるでしょう。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。無料で利用できるので、登録してどんな施設があるかチェックしてみてください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。