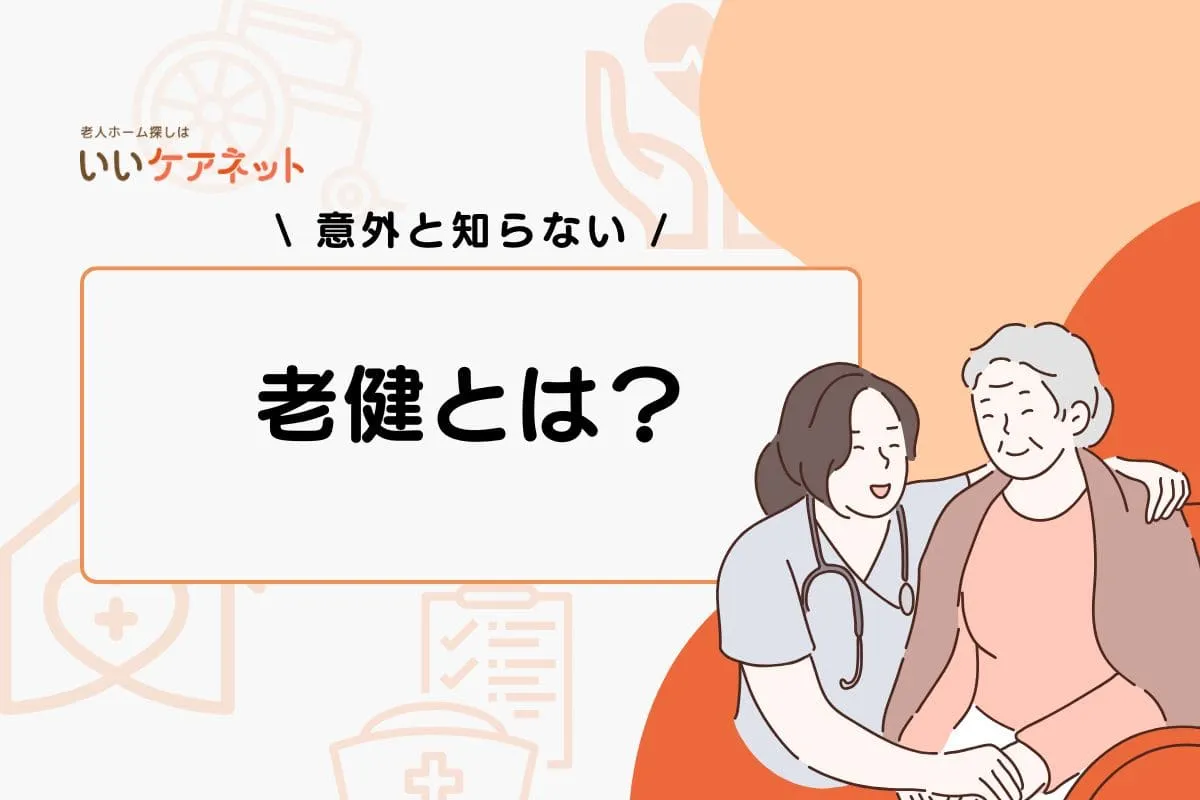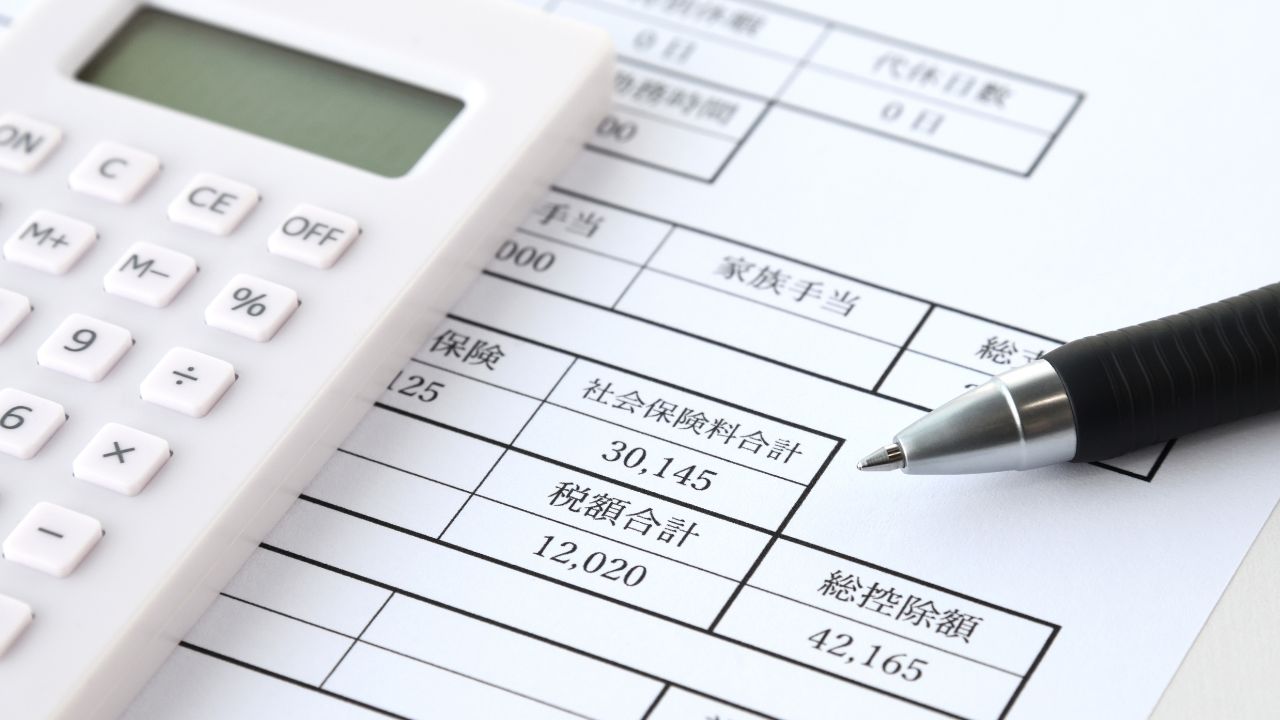「特別養護老人ホームに入りたいけど費用はどれくらいかかるの?」「お金がかかると施設で過ごすのは難しいかもしれない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
特養の自己負担は月額約6~14万円で、入居する方の年間所得に応じて自己負担は変わりますが、10万円以内に収まるケースが多くあります。
この記事では、特別養護老人ホームの費用や自己負担について解説します。
費用が高額になったときに利用できる制度や、負担を軽減する制度についても解説するので、参考にしてください。
特別養護老人ホームにかかる費用

特別養護老人ホームにかかる費用の自己負担は、月額約6~14万円で、内訳は下記のとおりです。
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
- 施設介護サービス費
- 介護サービス加算費用
それぞれ料金がどれくらいかかるのか解説するので、参考にしてください。
入居金
特別養護老人ホームは、公的施設のため入居金がかかりません。
入居金がかからないため、特養はお金に余裕のない方も安心して利用できます。
居住費
特養の居住費は自己負担であり、通常2.8万円~6.3万円です。多床室やユニット型など部屋の種類によって料金が変わります。
| 多床室 | 個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型 |
| 一部屋に4人分のベッドがあり複数の方と過ごす部屋
居住費は月額2.8万円である |
一人ひとりの個室がある
居住費は月額3.7万円である |
同じ部屋で過ごすが、仕切りがある。通常の多床室と比べてプライバシーが確保される
居住費は月額5.3万円である。 |
一人ひとりの個室がありプライバシーを重視する方向け
居住費は月額6.3万円である |
(文献1)
ユニット型は共有スペースがあり、9~10人程度が同じ空間で過ごします。
多床室を採用している施設では、同じ老人ホームで過ごす30名以上の方が食堂に集まるため、顔見知りの関係性は作りにくいです。
ユニット型であれば、少人数の同じメンバーで過ごすため馴染みの関係ができる可能性が高くなります。
居住費は生活保護を受給していたり、住民税が非課税かつ年金や所得が低かったりする場合は、負担軽減の対象になります。
食費
食費は、通常1日1,445円かかり、月額で4.4万円になります。(文献1)
生活保護受給者や住民税非課税で所得の少ない方であれば、負担軽減の措置があります。
負担軽減を受けた場合の費用は、1日300円~1,360円まで減額され、月額では1万円~4.1万円です。(文献1)
日常生活費用
日常生活費用は、本人の衣服や趣味、医療機関を受診する際にかかる費用です。
特養では、パジャマと普段着に定期的に着替えるため、入居時は衣服代がかかるかもしれません。
しかし、衣服は自宅にあるもので問題無いため、大きな出費とはならないでしょう。
特養に入居中は、破れたり汚れたりするため、定期的に購入する必要があります。
また、趣味があったり、医療機関を定期的に受診したりする方もいるため、月額1万円程度かかると見積もっておくと安心です。
施設介護サービス費
施設介護サービス費は、月額約2~3万円で、要介護により変わります。(文献2)
また、年収に応じて負担が1割~3割と変化し、2割の場合は約5~6万円、3割の場合は約7~9万円と増えます。
負担が2割以上になる方は、下記のとおりです。(文献3)
| 1割負担の方 | 2割負担 | 3割負担 |
| 年金+その他の所得が単身世帯では280万円未満
夫婦世帯は346万円未満の方 |
年金+その他の所得が単身世帯で280万円以上
夫婦世帯で346万円以上の方 |
年金+その他の所得が単身世帯で340万円以上
夫婦世帯では463万円以上の方 |
2~3割負担に該当する方は、2021年3月時点で8.2%と報告されており、当てはまるケースは少ないでしょう。(文献3)
介護サービス加算
介護サービス加算は、施設によって取得している内容が異なる費用です。
取得している介護サービス加算が多ければ、利用料も増えるためデメリットに感じるかもしれません。
しかし、加算が取れている場合は、施設の体制が整っており、手厚いケアを提供できる環境であるともいえます。
介護サービスが多い場合は、利用料が多くなるため複数の施設を比較して、入居する方に合う特養を見つけましょう。
特養の費用を軽減するために利用できる制度

特養の費用を軽減するために利用できる制度には、下記があります。
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算制度
それぞれの制度は利用できる方が異なりますが、負担を減らせるため対象か確認しておきましょう。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は、低所得者の方が特養などの施設やショートステイを利用する場合に適用できる制度です。
制度が利用できると、食費・居住費の負担を下記のように軽減してもらえます。(文献4)
| 食費 | 居住費 | ||||
| 多床室 | 個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | ||
| 第1段階 | 0.9万円 | 0円 | 1.2万円 | 1.7万円 | 2.8万円 |
| 第2段階 | 1.2万円 | 1.3万円 | 1.5万円 | 1.7万円 | 2.6万円 |
| 第3段階① | 2万円 | 1.3万円 | 2.7万円 | 4.2万円 | 4.2万円 |
| 第3段階② | 4.1万円 | 1.3万円 | 2.7万円 | 4.2万円 | 4.2万円 |
| 基準月額 | 4.4万円 | 2.8万円 | 3.7万円 | 5.3万円 | 6.3万円 |
軽減される方は4種類に分けられ、条件は下記のとおりです。
| 対象者 | 預貯金額(夫婦の場合) | |
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし |
| 世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 | |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入+合計所得額が80万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入+合計所得額が80万円1円~120万円以下 | 550万円(1,550万円以下) |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入+合計所得額が120万円1円以上 | 500万円(1,500万円)以下 |
特定入所者介護サービス費の対象者になるかは、住民税が非課税であることが前提条件です。
非課税+年間の収入が一定以下であれば、特養の自己負担を軽減できます。
高額介護サービス費
高額介護サービスは、食費・居住費、福祉用具の購入費用など、一部を除いた料金が所得ごとに決められた上限を超えた場合に介護保険から支給される制度です。
所得は4段階に分けられており、詳細は以下のとおりです。(文献4)
| 区分 | 対象となる方 | 月の負担上限額 |
| 第1段階 | 1.生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
| 2.15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない方 | 15,000円(世帯) | |
| 3.住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
|
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で年金収入やその他の所得金額が合計80万円以下 | 24,6000円(世帯)
15,000円(個人) |
| 第3段階 | 住民税非課税世帯で第1・2
段階に該当しない方 |
24,6000円(世帯) |
| 第4段階 | 1.住民税課税世帯で年収約770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
| 2.年収約770万円~1,160
万円未満の方 |
93,000円(世帯) | |
| 年収1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
「世帯」と記載している上限額は、同一世帯で介護保険サービスを利用した場合の合計金額です。
複数名で特養に入居している場合は、利用料が増加するため、上限額に該当する可能性が高くなります。
第4段階の課税所得は65歳以上の方が対象となるため、当てはまる方は少ないでしょう。
高額介護サービスを支給してもらうためには、市区町村への申請が必要なため、忘れないようにしましょう。
高額介護サービス費について、詳しく知りたい方は、下記の記事も読んでみてください。
関連記事:高額介護サービス費とは?わかりやすく対象サービスや申請方法を解説
高額医療・高額介護合算制度
高額医療。高額介護合算制度は、世帯内で医療保険・介護保険の費用が発生したときに、一定以上の負担額があれば、支給してもらえる制度です。
特養のみの費用負担では、利用できないケースがほとんどです。
世帯内で特養に入居している方の他に、病気により入院した方がいる場合は、利用できる可能性が高くなります。
制度を利用するには、市町村に申請が必要です。
一定以上の負担額に該当するかは、世帯の所得により決まるので、以下を参考にしてください。(文献4)
| 70歳未満 | 70~74歳 | 75歳以上 | ||
| 介護保険+被用者保険もしくは国民健康保険 | 介護保険+後期高齢者医療保険 | |||
| 住民税非課税世帯かつ年金収入が80万円以下 | 本人のみ | 34万円 | 19万円 | 19万円 |
| 介護利用者が複数 | 34万円 | 31万円 | 31万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 | 31万円 | |
| 年収約370万円未満 | 60万円 | 56万円 | 56万円 | |
| 年収約370万円~約770万円 | 67万円 | |||
| 年収約770万円~約1,160万円 | 141万円 | |||
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | |||
上記のように年収が370万円以上では、年齢による負担額は変わりません。
しかし、住民税が非課税であったり、世帯年収が370万円未満であったりする場合は、負担額が少なくなり高額医療・高額介護合算制度を利用できるかもしれません。
特別養護老人ホームと合わせて検討したい老人ホーム

特別養護老人ホームと合わせて検討した施設は、下記の2つです。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
特別養護老人ホームは、費用が安く入居待ちになるケースがあります。
すぐに入居できなければ自宅での介護は難しかったり、介護離職が必要であったりと困ってしまうかもしれません。
同程度の費用で入居できる施設もあるため、特養が入居待ちになったときの参考にしてください。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、老人であれば入居が可能です。健康型・住宅型・介護型の3種類があります。
特養に入居を考えている方は、原則要介護3以上のため、住宅型や介護型の有料老人ホームへの入居が主な選択肢です。
費用は、特養と比べて高くなる傾向にあります。入居待ちがない施設もあるため、特養の入居順になるまでの間、利用する方もいます。
有料老人ホームは、施設ごとに費用や設備が異なるため、入居を考える方は、いいケアネットで条件に合う施設を探してみてください。
住宅型有料老人ホームについて、下記の記事で解説しているので、合わせて読んでみてください。
関連記事:住宅型有料老人ホームとは?主なサービス内容や必要な料金をわかりやすく解説!
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は、安否確認や日常生活の買い物などを支援してもらえる施設です。
一般型と介護型があり、特養に入居を考えている方であれば、介護型がおすすめです。
一般型は一人で生活できる方向けであり、介護サービスは外部サービスとの契約が必要になったり、日常の健康管理はスタッフから提供してもらえなかったりします。
外部サービスを契約した場合、提供されるケアの量で金額は変動し、回数が多くなると負担が増えてしまうかもしれません。
介護型であれば、サ高住のスタッフから介護を日常的に提供してもらえるため、介護度の高い方であっても費用が一定料金で済みます。
介護型のサ高住を探すときは、いいケアネットにご相談ください。
サービス付き高齢者向け住宅について、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
関連記事:サービス付き高齢者向け住宅の問題点とは?失敗しない選び方も解説
まとめ|特養の費用を理解して入居に向けて準備しよう

特養の費用は、月額約6~14万円の自己負担があります。施設や収入額によって、自己負担額は変わるため、今回解説した制度を利用できるか確認してみてください。
特養は入居待ちとなる可能性が高い施設です。入居までの間、自宅で介護もしくは、他の施設で過ごしてもらうか洗濯しなければいけません。
いいケアネットでは、介護度の高い方に合わせた施設も紹介しています。
有料老人ホームやサ高住などですぐに入居できる施設を探すサポートも可能なため、いいケアネットにお気軽にご相談ください。
特養にかかる費用が気になる方からよくある質問
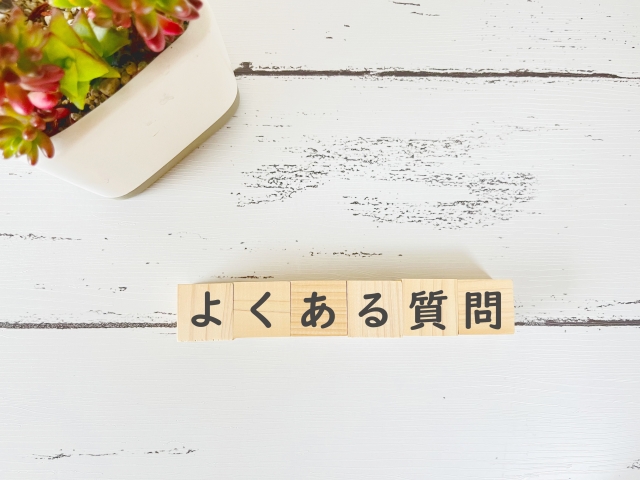
特養と老健ではどちらが安いですか?
特養と老健の料金は、どちらも変わりません。
リハビリをして自宅退院を目指す方は老健、今後は施設で生活する場合は特養への入居を検討します。
老健はリハビリが主な目的のため、3ヵ月ごとに入居を継続するか判定があり、早ければ3ヵ月で退去になるかもしれません。
老健へ入居しても、同じ施設で長期的に過ごせるわけではないため、今後の方向性を考える必要がある点に注意しましょう。
特養と老健の違いについて、下記の記事で詳しく解説しているので、気になる方は読んでみてください。
関連記事:老健と特養の違いは入居期間だけじゃない!入居条件や費用などの違いを解説
お金がない老人はどうしたらいいですか?
お金がなく施設を選べないと感じている場合は、年金の範囲内で利用できる施設や、負担軽減制度を利用すると入居できる施設が見つかるかもしれません。
どうしてもお金がない場合は、生活保護の受給も視野に入れておきましょう。
老人ホームのお金が払えないと悩んでいる方は、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:老人ホームの費用が払えない場合は生活保護を活用すべき?入居可能な施設の種類を解説
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。