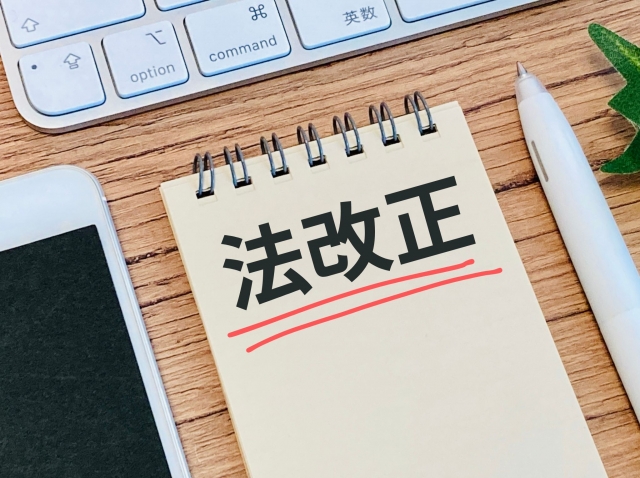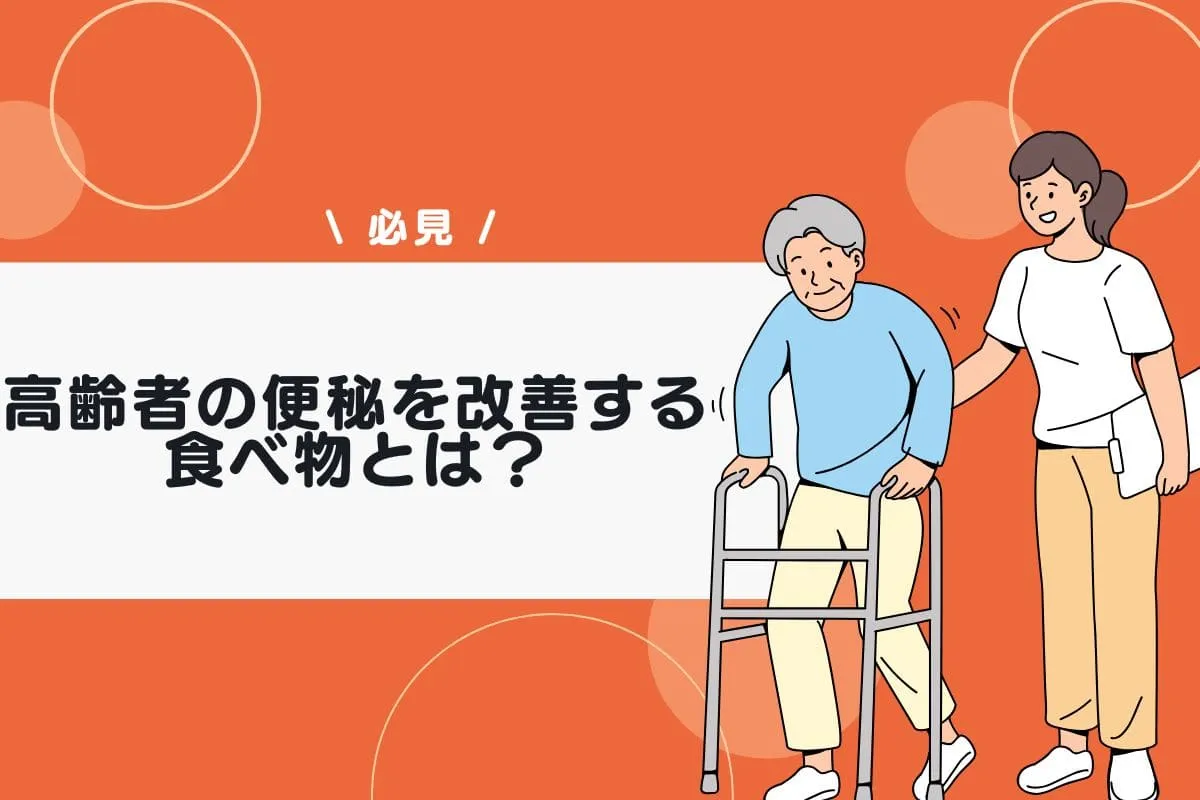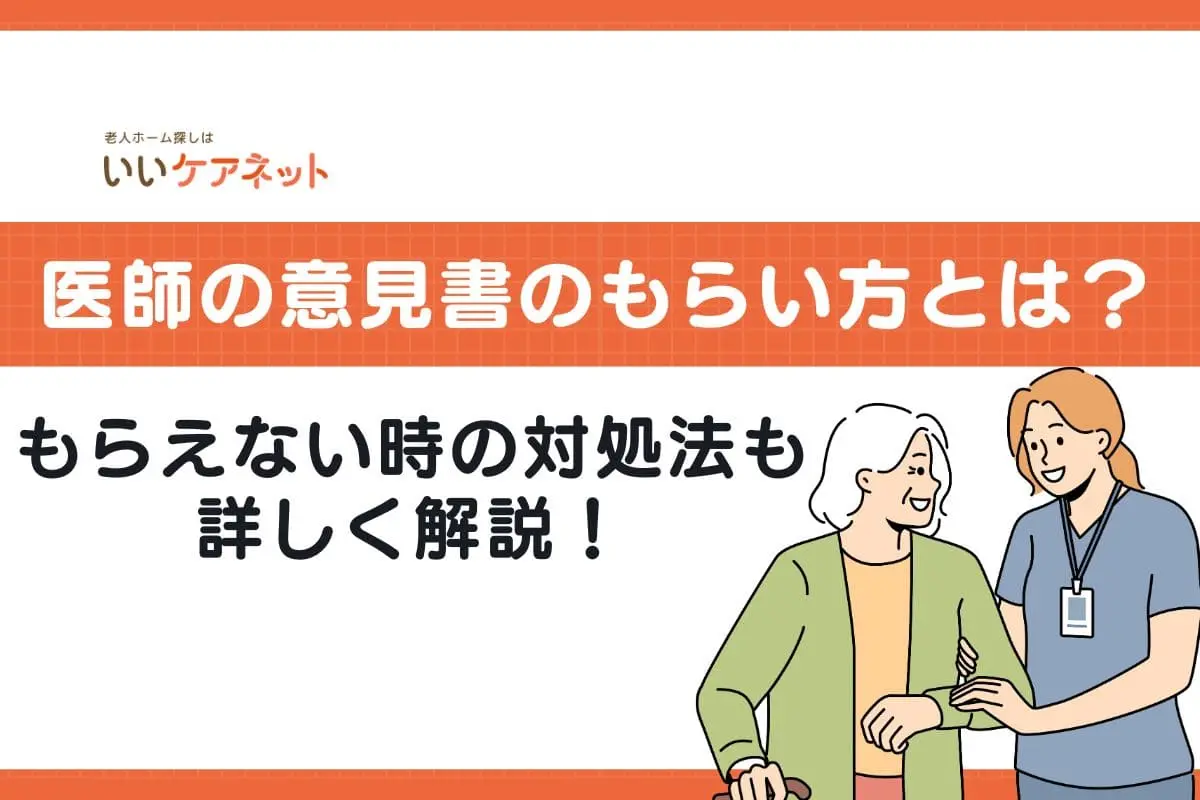介護保険制度は、高齢化や核家族化が進む中、介護を家族だけで担うことが難しくなった社会背景を受けて、2000年4月に開始された制度です。
介護保険制度ができるまでの措置制度では、医療機関への長期入院や家族負担の増加が大きかったため、公平かつ利用者主体の仕組みが求められたことで創設されました。
本記事では、介護保険がいつ・なぜ始まったのかや介護保険制度の歴史、改正内容をわかりやすく解説します。
介護保険制度はいつから始まった?
介護保険制度は、急速な高齢化と核家族化を背景に、家族だけの介護では限界が見え始めた頃に誕生しました。
施行されてからも介護保険制度は常にアップデートされ続けており、介護に関する課題解消に向けて改善されています。
以下では、介護保険制度が施行されてから現在に至るまで、どのようにアップデートされてきたのかを解説します。
介護保険制度は2000年からスタート
介護保険制度は1997年に成立した「介護保険法」を基盤に、2000年4月から運用が始まりました。
介護保険制度の発足により、高齢者やその家族が安心して介護サービスを利用できる体制の基盤が作られ、介護に関する負担が低減されやすくなりました。
たとえば、介護保険制度を利用すると要介護認定を受けた高齢者が訪問看護や特別養護老人ホームを利用する際、保険給付によって費用負担が軽減されます。
これにより、家族の過度な負担を防ぎ、本人も必要なサービスを選びやすくなりました。
参考:厚生労働省『介護保険制度の概要』
介護保険制度の歴史が分かりやすい、年表形式ダイジェスト
介護保険制度は2000年の施行以降、大きな改正を何度も積み重ねて進化してきました。
以下では年表形式で主な出来事を簡潔にまとめ、制度がどのように形作られてきたかを紹介します。
1997年: 介護保険法成立
高齢化社会への対応策として1997年に「介護保険法」が制定され、家族依存型の介護から社会全体で支える仕組みへ移行する道筋が示されました。
高齢者の自立支援や家族負担軽減を目標として施行され、2000年の制度施行に向けた準備する基盤となる法律として今でも運用されています。
関連記事:介護保険法をわかりやすく解説!制度の基本から最新の改正まで
2000年: 介護保険制度施行
2000年4月に介護保険制度が正式にスタートし、第1号被保険者(65歳以上)・第2号被保険者(40~64歳)を対象とする仕組みが稼働しました。
財源は公費と保険料を折半し、利用者はケアマネージャーと話し合いながら必要なサービスを選択できるよう設計されています。家族の負担軽減と高齢者の自立を両立する、画期的な仕組みとして導入されました。
2005年: 地域包括ケアシステム導入
2005年の大幅な改正では、地域包括ケアシステムが初めて導入され、高齢者が住み慣れた地域で医療・介護・生活支援を一体的に受けられる体制が整備されました。
要支援者向けの「予防給付」も設けられ、介護が必要になる前にリスクを抑え、自立を促す考え方が広まり始めました。
2011年: 認知症対策強化
認知症高齢者が増加する中、2011年には認知症ケアを充実させる取り組みが進みました。
地域包括支援センターの役割が拡大するだけでなく、認知症ケアに特化した施設やサービスの整備が加速するきっかけにもなった取り組みです。
早期発見・早期対応を重視し、認知症高齢者と家族が地域で安心して暮らせるよう支援体制を強化しています。
2014年: サービス利用基準の見直し
2014年の改正では、要支援者向けサービスを市町村事業に移し、特別養護老人ホームの入所基準を「要介護3以上」に変更するなど、重度者へのケアを優先する仕組みが導入されました。
財源の効率化と重度要介護者への重点支援を目的とし、軽度者には地域支援事業を中心にサポートを行う方針が打ち出されています。
2017年: 高所得者負担増加
2017年には高所得者の自己負担割合を2割・3割へ引き上げる改正がおこなわれ、利用条件も一部厳格化されました。
これは介護保険財政の悪化を防ぎ、公平性を保つための措置でもあります。財政負担の偏りを是正する動きとともに、サービス全体の持続可能性を高める目的でも改正が行われました。
2020年: ICT活用と業務効率化
2020年頃からは、ICT技術を介護現場に導入して業務を効率化し、人材不足に対応する取り組みが本格化しました。
医療・介護データを連携させる試みや介護ロボットの活用が進み、ケアの質を維持しながら職員の負担を軽減する環境が整い始めたのは2020年前後です。
業務効率化にともない、介護サービス従事者の処遇改善や働きやすい職場づくりにも働きかけました。
2024年: 地域包括ケアシステムの深化
2024年には、地域包括ケアシステムがさらに強化されます。
在宅医療と介護の連携を推進し、データ基盤整備による効率化が行われたほか、社会福祉連携推進法人制度の創設などにより地域間の連携も強化されました。
高齢者の暮らしを地域全体で支えるための取り組みが、より一層深化していく見込みです。
介護保険制度の保険料は高齢化に伴い年々引き上げ
介護保険料は以下の4つの要因によって年々引き上げられており、今後も引き上げられる可能性があります。
- 高齢者数の増加
- サービス利用者の拡大
- 介護サービス運用における人件費上昇
- 公費だけで賄いきれない状況
介護保険制度が始まった2000年当初は、1人あたりの月額保険料が約2,911円でしたが、高齢化や利用者数の増加に伴って年々引き上げられ、2024年には約6,225円に達しました。
参考:65歳以上の介護保険料 改定で月額いくら?東京 千葉 埼玉 神奈川などの市町村別の保険料 一挙掲載 | NHK
とくに2014年以降は認知症対策の強化や重度要介護者への重点支援などが進み、財源確保のために高所得者の負担割合が拡大しています。
介護保険制度が創設された目的と背景
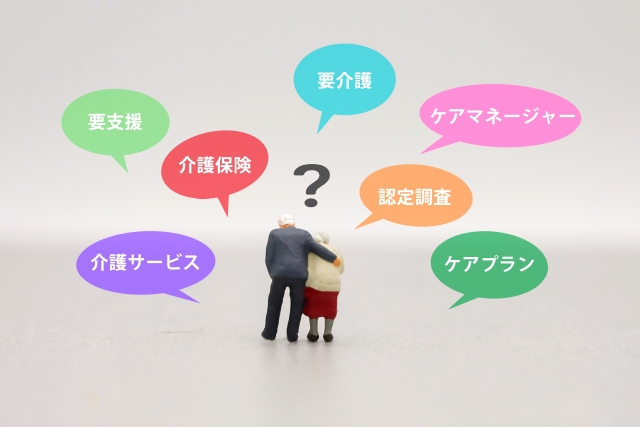
少子高齢化が深刻化する中、従来の措置制度では増加する要介護者のニーズに応えきれず、公的な補完が強く求められていました。その解決策として2000年に施行されたのが介護保険制度です。
急速な高齢化に加え、核家族化が進む中で、家族だけに負担が偏る介護体制を改善するため、介護保険制度は2つの目的のもと施行されました。
では、どのような目的で介護保険制度がアップデートされ続けているのかを、チェックしてみましょう。
高齢者を社会全体で支える仕組みづくり
核家族化や共働き世帯の増加により、家族が24時間介護を担うのは限界があります。
介護保険制度はこの課題にも対応しており、高齢者やその家族がケアマネージャーと相談し、家族が不在でも高齢者が適切な介護サービスを自由に選択し利用できる仕組みを設けました。
全額自己負担の場合、金銭的な負担に対する懸念点だけでなく、適切なサービスを利用できない高齢者が多発してしまいます。
そこで介護保険制度は保険料や公費で費用をカバーし、経済的にも介護支援を受けやすくする目的で施行されました。
長期の入院や介護に伴う医療費問題の解消
高齢者が医療機関に長期間入院する「社会的入院」が医療費を押し上げ、大きな社会的課題となっています。
介護保険制度はこの問題を改善すべく、医療と介護の役割を切り分け、在宅ケアや地域密着型サービスを充実させ、長期入院を減らし医療費を適正化するためにも施行された制度です。
高齢者は入院以外にも、保険給付で利用できる在宅サービスや短期的な介護施設への入所などを選べるようになりました。
これにより医療機関への過剰な依存を減らし、在宅ケアや地域密着型サービスを推進し、医療費抑制を図っています。
関連記事:家族の介護でもらえるお金は?ジャンル別に9つの制度を解説
介護保険制度で受けられるサービス一覧
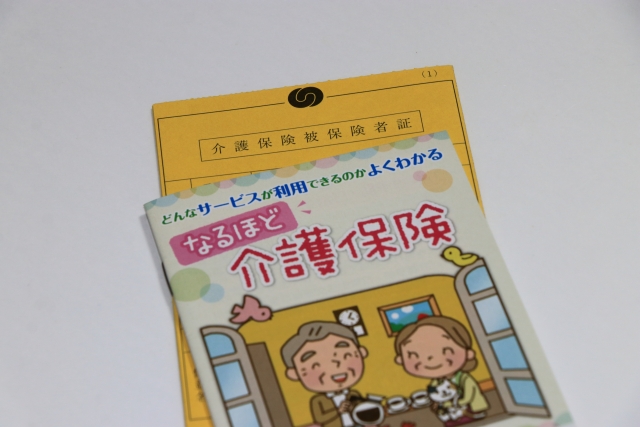
介護保険制度では老人ホームへの長期入所だけではなく、大きく分けて7つの介護サービスを利用できます。
- 在宅サービス
- 通所サービス(デイサービス・デイケア)
- 短期入所サービス(ショートステイ)
- 福祉用具貸与・購入費補助
- 地域密着型サービス
- 入所系サービス
- その他の支援
それぞれ介護保険制度で利用できるサービスがどのようなサービスで、どのような利用メリットがあるのかを紹介します。
在宅サービス
自宅での生活を続けながら支援を受けるのが「在宅サービス」です。
在宅サービスは大きく分けて、4つのサービスから選択できます。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護(ホームヘルプ)では食事や排せつ介助など日常生活を手助けし、訪問看護では看護師が医療ケアや健康管理をおこなうのが基本です。
高齢者の介護が必要な状況に応じて、理学療法士が自宅に来る訪問リハビリテーションや、日中・夜間を通じて定期的に訪問する定期巡回・随時対応型訪問介護看護などを利用出来ることもあります。
通所サービス(デイサービス・デイケア)
日中だけ施設に通って受けるケアが「通所サービス」です。
デイサービスでは入浴や食事、レクリエーションなどの支援が中心で、外出の機会や他者との交流が少なくなりがちな高齢者の生活に刺激をもたらします。
一方、デイケア(通所リハビリテーション)は、介護が必要になる前に近い日常生活が送れるよう、高齢者ができることを増やすためのサービスです。
デイケアは医療機関や老健施設などに通い、理学療法や作業療法といった専門的なリハビリを実施します。
どちらの通所サービスも家庭の負担軽減と社会的接点を増やす役割があり、高齢者の心身機能の維持にも効果的です。
ショートステイは、短期間だけ施設に入所して介護や支援を受けるサービスです。
家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護が困難になる場合や、在宅で高齢者を介護する家族の負担軽減、リフレッシュを目的とする場合に活用されます。
入所したい介護施設に申し込み、入所できるまでの待機期間で、施設スタッフに高齢者の現状を知ってもらうための足がかりとしての利用もおすすめなサービスです。
ショートステイを提供するのは、特別養護老人ホームや老人保健施設などが多く、日常生活支援からリハビリテーションまで幅広いサポートを受けられます。
利用できる期間は数日から数週間程度が多く、在宅サービスや通所サービスと組み合わせれば、より高齢者やその家族の状態に合った福祉を受けやすくなるのが特徴です。
福祉用具貸与・購入費補助
リハビリや施設利用だけではなく、車いすや介護ベッド、歩行器などの福祉用具をレンタルできる「福祉用具貸与」、住宅改修費用の一部に対する補助金も介護保険制度で利用できるサービスです。
住宅改修は手すりの設置や段差の解消などバリアフリーを目的とした工事が対象であり、原則として20万円まで改修費用が補助されます。この補助制度により、全額自己負担よりも低コストで住宅をバリアフリー化できるようになりました。
地域密着型サービス
地域に根ざした小規模施設で利用できる「地域密着型サービス」は、大きく分けて3つのサービスがあります。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 看取り対応施設
小規模多機能では訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)を柔軟に組み合わせて利用できるため、柔軟なケアを受けられます。
グループホームは、認知症の方が安心して過ごせる環境を確保したい方におすすめのサービスです。
入所系サービス
介護保険制度で利用できる入所系サービスは、大きく分けて3つです。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 老人保健施設(老健)
- 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
特養は原則として要介護3以上が入所条件となり、日常生活全般を手厚く支援する施設です。
老健は在宅復帰を目指す中間施設として機能しており、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は食事や見守りなど生活サポートを受けられます。
どの施設に入所するかは、本人の希望や状態に合わせて選択が可能です。
その他の支援
先述したサービスのほかにも、夜間専用の訪問介護や認知症高齢者を対象にしたデイサービスなど、利用者のニーズに合わせた多様な支援が整備されています。
とくに認知症対応型通所介護は少人数制で運用されており、専門的なスタッフが対応するため、落ち着いた環境でケアを受けられるのが特徴です。
終末期ケアを含むみとり対応施設も増えており、本人と家族が安心して最期まで過ごせるような体制づくりが進められています。細かいサービス内容は自治体や事業所によって異なるため、ケアマネージャーに相談したり、自治体のホームページを確認したりするようにしましょう。
【まとめ】介護保険制度はいつから始まった?知っておきたいポイント

介護保険制度は、1997年の「介護保険法」成立を経て2000年4月から本格的に始まりました。
高齢化や核家族化による介護負担の増大、長期入院による医療費問題などを背景に、家族だけに頼らず社会全体で支える仕組みとして導入されたのが大きな特徴です。
40~64歳が負担する保険料は年々増加しているものの、その分在宅や施設、地域密着型など多様なサービスが充実し、利用者のニーズに合わせて柔軟に選べるメリットがあります。
必要な支援を適切に活用するためにも、制度の歴史や目的、サービス内容を理解しておきましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。