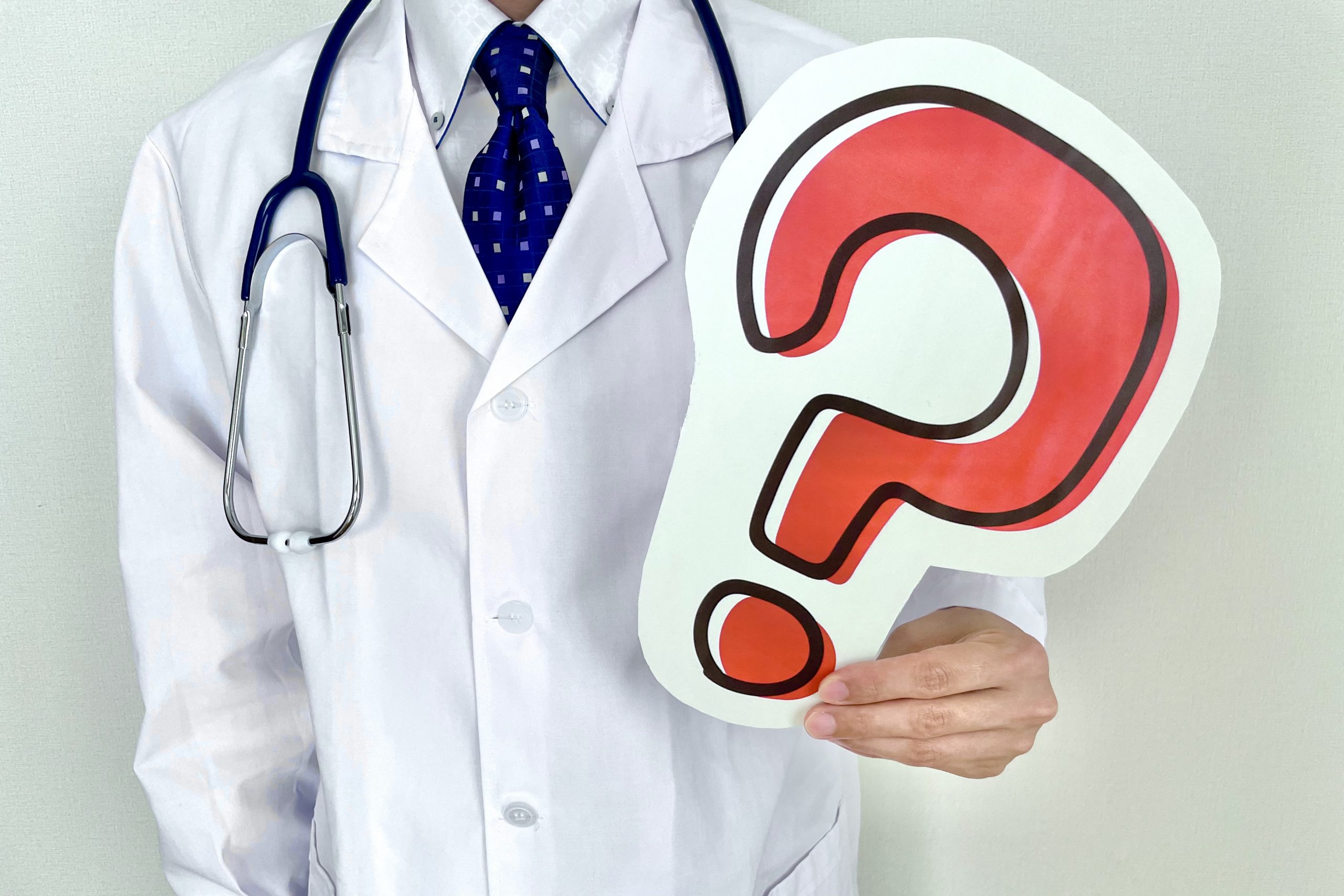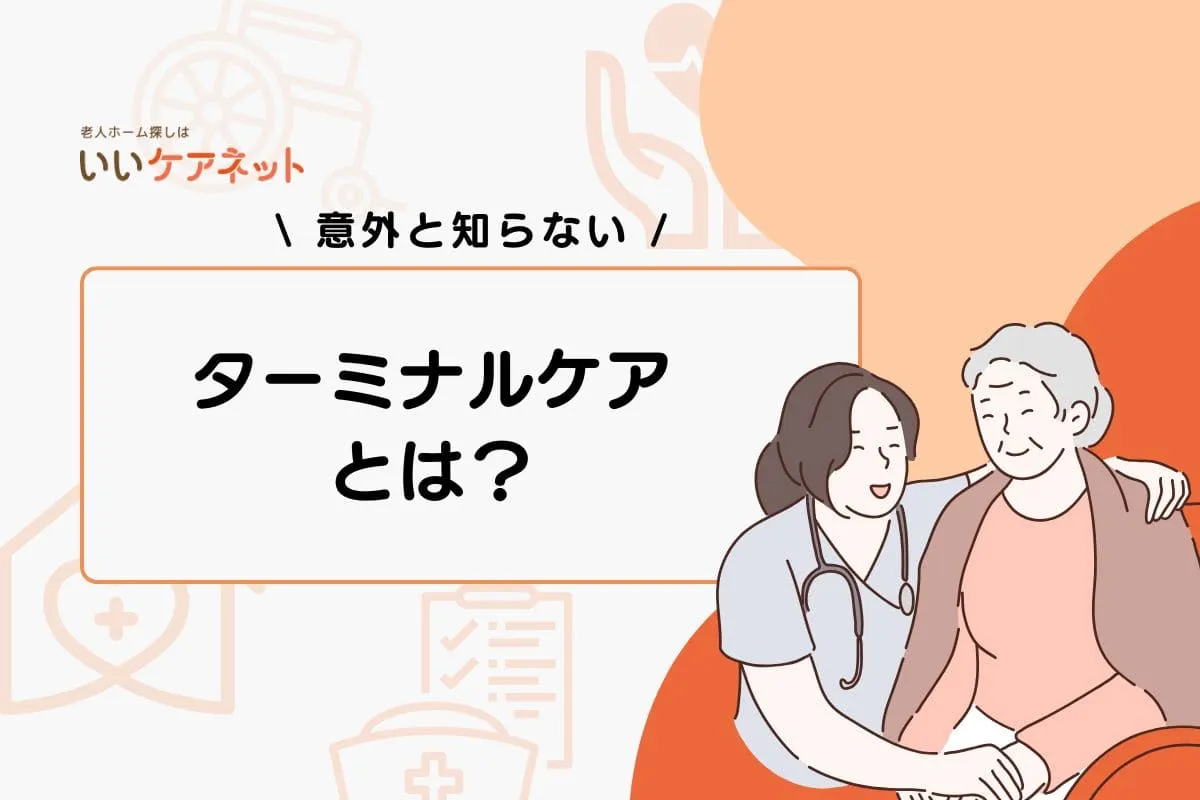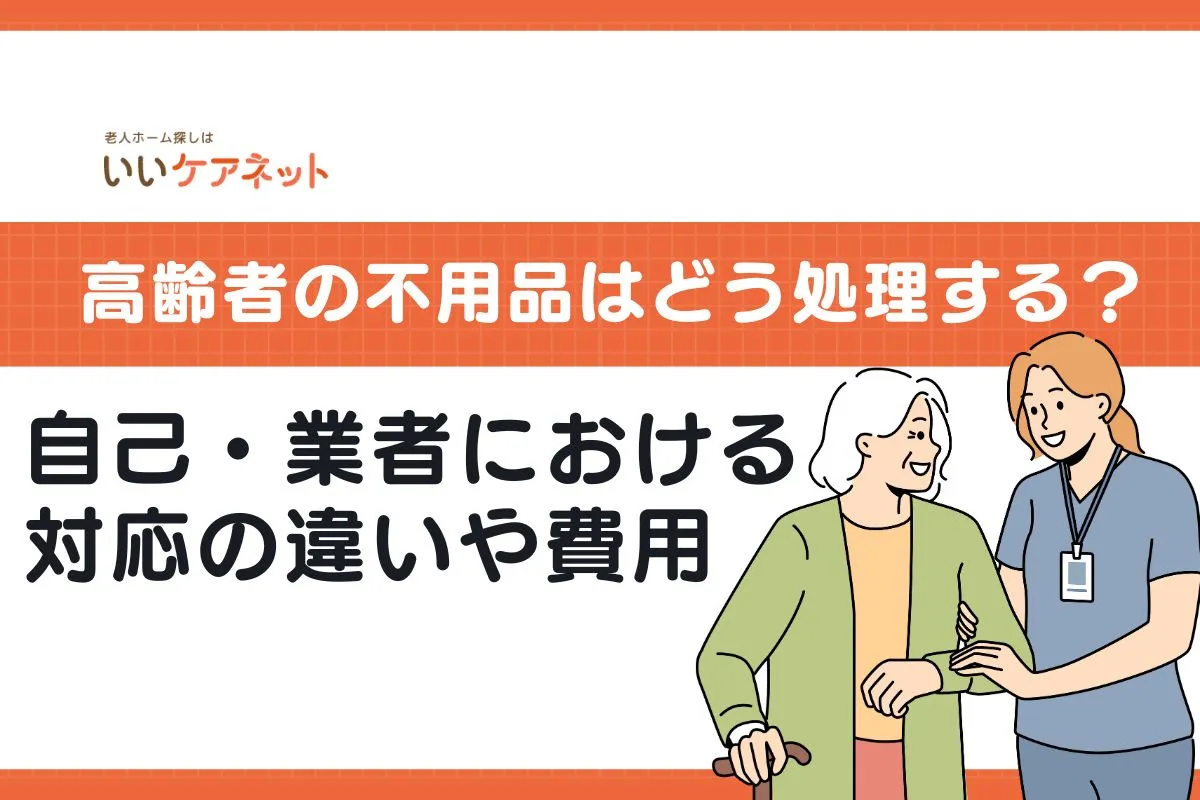胃ろうは、患者さんと家族にとって大きな決断となる医療処置です。口から食べることが難しくなった場合に栄養補給の方法として選択されますが、その後の平均寿命や生活の質に不安を抱える方もいるでしょう。
胃ろうをしてからの平均寿命は、基礎疾患や患者さんの状態によって異なるのが一般的です。また、毎月の費用や介護の負担、合併症のリスクなど考慮すべき点も多くあります。
本記事では、胃ろうをした後の平均寿命や導入前にしておきたいことを解説します。家族での話し合いや、医療者との相談の場において、ぜひ参考にしてみてください。
【結論】胃ろうにした後の平均寿命は約3年

胃ろうを導入した後の平均余命は、3年程度とされています。ただし、患者の病状や年齢、健康状態などによって異なります。
胃ろうをするのは、嚥下障害で口からの食事が困難になった方に栄養補給をするためです。胃ろうによって適切な栄養管理が可能になると、体力の維持や生活の質の向上が期待できます。
ただし、胃ろうは直接的に寿命を延ばすものではありません。あくまでも栄養補給を確実におこなうための手段であることを理解しておきましょう。
【症状別】胃ろうの寿命

胃ろうを造設した後の寿命は、患者さんの基礎疾患や身体の状態によって異なります。次の3つの症状ごとに平均寿命を詳しく見ていきましょう。
- 認知症
- 脳梗塞
- 寝たきり
認知症
脳梗塞の患者さんの胃ろう造設後の平均寿命は、約2カ月(53日)です。
イギリスのウェスト・ヨークシャーにある病院でおこなわれた調査では、平均寿命の範囲が2~528日(約1年半)と広い結果になりました。脳梗塞の胃ろうでは、重症度や年齢、合併症の有無などによって大きく余命が変動するのが特徴です。
参考:Semantic Scholar『Nutrition and Outcome of 100 Endoscopic Gastrostomy-Fed Citizens with Severe Dementia』
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART2】~認知症の種類・症状について~ | シニアライフアドバイザー監修 介護Q&A【いいケアネット】公式
脳梗塞
脳梗塞の患者さんの胃ろう造設後の平均寿命は、約2カ月(53日)と報告されています。
おこなわれた調査では、平均寿命の範囲が2~528日(約1年半)と広い結果となりました。重症度や年齢、合併症の有無などによって変動するのが大きな特徴です。
早期のリハビリと適切な栄養管理を組み合わせると、予後が改善される可能性があります。
参考:Oxford Academic『Outcome in Patients Who require a Gastrostomy after Stroke』
寝たきり
ある研究によると、寝たきり状態で胃ろうをした後は、60%の患者さんが1年以内に亡くなったと報告されています。
長く寝たきりの状態になると、合併症のリスクが高くなるためです。そのため、床ずれや誤嚥性肺炎などの予防が重要になってきます。
定期的な体位変換や口腔ケアなどをおこなうことで、合併症の予防につながり寿命が延びる可能性があります。
参考:Annals of the American Thoracic Society『Days out of Institution after Tracheostomy and Gastrostomy Placement in Critically Ill Older Adults』
関連記事:寝たきりの原因と予防対策 | シニアライフアドバイザー監修 介護Q&A【いいケアネット】公式
胃ろうにかかる毎月の費用

胃ろうの維持管理には、月額およそ7~9万円程度の費用がかかります。費用の内訳は、以下のとおりです。
| 内容 | かかる費用 |
| 訪問診療費 | 3万円 |
| チューブの交換費用 | 1〜2万円 |
| 栄養剤代 | 2万円 |
| その他の管理費 | 1〜2万円 |
中でも、栄養剤は医療品として扱われるため、保険が適用されます。ただし、これらの費用は患者さんの状態によって変動するケースがあるため、あくまで目安としておきましょう。
胃ろう導入を検討する際は、長期的な経済的負担も考慮に入れながら、介護保険サービスも上手く活用するのがポイントです。
胃ろうで後悔しがちな4つのこと

胃ろうで後悔しがちなことには、次の4つがあります。
- 自分で胃ろうを抜いてしまう
- 炎症や感染症のリスクがある
- 誤嚥性肺炎を引き起こす恐れがある
- 長期的な栄養管理やケアが必要になる
胃ろうをする際には、リスクや課題がある旨を理解しておきましょう。
自分で胃ろうを抜いてしまう
胃ろうチューブを自分で抜いてしまうことは、認知症の方に起こりやすい問題です。
胃ろうは体の中に異物を入れる処置であるため、身体への違和感が強く、精神的な不安定さから抜いてしまうケースがあります。
胃ろう後にチューブを抜いてしまうと、腹膜炎や出血などを起こすリスクが高まるのです。
自分で抜かないためには、つなぎ服を着用したり、チューブを出す位置を工夫したりする必要があります。
炎症や感染症のリスクがある
胃ろうをすると、炎症や感染症にかかりやすくなる可能性があります。
胃ろうの挿入部は外部と内部がつながるため、細菌が侵入しやすくなるためです。その結果、粘膜が赤く盛り上がる「不良肉芽」や皮膚のただれなどの症状が発生します。これらの症状は、患者さんにとって強い不快感をもたらします。
炎症や感染症を予防するためには、毎日の丁寧な清潔ケアや固定具の管理が大切です。
参考:NPO法人PDN『皮膚のトラブル』
誤嚥性肺炎を引き起こす恐れがある
胃ろうを使用していても、誤嚥性肺炎のリスクは完全には防げません。
胃の内容物が逆流して気管に入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。とくに体位や注入速度が不適切な状態になると、リスクが高まります。
栄養剤を注入するときは30度以上の上体を起こし、注入後30分以上はその姿勢を保ちましょう。1回の注入量や注入速度も患者さんの状態に合わせて調整します。
胃の負担を和らげることで、誤嚥のリスクを下げることにつながるのです。
長期的な栄養管理やケアが必要になる
胃ろうでは長期間の栄養管理やケアが必要なのも、後悔しがちな点です。
3~6カ月ごとにチューブを交換したり、挿入部位を清潔に保持したりするなど、専門的な知識と時間が欠かせません。具体的な作業は以下のとおりです。
- 栄養剤の注入
- 体位管理
- 口腔ケア
- チューブの閉塞予防
介護者の方は管理方法を習得する必要があります。訪問看護などの医療サービスを利用し、負担を減らすことも検討してみましょう。
胃ろうを選択する前にしておきたいこと

胃ろうの導入は、患者さんと家族の生活に大きな変化をもたらす重要な決断です。胃ろう導入前に押さえておきたいポイントは3つあります。
- 医療・介護の専門職とよく話し合う
- 本人の意志を尊重する
- 胃ろうについての知識や対応方法を身につける
導入を検討する際には、医療面だけでなく、介護や経済面なども含めて総合的に判断しましょう。
医療・介護の専門職とよく話し合う
胃ろうの導入を考える前に、医療・介護の専門職と十分に話し合うことが重要です。胃ろうが救命治療的なものなのか、延命治療的なものなのかを明確にするためです。
たとえば、脳卒中後の嚥下障害に対して胃ろうをおこなうときは、救命治療的な胃ろうとなります。一方で、認知症の進行により食事が困難になったときは、延命治療的な胃ろうとなる可能性が高いです。
また、他の治療方法との比較もしてみましょう。栄養補給の方法としては、点滴栄養や食形態の見直し、嚥下リハビリなどがあります。胃ろうを導入する判断は、専門職の意見が不可欠のため、医療・介護の専門職との対話が必要です。
老人ホーム探しはプロに入居無料相談・ご紹介 | 有料老人ホーム・介護施設を探すなら【いいケアネット】公式(CTA)
本人の意志を尊重する
胃ろうをする際は、本人の意思を尊重しましょう。
家族の意思だけで決めてしまうと、患者さんを不安にさせてしまいます。まだ意思疎通ができる段階であれば、胃ろうについての説明を丁寧におこない、本人の希望や不安な点を確認しましょう。
認知症のように意思確認が難しいケースでも、これまでの本人の価値観や人生観を踏まえて、家族で話し合いを重ねるのも大切です。
胃ろうについての知識や対応方法を身につける
胃ろうの日常的なケアは、適切な訓練を受けた家族も実施できます。
管理方法や起こりうるトラブルへの対応など、必要な知識と技術を事前に習得すれば在宅介護が可能です。
たとえば、訪問看護師から栄養剤の注入方法や観察ポイントなどの指導を受けたり、必要な医療器具や栄養剤の準備をおこなったりするのも良いです。
また、胃ろうケアに関する講習会への参加、同じ立場の家族との情報交換なども知識を深める良い機会となります。
寿命を延ばすために知っておきたい胃ろうに関するQ&A

胃ろうの管理にはさまざまな注意点があり、適切な対応が寿命に影響を与える可能性があります。胃ろうに関する3つの疑問を解説します。
- 高齢者が胃ろうをするときの注意点は?
- 認知症の終末期での胃ろうはどうするべき?
- 家族が知っておくべきことは?
それぞれの状況に応じた対応方法を理解すれば、より良い胃ろうの管理につながります。
高齢者が胃ろうをするときの注意点は?
高齢者が胃ろうを使用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 手術後のケア:高齢者は術後の感染リスクが高くなります。
- 栄養管理:高齢者は栄養素の吸収が低下しているケースがあるため、専門の栄養士と相談しながら食事内容を決定するのが重要です。
- 心理的サポート:高齢者は胃ろう導入による生活の変化にストレスを感じやすいため、家族やケアスタッフがしっかりとサポートする必要があります。
また、定期的な医療チェックも欠かせません。高齢者は他の病気を併発している可能性が高いため、定期的に健康診断に行きましょう。
認知症の終末期での胃ろうはどうするべき?
認知症の終末期において胃ろうを導入する場合、3つの配慮が必要です。
まず、認知症患者は新しい環境や変化に対して敏感です。胃ろうの導入によるストレスが認知症の症状を悪化させる可能性があります。
次に、認知症の患者さんは自分での食事が難しく、胃ろう導入のタイミングを見極めなければなりません。
また、家族やケアスタッフが認知症の患者さんをサポートするのも重要です。高齢者にみられやすい食事の嚥下障害や便秘などに対する対策をしましょう。
家族が知っておくべきことは?
胃ろうの管理は家族の協力が不可欠であり、さまざまな知識と準備が必要です。
まず重要なのは、日常的なケアの方法や緊急時の対応について医療者から十分な説明を受けることです。たとえば、栄養剤の注入方法、チューブの管理方法、合併症の早期発見のポイントなどを、実践的に学んでおきましょう。
また、介護保険サービスの利用や医療費の助成制度など利用可能な支援についても事前に確認しておくことをお勧めします。
一人で介護を背負おうとせずに、家族や介護サービスなどの利用も検討してみてください。
関連記事:親の介護を兄弟で分担すべき3つの理由|兄弟トラブル回避の方法も解説
まとめ|胃ろうは寿命に直接的な影響を与えるわけではない

胃ろうを造設した後の平均寿命は約3年とされていますが、基礎疾患や患者さんの状態によって異なります。
胃ろうをする際には、感染症や誤嚥性肺炎などのリスクがあるため、長期的な栄養管理やケアが必要です。導入を検討するときは、医療・介護の専門職に相談したり、本人の意思を確認したりしましょう。
胃ろうは直接的に寿命を延ばすものではありません。しかし、適切な栄養管理によって患者さんの生活の質を維持・向上させられます。
導入の判断は、患者さんの状態や家族の介護力など、さまざまな要因を総合的に考慮してみましょう。一人での介護が難しいときは、介護サービスの利用も検討してみてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。