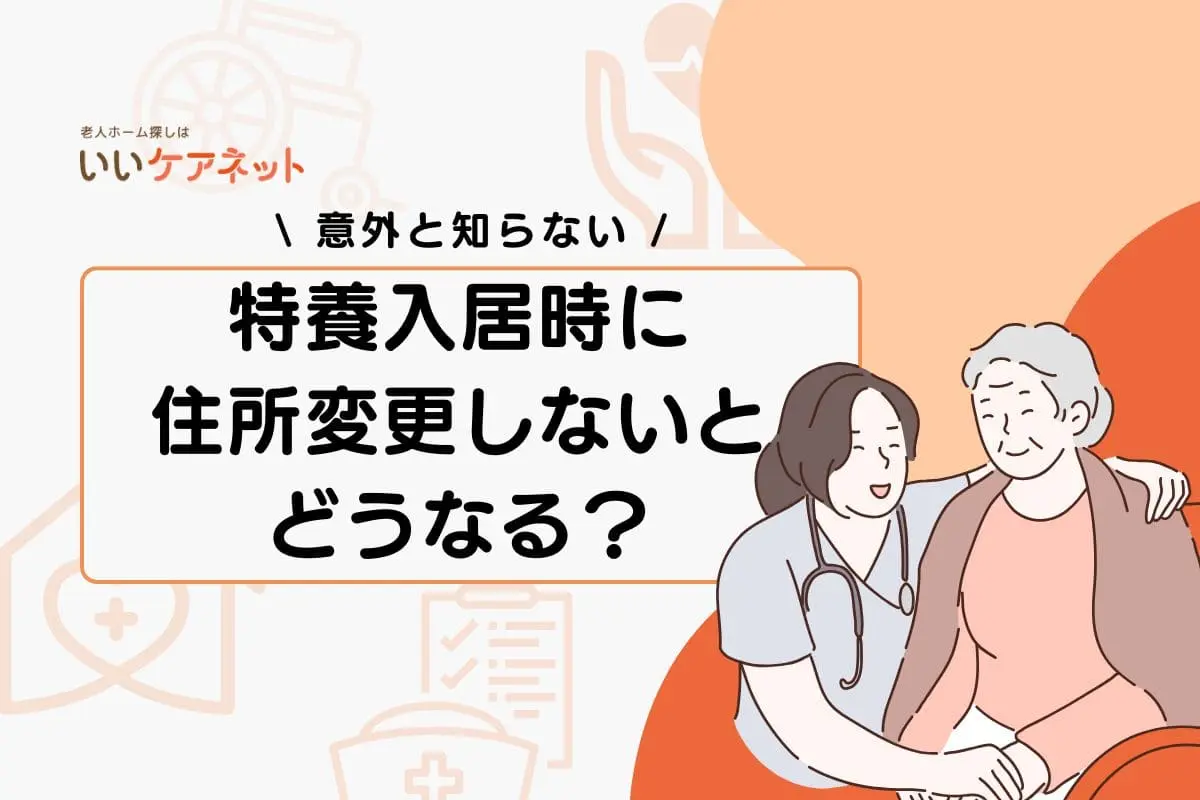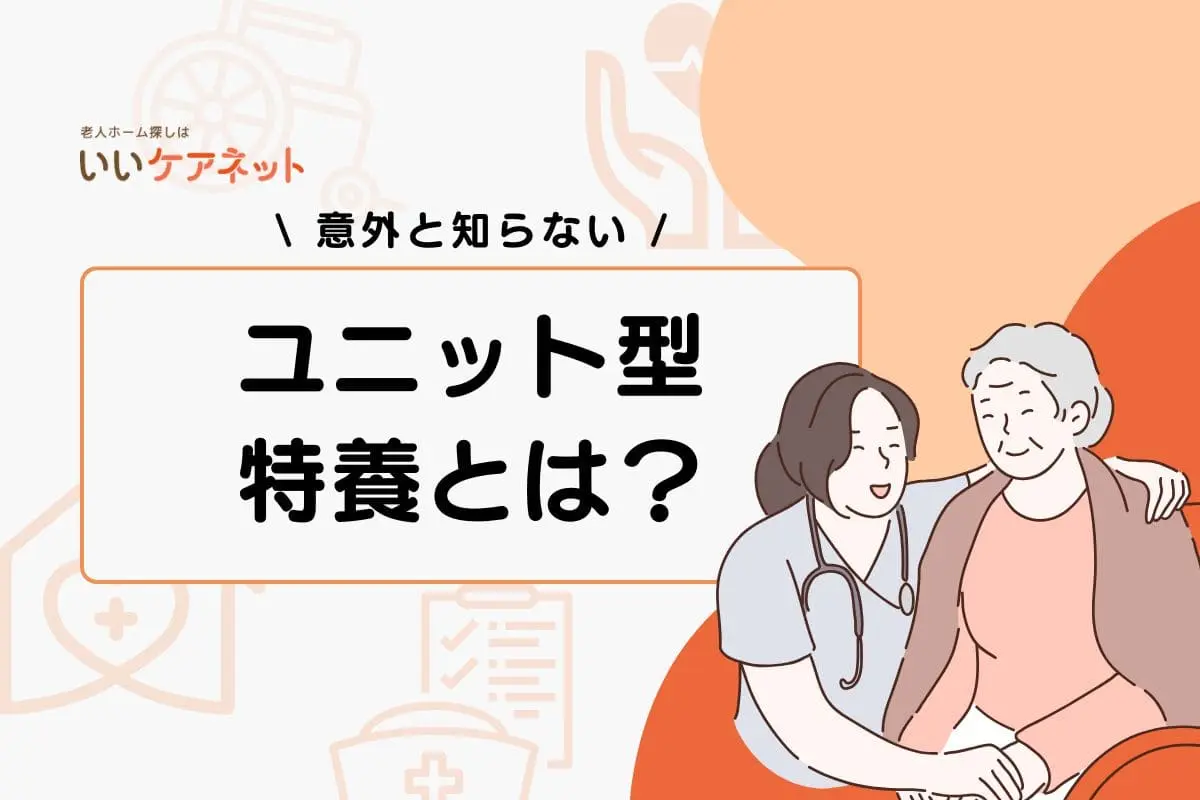高齢化が進む日本社会では、誰にも看取られずに亡くなり、発見まで時間がかかる「孤独死」が深刻な問題になっています。
親はまだ元気そうだけれど、年齢的に体力や健康面が心配で、いざというときを考えると「誰もいなくて大丈夫なのか?」と感じる方は多いでしょう。
同居するのは難しいものの、どのような孤独死対策をすれば良いのかわからないと思う方は少なくありません。
記事では、孤独死が起こってしまう主な原因を3つに整理しつつ、あらかじめできる予防策について解説します。
高齢のご家族ができるだけ安心して暮らせるように、家族として何ができるのか、一緒に考えてみましょう。
孤独死とは?現状や傾向について解説

ニュースで話題として取り上げられることが少なくない孤独死は、誰に起きても珍しくない亡くなり方です。
「孤独死」といった言葉を耳にすると、離れて暮らす高齢の親を思い出して不安になるように、一人暮らしの高齢者はとくに注意しなければいけません。
まず、そもそも孤独死とはどのような亡くなり方なのかを解説します。
孤独死とは誰にも看取られず長期間放置される亡くなり方
孤独死は「誰にも看取られずに死亡し、一定期間が経過してから発見される状態」を意味する亡くなり方です。
法的な定義はないものの、内閣府の資料では、孤独死を「誰にも看取られることなく息を引き取り、その後相当期間放置されるような悲惨な死」と定義しています。
たとえば、一人暮らしの高齢者が病気で倒れて誰にも発見されず、数日後に異臭や郵便物の滞留を不審に思った隣人に発見されるような亡くなり方が孤独死です。
亡くなる原因はさまざまであり、子ども世帯とは離れて暮らしていたり、近隣住民との交流がなかったりなど、社会的接点が少ない人は孤独死を迎えやすい傾向にあります。
体調が急変しても適切な医療を受けられず、誰にも看取られずに亡くなってしまうのが孤独死の大きな特徴です。
厚生労働省は「孤立死ゼロ・プロジェクト」を立ち上げ、国として「孤立死」を防止するための取り組みを始めています。
省庁や自治体では孤立死を使い、メディアでは「独」が付く孤独死を使う傾向にありますが、意味合いはどちらも同じ意味合いです。
高齢者の孤独死人数は増加傾向にある
少額短期保険協会がおこなった調査結果(「第7回 孤独死現状レポート」および「第9回 孤独死現状レポート」)によると、2021年から2023年にかけて孤独死の件数は増加傾向にあるとわかりました。
とくに、東京23区や大阪市のように賃貸物件に住む単身世帯が多い都心部では、近隣住民との接点が乏しい傾向にあり、体調不良や緊急事態でも気付かれにくい風潮です。
高齢化が進むにつれ、子どもが遠方に住んでいるケースや配偶者を失って独りで生活しているケースが珍しくありません。
一人暮らしの高齢者が増え、近隣住民との接点も少ない都市部では、体調急変時に誰も気付かずに亡くなるリスクが高まります。
高齢者の孤独死は男性が多い
先述の少額短期保険協会の調査では、高齢者の孤独死において男性の割合が女性よりも高い傾向が見られます。
妻に先立たれた高齢男性が一人暮らしとなり、食事や掃除、健康管理をうまくこなせる男性が少ないのは男性の孤独死が多い理由のひとつです。
さらに、長年働いてきた男性ほど退職後に社会との接点を失いやすく、周囲の助けを借りるのが苦手な傾向も指摘されています。
日常的な体調管理がうまくいかないことで持病が悪化したり、栄養不足で生活習慣病を患ったりしても誰にも気付かれず、倒れてからしばらくして発見されるケースは、けっして他人事ではありません。
孤独死が起きる3つの原因

孤独死を引き起こす要因は、一つだけではありません。
健康状態や社会的孤立、経済状況など、さまざまな状況が重なったときに孤独死が起きやすいため、さまざまな観点から対策を講じる必要があります。
以下では孤独死につながりやすい3つの原因を紹介します。離れて暮らす高齢の家族がこれらのリスクを抱えていないか、チェックしてみてください。
健康上の問題や医療・介護体制の不足
ひとつめは、要介護状態や慢性的な持病があるにもかかわらず十分な医療・介護を受けられないケースです。
たとえば、遠方に住む子どもがなかなか実家に帰れず、転倒や寝たきりが心配でもサポートが追いつかないまま放置されてしまうケースは少なくありません。
東京都世田谷区の調査では、孤独死された方の約7割近くが福祉サービスを利用していなかったとの報告もあり、心身の不調と社会との接点の薄さが組み合わさった結果で孤独死が起きてしまったと言えます。
また、認知症やうつ病を抱えている高齢者が通院を拒否してしまうケースも起きています。
高齢者本人が周囲からの助言にも耳を傾けず周囲との接点を絶ってしまうのは、病状が悪化しても気付かれずに孤独死を迎えやすく危険な状態です。
持病の急変の際に救急車の手配や応急処置をできる人がいない場合、持病を抱える高齢者は孤独死を迎えやすくなります。
関連記事:老老介護とは?知っておくべき原因や問題点、解決策について
家族や友人、近隣住民等との交流頻度低下
そもそも一人暮らしの高齢者は、会話の機会が少なさが極端です。
内閣府のデータでも、健康状態が良い人ほど「毎日誰かと会話する」割合が高い一方、健康状態が良くない高齢者では約13.1%もの人が「ほとんど会話をしない」と回答しています。
日常的に人と接しない環境では、万が一体調に異変が起きても気付いてもらえず、孤独死へとつながるリスクが高まるわけです。
会話の機会が減るほど体力や気力も低下しやすいだけでなく、万が一の異変を助け合う人脈もないため、孤独死リスクが大きくなります。
都心部の賃貸物件で生活している場合、隣人との交流がほぼ皆無なケースは珍しくありません。周囲に誰一人として気にかける人がいない状態が続くと、部屋で倒れて亡くなった場合でも遅れて発見されるケースは多数あります。
なお、都心部とは逆に地方の過疎地域では、住民が減り助けを求める相手がいない場合も多く、環境要因で孤立が深まる事例も後を絶ちません。
生活費や貯蓄の不足など経済的困窮
経済的に厳しい状況は医療や介護の利用や食生活など、さまざまな面で制限が発生するため、孤独死のリスクが高まります。
たとえばお金がないために病院に行けず、持病が重症化して命を落としてしまう人も一定数存在するのは事実です。
また、光熱費を節約するためにエアコンや暖房器具を極力使わず、熱中症や低体温症を起こしてしまう事例も、多数報道されています。
食事の栄養バランスが崩れることで生活習慣病が悪化し、治療費も捻出できないまま自宅で倒れると、発見が遅れて孤独死につながるわけです。
お金の問題からデイサービスや介護施設への入所を諦め、日々の生活を誰にも相談せず暮らす高齢者も一定数います。
経済的困窮と健康リスクが相互に影響しあうのも、孤独死が起きる理由のひとつです。
関連記事:セルフネグレクトとは?原因や対策を解説【高齢者は要注意】
高齢者の孤独死を防ぐ3つの対策

孤独死を防ぐためには、公的サービスや周囲の協力を活用するだけでなく、高齢者本人や家族による積極的な行動が、孤独死を防ぐ対策として機能します。
以下では、代表的な孤独死対策を3つ紹介します。
訪問介護やデイケア、介護施設を利用する
訪問介護でヘルパーが定期的に来てくれれば、家事サポートや介護だけでなく、安否確認の面でも安心できます。
デイケアやデイサービスの利用は、高齢者が家に閉じこもらず人と触れ合う時間を持てるのも大きなメリットです。
実際にデイケアの送迎で利用者の体調異変が早期発見された例もあり、些細な変化を第三者が察知できれば、孤独死を迎えずに済む可能性が上がります。
より確実な対策を求める場合は、介護施設への入所を視野に入れましょう。
介護施設であれば、常にスタッフやほかの利用者の目があるため、24時間体制で見守りと専門的ケアが受けられます。
自宅での暮らしが厳しい人や医療的ケアが必要な方にとって、施設の利用は孤独死リスクを大きく下げる有効策です。
地域・自治体による孤独死対策
多くの自治体は、孤独死を減らすためにさまざまな施策を実施しています。
たとえば、神奈川県相模原市では65歳以上の独居高齢者向けに牛乳配達と連携した見守りサービスを実施し、配達員が異変を感じたら市と連携して対応するサポートをおこなっています。
そのほかの自治体でもおこなわれていることが多いのは、週1回の訪問員による安否確認、緊急通報装置の貸し出しなどの対策です。
自治体によっては、緊急通報装置の貸与や電話訪問などをおこなっていることもあるため、できれば親御さんの住む地域のサービスを一度調べてみましょう。
地域包括支援センターや市区町村の福祉課などが相談窓口を開放していることが多いため、遠方の家族に関して気になる際は、早めに問い合わせるのがおすすめです。
関連記事:高齢者一人暮らし|限界を見極めるポイントは?対策や支援方法を解説
ITツールを利用する
遠隔地に住む家族が高齢の親を見守る手段として、カメラやセンサーを活用するITツールが注目されています。
たとえば家電の稼働状況や室内の人感センサーを遠隔監視し、動きが長時間なければアプリに通知が届く仕組みは、遠方の家族を見守るサービスとして人気です。
セコムが提供しているApple Watchとの連携サービスでは、転倒検出後に操作がない場合自動で連絡が入り、家族にも共有されるようになっています。
IT技術をうまく活用すれば、離れて暮らしていても高齢者の異常を早期発見できる可能性が高まります。
加えて、スマホを使ったビデオ通話などでこまめに様子を確認するのも有効な手段です。
ITツールだけですべてが解決するわけではありませんが、従来の見守り体制に加えて利用すれば、孤独死のリスクを大幅に軽減できます。
もし親御さんがデジタル機器に抵抗を感じる場合は、できるだけ簡単な仕組みを選ぶと良いでしょう。
孤独死の原因を把握して事前の対策をしよう【まとめ】

孤独死は「誰にも看取られず、長期間放置される亡くなり方」を意味しており、高齢化社会や地方の過疎化などが進む日本で急増しつつある重大な問題です。
孤独死が起きる原因としては、健康上の問題や医療・介護体制の不足、家族や近隣住民などとの交流頻度低下、生活費や貯蓄不足などの経済的困窮が挙げられます。
さまざまな原因が重なると、一人で暮らす高齢者が体調を崩しても周囲が気付けないまま亡くなるケースは少なくありません。
高齢の家族と離れて暮らしている場合は、親御さんの生活や健康状態をしっかり把握した上での地域の福祉サービス利用や、家族同士の連絡体制の整備などが孤独死対策につながります。
孤独死はけっして他人事ではなく、誰にでも起こり得る問題です。
今のうちにできる対策を検討し、離れていても家族が安心して長生きできる環境を目指しましょう。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。