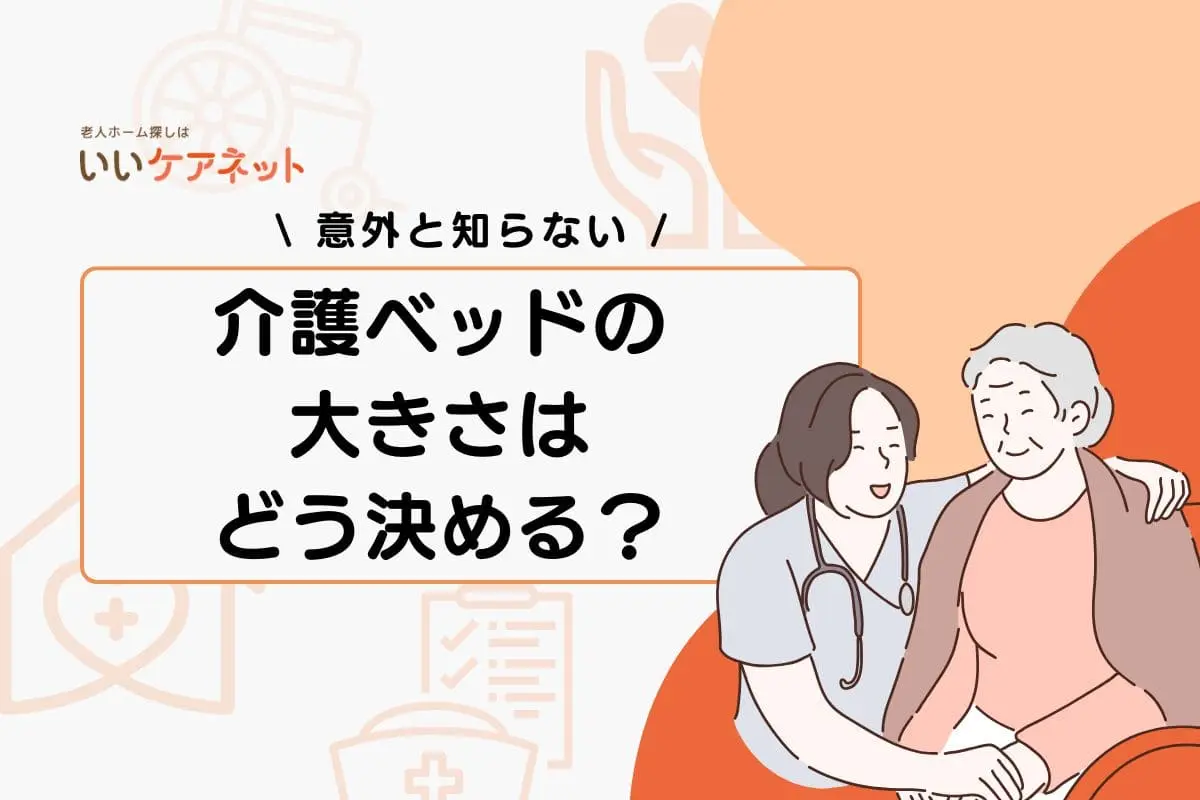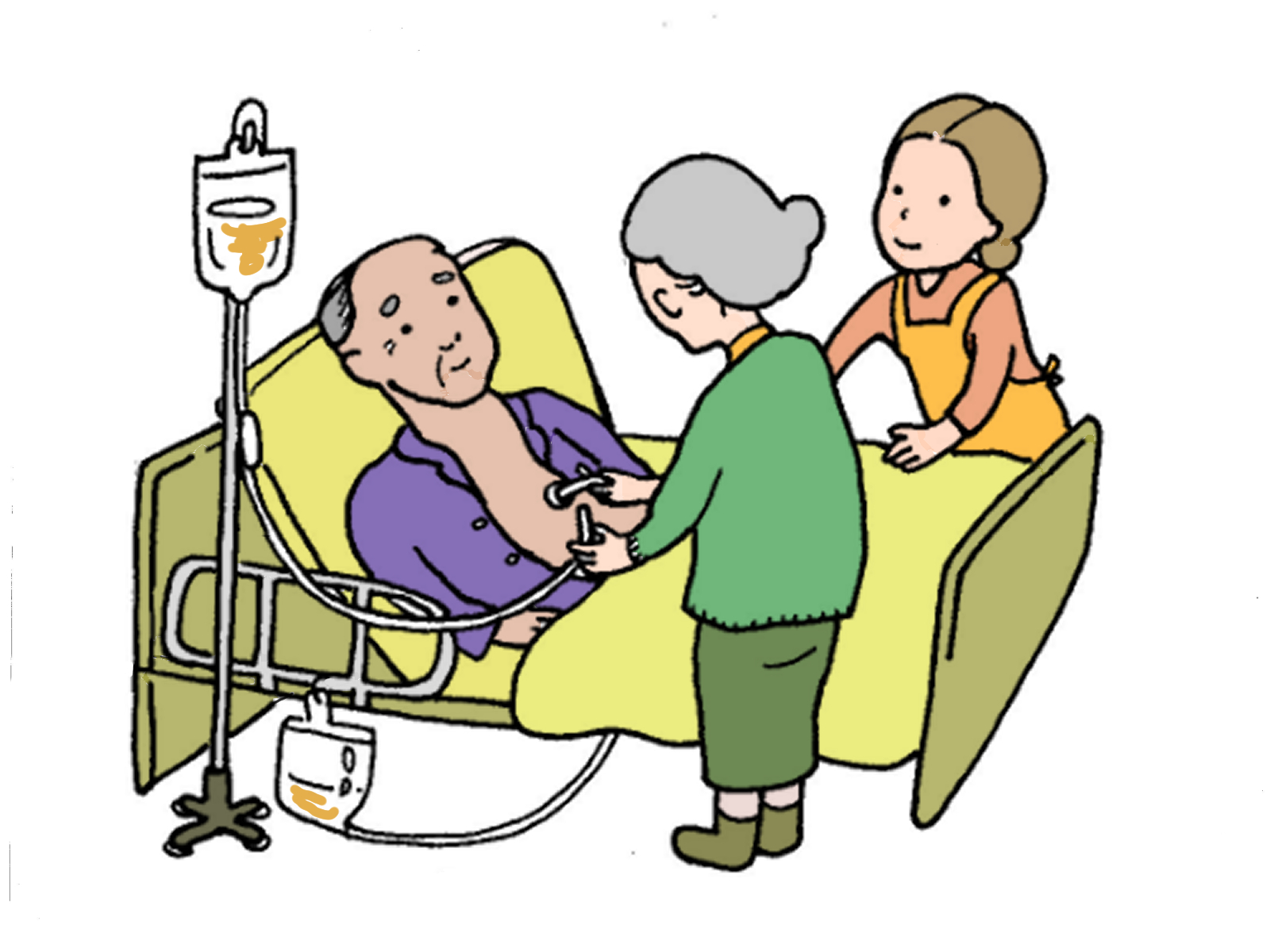介護と仕事の両立に悩む方は多いのではないでしょうか。
介護離職を避けつつ、仕事を続けること自体は可能ですが、職場からの理解が得られるかが不安になるものです。
そこで本記事では、介護と仕事を両立するための具体的なポイントや制度を詳しく解説します。
介護と仕事の両立を実現するための介護サービスや両立支援制度、環境の整え方などを紹介しています。
仕事が忙しく、十分に介護できるか不安に感じている方を含め、ぜひ本記事を参考にしてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
介護と仕事の両立はできない?きついとの声が大多数
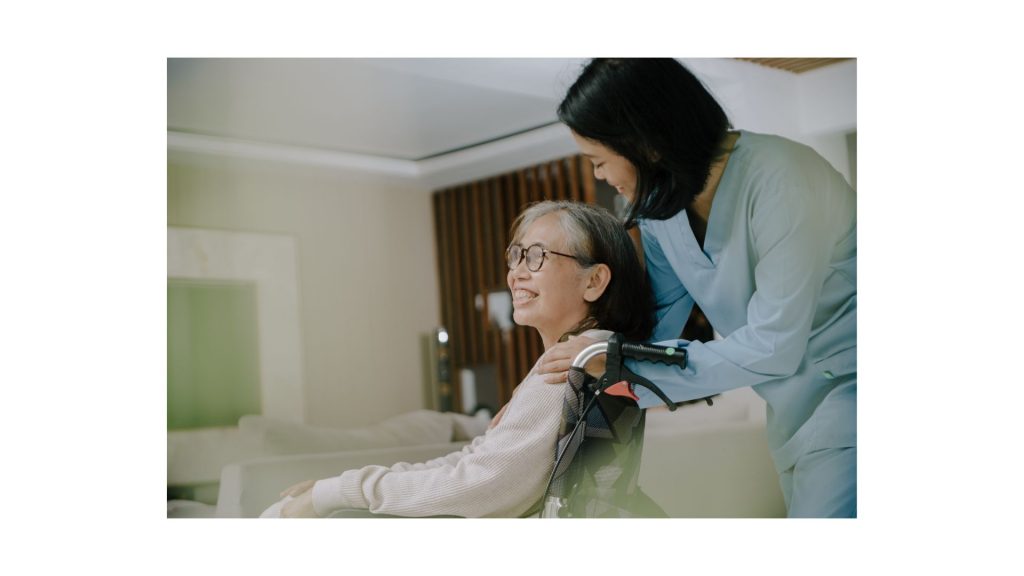
介護と仕事の両立について「仕事との両立は難しい」との声に溢れています。
2024年株式会社ビースタイルホールディングスの調査結果によると、約61.8%の方が「とても難しい」と答える結果が出たのです。
介護と仕事の両立における印象調査でも、95.6%の方が「難しい」と考えている結果が出ており、両立できないと捉え、介護離職した方もいます。
同調査のフリーコメントでも介護と仕事の両立がきついと職場にも捉えられ、アルバイト雇用されている方が「来年の更新はしない」との結果もあります。
成長を見守る育児とは異なり、衰退していくのを見守る介護における精神的な疲れや体力的な限界を感じ、両立できないとの声が大多数です。
介護と仕事を両立するためには、職場からの理解だけでなく自分の体力も考慮した環境に整えていく必要があります。
参考:PRTIMES|“介護と仕事の両立”について、どう思う?「両立は難しい」95.6%「介護することになりそう」52.3%
介護と仕事を両立させるためのポイント

介護と仕事を両立させるには、以下のポイントを重視するのがおすすめです。
- 職場に在宅介護をしていると伝える
- 介護サービスを利用して家族の負担を減らす
- 早めに介護保険の申請をする
- 1人で悩まない環境を整える
- 近所の方と良好な関係を構築する
それぞれ厚生労働省の「【確定版】仕事と介護の両立支援_概要版」をもとに解説するので、ぜひ参考にしてください。
職場に在宅介護をしていると伝える
介護と仕事を両立させるには、職場に在宅介護が必要な親がいる、もしくは在宅介護になりそうと伝えなければいけません。
要介護者の状況によっては、週(または月)に一度、病院に付き添わなければいけない日があります。
病院の混雑状況にもよりますが、病院の付き添いがある日は午前中だけでも休んだり遅れての出社を許してもらったりする必要が考えられます。
休みの日が増えると、ほかの従業員への負担が増えるため、職場の協力体制を整えなければいけないのです。
介護に直面したら、まずは職場に介護の状況を伝えつつ、働き方の変更が可能なのかを相談しましょう。
関連記事:在宅介護のメリットやデメリットは?家族の負担ポイントなどを解説!
介護サービスを利用して家族の負担を減らす
介護と仕事を両立させるには、介護サービスを利用して家族の負担を減らすのがおすすめです。
介護サービスは自宅にスタッフが来てもらう訪問介護や、日帰りで利用するデイサービス、宿泊するショートステイなど、多くの選択肢があります。
以下の表では、介護と仕事を両立させるための介護サービスの一例をまとめました。
| 介護サービス名 | 説明 | 利用のメリット |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 専門の介護スタッフが自宅を定期訪問し、食事の準備や清掃などをおこなう | 家族が仕事中でも問題なく、介護の負担を分散できる |
| デイサービス | 日中、介護が必要な方を施設で預かり、リハビリやレクリエーション活動を提供している | 家族が仕事や自分の時間を持てる |
| ショートステイ | 介護を必要とする家族を一時的に施設に預ける | 家族が休息を取り、心身をリフレッシュできる |
関連記事:介護が必要になったら何から始めるべき?受けられるサービス内容とは?
早めに介護保険の申請をする
介護と仕事を両立させるためには、制度の活用が不可欠で、介護保険の申請を早めに済ませておくのが重要です。
多くの方が介護が必要になってから手続きをはじめる傾向にありますが、申請手続きには時間がかかるため、早めの準備が求められます。
介護保険制度を活用するために必要な要介護認定には、申請から最大30日かかってしまうのです。
退院時期が2週間後と決まった場合、退院後に要介護認定の申請をするのではなく、入院中に申請しておくとスムーズに介護サービスが受けられます。
退院後、いきなり介護が必要になっても、仕事の両立が難しくなってしまうため、1カ月程度の余裕を持たせて介護保険の申請を済ませておきましょう。
関連記事:介護保険法をわかりやすく解説|目的や制度の仕組み、最新の改正まで
1人で悩まない環境を整える
介護と仕事を両立させるには、専門家の意見を聞ける環境を整えておく必要があります。
介護サービスを受けるために必要な要介護認定の申請には、ケアプランの作成が必要であり、作成にはケアマネジャーとの連携が必要です。
なお、ケアマネジャーの仕事はケアプランの作成だけでなく、介護者との会話を通じた悩み・不安の解消も含まれます。
つまり介護の不安である仕事との両立について、1人で悩まず担当のケアマネジャーに相談するのがおすすめになるのです。
介護保険制度を活用すれば、月1回以上要介護者の自宅に訪問してくれるだけでなく、電話やメールでの相談を受け入れています。
各自治体や地域包括支援センターなど、相談先は複数あるため、1人で抱えずにすぐ相談して悩みを解消していきましょう。
関連記事:地域包括支援センターの対応がひどい?認知症家族に役立つ相談先と施設
近所の方と良好な関係を構築する
介護と仕事の両立において、地域の支援は大きな助けとなります。
近所の方と良好な関係を築いておくと、急な用事や緊急時に助けを求めやすい環境が整います。
近所の方と良好な関係を構築し、介護と仕事の両立を叶えやすくするポイントは以下のとおりです。
- 日常的な挨拶や会話を通じて交流を深め、信頼関係を築く
- 地域のイベントや集まりに参加して顔を合わせる機会を増やす
- 介護の状況を軽く共有して理解を深めてもらう
- 地域の自治会や町内会に参加し、地域の情報を得る
- 感謝の気持ちを忘れずに伝える
近所の方と良好な関係を構築しておけば、本人が認知症で徘徊してしまっていたとしても、早期発見につながる可能性を高めてくれます。
仕事の関係で家を離れなければいけない日が定期的にある方は、近所の方に在宅介護をしていると伝えられる信頼関係を構築しておきましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
介護と仕事の両立支援できる制度一覧

介護と仕事を両立するために利用できる制度は、多くの働く介護者にとって大きな助けとなります。
数多くの両立支援制度があるため、一例を以下の表で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得できる。 |
| 介護休暇 | 年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで取得可能。時間単位での取得も可能。 |
| 所定外労働の制限 | 1回の請求で1カ月以上1年以内、請求回数に制限なし。事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は請求を拒める。 |
| 時間外労働の制限 | 1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる。1回の請求で1カ月以上1年以内、請求回数に制限なし。 |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時までの労働を制限できる。1回の請求で1カ月以上6カ月以内、請求回数に制限なし。 |
| 所定労働時間の短縮等の措置 | 短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、介護費用の助成措置のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用が可能。 |
| 介護休業給付 | 要件を満たした介護休業取得者は給与の67%の介護休業給付金を受給できる |
上記の制度があると把握し適切に活用すると、介護と仕事の両立を助ける要因になります。
制度の詳細や条件については、各自治体や企業の担当窓口に問い合わせて確認しましょう。
関連記事:親の介護で退職する前に|メリット・デメリット、介護の制度を解説
介護と仕事における両立支援制度や介護サービスの活用事例

ここからは介護と仕事を両立するための助けとなる両立支援制度や介護サービスを活用した事例を紹介します。
厚生労働省の「仕事と介護の両立モデル」を参考にした活用事例をもとに解説していきます。
家族の声に耳を傾けたサポート
80代の両親に対し、正社員・フルタイム勤務している50代の女性が介護と仕事を両立させた事例を紹介します。
とくに母親は股関節が曲がったため、杖をついた歩行も困難になり、要介護2と判定された方の事例です。
介護と仕事を両立させるために、担当のケアマネジャーは50代女性の両親や主治医と話し合い、仕事に集中できるケアプランを提出しました。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自身が実施している介護内容 | ・母:3年前に要支援2の認定。股関節の問題で歩行困難。
・父:糖尿病による目の手術を複数回経験。要介護1。 ・父母ともに日中は自宅で過ごす。母が主に父の様子を確認。 |
| 介護サービスの利用状況 | ・母:リハビリ中心のデイサービスを週2回利用。
・父:デイサービスを週1回利用。専門家による訪問リハビリを週1回。 |
| 勤務先の支援 | ・貨物輸送業の経理課長。フルタイム勤務。
・有給休暇の取得が増加。土曜日の休暇取得に職場の理解あり。 ・介護休業や介護休暇制度についての情報不足。 |
職場に介護の事情を話し施設に入所
80代の両親、とくに父親が脳卒中で半身不随、言語障害になっている方への介護で仕事と両立させた50代女性の事例を紹介します。
50代女性は製造業で管理職に従事していたため、勤務先の規定内で働けるよう相談し、介護サービスを利用しました。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自身が実施している介護内容 | ・市からの助成金で自宅改修。父は現在、介護老人保健施設に入所。
・母は心筋梗塞後、介護保険サービスを利用。家の中での介助は不要。 ・母の腎機能低下により料理の下処理を担当。 ・介護福祉士の資格を取得し、知識と経験を活かして介護を実施。 |
| 介護サービスの利用状況 | ・母はデイサービスを週2日利用。異なる事業所を選択。
・母はデイサービス利用に抵抗感があったが、現在は積極的に参加。 ・ケアマネジャーとの信頼関係を築き、面談や報告に配慮がある。 ・母は介護タクシーを利用し、父の施設に面会。 |
| 勤務先の支援 | ・勤務先の規定内で始業・終業時間を調整。
・介護休業制度を調べ、有給休暇を活用。 ・35時間分の時間単位の有給休暇と25日分の有給休暇を取得。 |
ケアマネジャーからの情報提供による認知症支援
認知症の疑いが出てきた70代女性(義母)に対し、フルタイム勤務の40代女性がケアマネジャーからの情報提供で介護と仕事を両立させた事例を紹介します。
70代女性は認知症による被害妄想が悪化してしまい「泥棒がいる」「通帳がなくなった」などというようになりました。
介護と仕事を両立するためにデイサービスやショートステイを利用し、認知症の支援をした方の事例です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自身が実施している介護内容 | ・日常的なサポート。
・家族一同での協力体制を構築する。 |
| 介護サービスの利用状況 | ・2012年からデイサービスを利用し、現在は週4日。
・ショートステイも月1回(1泊2日)利用 |
| 勤務先の支援 | ・上長と同僚の理解を得る。
・デイサービス利用時には柔軟な勤務時間の調整をしてもらう。 |
介護と仕事の両立に悩む前に専門家に相談しよう!【まとめ】

介護と仕事の両立は、多くの方にとって大きな課題ですが、適切なサポートと工夫を取り入れると、負担を減らせる体制が整います。
まずは、職場に自分の状況を理解してもらい、在宅介護の現状を共有するのが重要です。また、介護サービスや介護保険を積極的に活用し、家庭内の負担を軽減しましょう。
さらに、周囲の人々と良好な関係を築き、1人で抱え込まないようにするのも大切です。
悩んだときは専門家への相談をためらわず、適切なアドバイスを受けるのをおすすめします。
なお、いいケアネットでは、介護と仕事を両立できるような介護サービスを含めた「入居無料相談」を受け付けています。
「仕事が忙しくて、なかなか相談の時間が確保できない」方も含め、気軽にご相談ください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。