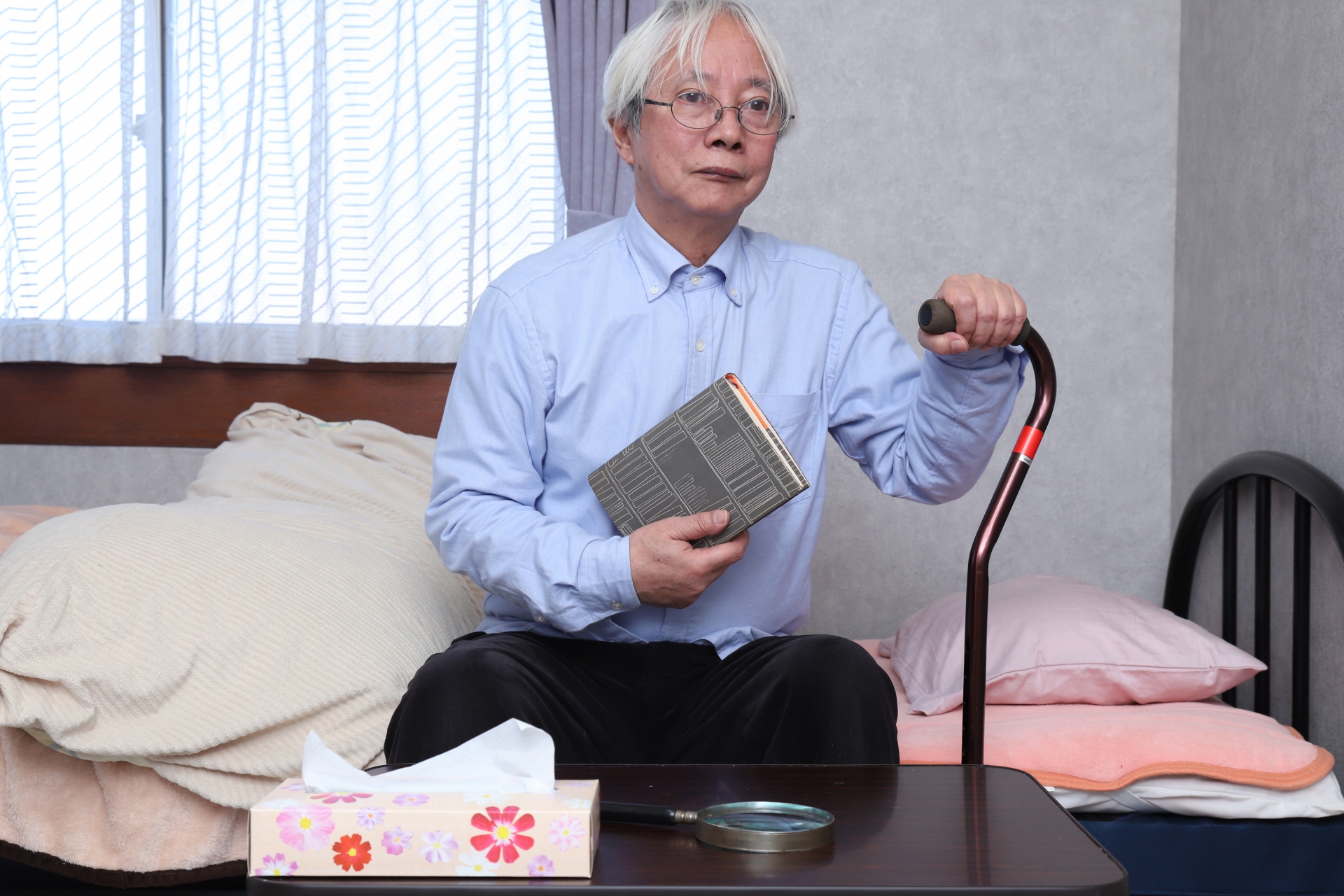「嚥下訓練のパタカラ体操ってなに?」
「パタカラ体操を実践するとどのような効果があるの?」
といった悩みを抱えていないでしょうか。
嚥下訓練であるパタカラ体操とは、口や舌の周りの筋肉を鍛える体操です。パタカラ体操を実施すると、誤嚥防止や噛む力の向上効果が期待できます。
本記事では、パタカラ体操をすると期待できる効果や具体的なやり方について解説します。親の介護をしていて、誤嚥対策が必要だと感じた方はぜひ参考にしてみてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
パタカラ体操とは簡単にできる嚥下訓練
パタカラ体操とは簡単に口や舌の周りを鍛えられる嚥下訓練のひとつです。
そもそも嚥下訓練とは、誤嚥対策や噛む力の低下に対する回復を目的にしたリハビリテーションを指します。
パタカラ体操は、厚生労働省の「口腔機能向上マニュアル」にて、嚥下をメインテーマにした事例にも記載されているほどです。試してみる価値は大いにあります。
とくに、加齢に伴う口腔機能の低下を予防したい方や誤嚥のリスクを減らしたい方は、パタカラ体操がおすすめです。
道具が不要であり短時間で効果を見込めるため、嚥下訓練の中でも簡単に取り組めます。
パタカラ体操で期待できる3つの効果と目的
パタカラ体操を実践した場合に、期待できる効果と目的は以下の3つです。
- 噛む力や飲み込む機能が維持され向上が期待できる
- 唾液の分泌が促進される(ドライマウスの防止)
- 発音がはっきりし、口が動きやすくなる
それぞれ詳しく解説していきます。
噛む力や飲み込む機能が維持され向上が期待できる
パタカラ体操によってもっとも期待できる効果は、噛む力や飲み込む機能の向上です。パタカラ体操をおこない、口や舌の筋肉を鍛えると、口が大きく開くようになります。
口や舌を動かしやすくなると、噛みやすさや飲み込みやすさが向上します。誤嚥の心配もなくなるので、介護者や家族にとっては大きな安心感が得られます。
唾液の分泌が促進される(ドライマウスの防止)
パタカラ体操により口や舌の筋肉を刺激すると、唾液腺が活発に働き、唾液が分泌されやすくなります。
ドライマウスの主な原因は唾液分泌量の低下です。パタカラ体操をすれば、ドライマウスの防止につながります。
また、ドライマウスは口の乾燥以外にも、オーラルフレイルに代表される口の機能の衰えのサインでもあります。口や舌の筋肉を刺激し唾液の分泌が促進されるのは、パタカラ体操をおこなう大きなメリットです。
発音がはっきりし、口が動きやすくなる
パタカラ体操を続けると、口が動きやすくなるため、発音がはっきりする効果も期待できます。
発音が良くなると、言葉が伝わりやすくなりコミュニケーションがスムーズになります。人間関係も良好になるかもしれません。
また、発音が刺激となり、脳の活性化にもつながります。パタカラ体操をおこない、綺麗に発音できるように取り組んでみてください。
【簡単】パタカラ体操のやり方とコツ
ここからは、パタカラ体操のやり方とコツを3つに分けて解説します。具体的には以下のとおりです。
- 「パ」「タ」「カ」「ラ」を一音ずつ発音する
- 連続して発音する
- 文章にして発音する
順番に見ていきましょう。
「パ」「タ」「カ」「ラ」を一音ずつ発音する
パタカラ体操では、「パ」「タ」「カ」「ラ」と一音ずつ発音していきます。発音するときには、口を大きく動かすようにしてください。
また、それぞれの発音時のコツを以下の表にまとめました。
| 発音する言葉 | コツ |
| パ | 唇をしっかり閉じる |
| タ | 舌を上あごにくっつける |
| カ | 喉の奥を閉めるようにする |
| ラ | 舌を丸める |
コツを意識しながらパタカラ体操をすると、効率よく口や舌の筋肉を鍛えられます。より効果を実感しやすくなります。
連続して発音する
次に、「パタカラ」と連続して発音する方法を紹介します。
「パパパ……」「タタタ……」「パタカラパタカラ……」のように連続しての発音を5回くり返しましょう。
発音するときは速くするのではなく、はっきりとするのがコツです。
文章にして発音する
「パタカラ」が含まれた文章を発音する方法もあります。代表的なものは以下のとおりです。
- ぱんだのたからもの
- なまむぎなまごめなまたまご
- となりのきゃくはよくかきくうきゃくだ
これら以外にも、早口言葉やかえるの合唱も介護施設や病院でよく活用されています。ぜひ以下の動画を参考に、一緒に試してみてください。
パタカラ体操をするタイミングは食事の前が効果的
パタカラ体操をするタイミングは、食事の前が効果的です。嚥下訓練をおこない、口の周りの筋肉を動かしておくと、誤嚥の予防になります。
食事の前にパタカラ体操をすると決めておけば、嚥下訓練を継続しておこなえるため、咀嚼や嚥下機能の向上が見込めます。
ただし、食事前に時間が取れないのであれば、無理におこなう必要はありません。できるときに負担にならない程度に実践するのがポイントです。
嚥下訓練のパタカラ体操についてよくある質問と回答
最後に、嚥下訓練のパタカラ体操について、よくある質問と回答を紹介します。
パタカラ体操とあいうべ体操は何が違うの?
パタカラ体操とあいうべ体操は、期待される目的や方法が異なります。以下の表にそれぞれの違いをまとめました。
| 目的 | やり方 | |
| パタカラ体操 | 噛んだり飲み込んだりするために口や舌の筋肉を鍛える |
|
| あいうべ体操 | 口呼吸を鼻呼吸に改善したり、口元の筋肉を引き締めたりするために唇の筋肉を鍛える |
|
パタカラ体操以外の嚥下訓練には何がある?
パタカラ体操以外の嚥下訓練には、以下の3つがあります。それぞれの特徴を表にまとめました。
| 目的 | やり方 | |
| 口腔体操 | 口や舌の筋肉を幅広く鍛える |
|
| 早口言葉 | 発音改善や嚥下防止 |
|
| かえるの合唱 | 喉の筋力向上と呼吸改善 |
|
それぞれ目的が異なる分、当然やり方も違います。パタカラ体操が上手くハマらない場合は、以上の3つも実践してみてください。
パタカラ体操は1日何回くらいすれば良い?
パタカラ体操をする回数は、毎食前の3回が推奨されています。
ただし、体調や誤嚥の危険具合などの状況に合わせて、頻度や回数を調整するようにしましょう。
パタカラ体操が難しい場合に何かできる方法はない?
パタカラ体操をするのが難しい場合は、「パタカラW」を活用してみてください。
「パタカラW」は、口腔機能を向上させるために作られた医療機器です。
1日に3〜4回、3分間口をつぐむだけで表情筋が刺激され、脳神経に良い刺激を与えます。また、正しい呼吸が促され、免疫機能の向上も期待できます。
嚥下訓練に積極的でない高齢者の方におすすめだといえます。
嚥下訓練のパタカラ体操を実践して誤嚥を防ごう
嚥下訓練であるパタカラ体操を実施すれば、簡単に口や舌の周りを鍛えられます。以下のような効果も期待できるので、高齢者の誤嚥が不安な方はぜひ取り入れてみましょう。
- 噛む力や飲み込む機能が維持され向上が期待できる
- 唾液の分泌が促進される(ドライマウスの防止)
- 発音がはっきりし、口が動きやすくなる
口腔予防のためにパタカラ体操を始めたものの、不安が残る方は、早めに専門家に相談してサポートを受けるのもひとつの手です。
嚥下訓練のパタカラ体操を取り入れて、誤嚥を防ぎ、日々の食事を楽しみましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。