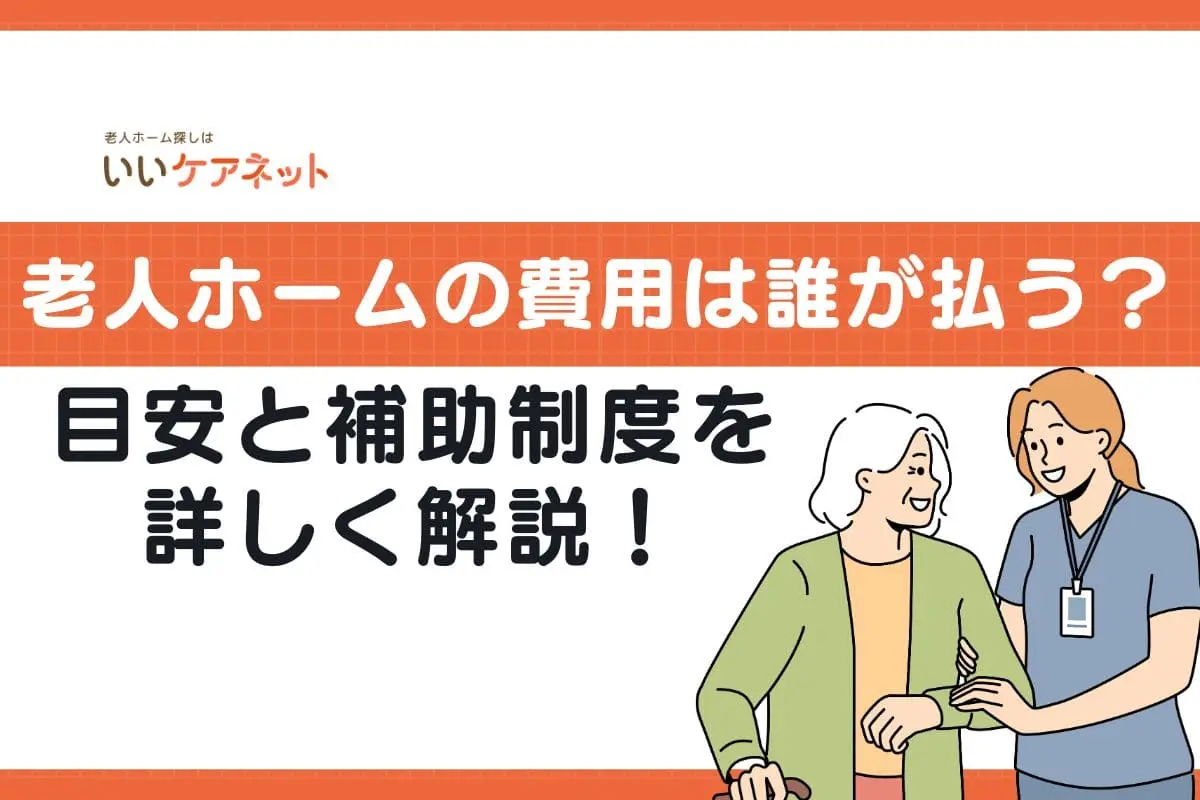介護を受ける側と介護する側が、ともに65歳以上の高齢者である状態を老老介護といいます。
介護の担い手がいなかったり、介護は家族がするものという意識があったりなど、老老介護に至った原因は人それぞれです。
現在は老老介護の状態で生活ができていたとしても、介護者が高齢である以上、いつ限界が来てもおかしくありません。老老介護は共倒れの危険を伴う状態といえるでしょう。
この記事では、老老介護にある高齢者を、共倒れから防ぐための解決策を紹介しています。老老介護で苦労した先人からの知恵袋をもとに解説していますので、ぜひご覧ください。
老老介護の問題点

老老介護にはさまざまな問題があります。問題なく生活できているからと老老介護を続けた場合、介護者の健康寿命を縮めてしまう可能性もあるのです。
ここでは、具体的にどのような問題点があるのか、詳しく解説します。
介護者が身体的に疲弊する
高齢者同士の介護であれば、介護者の体にかかる負担は大きいものです。被介護者が自分で身の回りのことができない場合、介護者が生活の大半をサポートしなければなりません。
排泄や入浴などのほか、移乗の介助は介護者の負担が大きく、足腰を痛めてしまう可能性があります。
被介護者の要介護度が高いほど介護者にかかる負担は大きくなり、介助中の事故のリスクも上がります。
さらに、介護者も高齢である以上、なんらかの持病を抱えていたり、体調を崩してしまったりする場合もあるでしょう。
介護者は自分の健康に目を向けている余裕がなく、体力的に追い込まれてしまうことが多いのです。
介護者の精神的負担が大きい
介護生活は、想像以上に精神的な負担が大きいものです。とくにふたりきりの環境で老老介護をしている場合、介護者の生活が被介護者を中心に回ってしまうことも多くあります。
老老介護では一日中介護に追われ、介護者が趣味に取り組む余裕もなくなってしまいがちです。
介護や家事をすべて一人でこなさなければならないプレッシャーは、介護者の負担になります。
また、老老介護がいつまで続くかも不明瞭なため、介護者の精神が追い詰められてしまうことも少なくありません。
介護者が精神的な負担を抱え続けることで、介護うつや思わぬ事故や事件を招く可能性もあります。
老人性うつについて詳しく知りたいときは、以下の記事もご覧ください。
老人性うつの場合どうすれば良いの?症状や認知症との違いなどを解説
介護者の変化に気づきにくくなる
老老介護において問題であるのが認認介護に至った場合に気がつきにくい点です。
認認介護とは、介護者と被介護者がともに認知症である状態を指します。
介護がスタートした段階では、介護者が心身ともに健康であっても、しだいに認知機能が低下していくことがあります。
認認介護状態は、介護者と非介護者にとって非常に危険な状態です。認知症専門の施設を利用したり、ほかの親族のサポートを受けたりする必要があります。
しかし、認認介護に陥っても本人に自覚がない場合がほとんどです。
自覚がなければ医療機関を受診する機会も少ないため、周囲が認認介護の状況に気が付いたときには、事態が深刻化している可能性もあります。
自分の親の介護問題に直面したときは、以下の記事もご覧ください。
親の介護をしないとどうなる?法的義務やできないときの対処方法を解説
老老介護の解決策

平均寿命が長くなった現代の日本において、老老介護は深刻な問題であり、今後も増加していくことが予測されます。
もし、自分や家族が老老介護状態になったとしたら、どのような解決策を取れば良いのでしょうか。
ここからは先人の知恵袋を参考に、老老介護で共倒れしないための解決策を紹介します。
地域包括支援センターへ相談する
老老介護が負担となってきた場合、まず地域包括支援センターへ相談がおすすめです。
地域包括支援センターとは、地域に住む人の医療や福祉といったサポートを総合的に担っている機関です。支援の専門家が介護だけでなく、生活全般にかかわる相談に柔軟に応じてくれます。
たとえば、「経済的な理由で介護施設に入れない」「介護がつらいので少し休みたい」といった相談をすると、利用可能な制度や必要なサービスを紹介してもらえます。
地域包括支援センターは、各地域に住んでいる65歳以上の高齢者とその家族が利用可能です。
相談は無料でできるため、まずはお住まいの自治体にある地域包括支援センターに問い合わせてみると良いでしょう。担当の地域支援包括センターは、厚生労働省のホームページから確認できます。
介護サービスを利用する
高齢者が一人で介護を続けていくのは、大きな負担がかかるもの。介護サービスを利用して負担を減らすことが、老老介護による共倒れの予防にもつながります。
介護サービスには大きく分けて、介護保険を利用するサービスと介護保険外のサービスがあります。
介護保険サービスは、要支援・要介護認定を受けた人が受けられるサービスです。65歳以上の高齢者が介護を必要とした場合、1割負担でサービスを利用できます。
たとえば、入浴や排泄の介助といった体への負担が大きい介護をプロに任せることで、介護者の負担が軽減可能です。
介護保険外サービスは、介護認定を受けていない高齢者でも利用可能なサービスです。
保険が適用されないため、負担額は高くなりがちですが、受診の付き添いや長時間の介護など、幅広いサポートが受けられるのが特徴です。
自治体によっては、老老介護専門の支援生活支援を提供しているところもあるので、地域包括支援センターやケアマネージャーなどに相談してみると良いでしょう。
参考:出雲市『老老介護生活支援サービスについて』
地域住民との交流を持つ
老老介護中に介護者の体調が悪くなっても、連絡のない限り離れて暮らす家族には様子がわかりにくいものです。
日ごろの安否確認も大切ですが、周囲の助けを借りられる環境を作っておくのもひとつの方法です。
たとえば、帰省した際には近隣住民に挨拶してつながりを作り、連絡先を渡しておくのも良いでしょう。
自治体によっては、民生委員や地域のボランティアが、高齢者の見守りをおこなっているところもあります。
介護者自身は、町内会のイベントや高齢者サロンに参加するなど積極的に人と関わる意識を持つことで、老老介護による孤立を防ぐのが大切です。
施設への入居を検討する
老老介護は老人ホームやグループホームといった福祉施設に入居すると、問題を根本から解決できます。
高齢者のなかには施設への入居をすすめると、「家族がいるのに、他人に世話してもらうなんて嫌だ」「自分はそこまで歳をとっていない」と考える人もいます。
しかし、共倒れしてからでは遅いのです。
介護者と非介護者、双方の安全を考えると、やはり福祉施設を利用したほうが良いでしょう。すぐに入居を決められなくても、家族とともに施設の入居条件などを調べておくと、いざというときの安心につながります。
老人ホームなどの施設入居を無料で相談するなら
老老介護の解決におすすめの介護サービス

今まで介護をすべて担っていた人は、誰かに介護を任せることに抵抗を感じる人もいるでしょう。介護サービスは種類が多くあり、サポートしてもらう範囲を選べるようになっています。
ここからは、老老介護に悩む人におすすめの介護サービスを紹介します。
介護サービスを選ぶ際の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
介護サービスや老人ホームを探すときに気をつけたいこと
デイサービス
デイサービスは通所介護のひとつで、日中に介護施設へ通い、介護サービスを受けられるものです。65歳以上、かつ要介護に認定された人を対象にしたサービスで、1日につき数百円〜2,000円ほどで利用可能です。
デイサービスを利用すると、被介護者が自宅にこもりきりになるのが防げます。さらに運動や体操、リハビリなどを行うことで、心身機能の維持が期待できます。
介護者は入浴や排泄介助といった負担の大きい介護から一時的に解放され、時間に余裕が持てるようになるでしょう。
ショートステイ
ショートステイは短期入所生活介護ともいい、要介護者が一時的に施設や事業所に入所できるサービスです。入所中は食事や入浴の介助といった介護サービスを受けながら、連続で最長30日まで滞在できます。
ショートステイを利用すると、介護者の介護疲労を和らげることが可能です。
どうしても家を留守にする必要がある場合や、介護者の体調不良の際に利用される場合もあります。
ショートステイは利用希望者が多いため、利用したい場合には早めにケアマネージャーなどに相談すると良いでしょう。
訪問介護
老老介護状態にある人のなかには、住み慣れた家から離れたくない人も多いでしょう。訪問介護はホームヘルパーに自宅まで訪問してもらい、サービスを受ける形態です。
サービス内容には、食事や排泄、入浴支援などの身体介助、掃除や買い物支援などの生活援助、通院時のサポートをおこなう通院介助があります。
訪問介護を利用することで、住み慣れた家を離れることなく、介護者の負担を減らした生活が可能です。
介護施設(老人ホーム)
要介護度が高く、介護者の負担が大きい場合には、介護施設の助けを借りるのがおすすめです。
たとえば要介護3以上の場合、24時間体制で介護を受けられる特別養護老人ホームの利用ができます。所得に応じて減免制度があるため、経済的に不安がある人にもおすすめです。
認知症の症状がある高齢者には、グループホームに入居する方法もあります。グループホームは地域に密着した施設であるため、住み慣れた地域を離れたくない人にもおすすめです。
ほかにも、特定施設入居者生活介護の指定を受けることで有料医療老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった施設で介護保険を利用できます。
入居費用や条件は施設によって異なるため、ケアマネジャーや各施設へ問い合わせてみると良いでしょう。
以下の記事では、高齢者施設の費用感や特徴を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
失敗しない!初めての老人ホーム選びの法則
まとめ|老老介護は周囲のサポートで解決しよう

高齢社会である日本において、老老介護は決して他人事ではありません。自分の家族はもちろんのこと、将来的には自分自身が老老介護の当事者となることも考えられます。
もし老老介護状態になってしまったら、まずは問題点を把握し、先人の知恵袋をもとに解決策を探すと良いでしょう。
老老介護では、自分たちだけで解決しようとせず、周囲の助けや公的サービスを適切に利用することが大切です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
老老介護の解決策についてよくある質問
老老介護をしている人はどのくらいいますか?
2022年の厚生労働省の調査によると、同居家族のうち、65歳以上の高齢者が主な介護の担い手になっている割合は63.5%に登ります。推移を見ても増加傾向にあるため、今後ますます老老介護をしている人の割合は増えていくと考えられます。
親が介護施設への入居を嫌がります。どう説得すれば良いですか?
介護について、日ごろから親と話し合っておくことをおすすめします。なぜ入居が嫌なのか、このまま家で暮らす場合どのようなリスクが考えられるのかなど、具体的な話をするのがおすすめです。
また、まだ施設への入居を考えていない場合でも、近隣の施設がどのような居室やサービスを提供しているかなどを調べておくと、いざというときの不安や拒絶も軽減できます。
施設への入居に消極的な人を説得するときには、以下の記事も参考にしてください。
嫌がる親を施設に入れる手順を解説!入居手順や在宅介護を続けるリスクも紹介
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。