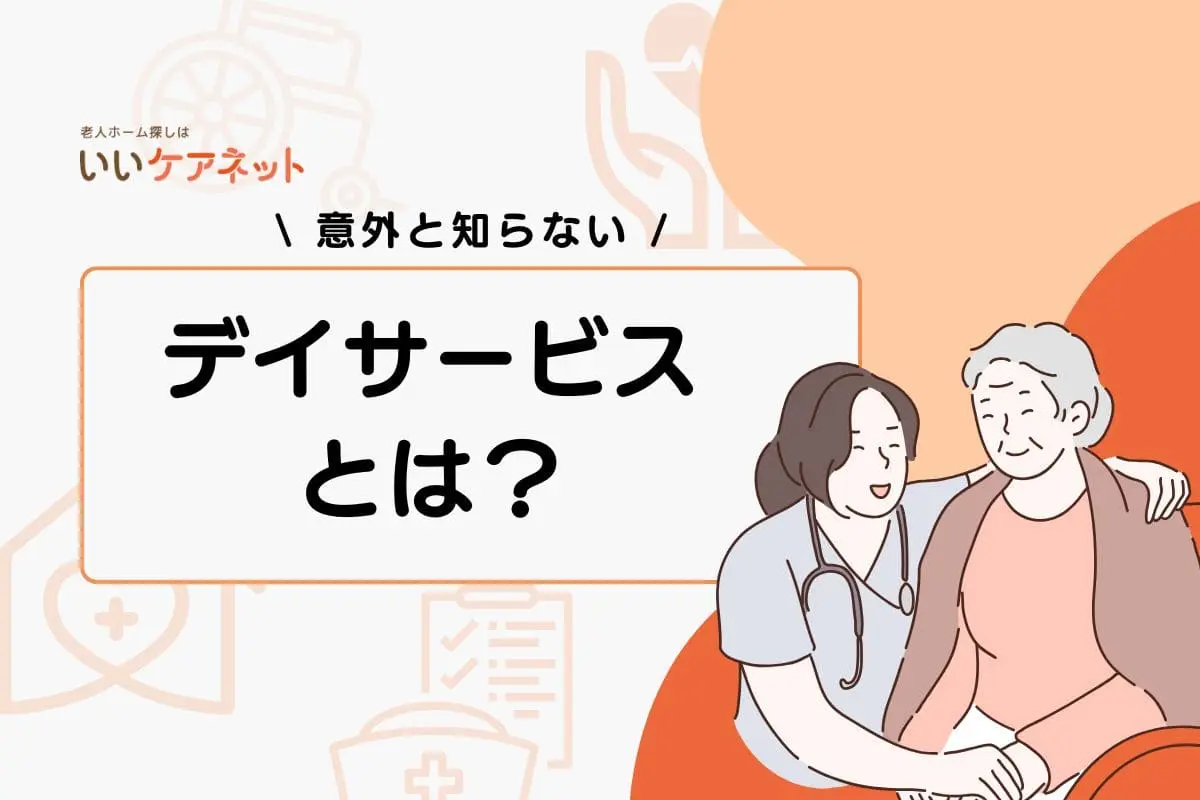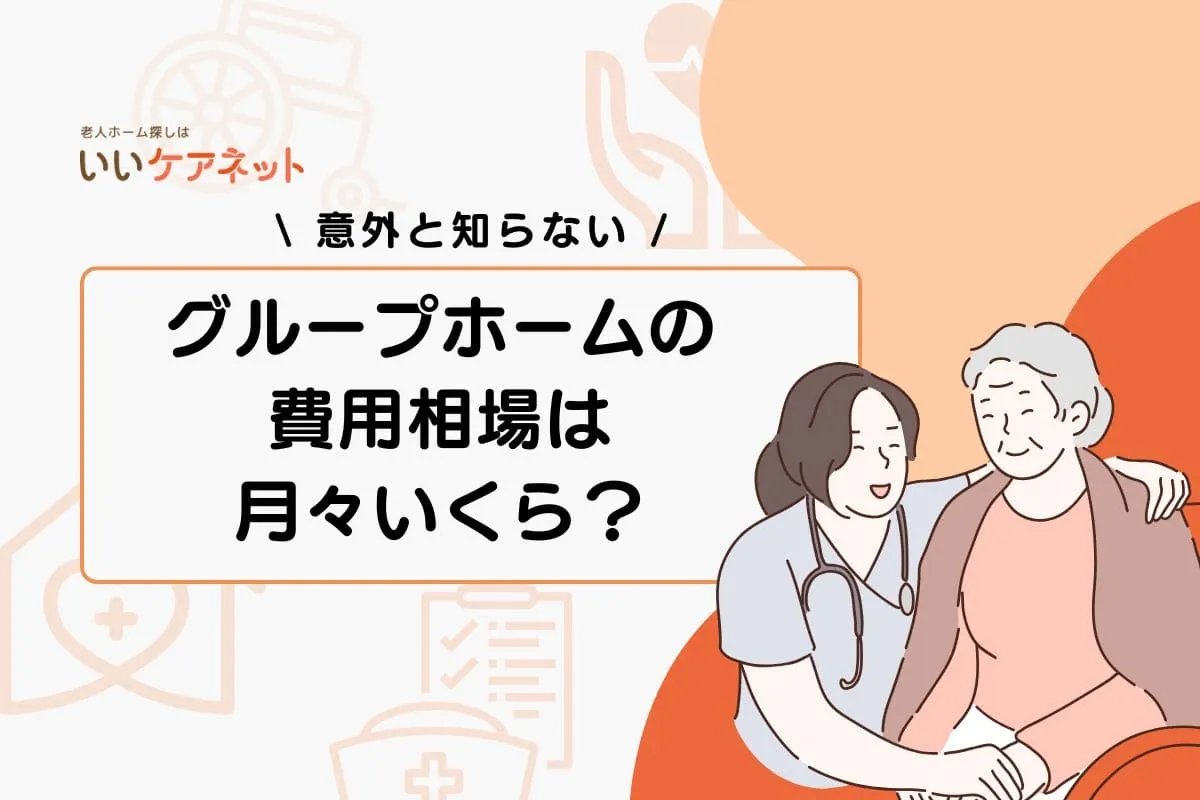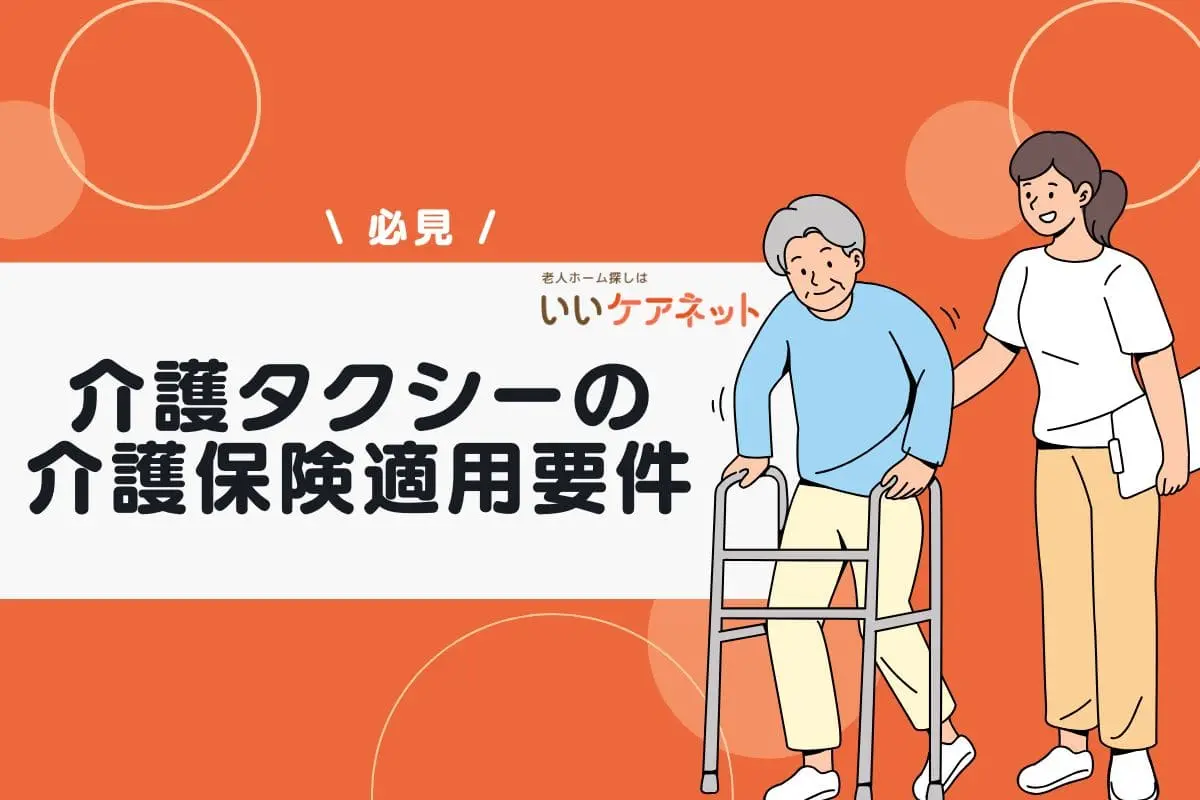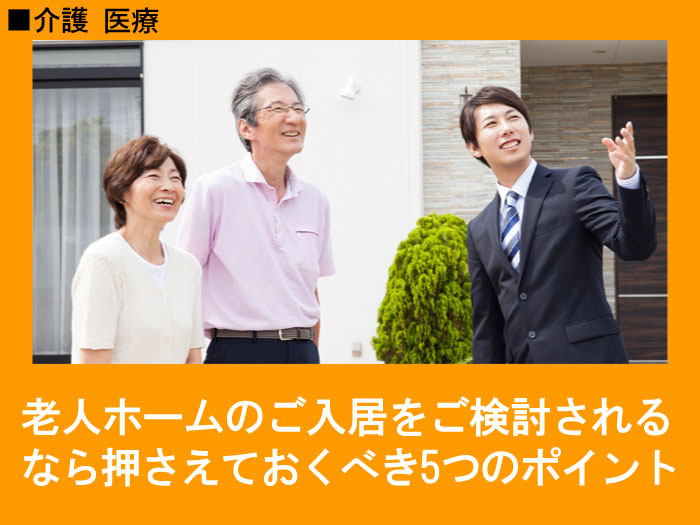親が介護を拒否する理由は、恥ずかしさやプライド、他人への抵抗感など多岐にわたります。
介護をおこなう側は、まず受ける側の気持ちを十分に理解し、受け入れてから対処方法を探る姿勢が重要です。
本記事では、介護を拒否する親の気持ちに寄り添い接するために知っておくべきポイントを解説します。
介護拒否を家族が受け入れて対応する4つの接し方

介護を受ける本人は「介護が必要」と認めたくない場合が多く、介護拒否が起きるケースは少なくありません。
介護を拒否された場合は、以下の4つを意識して接するようにしましょう。
- 親の気持ちに寄り添う
- 親が介護を拒否したくなる理由や背景を理解する
- 本人の尊厳を保つコミュニケーションを心がける
- 無理に押し付けず、段階的に導入する
それぞれ、どのように接するべきか解説します。
親の気持ちに寄り添う
親が介護を拒否する背景には、不安や恐れ、プライドの傷つきなど多様な心理があります。
無理に説得しようとせず「そう感じるのも無理はないよね」と気持ちで受け止めるのが大切です。
自分でも一部はできる場合は、本人の気持ちや自主性を大切にしましょう。共感の気持ちをもって接すると、今後の会話もスムーズです。
親が介護を拒否したくなる理由や背景を理解する
「他人に世話されたくない」と感じていたり、少し物忘れがあるために状況がよくわからなかったり、人によって理由はさまざまです。
介護サービスのしくみを知らないがゆえに、利用を拒否する方も少なくありません。
理由をきちんと理解すると、誤解が解けて良い方法が見つかる場合もあります。
まずは親が介護を拒否する理由や背景に向き合い、誤解がないか確認するのがポイントです。
もし認知症の可能性がある場合は、医師や専門家に相談しましょう。
本人の尊厳を保つコミュニケーションを心がける
話すときは、強い口調は避けて「お父さんはどう思う?」とやわらかく話しかけ、本人の意見を聞く習慣付けをしましょう。
「いつもありがとう」「助かっているよ」などの言葉は、本人の自尊心を保ち、協力的になりやすいとされています。
さらに「ここはお母さんにお願いできる?」といったサポートを求める声かけで、できる役割を任せると、必要な支援や介助を自然に受け入れてもらいやすくなります。
無理に押し付けず、段階的に導入する
いきなり本格的な在宅介護を導入すると、拒否が強くなる場合もあります。
まずは短時間の訪問介護や、デイサービスの見学など、気軽にできるきっかけ作りからはじめると、介護を拒否する気持ちが薄れやすいです。
少しずつ慣れていくと、サービスへの抵抗も減っていきます。
また、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談して、第三者のサポートを受けるのもおすすめです。
家族だけで抱え込むと精神的な負担が大きいため、介護サービスを上手に活用していきましょう。
高齢者が介護を拒否する4つの理由

高齢者が介護を拒否する理由は、以下の4つのようなものがあります。
- 自分のプライドが傷つけられたくない
- 自分の状態を客観的に判断できていない
- 家族以外の他人を家に入れたくない
- 介護サービスの費用で家族に迷惑をかけたくない
これらの理由が発生する背景を踏まえて接すると、適切な対応を選びやすくなります。
家族が介護を拒否する理由はどれに該当するかを確認し、適切な対応を模索してみましょう。
自分のプライドが傷つけられたくない
高齢者が介護を拒否する理由には、「できないと認める行為」に強い抵抗感が生じる場合があります。長年、家族を支えてきた存在として「子どもに迷惑や手間をかけたくない」と考える方は少なくありません。
さらに他人に弱みを見せたくないと羞恥心が加わり、介護そのものを拒否しがちです。そのため、本人の自尊心を傷つけないアプローチが不可欠です。
自分の状態を客観的に判断できていない
認知症や脳機能の衰えがあると、自分の状態を正しく把握できない場合があります。自分では「ちゃんとできている」と思い込み、介護を必要とする状況を理解できないケースも少なくありません。
記憶力の低下で困りごとを忘れてしまう場合もあるため、客観的に状況を見守り、必要なら専門家の助言を仰いでください。
関連記事:父親が怒りやすくなった!70代の高齢者に多くみられる状況の原因や対処法を解説
家族以外の他人を家に入れたくない
「生活を見られるのが嫌だ」と思ったり、環境の変化を嫌がる方は少なくありません。
とくに自宅はプライベートな空間のため、他人を家に入れて世話をされる状態に、強く抵抗感を抱く場合があります。長年使ってきた家事エリアを人に触られたくないと思うケースもあり、繊細な対応が必要です。
介護サービスの費用で家族に迷惑をかけたくない
介護サービスには費用がかかるイメージがあり、親としては「子どもに負担をかけたくない」と考えてしまいがちです。
実際には、介護保険で自己負担を抑えられる制度が整っています。
しかし、具体的に仕組みを知らないと大きな金銭的負担を想像してしまい、結果としてサービスを避けてしまうケースは少なくありません。
事前に必要な費用を正確に伝え、誤解を解消するのが安心感を高めるポイントです。
【パターン別】介護を拒否された時の対応例

一口に介護拒否と言っても、以下のような多数の場面で介護拒否は発生します。
- 食事を嫌がる場合
- トイレやおむつを嫌がる場合
- 入浴を嫌がる場合
- 介護サービス全般を拒否する場合
- 訪問介護を嫌がる場合
どのようなときも無理に説得せず「なぜ嫌がっているのか?」を探ったうえでの、細かな対応が大切です。
ここでは、場面ごとに具体的な対処法を紹介します。
【食事の介護拒否】体調が原因でないかを確認する
まずは、体調が悪くないかを確認しましょう。
食欲がないのは、病気や薬の副作用が原因かもしれません。その場合は医師に相談してください。
また、食事を飲み込む力が弱まっていると、食事自体を怖いと感じる場合もあります。
食べ物の硬さや味、彩りを見直し、少量でも栄養価の高いものを使うのがおすすめです。
少しでも食べたら褒めると、食べる意欲が出る場合もあります。
関連記事:高齢者が食べられないときに食欲を回復する方法!食欲不振の原因や対策法を解説
【トイレやおむつの介護拒否】プライバシーを重視する
介護の必要性を問わず、多くの人が恥ずかしさからトイレ介助を嫌がるでしょう。
できるだけ同性の介助者にし、体を見せる範囲を少なくすると、拒否感が和らぎます。
おむつという言葉を避けて「パッド」など抵抗感の少ない表現をしたり、大人用おむつではなく下着型を選んだりする工夫が大切です。
なるべく本人が自分で排泄動作をする機会を残す方法もあります。
鍵やカーテンなどを準備してプライバシーを守りつつ、本人の尊厳を大切にしましょう。
【入浴介護の拒否】コミュニケーションを細かく取る
入浴は体力を使い、恥ずかしさもあるため、嫌がる人が大半です。本人の体調や気分を見ながら、無理のないタイミングで提案しましょう。
いきなり入浴ではなく、シャワーだけや足湯などからはじめて段階を踏むと、心理的なハードルが下がりやすいため、おすすめです。
なるべく毎回同じ介助者が対応すると、安心感も高まります。
【介護サービス全体の拒否】ケアマネージャーと連携する
家族だけで説明しきれない場合は、ケアマネージャーや地域包括支援センターの協力が有効です。
本人の心理的抵抗が大きいときこそ、第三者の視点が役立ちます。ケアマネージャーのような専門家が入って面談すると、スムーズに話が進むケースもあります。
それでも拒否が強いサービスは一度やめて、本人が受け入れやすい介護からはじめるのがコツです。
【訪問介護の拒否】使いたくない根本的な理由を把握する
訪問介護・看護を拒否する場合は、何が嫌なのかを本人に聞いてみましょう。
たとえば「他人を家に入れたくない」「特定の介護者が合わない」など、拒否の内容を特定すると対応策を考えやすくなります。
「介護」という言葉に抵抗を感じる方も多いです。たとえば「お手伝い」「健康チェック」など、やわらかい表現に言いかえてみましょう。
言葉を工夫するだけでも、受け入れやすくなる場合があります。家族だけで説得しようとせず、専門職の力を借りるのも大切です。
すでに信頼しているかかりつけ医や看護師などから勧めてもらうと、本人も安心して話を聞きやすくなります。また、最初から本格的にはじめるのではなく「体験」のように軽い提案から入ると、受け入れやすくなります。
関連記事:「訪問看護」で受けられるサービスの内容
介護を拒否されたら強制せず原因を丁寧に理解する【まとめ】

介護を拒否する親に対しては、頭ごなしに説得するのではなく、「なぜ拒否するのか」の丁寧な理解が大切です。拒否の背景には、不安やプライド、恥ずかしさ、介護への誤解など、さまざまな考えがあります。
対応のポイントは、本人の気持ちや尊厳を大切にしながら、段階的にサポートを取り入れていくことです。
言葉の選び方や接し方に配慮し、無理のない形で信頼関係を築いていきましょう。また、ケアマネージャーや医師、地域包括支援センターなど、第三者の力を借りるのも有効です。
拒否の場面ごとに適切な対応を心がければ、少しずつでも介護サービスを受け入れてもらえる可能性が高まります。
家族だけで抱え込まず、必要なサポートを上手に活用していきましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。