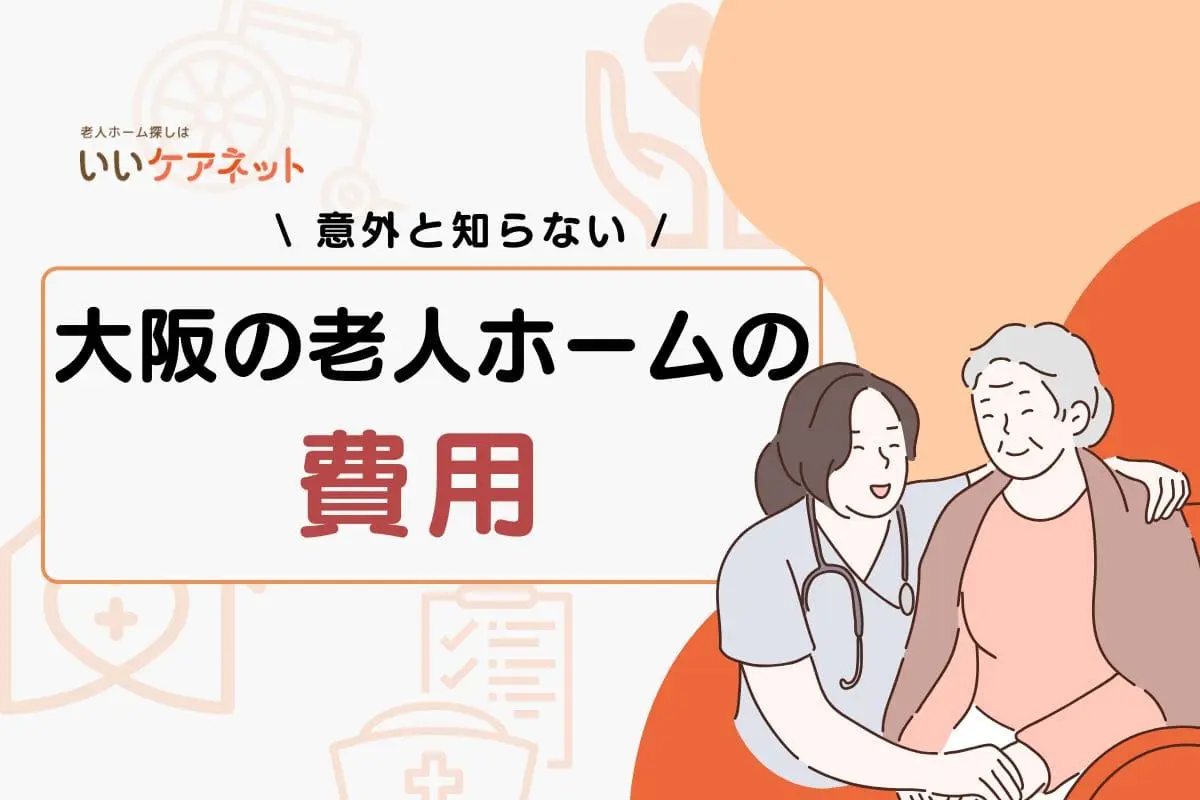節税を目的に親を扶養に入れたいと考える方は多いですが、子の扶養に加入すると親に多数のデメリットが発生します。
たとえば、親が住民税非課税世帯の場合、子の扶養に入り課税世帯に移行すると介護保険料の負担額が数万円単位で増えるケースは多く存在します。
このように、親を扶養に入れてからデメリットに気付くことは少なくありません。
そこで本記事では、親を扶養に入れると発生する4つのデメリットを解説し、制度を理解するうえでの注意点を解説します。
親を扶養に入れると発生する変化や、よくある質問についても解説しているので、親を扶養に入れるか迷っている方は参考にしてみてください。
親を扶養に入れる4つのデメリット

親を扶養に入れると、税金控除をはじめとする一定のメリットは発生します。一方で、医療費や介護保険料の負担増などのデメリットが存在するのも事実です。
親を扶養に入れるとどのような不利益が発生するのか、代表的なデメリットを4つ説明します。
親の医療費負担額が増える
親を扶養に入れ同一世帯になると、高額療養費制度での自己負担限度額が子の所得区分に引き上げられる可能性があります。
高額療養費制度とは、1か月の医療費が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる仕組みです。
上限額は世帯の課税状況によって決まります。上限を超えた医療費は払い戻されるか、事前に申請していれば自己負担は発生しません。
たとえば、65歳で住民税非課税の場合は、上限額が3万5,400円です。
しかし、扶養に入ると子と同じ世帯に分類されるため、非課税のときよりも自己負担額の上限が高くなりやすい点に注意が必要です。
子の報酬月額が27万円以上〜51万5,000円未満であれば、上限額は「8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1%」で決まります。
そのため、非課税時の上限と比べると、最低でも自己負担額が4万4,700円は増えることがわかります。
扶養加入は医療費の支出が膨らむリスクがあるため、親の通院や介護の状況を踏まえて扶養に入れるべきかを判断しましょう。
要介護認定後のサービス利用負担額が増える
要介護認定を受けた親が介護保険サービスを利用する際、自己負担割合や上限額は世帯の課税状況によって変動します。
親が別世帯で住民税非課税の場合は、月々の介護利用料が非常に低く抑えられる可能性は少なくありません。
しかし、課税世帯に分類されると、介護に関する減免精度や支援事業の利用額が制限され、月々の費用が増える可能性があります。
親の介護状況次第では、扶養控除で得られる節税額よりも、介護費用の増加が上回る可能性は否定できません。
現在の状態だけではなく、将来的な介護の必要性についても考慮した上で扶養に入れるかを検討しましょう。
親の介護保険料が増える
65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者として、本人の所得や世帯の課税状況に応じて保険料が決まります。
所得が年金受給のみの場合は単独世帯で非課税となり、介護保険料は最も低い区分に設定されるケースがほとんどです。
令和3~5年度の東京都新宿区であれば、65歳以上で非課税かつ年金受給者の場合は介護保険料の年額は1万9,200円でした。
しかし、扶養に入れて課税世帯とみなされると一気に上位区分へ移行し、年間で数万円規模の負担が増える場合があります。
たとえば、東京都新宿区のケースで比較してみましょう。
本人は住民税が非課税で所得80万円以下とします。
この条件であっても、扶養に入っている子が住民税課税世帯の場合は、介護保険料が年間で6万1,440円まで上がります。
差額で考えると、負担額が4万2,240円増える計算です。
収入が年金受給のみの親にとっては数万円の出費増は生活を圧迫しかねないため、扶養に入れる前の保険料シミュレーションが大切です。
介護施設入所時の負担額が増える
介護保険の施設サービスを利用するとき、食費や居住費は全額自己負担が原則となる点に注意しましょう。
住民税非課税世帯の高齢者には自己負担額を抑える軽減制度を使えます。
特別養護老人ホームを利用する課税世帯の高齢者は、1日あたり1,445円の食費がかかります。
一方、非課税世帯は食費が1日300円まで下がることをご存じでしょうか。
たとえば、非課税世帯で30日入所すると総額で6万1,800円以上の差が生じます。
要介護度が高くなり長期の施設入所が必要になった場合、課税・非課税による差額は家計に大きな影響を与えかねません。
将来的に施設入所を視野に入れている方は、扶養に入れるメリットと施設利用費増額のリスクを比較・検討しましょう。
親を扶養に入れると何が変わる?
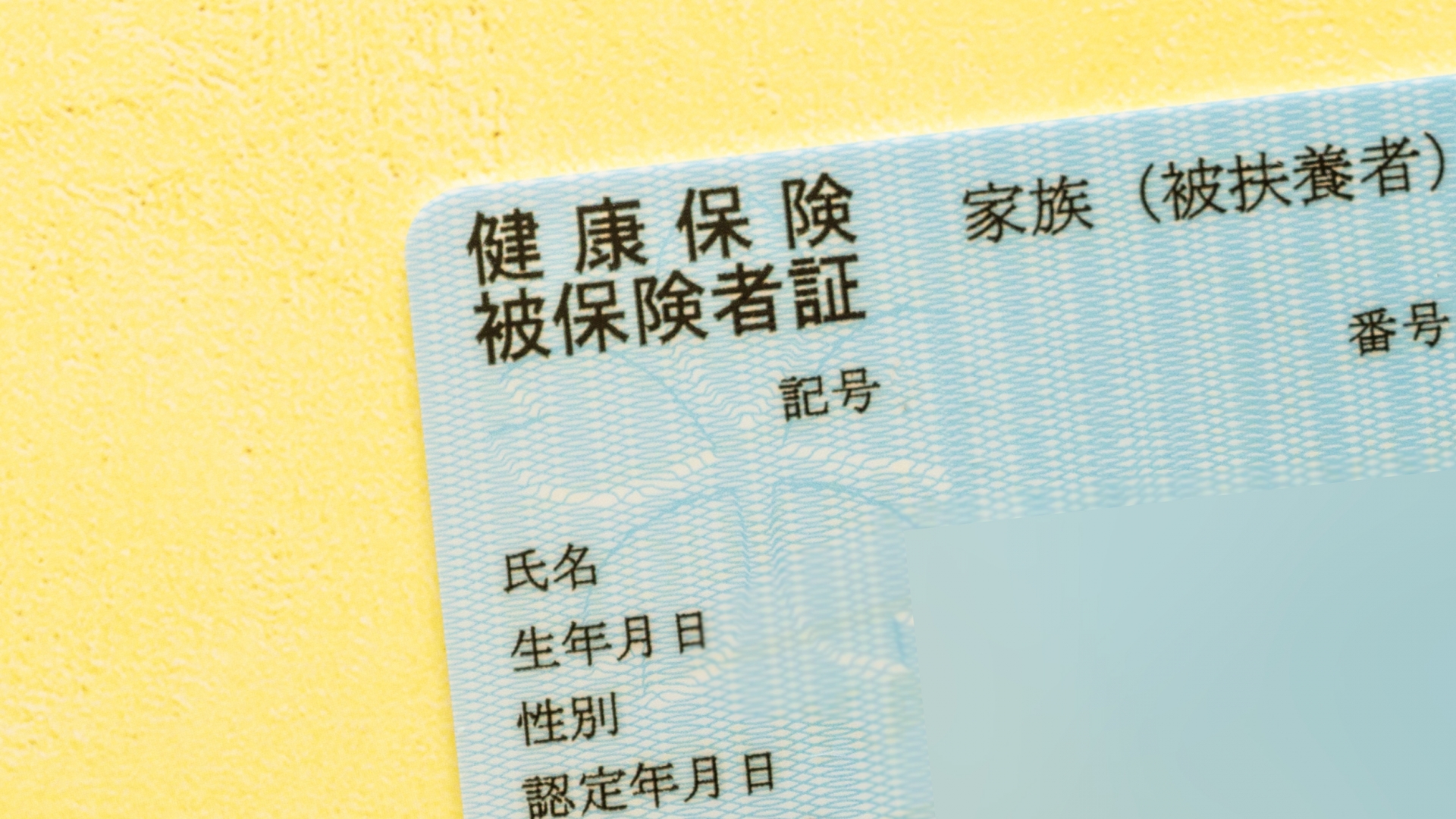
親を扶養に入れると、税法上は「扶養親族」と見なされ、子は扶養控除を利用できます。
一方で、住民税非課税世帯の優遇から外れると、親本人の医療費・介護費用が増えるリスクにも目を向けなければなりません。
ここでは親を扶養に入れると生じる、主な変化を整理します。
親と自分が同一世帯となり課税・非課税が決まる
親と同居・扶養関係になれば、住民票上でも同一世帯として扱われます。
非課税世帯の親が医療保険や介護保険料などの減免措置の恩恵を受けていた場合、課税世帯に移行した後は適用されません。
医療保険や介護保険だけでなく、自治体独自の高齢者向け減免措置・福祉サービスは非課税世帯のみ利用可能な制度は多数存在します。
課税世帯になるだけで利用条件から外れてしまうケースは珍しくありません。
親を扶養に入れる前に、現在どのような制度や減免を受けているのか、今後受ける可能性がある福祉制度などを把握しておきましょう。
課税世帯になると使えなくなる支援制度をリストアップしておくのが理想的です。
関連記事:世帯分離とは?メリット・デメリット、手続き方法をわかりやすく解説
75歳以下の親は健康保険の被扶養者になる
親が75歳未満で、かつ収入要件を満たす場合は、子の加入する健康保険の被扶養者として保険料の支払いが不要です。
たとえば、会社員の健康保険に子が加入している場合は、親が年収要件を満たしていれば、親は国民健康保険料が無料になります。
ただし、親の年収が上限以上ある場合には被扶養者認定を受けられません。
また、75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の扶養には入れなくなります。
親が条件を満たす場合は扶養控除を受けられる
親の合計所得48万円以下のような条件を満たす場合、親を扶養に入れた子は所得税や住民税の控除を受けられます。
70歳以上の親を扶養している際は控除額が増え、子の税負担が以下のように軽減される仕組みです。
| 親の状況 | 控除額(所得税/住民税) | 収入限度額 |
| 70歳未満(同居・別居) | 38万円/33万円 | ・年金収入:158万円以下
・給与収入:103万円以下 |
| 70歳以上・別居
(老人扶養親族) |
48万円/38万円 | ・年金収入:158万円以下
・給与収入:103万円以下 |
| 70歳以上・同居
(同居老親等) |
58万円/45万円 | ・年金収入:158万円以下
・給与収入:103万円以下 |
親を扶養に入れる前にメリット・デメリットは詳しく確認しておこう

子の節税を優先して親を扶養に入れると、親が住民税非課税世帯の恩恵を失い、さまざまなデメリットが発生する場合があります。
親が非課税世帯の恩恵を失った場合、子は減税が適用されても、トータルで見ると損をしてしまうケースは少なくありません。
とはいえ、親を扶養に入れた場合は扶養控除を利用できたり、75歳未満の親は保険料を大幅に減らせたりなどのメリットはあります。
将来的に親に介護の必要性が発生する可能性や現状の医療費などを踏まえ、親を扶養に入れる前に、以下の点を確認してみてください。
- 親の年間所得(年金・パート収入など)の確認
- 親の医療・介護状況、および近い将来の見通し(病気や体力低下など)
- 親が現在受けられている非課税世帯向け優遇・減免の有無
- 扶養控除による節税効果と医療費・介護費の増加額のバランス
実際のメリット・デメリットは家庭の状況次第で大きく異なります。
親子それぞれの情報を整理し、よく話し合ってから親を扶養に入れるべきかを検討しましょう。
親を自分の扶養に入れる際によくある質問

最後に、親を子の扶養に入れる際によくある質問に回答します。
親を扶養に入れるタイミングは?
親が退職して所得が減り、扶養控除の対象になったタイミングが一般的です。
だし、年の途中で退職した場合などは年収要件を超えやすい場合もあり、一度計算してみる必要があります。
親の退職月や雇用形態に注意しながら、確実に所得条件を満たしているかを確認しましょう。
会社員であれば年末調整前に扶養申告を済ませ、親の所得状況を把握しておけば、タイミングを逃さずに扶養控除を利用できます。
別居している親でも扶養に入れられる?
別居状態でも「生計が同一」と認められれば扶養控除を利用できます。
具体的には、定期的に仕送りをおこない、家賃や生活費をサポートしている実態があれば別居状態でも親を扶養に入れられます。
ただし税務署から証拠の提示(送金記録など)を求められる場合もあるため、振込記録や送金履歴などを保管しておきましょう。
高齢の親が地方で暮らしている方でも、仕送りにより実質的に生活を支えていれば、扶養として認定される可能性は十分にあります。
関連記事:親にお金をあげると税金(贈与税)はかかる?非課税になる条件や税率の計算方法を解説
親を扶養に入れる所得税以外のメリットは?
親が75歳未満の場合、子の健康保険の被扶養者となると親の国民健康保険料の負担が0円になるメリットがあります。
親の収入が少ない場合、国民健康保険料が生活を圧迫しがちです。被扶養者として加入できれば親の手元に使えるお金が増えやすくなります。
また、会社によっては扶養手当(家族手当)が支給される場合もあるため、就業先の規定を確認してみるのもおすすめです。
ただし、75歳以上の親が後期高齢者医療制度に移行している場合は、親の国民健康保険料の減免は適用されません。
後期高齢者の親を扶養に入れるとどうなる?
75歳以上の親を扶養に入れた場合も、収入要件を満たす場合は扶養親族として扶養控除を使えます。
ただし、75歳以上は健康保険制度が後期高齢者医療制度に切り替わり、健康保険料を負担するのが親です。
後期高齢者医療保険料は、扶養に入った世帯に課税者がいると軽減措置が外れ、保険料が上がるリスクがあるので注意してください。
また、介護保険料や医療費助成が課税世帯扱いとなり、自己負担額が増える可能性は大いにあり得ます。
課税世帯化による親の負担増と、自身の税金軽減メリットをよく比較検討しましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。