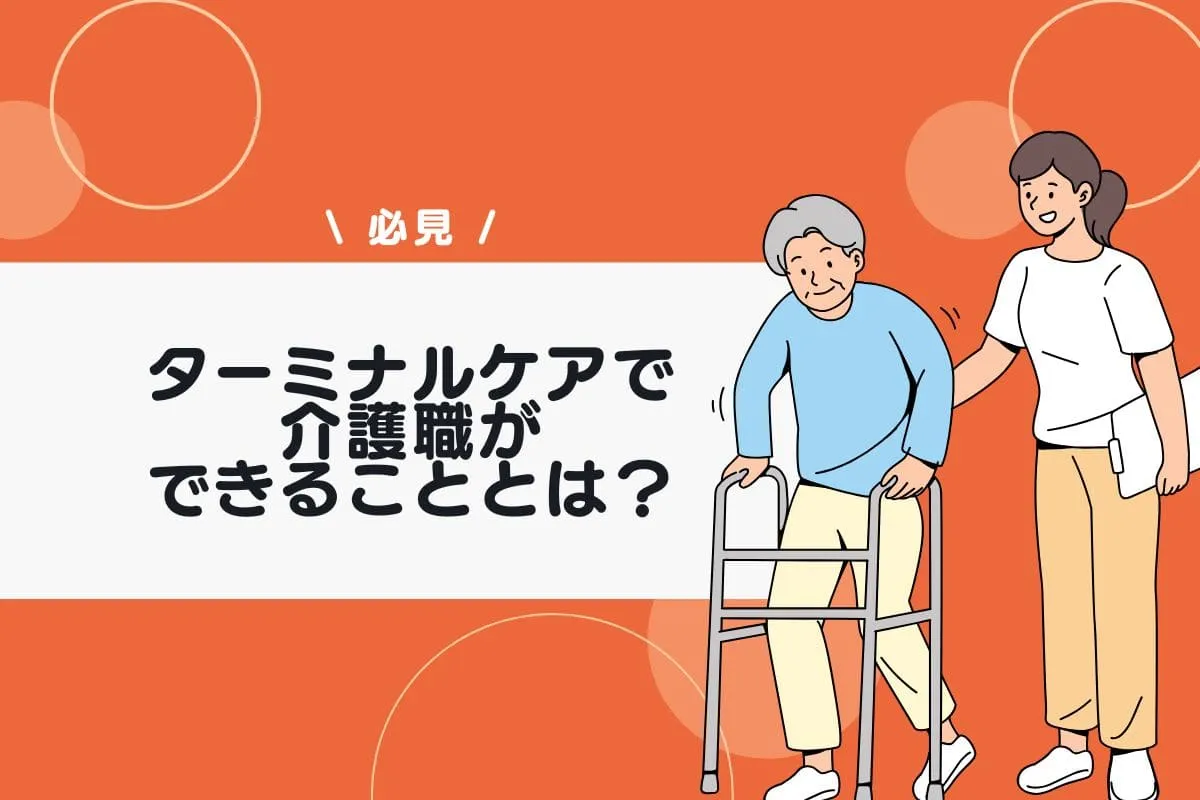「最近、親の足の爪が長くなっているけど、このままで大丈夫かな…」
「足の爪のケアをしてあげたほうがいいのかな…」
このような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
足の爪を伸ばしすぎると、巻き爪や爪の欠損、転倒など、思わぬ健康リスクにつながる可能性があります。リスクを減らすには、適切な長さに整え、爪の形にも配慮する意識が大切です。
本記事では、足の爪を伸ばしすぎることによるリスクを詳しく解説します。家庭でできるケア方法や爪切りの適切な頻度についても紹介しているので、参考にしてみてください。
足の爪の伸ばしすぎが引き起こすリスク

足の爪を伸ばしすぎると、さまざまな健康上のリスクが生じる可能性があります。
主なリスクは以下の5つです。
- 爪が割れる・折れる
- 巻き爪・陥入爪(かんにゅうそう)になる
- 細菌が繁殖しやすくなる
- 歩行時に痛みを感じる
- 転倒リスクがある
起こりうるリスクを把握して、足の爪をケアする大切さを理解しましょう。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護にまつわる記事を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
爪が割れる・折れる
爪を伸ばしすぎると、割れたり、折れたりする可能性があります。
とくに高齢になると、爪が厚くなったり、硬くなったりして、やわらかさが失われる傾向にあります。そのため、固い物に爪をぶつけたときに衝撃が吸収されず、足の爪が割れやすくなるのです。
また、爪が長いと靴下や布団などに引っかかりやすく、思わぬ力が加わって折れる恐れもあります。折れた部分が深くなると、深爪になったり、爪床(爪の裏側と密着している指先の皮膚)を傷つけて傷ができたりもします。
巻き爪・陥入爪(かんにゅうそう)になる
足の爪の伸ばしすぎは、巻き爪や陥入爪(かんにゅうそう)につながるリスクも高まります。
巻き爪と陥入爪の特徴を以下の表にまとめました。
| 症状 | 特徴 |
| 巻き爪 | 爪の端が内側へ巻き込むように変形し、つま先から見ると湾曲して見える状態 |
| 陥入爪 | 爪が皮膚に食い込み、炎症や痛みを引き起こす状態 |
巻き爪が進行すると、爪が皮膚を圧迫して歩くときに痛みを感じたり、安静にしていても痛みが続いたりする場合があります。巻き爪を放置すると、爪が皮膚に食い込んで陥入爪に発展するケースも珍しくありません。
陥入爪は症状が悪化すると、傷口が感染して化膿したり、肉芽(過剰な肉の盛り上がり)が見られたりします。
細菌が繁殖しやすくなる
爪の中は湿気がこもり、細菌が繁殖しやすい環境です。
構造的に、爪と皮膚のすき間には、垢や汚れ(ほこり・ちりなど)がたまります。そこから、細菌やカビが発生するケースも少なくありません。
免疫システムの働きが弱くなる高齢者は、細菌やカビの繁殖から炎症や感染症を引き起こすリスクが高まります。
たとえば、爪周囲炎(爪の周りの皮膚の炎症)や爪白癬(つめの水虫)などです。
足の爪を清潔な状態を保てば、こうした感染症の予防につながります。
歩行時に痛みを感じる
足の爪が長い状態で靴を履くと、圧迫されて歩行時に痛みを感じる場合があります。靴の中は狭い空間のため、隣の指にぶつかりやすくなり、巻き爪や陥入爪に発展する可能性も少なくありません。
痛みが継続すると、外出がおっくうになる方もいるでしょう。外出が減れば、身体を動かす機会も少なくなり、筋力の低下や健康状態の悪化につながりかねません。
関連記事:「生活リハビリ」の意味と具体的な方法、リハビリを続けるコツを紹介!
転倒リスクがある
足の爪を伸ばしすぎると、身体のバランスを保ちにくくなります。結果として、ふとした瞬間に身体がよろけやすくなり、転倒リスクが高まります。
実際に、医療関係者が協力して実施した調査で「認知症と減薬の相関性及びフットケアによる転倒予防の効果」の報告書によると、フットケアを行った高齢者の転倒発生率が29%減少したという結果が出ています。
調査時のフットケアの内容は、巻き爪や肥厚爪(分厚くなってしまった状態の爪)、足裏や足指にできるタコ・角質などのケアです。
適切な爪のケアは、転倒予防にも効果的であることがわかります。
関連記事:高齢者に多い病気ランキング5選!病気になりやすい理由も解説
足の爪は適切な長さと形に整える
足の爪を適切な長さと形に整えれば、爪の伸ばしすぎから生じるリスクは軽減します。
以下は、爪の長さと形の理想的な基準です。
|
理想的な基準 |
|
| 爪の長さ | ・指の先端から1〜2ミリほど白い部分が残る程度が目安 ・短すぎると皮膚を刺激し、長すぎると靴にあたって痛みの原因になる |
| 爪の形 | ・理想の形は、スクエアオフカット(四角に近く両端にやや丸みをつけた形) ・とくに巻き爪の予防につながる |
爪を切る際はよく切れる爪切りを使いましょう。切れ味の悪いものを使用すると、爪に余計な力が加わって、爪が割れたり、ひびが入ったりする原因になります。
なお、入浴や手浴の介護で身体の状態を確認できる際に、爪の長さを確認するのも良いでしょう。入浴後は爪が柔らかくなるため、切りやすくなります。
関連記事:手浴の手順を徹底解説|用意する物や注意点も紹介 | シニアライフアドバイザー監修 介護Q&A【いいケアネット】公式
足の爪を切る頻度【目安は月1回程度】

足の爪を切る頻度は、月に1回程度を目安にしましょう。
高齢者は若い世代と比較して、爪の伸びる速度が遅い傾向にあります。遅いからといって爪切りを怠ると、巻き爪や陥入爪、転倒リスクの増加につながるため、定期的に長さの確認をするようにしてください。
足の爪は適切にケアして伸ばしすぎで起こるリスクを回避しよう【まとめ】

足の爪を伸ばしすぎると、見た目だけでなく健康面にも影響します。巻き爪や細菌の繁殖、転倒といったトラブルの原因にもなるため、定期的なケアが大切です。
本記事で紹介したリスクと対処法を参考に、足の爪のケアに取り組んでみてください。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護にまつわる記事を「いいケアジャーナル」で随時更新中です!足の爪のケア以外にも、口内ケアや認知症予防といった健康管理に関する疑問・お悩みが必要な方は、気になる記事をチェックしてみてください。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。