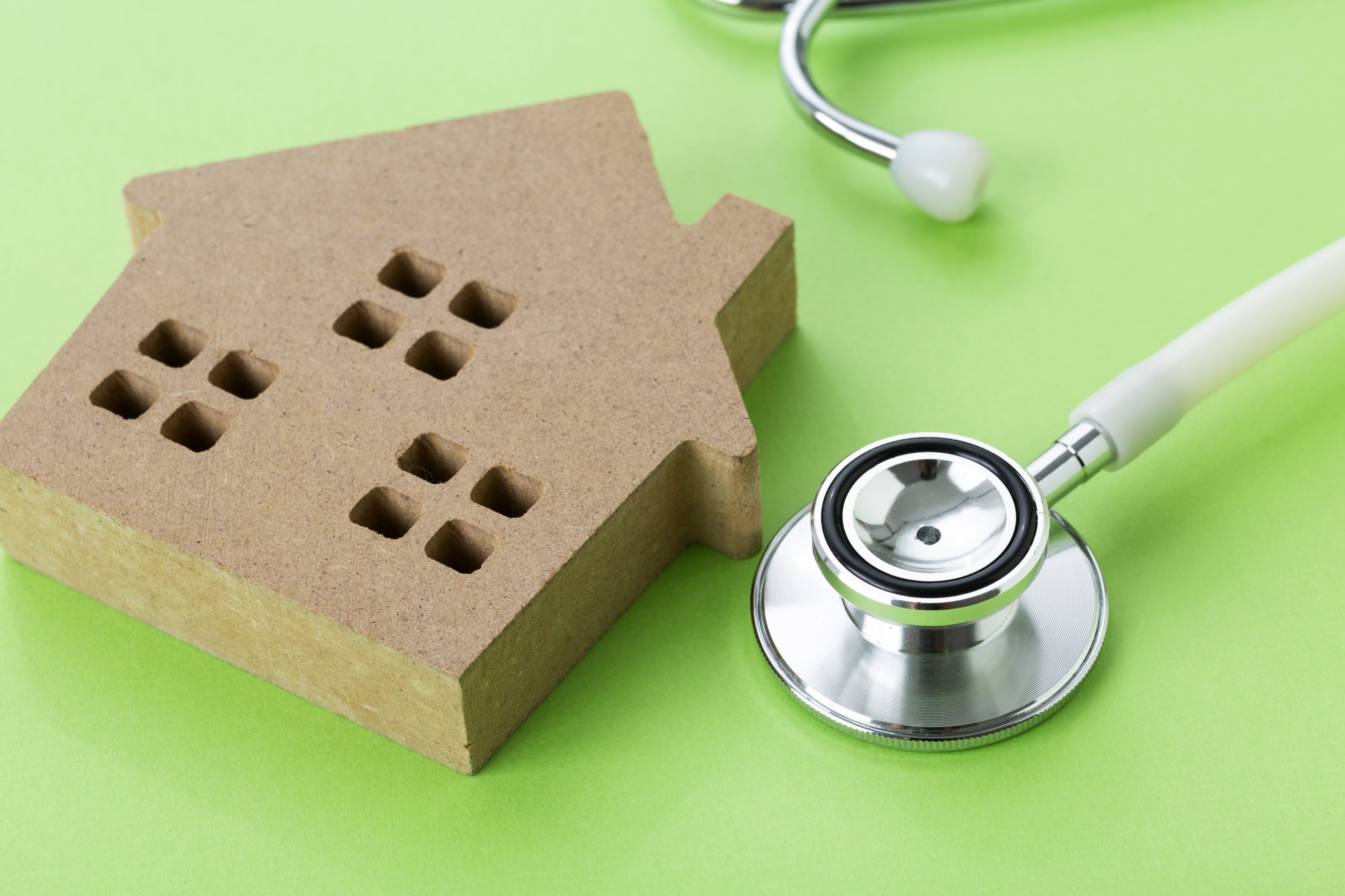「最近、家族から口臭について注意を受けた」
「日頃からエチケットしているけれど原因がわからない……」など悩んでいませんか。
実はその症状、口の中に膿栓(臭い玉)が発生している可能性があります。
口臭の原因として考えられているケースもあり「できればすぐに除去したい!」と悩む人も少なくありません。
口の中はとてもデリケートなので、自己判断でむやみに対処することは好ましくありません。
そこで、今回では膿栓(臭い玉)の取り方だけでなく、原因や予防法などを紹介します。
口の中にある出来物が気になる人は、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
膿栓(臭い玉)の取り方

膿栓(臭い玉)を自分で簡単に取りたいと考える人もいるでしょう。
結論、自分で膿栓(臭い玉)を取るには、細菌が入り込むため、おすすめはできません。
しかし、喉に違和感がある膿栓(臭い玉)だからこそ、取り方が気になる人もいるでしょう。膿栓(臭い玉)は、以下の取り方であれば簡単に取れる可能性があります。
- ガラガラうがいをする
- 綿棒を使用する
- 水圧をかける
- 耳鼻咽喉科で受診する
自分で簡単に取れる方法と、専門家による受診、それぞれの視点から解説していきます。
ガラガラうがいをする
膿栓(臭い玉)を自分で簡単に取りたいと考える人は、まずガラガラうがいから試してみてください。
意識するポイントを踏まえた取り方の手順は以下の通りです。
- 「あ〜」「う〜」などと、声を出しながらうがいする
- 15秒程度続けたら吐き出して新しい水を含む
- 2〜3回繰り返す
声を出しながらガラガラうがいすると、音の振動が膿栓(臭い玉)へ伝わった結果、取れる可能性があります。
綿棒を使用する
膿栓(臭い玉)が喉の奥ではなく、比較的手前にあるなら綿棒を使った取り方もおすすめです。ゴリゴリと削るような取り方はせず、押し出すイメージで試してみてください。
ポロっと取れる可能性はありますが、無理に押し込んでしまうと、かえって扁桃腺を傷つけてしまう恐れがある点には注意しましょう。
水圧を当てる
膿栓(臭い玉)はシャワーやハンディ・クラウン(丸型洗浄瓶)を使った水圧で取れる可能性もあります。とくにハンディ・クラウンの場合は、ピンポイントに膿栓(臭い玉)へ水を当てられるので効果的です。
鏡で確認しながら水圧を当てて膿栓(臭い玉)が取れるのであれば、おすすめの取り方になります。しかし、喉の奥にあったり膿栓(臭い玉)が大きかったりすると、水圧ではなかなか取れません。
喉の粘膜を傷つけてしまう恐れがあるため、後述する耳鼻咽頭科で受診するのが無難です。
耳鼻咽喉科で受診する
膿栓(臭い玉)を自分で簡単に取ろうとした結果、かえって取りにくい場所に入ってしまうケースもあるため、早い段階から耳鼻咽頭科で受診するのがおすすめです。
口の中にできる膿栓(臭い玉)なので「歯医者で相談しよう」と思う人もいますが、膿栓(臭い玉)は耳鼻咽頭科が専門分野になります。
耳鼻咽頭科で受診すれば、ハンディ・クラウンよりも専門的な器具を使った取り方を実施してくれます。
吸引による取り方も実施しているだけでなく、膿栓(臭い玉)ができる原因や適切な対処法も教えてもらえるでしょう。
ガラガラうがいや綿棒など、自分で簡単にやる取り方で解決しない人は、耳鼻咽頭科で受診するのをおすすめします。
そもそも膿栓(臭い玉)とは
膿栓(臭い玉)とは、喉の奥にある扁桃線に発生する小さく白い(もしくは乳白色、黄色)塊です。
扁桃腺の周りには「陰窩(いんか)」と呼ばれるくぼみがあり、そのくぼみに溜まった白い塊が膿栓(臭い玉)です。
触ってみると柔らかいのが特徴で、つぶすとドブのような強烈なにおいを発します。
5〜6mm程度の大きさなので、口を大きく開けて見た際、喉の奥に白い塊が見えたら膿栓(臭い玉)ができている可能性があります。
膿栓(臭い玉)ができる原因

膿栓(臭い玉)は主に、以下が原因となり発生します。
- 細菌やウイルスの影響
- 食べかすの蓄積
ここからは、膿栓(臭い玉)が発生する具体的な原因について解説していきます。
細菌やウイルスの影響
膿栓(臭い玉)ができる原因の1つが、細菌やウイルスによる影響です。
そもそも扁桃腺は細菌やウイルスを撃退するために存在しています。
扁桃腺が細菌やウイルスと戦った後、組織の一部が炎症産物となって、蓄積した結果できるのが膿栓(臭い玉)なのです。
膿栓(臭い玉)があるのは、扁桃腺が細菌やウイルスと戦った証拠でもあります。
また、外部から侵入してきた菌やウイルスだけではなく、口内の乾燥などによって発生した細菌とも戦います。
つまり、口内環境によっては常に扁桃腺が戦っている状況となり、膿栓(臭い玉)が増えるケースもあるのです。
食べかすの蓄積
膿栓(臭い玉)は食べかすの蓄積でも発生します。食べかすがカルシウムやミネラルなどの成分によって硬くなり、扁桃腺に蓄積されます。
ただし、食事をしたからといって必ずしも膿栓(臭い玉)が発生するわけではなく、口の中で食べかすが残った場合に発生するケースがほとんどです。
なお、仮に食べかすによって膿栓(臭い玉)が生じてしまったとしても、腐敗して健康被害をもたらすことはありません。
膿栓(臭い玉)を作らないための予防法

膿栓(臭い玉)が健康に影響はないとしても、口の中から悪臭がするのは気になるものです。
しかし、自分で取るのは好ましくないため、根本的な問題解決としては「予防」が重要となります。
膿栓(臭い玉)を作らないための予防法は主に、以下の方法があげられます。
- 口腔内の清潔さを保つ
- 水や白湯をこまめに補給する
- こまめにうがいをする
- 食事の際はよく噛む
- 鼻呼吸を意識する
- 唾液腺マッサージを行う
膿栓はどのように予防すれば良いのか、具体的な対策について見ていきましょう。
口腔内の清潔さを保つ
膿栓(臭い玉)の発生を予防するには、口の中を清潔に保つのがおすすめです。
口の中を清潔に保つには、日頃のうがいや歯磨きだけでなく、歯医者で定期的に歯石の除去をしてもらうのも効果的です。
膿栓(臭い玉)ができる原因で紹介した2つとも、口の中の清潔さも実は関係しています。
「日頃から歯磨きは丁寧におこなっている」と思っていても、歯の間や溝まで手入れするのは困難でしょう。
デンタルフロスで普段からケアしていても、どうしても限界があります。
口の中を清潔に保つためにも、歯医者で定期的にクリーニングしてもらいつつ、定期検診してもらいましょう。
口腔内のケアについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてチェックしてください。
関連記事:知らないと怖い!?正しい口腔ケアの方法をご存知ですか?
水や白湯をこまめに補給する
水や白湯をこまめに補給するのも、膿栓(臭い玉)の予防策としてあげられます。
冬のように乾燥している時期に風邪を引く人が多いように、口の中も乾燥していると細菌が増えてしまいます。
そこで水や白湯をこまめに補給すると、口の中が潤い、膿栓(臭い玉)の発生を予防してくれるのです。
厚生労働省が後援する「健康のため水を飲もう」推進委員会の資料にも「1日に2.5L水が必要です」と書かれています。
そのうち1.2Lは飲み水で摂取するのが推奨されているため、健康の一環としてもこまめに水や白湯を補給するのがおすすめです。
こまめにうがいをする
こまめにうがいをするのも膿栓(臭い玉)の発生予防につながります。うがいは口の中に発生している細菌を洗い流せるため、帰宅時に実施している人も多いでしょう。
しかし、うがいは帰宅時以外で実施しなくていいわけではありません。口の中に発生した細菌は、外出しなくても乾燥が1つの原因として発生しています。
つまり、外出していなくても、こまめなうがいは膿栓(臭い玉)の発生を予防する1つの策になるのです。
乾燥している冬場はとくに、こまめなうがいを行いましょう。
いいケアネットでは、口腔内のケアを含めた福祉サービスを実施している老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。
「うがい1つにも介助が必要で困っている」という人も含め、気兼ねなくご相談ください。
食事の際はよく噛む
膿栓(臭い玉)を予防するためにも、食事の際はよく噛むのを意識しましょう。
食事でよく噛むと、唾液が分泌されて口内を潤してくれます。
また、唾液の殺菌・抗菌作用によって、口内の雑菌を減らし、扁桃腺が細菌と戦う事態に陥るのを減らせるのも特徴です。
現代人は忙しさからか、早食いをする人も多いでしょう。膿栓(臭い玉)を防ぐためにも、ゆっくりとよく噛んで食べるのを意識してみてください。
鼻呼吸を意識する
膿栓(臭い玉)を防ぎたいのであれば「鼻呼吸」を意識しましょう。
口呼吸が多い人の場合、口内が乾燥しやすく雑菌が繁殖しやすい環境となってしまいます。
空気中の細菌を直接取り入れるため、扁桃腺が細菌と戦わなければならず、膿栓(臭い玉)を発生させてしまうのです。
鼻呼吸を意識すれば、口内の感想を防げる上に、口から入ってくる細菌やウイルスをブロックしやすくなります。
また、就寝時に口呼吸になってしまう人は、専用のテープを使用したり、マスクを着用したりして、口呼吸になってしまうのを防ぎましょう。
唾液腺マッサージを行う
膿栓(臭い玉)を防ぐ方法として「唾液腺マッサージ」もあげられます。
唾液腺マッサージとは、口内の唾液腺を刺激して唾液の分泌を促進するマッサージです。
唾液腺は大きく3つあり、それぞれ「顎のとがった部分の裏側のくぼみ」「耳の前」「左右のフェイスライン」に位置します。
ゆっくりと押し込むようにして刺激し、唾液の量を増やしましょう。
膿栓(臭い玉)の再発防止を日常生活で意識しよう【まとめ】

膿栓(臭い玉)を見つけると不快な気持ちになってしまうものです。
しかし、ガラガラうがいや綿棒などを使って、むやみに取り除くのはおすすめできません。
膿栓(臭い玉)を放置していても健康を害することはないものの、無理に取り除こうとしないようにしましょう。
また、膿栓(臭い玉)が気になる人は今回紹介した「予防法」に重点を置き、膿栓(臭い玉)の発生を抑えていきましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームを含めた施設の疑問や関連する情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
膿栓(臭い玉)に関するよくある質問
ここからは膿栓(臭い玉)に関するよくある質問を取り上げます。
膿栓(臭い玉)の取り方以外に、以下のような疑問を抱えていませんか。
- 膿栓(臭い玉)ができやすい人の特徴は?
- 膿栓(臭い玉)を取っても臭いが気になる場合どうすればいいの?
今回は、上記2点について詳しく回答していきます。
膿栓(臭い玉)ができやすい人の特徴は?
膿栓(臭い玉)が今、仮にない人でも、以下のような状況を抱えている人は、膿栓(臭い玉)ができやすい人と言えます。
| できやすい人の特徴 | できやすい理由 |
| 口腔内の環境が悪い人 | 口の中で細菌やウイルス、食べかすが溜まっていると膿栓(臭い玉)が発生しやすいから |
| 鼻炎のある人 | 鼻水が喉に流れてくる「後鼻漏(こうびろう)」や鼻炎薬の副作用の影響 |
| 扁桃炎になりやすい人 | 免疫力の低下により扁桃炎になり、口腔内の防御力も低下するから |
| 口腔乾燥症(ドライマウス)の人 | 唾液の分泌量が少なく、口腔内が乾燥し細菌の繁殖が進むから |
上記のように、たとえ健康な人でも膿栓(臭い玉)は発生するので、日頃からのケアが大切です。
一方で、膿栓(臭い玉)以外で口の臭いが気になっている人もいるでしょう。
以下の記事では口の臭いが発生しているもう1つの理由とも言える「舌苔」について詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
膿栓(臭い玉)を取っても臭いが気になる場合どうすればいいの?
ここまで紹介した通り、膿栓(臭い玉)を取っても臭いが気になる人もいるかも知れません。
口臭が気になる人は、膿栓(臭い玉)や舌苔以外に、以下が原因になっている可能性があります。
| 概要 | 原因 | 解決策 |
| 生理的要因 | 起床時や空腹時など、唾液の分泌量が少ない | うがいや水の摂取などを含めた生活習慣の改善 |
| 外因性要因 | 香りの強いニンニクやねぎなどを食べたから | 時間の経過とともに改善 |
| 病的要因 | 歯周病や虫歯、糖尿病などの病気 | 原因となっている病気に対する医療機関での受診 |
| 心因性要因 | 口臭がひどい、との思い込み | 歯医者で専門的な口臭チェック |
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームを含めた施設の疑問や関連する情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。