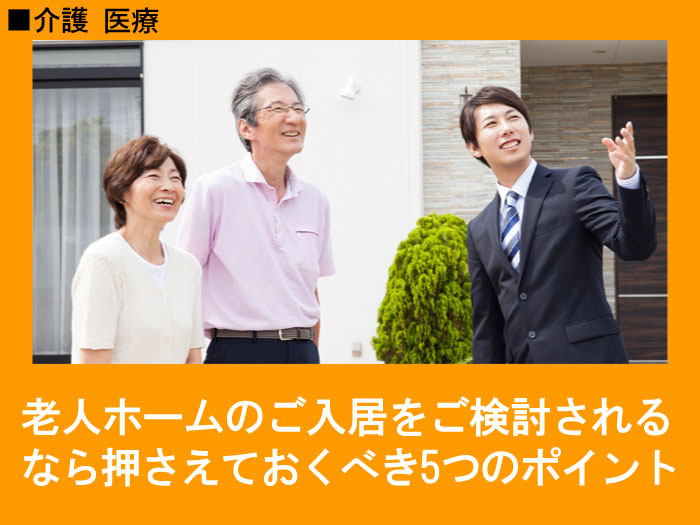「介護施設で親の身体に床ずれができてしまって…どうすればいいのかわからない」
「スタッフが気づいてくれると思っていたけど、なかなか対処してもらえない」
このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
床ずれ(褥瘡)は、体を動かすことが難しい高齢者にとって、深刻な健康リスクとなる場合があります。
とくに介護施設では、スタッフの対応や設備の違いによって、床ずれの発生や進行に差が出るケースも珍しくありません。
床ずれは早期に発見し、適切な処置をすれば悪化を防げる損傷です。
だからこそ、床ずれの正しい知識を持ち、施設選びや日頃のケアについて理解を深めておく意識が大切です。
本記事では、介護施設で床ずれが起こる原因や対処法を解説します。
床ずれの方を受け入れ可能な施設の選び方も紹介しているので、参考にしてみてください。
介護施設で床ずれ(褥瘡)が起きる原因

床ずれ(褥瘡)とは、身体の同じ部位が長時間圧迫され続けることで皮膚が炎症したり、最悪の場合は壊死状態に陥ったりする現象です。
とくに寝たきりの方や車椅子で過ごす時間が長い方に発生しやすく、骨の出っ張った部分(仙骨部・後頭部・肩・踵など)で起こりやすいです。
介護施設のタイプによっても床ずれのリスクは変わります。以下でリスクの違いを確認しましょう。
| 介護施設のタイプ | 床ずれリスク |
| 24時間スタッフ常駐施設 | ・リスクが低い ・定期的な体位変換や皮膚状態の確認が行われるため、床ずれの予防が徹底される |
| 自立型施設 | ・リスクが高い ・入居者自身や家族によるケアが必要で、ケアが不十分だと床ずれが発生しやすい |
施設のタイプによって床ずれリスクは異なります。24時間スタッフ常駐の施設でも、人手不足で十分なケアが難しいでしょう。
自立型施設では、本人や家族による予防が重要です。
失禁や発汗による湿潤環境も床ずれの原因です。とくにおむつを使用している方は、排泄物による皮膚への刺激や湿気で床ずれのリスクが高まります。
介護施設で床ずれを見つけたときの対処法

介護施設で大切な方の床ずれを発見した場合、迅速かつ適切な対応が必要です。
床ずれは早期発見・早期対処が重要であり、放置すると重症化するリスクがあります。
以下では、床ずれを見つけた際の具体的な対処法を5つ紹介します。
- スタッフに報告する
- 病院を受診する
- クッションを使って体圧を分散させる
- 介護保険適用の福祉用具をレンタルする
- 介護施設を変える
いざというときに落ち着いて対応できるよう、床ずれの対処法を理解しておきましょう。
床ずれのケアに特化した施設を探す際は、「いいケアネット」の検索サービスが便利です。「床ずれの方受け入れ可能」と明示している施設を効率よく見つけられるので、床ずれケアでお悩みの方はぜひご活用ください。
スタッフに報告する
介護施設で床ずれを発見したら、施設のスタッフに速やかに報告します。
スタッフは日々多くの入居者のケアに追われており、気づいていない場合もあります。
報告では以下の内容をスタッフに伝えましょう。
- いつから症状があるのか
- どの部位に発生しているのか
- 痛みや赤みの程度か
遠慮せずに事実を伝え、床ずれの状態を写真に撮って記録しておくと良いでしょう。
施設での対応方針や今後のケア計画について確認し、必要に応じて提案する姿勢も大切です。
床ずれの進行度によっては、専門的なケアが必要になるため、施設と連携して定期的に状態を確認する体制を作りましょう。
病院を受診する
床ずれが進行している場合は皮膚科や形成外科などの専門医へ受診しましょう。
とくに床ずれが第2段階以上(皮膚がただれている、水ぶくれがある状態)に進んでいる場合は、早急な医療的対応が必要です。
以下は、床ずれの進行段階と段階ごとに見られる症状例です。
| 進行段階 | 症状 |
| 第1段階 | ・皮膚に赤みが現れる(押しても赤みが消えない) ・痛みがある場合もある |
| 第2段階 | ・真皮まで進行 ・水ぶくれやただれが現れる ・分泌物が見られる場合もある |
| 第3段階 | ・組織欠損が皮下組織に及ぶ ・傷口が深くなり、壊死が見られる場合もある |
| 第4段階 | ・筋肉や骨、腱にまで傷が達する ・感染症を伴うことが多い |
参考:一般社団法人 日本褥瘡学会『改定DESIGN-R® 2020 コンセンサス・ドキュメント』
症状を確認したら介護施設のスタッフと相談し、受診の手配をします。
診察では医師から適切な処置や薬の処方、専門的なケア方法の指導を受けられます。
悪化すると感染症を引き起こし、敗血症など命に関わる合併症のリスクもあるため、早期の受診が重要です。
関連記事:
床ずれ(褥瘡)がひどいときの治し方は?主な原因や受診先も解説
床ずれにワセリンは使える?効果や塗り方のポイント・注意点を解説
クッションを使って体圧を分散させる
床ずれの応急処置として、すぐに実践できるのが体圧分散です。
床ずれは同じ部位に長時間圧力がかかることで発生するため、クッションを使って圧力を分散すると床ずれの予防につながります。
とくに仙骨部(お尻の上部)や踵など、骨が出っ張っている部分は床ずれが起こりやすい部位です。圧力がかかりやすい部位にクッションを使う意識を持つと良いでしょう。
体圧を分散させる方法は、以下のとおりです。
- 車椅子に座っているとき:座面にクッションを使用して圧力を分散させる
- ベッドで横たわっているとき:骨の出っ張りがある部分にクッションを使用して浮かせる
市販のクッションがない場合は、柔らかいタオルを折りたたんで代用も可能です。
これらの応急処置は専門的なケアの前に、すぐに実践できる対策として有効です。
介護保険適用の福祉用具をレンタルする
介護保険を利用すれば、さまざまな福祉用具を経済的な負担を抑えてレンタルが可能です。
介護保険の認定を受けている方であれば、自己負担額は原則として費用の1割(所得によっては2割または3割)となります。
床ずれ防止用具は、以下のとおりです。
- エアマットレス
- ウレタンマットレス
- 体圧分散クッション
- 体位変換器種類
参考:厚生労働省 『どんなサービスがどんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与あるの? – 福祉用具貸与』
レンタルする福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら、ご家族の状態に最も適したものを選びましょう。
たとえば、床ずれのリスクが高い方には圧切替型エアマットレスが、予防段階の方には静止型マットレスが適しています。
福祉用具をレンタルする際は、必ずケアマネジャーに相談し、介護保険の支給限度額内で計画的に利用しましょう。
関連記事:「福祉用具」について
介護施設を変える
適切なケアを受けるために、現在の介護施設から別の施設への移動を検討するのも重要な選択肢です。
床ずれができた状態で施設のスタッフによる対応が不十分だったり、予防策が適切でなかったりします。
新しい施設を選ぶ際は、床ずれケアに関する方針や体制を事前確認が大切です。
以下のような質問をすると方針と体制の確認ができます。
- 定期的な体位変換の実施状況
- 専門的な知識を持つ看護師の配置
- 床ずれ予防用具の使用状況
- 床ずれがある方の受け入れ実績
- 床ずれがある入居者へのケア方法
施設見学の際は実際のケア現場を見せてもらい、他の入居者の様子や職員の対応を観察することも大切です。
移転は負担も大きいですが、適切なケアを受けられる環境を選ぶことが家族の方の尊厳を守り、心身ともに豊かな暮らしにつながります。
床ずれの方を受け入れ可能な介護施設もある

介護施設を探す際、「床ずれの方受け入れ可能」と明示している施設があります。
このような施設は、床ずれケアに関する専門知識や技術を持ったスタッフを配置し、適切な予防・処置のための設備が整っています。
施設によっては褥瘡専門の看護師が在籍していたり、エアマットレスなどの専用器具が十分に用意されていたりと、ケア体制が充実しており安心です。
入居を検討する際は、施設見学時に床ずれケアの具体的な方法や頻度、使用している器具などについて詳しく質問することが大切です。
また、現在の床ずれの状態を正確に伝え、適切なケアが可能かどうかを確認しましょう。
「いいケアネット」などの老人ホーム・介護施設検索サービスを利用すれば、床ずれの方を受け入れ可能な施設を効率よく探せます。専門アドバイザーに相談することで、家族の状態に最適な施設を見つける手助けとなります。
入居前の不安や疑問点は遠慮なく相談し、安心できる環境を選びましょう。
介護施設で床ずれを見つけたら早期に対処しよう【まとめ】

介護施設に入居している大切な方に床ずれが発生した場合、早期発見と適切な対応が重要です。
床ずれは放置すると急速に悪化し、感染症などの深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
まずは施設スタッフへの速やかな報告と状態の記録を行い、必要に応じて専門医の診察を受けましょう。
日常的なケアとしては、クッションなどを活用した体圧分散や介護保険を利用した福祉用具のレンタルが効果的です。
現在の施設でのケアが不十分と感じる場合は、「床ずれの方受け入れ可能」と明示している施設への転居も選択肢の1つです。
これらの施設は褥瘡ケアの専門知識を持つスタッフや設備が整っており、安心してケアを任せられます。
「いいケアネット」では、床ずれケアに対応可能な施設を効率よく探せるほか、専門アドバイザーに無料相談できるサービスも提供しています。ご家族の状態に合った最適な施設選びをサポートしますので、お気軽にご相談ください。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。