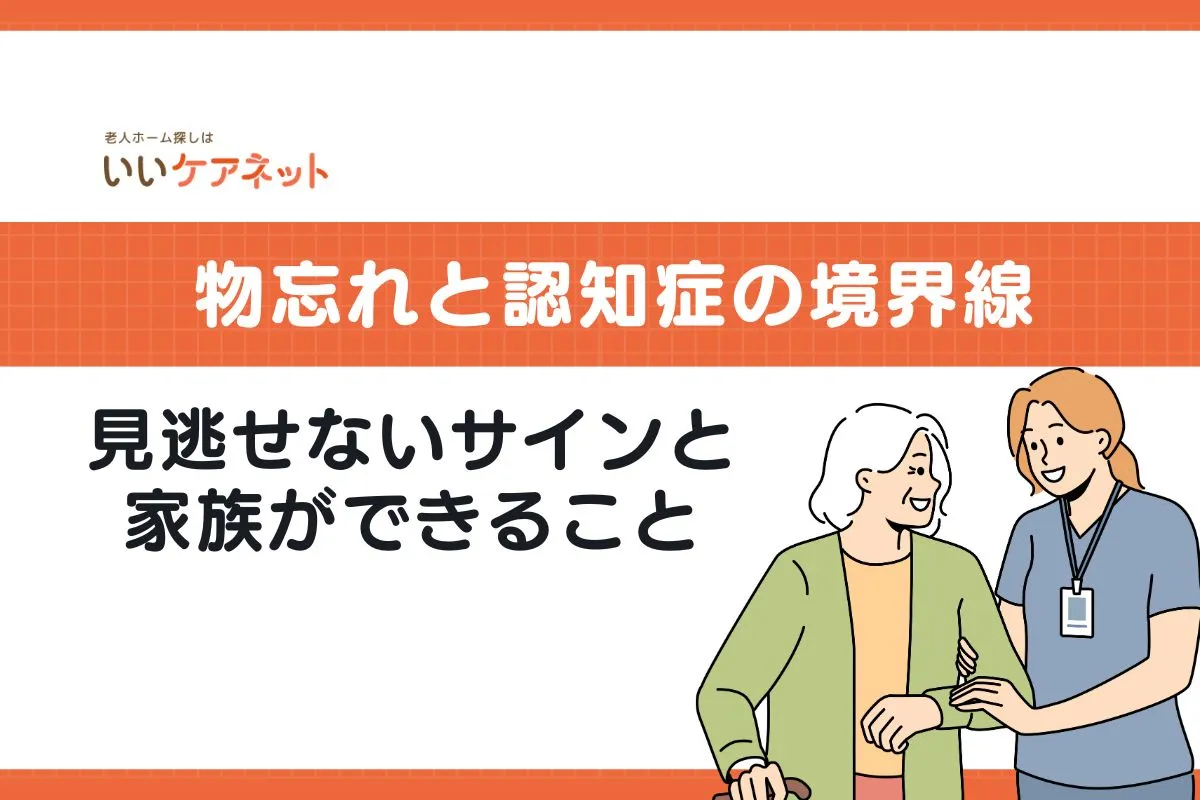「一人暮らしを続けられるだろうか」
「どんなサービスを受ければ良いか」
「施設への入所を考えるべきか」
一人暮らしの親が要介護4の認定を受けたとき、このように考える方もいるでしょう。
要介護4の状態で一人暮らしを続けることは簡単ではありません。しかし、適切な介護サービスを組み合わせることで、自宅での生活を維持している方もいます。本記事では、要介護4の方の一人暮らしに焦点を当て、利用できるサービスやケアプラン例、一人暮らしを継続する際の注意点などについて詳しく解説します。
要介護4は日常生活の大半で介護を必要とする状態

要介護4は、食事や排泄、入浴、着替えなど、日常生活の大半で介助が必要な状態です。立ち上がりや歩行が困難で、自力でできることは限られます。また、認知機能の低下により、理解力や判断力が低下している場合も多く、さまざまな行動の障害が見られることもあります。介護にかかる時間の目安である要介護認定等基準時間は90分以上110分未満とされています(文献1)。
要介護5との違いは
要介護5は、要介護4よりもさらに重度でほぼ寝たきりの状態です。日常生活で必要なすべての動作に介助が必要で、意思疎通も困難な場合があります。一方要介護4は、介助があれば食事を自分で食べられる、わずかに自力でできる動作が残っているなど、要介護5に比べてできることが少しだけ残されている状態です。しかし、どちらも日常生活には全面的な介護が必要な状態であることに変わりはありません。
要介護3との違いは
要介護3は、食事や排泄など、一部の日常生活動作に介助が必要な状態です。立ち上がりや歩行が不安定な場合もありますが、要介護4ほどではありません。また、認知機能の低下が見られることもありますが、要介護4ほど著しくないことが多いです。要介護4の方は、要介護3よりも身体能力、認知機能ともに衰え、より多くの介助を必要とします。日常生活のほぼすべてに介助が必要かどうかが、大きな違いと言えるでしょう。
要介護4でも一人暮らしは可能?

要介護4での一人暮らしは簡単ではありませんが、不可能というわけではありません。日常生活の多くで介助が必要な状態であり、介護する方の負担は大きくなるでしょう。しかし、適切なサポート体制を整えれば、一人暮らしを継続できる可能性はあります。
厚生労働省が実施した「2022年国民生活基礎調査(文献2)」によると、要介護4で一人暮らしをしている方は5.9%と、少数ではありますが、ゼロではありません。これは、さまざまなサービスや制度を活用して工夫することで、一人暮らしを続けている方がいることを示しています。
要介護4、一人暮らしで利用できるサービス

ここでは、要介護4と認定された場合に利用できるサービスをまとめています。
自宅で受けるサービス
在宅サービスは、自宅で受けられるサービスです。サービス事業者の担当者が自宅に訪問してくれるので、自宅にいながら必要な介護や看護、リハビリなどのサービスを受けられます。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所によるサービス
通所によるサービスは、自宅から日帰りで通って受けるサービスです。主にデイサービスやデイケアと呼ばれるサービスですが、提供している事業所のサービス種別によって、呼び方や目的が異なります。
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
施設サービス
施設サービスは、施設に入所して介護を受けながら生活するサービスです。
在宅介護を続けていると、施設への入所を考える方も多いでしょう。施設サービスについては、定員や入所判定などの関係で、入所までに時間がかかる場合もあります。そのため、検討だけは早い段階から始めておくのがおすすめです。
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
その他のサービス
他にも、あらかじめ日数を決めて利用するショートステイや福祉用具貸与などのサービスがあります。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与・購入費の支給
- 住宅改修費の支給
要介護4で一人暮らしをする際のケアプラン例

ケアプランとは、介護が必要な方が、どのような介護サービスをいつ、どれくらい利用するかを具体的に示した計画書のことです。たいていはケアプランをもとにサービスが提供されるため、介護保険サービスを利用する上ではなくてはならない書類です。
ケアプランは、利用者本人や家族の希望、心身の状態、生活環境などを考慮し、主にケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアプランに基づいてサービスが提供されることで、利用者は自立した生活を送るための支援を受けることができます。
以下は、一人暮らしの要介護4の方のケアプランの一例です。
| サービス名 | 利用回数/月 | 内容 |
| 訪問介護A(午前) | 毎日 | 着替え、排泄介助、朝食介助など |
| 訪問介護B | 週2回 | 排泄介助、病院の付き添いなど |
| デイサービス | 週1回 | 入浴介助、レクリエーション活動 |
| 訪問看護 | 週1回 | 栄養状態や体調の確認 |
| デイケア | 週1回 | 機能訓練、入浴介助 |
| 訪問介護A(午後) | 毎日 | 夕食介助、排泄介助、就寝準備など |
| 福祉用具貸与 | 定額 | 車いす、特殊寝台およびそれらの付属品 |
| ショートステイ | 7日間 | 日数を決めて短期間施設へ入所 |
このようなケアプランの場合、公的介護保険の自己負担額(1割負担の場合)は約30,000円となります。ただし、地域や利用するサービスによって金額は異なるため、必要なサービスや費用について、ケアマネジャーとよく相談する必要があります。
要介護4でかかる費用

要介護4の方の介護にはどのくらいの費用がかかるのか、不安に思う方も多いでしょう。ここでは、介護保険サービスの自己負担や、保険適用外の費用について解説します。
介護保険の負担割合と区分支給限度額
介護保険サービスを利用した場合、かかった費用のうち一定割合を自己負担します。負担する割合は所得によって決められ、原則1割から3割です。
また、負担が大きくなりすぎるのを防ぐために、自己負担額の上限(区分支給限度額)が決められています。要介護4の方の場合、支給限度額は負担割合によって309,380円から352,693円です。そのため、1割負担なら約30,000円が自己負担額の目安です。
支給限度額を超えた場合の負担
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。要介護4の一人暮らしでは多くのサービスが必要になり、限度額を超過する可能性もあります。とくにショートステイを長期間利用する場合、利用中に限度額を超えてしまうことがあるため注意が必要です。限度額内で効果的なサービス利用ができるよう、ケアマネジャーとよく相談する必要があります。
介護保険適用外の費用
サービス利用時には、介護保険の適用外の費用もかかります。たとえば、デイサービスやショートステイを利用した場合の食費や居室代、散髪代のような日常生活費は、原則として全額自己負担です。これらの費用も月々の負担として考慮し、事前にどのくらいかかるか把握しておくことが大切です。
要介護4で受けられる給付金制度

介護にかかる費用負担は大きいですが、負担を軽減するための制度があります。ここでは、要介護4の方が利用できる主な給付金や助成制度を紹介します。利用できる制度がないか確認し、経済的な負担を抑えられないか検討してみてください。
高額介護サービス費制度
1カ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割〜3割負担分)が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は世帯の所得状況によって異なります。多くの自治体では、一度申請すれば次回以降は自動的に振り込まれますが、初回の申請が必要な場合が多いので、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認してみると良いでしょう。
高額介護サービス費に関しては、別記事『高額介護サービス費とは?わかりやすく対象サービスや申請方法を解説』でも詳しく解説しているのでご参照ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯単位で合算できます。こちらも申請が必要となる場合が多いため、加入している医療保険の窓口や市区町村の介護保険担当課に確認が必要です。
自治体独自の助成制度
国の制度に加え、市区町村が独自に助成制度を設けている場合があります。たとえば以下のような制度があります。
- おむつの現物支給・購入費の助成
- 家族介護慰労金
- 介護保険料の減免など
内容は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口や、地域包括支援センターなどで確認してください。
医療費控除
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税・住民税の還付や軽減を受けられる制度です。介護保険サービス利用料の一部(医療系サービスなど)やおむつ代も対象となる場合があります(文献3)。領収書は必ず保管しておきましょう。
要介護4で一人暮らしをする際の注意点

要介護4での一人暮らしは、さまざまなリスクや課題が伴います。しかし、適切な準備と対策を講じることで、安全に生活できる可能性は高まります。ここでは、とくに重要な3つの注意点について解説します。
サービスを適切に利用して、介護者の負担を軽減する
要介護4の方の一人暮らしでは、本人の生活を支えるために、介護保険サービスを適切に活用することが重要です。訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイなどを組み合わせ、24時間切れ目のないサポート体制を構築します。とくに見守りや安否確認は欠かせません。民間の見守りサービスや、自治体の配食サービスなどの利用を検討することもあります。
制度を理解して、経済的負担を軽減する
介護保険の自己負担額を軽減するため、自己負担上限額を超えた分が払い戻される高額介護サービス費制度を活用できます。また、介護慰労金やおむつ代助成など、自治体独自の支援制度を設けている場合があります。これらの制度を理解して活用することで、経済的な負担を軽減できます。収入が少ない場合は、生活保護の申請を検討するのも選択肢のひとつです。まずはお住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。
緊急時の対応を決めておく
一人暮らしで最も心配なのは、急な体調不良や転倒などの緊急事態です。かかりつけ医や訪問看護ステーション、家族、近隣住民など、緊急連絡先を明確にしておき、すぐに連絡が取れる体制を整えておくことが重要です。普段から近所付き合いを大切にし、何かあったときに助け合える関係を築いておくことも大切です。
要介護4で一人暮らしの方が施設入所を考えるタイミング

要介護4は、多くのケアマネジャーが施設入所を勧める段階です。
- 家族の健康を損なうほど負担になっている
- 認知症の症状が進行し、在宅での安全確保が難しくなっている
- 医療的ケアの必要性が高まっている
- 介護者が高齢で、老老介護の状態になっている
このような場合は、施設入所を真剣に検討する時期かもしれません。
施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホームなど、さまざまな種類があります。それぞれの施設の特徴、費用、サービス内容を比較検討し、ご本人の状態や希望、経済状況に合った施設を選ぶことが大切です。
まとめ

要介護4で一人暮らしを続けるのは簡単なことではありません。しかし、適切なサービス利用や費用負担を軽減する制度を活用すれば継続も可能です。
自宅での生活がいよいよ難しくなったときには、施設入所も選択肢となります。ご本人に合った介護を見つけるために、情報収集を続けることが大切です。
いいケアネットでは、要介護4の方でも利用できる施設の紹介が可能です。無料で利用できるので、まずはお気軽にご相談ください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。