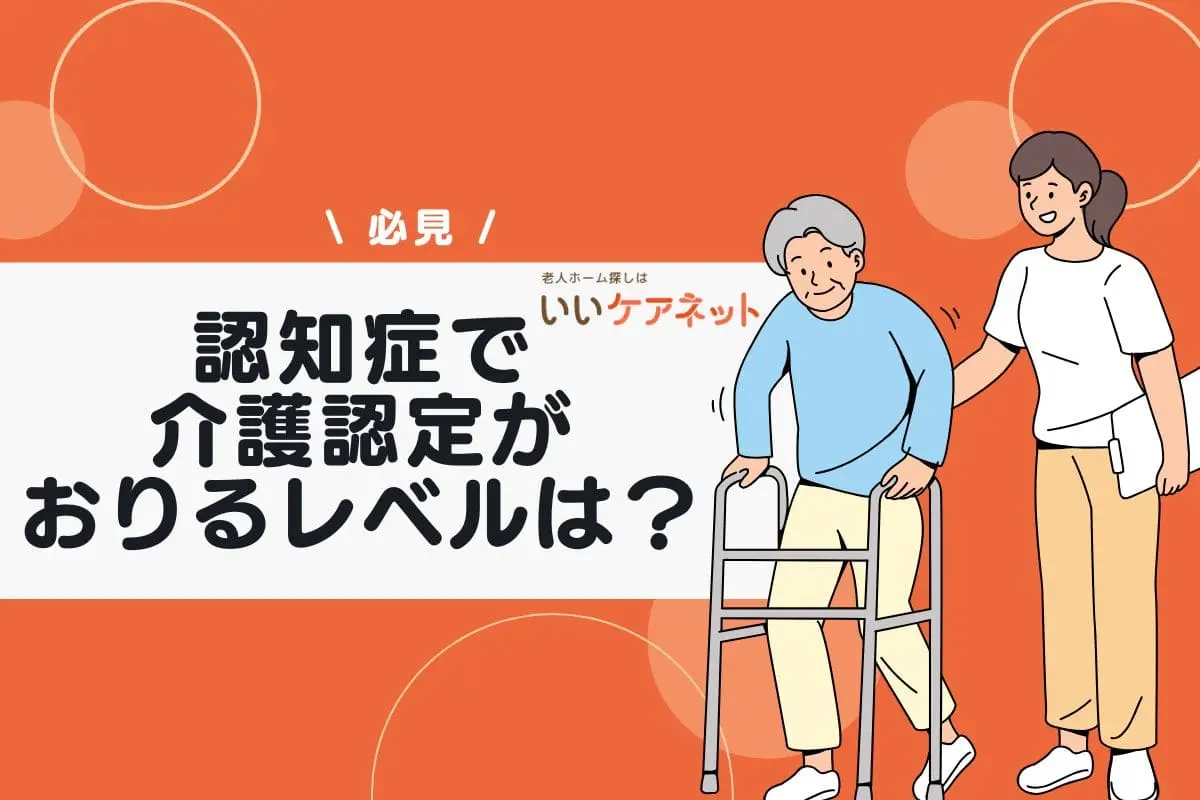福祉の分野において、スウェーデンは世界的に非常に優れているといわれています。しかし、スウェーデンの高齢者介護にはデメリットがないのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
スウェーデンでは高齢者が自宅で安心して暮らせるよう幅広いサービスを提供していますが、デメリットも存在します。
本記事では、スウェーデンの高齢者介護に関するデメリットについて解説します。メリットや日本との違いも紹介するので、スウェーデンの福祉事情が気になる方は参考にしてください。
いいケアネットでは、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。
スウェーデンの高齢者福祉に関するデメリット
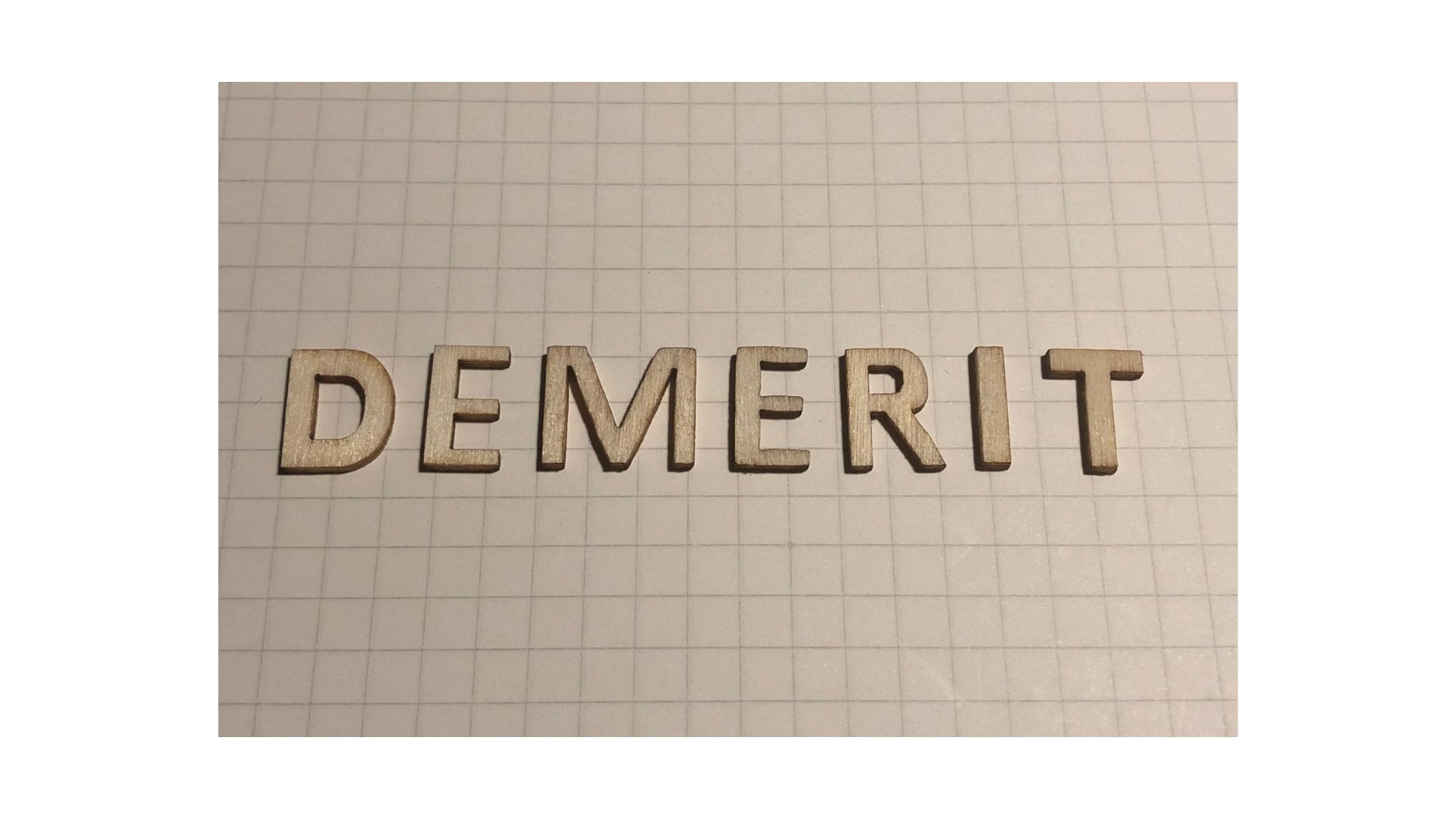
スウェーデンの高齢者福祉のデメリットは、以下の通りです。
- 介護・福祉に関する税負担が大きい
- 老人ホームや介護職員の人手が少ない
- 医療が福祉に介入しない
福祉大国と呼ばれているスウェーデンの課題を解説するので、参考にしてください。
介護・福祉に関する税負担が大きい
スウェーデンの介護・福祉は地方税を財源としており、税負担が日本に比べて大きい傾向にあります。
日本と異なり、スウェーデンには介護保険制度がなく、地方税が介護や福祉、学校教育などのサービスを提供する資金となっています。
国税庁のデータによると、スウェーデンと日本の国民負担税率は以下の通りです。
| スウェーデン | 日本 | |
| 租税負担率 | 49.5% | 28.2% |
| 社会保障負担率 | 5.1% | 19.8% |
| 租税負担率・社会保障負担率の合計 | 54.6% | 48.0% |
スウェーデンの国民負担税率は54.6%と、日本に比べて高いことがわかります。社会保障制度が充実しているものの、住民の税負担が大きい点はスウェーデンの福祉におけるデメリットです。
老人ホームや介護職員の人手が少ない
スウェーデンでは老人ホームや介護職員の人手不足により、介護は自宅でホームヘルパーと家族が行うのが一般的です。1990年代に、スウェーデンではエーデル改革がありました。
エーデル改革とは、地方自治体がすべての高齢者介護を担う制度です。医療措置が必要ない高齢者が病院に滞在し続ける場合、費用は地方自治体が支払わなければならなくなりました。
エーデル改革によって、医療と介護の連携が必要な認知症グループホームなどの老人ホームが廃止され、特別高齢者住宅に切り替わったのです。つまり、スウェーデンでは高齢者向け施設の少なさや介護職員の人手不足により、介護に関しては家族の負担が大きいデメリットが生じます。
医療が福祉に介入しない
スウェーデンは医療が福祉に介入しないため、介護において自立の考えが根付いています。前述したように、エーデル改革によりスウェーデンの医療と介護・福祉は、運営する自治体が分かれています。
スウェーデンでは、最後まで自立して生きる力を保つ感覚が根付いており、食事介助や栄養点滴がほとんどありません。自力で食事をとる意識が根強いため、身体が不自由な方向けの食器や器具が発達しています。
しかし、医療と介護の機能分担により往診や在宅医療、入院など外部医療の利用は最小限となる点が、スウェーデンにおける介護のデメリットです。
スウェーデンの高齢者福祉に関するメリット

スウェーデンの高齢者福祉に関するメリットは、以下の通りです。
- コミューンがサービスやヘルスケアを提供している
- 在宅介護を重視している
- 介護費用は地方税によって賄われている
日本とは異なるスウェーデンの介護事情を知りたい方は、参考にしてください。
コミューンがサービスやヘルスケアを提供している
コミューンとは、日本の市町村に近い自治体です。社会福祉サービスや教育、地域交通などコミューンはさまざまな公共サービスにおける役割を担っています。
社会福祉において、コミューンは高齢者が自宅で生活できるよう自宅改造や在宅介護サービスなどを提供しています。また、サービスを利用する費用はコミューンの税財源と個人の自己負担で賄う仕組みです。
自己負担金はコミューンによって異なりますが、利用者の所得に応じて最低所得や負担額の上限が設けられているため、費用負担が高額になるケースはありません。
在宅介護を重視している
スウェーデンでは在宅介護を重視しており、ほとんどの高齢者が自宅で生活を送っています。
高齢者が安心して自宅で過ごせるよう、コミューンでは介護サービスを受けられる体制を整えているのがスウェーデンにおける社会福祉の特徴です。
例えば、高齢者が体調を崩した場合でもコミューンが介護してくれる環境が形成されています。また、ホームヘルプサービスやデイケアサービスなど、スウェーデンでは高齢者向けサービスが充実しています。老後は自宅で生活を送りたい方にとって、スウェーデンの社会福祉はメリットです。
在宅介護のメリット・デメリットについては、以下で詳しく解説しています。
関連記事:在宅介護のメリット・デメリット|費用〜在宅介護の限界まで解説!
介護費用は地方税によって賄われている
スウェーデンの介護費用は地方税によって賄われているため、介護状態になっても費用負担が少ない点がメリットになります。
日本では介護保険制度によって介護の財源を確保していますが、老後の備えに不安を抱く方は少なくありません。
対して、スウェーデンでは、足が不自由になった場合でもコミューンのサービスにより自宅改造が可能で、資金も援助されます。
税金で介護サービスを運営できるため、老後の備えに対する不安を感じにくい点がメリットになります。
スウェーデンにおける高齢者福祉の支援策

コミューンにより、スウェーデンではさまざまな高齢者福祉の支援策を実施しています。ここでは、スウェーデンにおける高齢者福祉の代表的な支援策を紹介します。
- 特別な住居
- ホームレスパイト
- ミーティングポイントの常設
- ホームヘルプサービス
- ナイトパトロール
福祉国家スウェーデンの支援策について知りたい方は、参考にしてください。
特別な住居
特別な住居とは、高齢者の療養型施設をいいます。主な療養型施設は、以下の通りです。
- サービスハウス
- 老人ホーム
- グループホーム
- ナーシングホーム
特別な住居には24時間介護職員が常駐しており、幅広い支援を受けられます。自宅での生活が難しいと判断された場合、特別な住居に入居が可能です。
ただし、スウェーデンでは一般的に在宅介護が推奨されているため、できる限り自宅で過ごせるように特別な住居での居住期間は短い点が特徴です。
ホームレスパイト
ホームレスパイトとはヘルパーを自宅に派遣して、家族介護者をケアするサポートです。スウェーデンでは自宅での介護がほとんどのため、家族への負担が大きい点が懸念されます。
ホームレスパイトは、家族介護者が自分の時間を確保できるようにするためのサービスです。また、ヘルパーの派遣費用は平日・休日ともに無料のため、家族介護者は気軽にサービスを受けられます。
ホームレスパイトで家族介護者へのサービスを提供している点が、スウェーデンにおける社会福祉の特徴です。
ミーティングポイントの常設
ミーティングポイントの常設とは、介護者出会いセンターや介護者援助グループの会などの施設で、介護者と被介護者が集まり飲食しながら談笑するサービスです。
コミューンにおけるサービスの一環となっており、介護者と被介護者の絆を深める機会を設けています。
ミーティングポイントの主な活動は、以下の通りです。
- カウンセリング
- 講演会
- 健康促進活動
- 趣味の活動 など
ミーティングポイントの設置は、スウェーデンの生活習慣の1つとして定期的に開催されています。
ホームヘルプサービス
ホームヘルプサービスとは心身機能の低下により、自立した生活が難しくなった高齢者に対して提供されるサービスです。
一般的にホームヘルプサービスは申請したのち、ホームヘルプアシスタントが高齢者を訪問して面談を実施してから開始されます。
ヘルパーが自宅へ訪問して、高齢者にさまざまなサポートをしてくれるのがホームヘルプサービスの特徴です。
主なサポートは、以下の通りです。
- 掃除
- 洗濯
- 食事の用意
- 買い物
- 入浴・排泄などのケア
- 薬の管理
- 医師や看護師とのコンタクト
なお、ホームヘルプサービスを提供している事業は複数あり、利用先は利用者本人が選択できます。
ナイトパトロール
ナイトパトロールとは、夕方から朝にかけてヘルパーや准看護師が介護者の自宅を訪問し、食事や就寝のサポートを提供するサービスです。
また、介護者の見回りや緊急の呼び出しにも対応してくれるのが、ナイトパトロールの特徴になります。
ナイトパトロールは、高齢者が自宅で安心して過ごせる介護サービスの一つです。夜に何かあった場合でも、自宅に駆けつけてくれる環境を整えているのがスウェーデンの福祉事情です。
スウェーデンと比較してわかる日本における高齢者福祉の課題

福祉大国のスウェーデンと日本では、介護・福祉にさまざまな違いが生じます。スウェーデンの社会福祉から学ぶ日本の課題は、以下の通りです。
- 地域で高齢者を支援する体制
- 高齢者を支える家族に対するサポートの実施
スウェーデンと日本の高齢者福祉の違いを踏まえたうえで、課題について理解を深めていきましょう。
地域で高齢者を支援する体制
日本では、地域で高齢者を支援する体制を整える環境作りが課題です。スウェーデンには、コミューンが作られており、地域で高齢者を支援するサービスが多数提供されています。
例えば、介護者が集まるミーティングポイントの設置や、高齢者が独立して生活できる支援などがスウェーデンでは利用可能です。
高齢者自身を支援できるよう、地域での取り組みを考えるのが日本の福祉における今後の課題といえます。自治体や包括支援センターがどのように高齢者支援を提供していくのかを明確にするのが、課題を解決するうえで重要です。
高齢者を支える家族に対するサポートの実施
日本では、高齢者を支える家族への支援策を検討する必要があります。スウェーデンでは在宅での介護がほとんどのため、家族の負担が大きくなってしまいがちです。
家族をケアできるよう、スウェーデンはホームレスパイトを提供しています。家族が1人の時間を作れる仕組みを作っているため、介護に対するストレスを緩和できるメリットがあります。
対して、日本ではスウェーデンのように、ホームレスパイトといった支援がありません。介護者家族へのサポート体制が十分ではないため、家族はストレスを抱えてしまいがちです。
介護者家族の介護疲れを緩和できるよう、日本でも支援策を検討するのが今後の課題といえます。
いいケアネットでは、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。入居に関する無料相談を受け付けているので、老人ホーム探しに関する疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
在宅介護のメリット・デメリットについては、以下で詳しく解説しています。
関連記事:家族の介護でもらえるお金は?ジャンル別に9つの制度を解説
スウェーデンの福祉に関するデメリットや支援を踏まえたうえで介護に備えよう【まとめ】

医療大国と言われるスウェーデンの福祉・老人ホームの体制は日本と比較しても非常に高いもので、
日本が参考にするべき内容も少なくありません。
しかし、スウェーデンの福祉は税負担が大きかったり医療が福祉に介入しなかったりするデメリットについても、理解しておく必要があります。
とはいえ、スウェーデンでは高齢者が自宅で安心して暮らせるサービスを多数提供しています。日本でも、スウェーデンのように地域で高齢者を支援する体制や、介護者家族に対する実施の検討が重要です。
いいケアネットでは、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。
監修者 日本介護福祉教育学会 城田 忠
大阪青山大学介護福祉別科准教授。介護教育と介護留学を専門とし、外国人留学生の介護福祉士国家試験の合格率向上や日本語教育に関する研究を行い、介護福祉業界の発展に貢献。