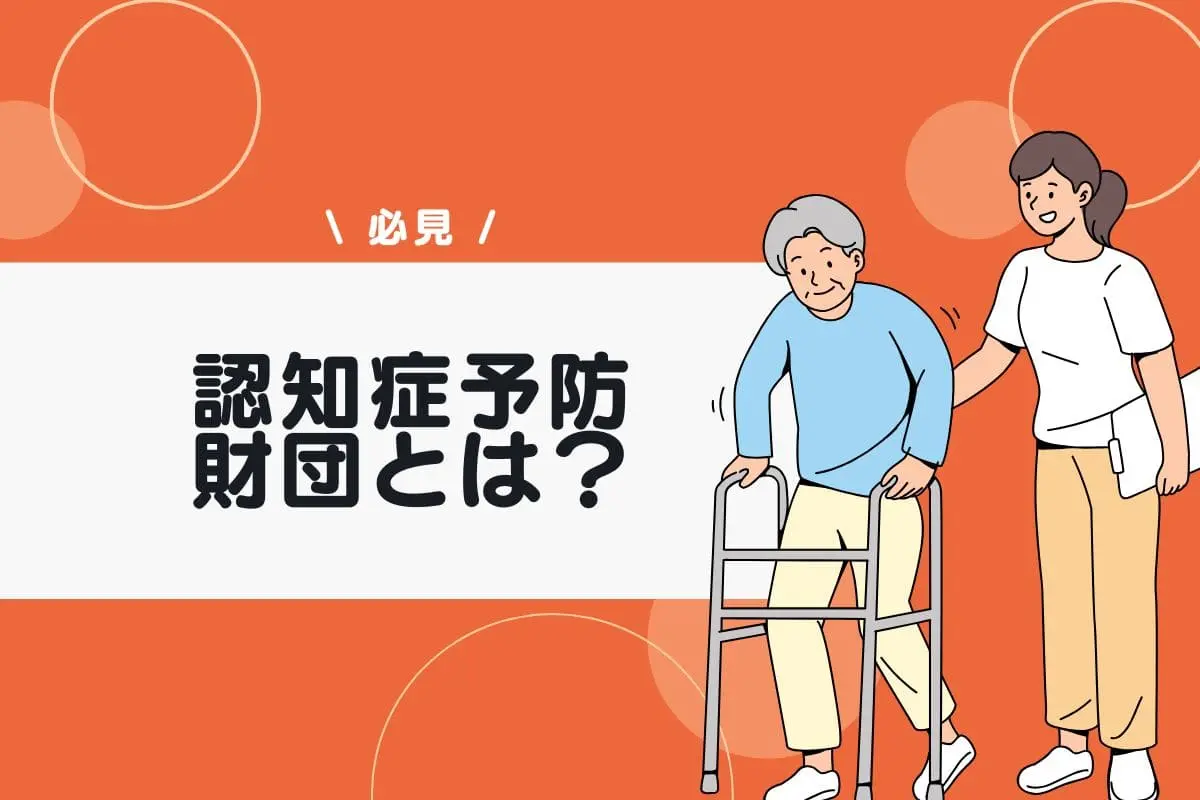「介護から解放された後の親を亡くした喪失感が辛い…」
「介護から解放されたら、社会から一人取り残された感じがして苦しい…」
このように、親の介護が一段落した後に、うつ病のような状態になっている方は少なくありません。
親を亡くした喪失感や孤独感といった心身にかかる負担から、うつ病や介護ロス症候群になる方もいます。
今後のあなたの人生を前向きに歩んでいくためにも、介護から解放された後の心身の不調における原因と対処法を理解しておきましょう。
この記事では、介護から解放された後に起きやすい心身の不調とその対処法を詳しく解説します。体調を崩さず介護を続ける方法も紹介しているので、参考にしてみてください。
介護から解放された後に起こり得る心身の不調と対処法

長期の在宅介護を終えると、解放感と同時に心身のバランスが崩れやすくなります。
たとえば、以下のような不調が起きるケースは珍しくありません。
- うつ病
- 介護ロス症候群
- 孤独感・孤立感
それぞれの病気や感情の特徴を見ていきましょう。
うつ病
大切な人を失った悲しみや喪失感は、時として深刻なうつ病へと発展する可能性があります。
うつ病の主な症状と治療方法は、以下のとおりです。
| 主な症状 |
|
| 主な治療法 |
|
症状が2週間以上続くときは、うつ病の可能性が高いです。大切な人を亡くした後に心身の不調が現れたら、心療内科や精神科への受診を検討してみましょう。
介護ロス症候群
介護ロス症候群とは、長期間の介護生活から解放された後に心身の不調を感じる状態のことです。親を失った喪失感や「私の介護は十分だったのだろうか」という後悔の念に苦しむ方が多くいます。
主な症状は身体面と精神面の両方に現れやすく、たとえば以下のような症状が出ることがあります。
- 食欲不振
- 好きなものを食べても「おいしい」と感じられなくない
- 疲れているのに眠れない
- 疲労感
- 気分のひどい落ち込み
- 人とのかかわりを避けるようになる
- 「自分なんて必要ない」という希死念慮を抱く
介護ロス症候群の症状は単なる一時的な落ち込みではなく、放置すると臨床的なうつ病へと進行するリスクが高いです。
介護期間中の「燃え尽き症候群」の延長線上にあるこの状態は、早急な専門的な支援により改善が期待できます。
孤独感・孤立感
長年介護に専念してきた方は、介護終了後に深い孤独感や孤立感に苦しむ場合があります。
介護期間中に社会との接点が減少し、友人関係や地域社会とのつながりが希薄になりがちです。介護が終わった後、急に一人になったような感覚に陥る方は少なくありません。
以下は孤独感・孤立感を和らげる対処法です。
- 地域のサークルや教室に参加する
- ボランティア活動に取り組む
- 家族や友人と連絡を取る
- 地域包括支援センターに相談する
- 心療内科やカウンセリングを受ける
一人で抱え込まず、周囲の人や専門機関に相談することが大切です。人々との交流は「ひとりではない」「仲間がいる」これらを実感させてくれるため、心理的負担を大きく軽減します。
介護から解放された後に体調を崩さないための方法

介護から解放された後の心身の健康を維持するためには、介護中から以下のような意識的な取り組みが重要です。
- 自分の頑張りを認める
- 家族で協力して介護する
- 専門家に相談する
- 介護サービスを積極的に利用する
- 介護施設への入所を検討する
それぞれのポイントを見ていきましょう。
自分の頑張りを認める
介護をしている間から心の健康を意識し、介護が終わった後の心と体の元気につながるという考えを意識しましょう。
介護うつになりやすい人には、「頑張りすぎる」「責任感が非常に強い」といった傾向があります。そういった人ほど、自分を後回しにしてしまいがちです。
日ごろから「自分は良く頑張っている」と認め、小さな成功体験を積み重ねていく自己肯定感の保持が大切です。
完璧を求めず、できる範囲で最善を尽くしている自分を褒める習慣をつけましょう。
家族で協力して介護する
一人で介護を抱え込むと、精神的なダメージが大きくなりやすいです。
家族で定期的に話し合いをして、介護の役割をはっきりさせることが大切です。お互いの生活やできる範囲に合わせて、無理のない協力体制を作るように心がけてみてください。
専門家に相談する
介護の悩みは一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。相談は決して恥ずかしい行為ではありません。
地域包括支援センターは高齢者とその家族の総合相談窓口として、さまざまな相談を無料で受け付けています。また、精神保健福祉センターでは、精神的な健康に関する専門的な相談や就労支援なども利用可能です。
専門家への相談は、客観的な視点から状況を整理し、適切な支援につなげてもらえるメリットがあります。
介護サービスを積極的に利用する
デイサービスや訪問介護などの介護サービスは、介護者の負担を大幅に軽減できるサービスです。
これらの介護サービスは、介護者の負担が減るだけで無く、介護を受ける側も専門的なケアを受けられる体制を整えられます。
介護サービスの利用は「家族の責任を放棄すること」ではなく、むしろ持続可能な介護体制を作るための賢明な選択です。
定期的にリフレッシュする時間を確保しながら、介護者自身の健康を維持し、結果的により良い介護を提供できるようになります。
ケアマネジャーと相談しながら、家族の状況に合った最適なサービスを組み合わせて活用しましょう。
関連記事:介護が必要になったら何から始めるべき?受けられるサービス内容とは?
介護施設への入所を検討する
在宅介護が限界に達する前に、介護施設への入所を検討も重要な選択肢です。
たくさんの介護者が「親を施設に入れることへの罪悪感」を抱きますが、これは決して親不孝ではありません。
むしろ、介護のプロによる24時間体制のケアは、在宅介護では限界がある安心と安全を確保できます。
施設入所により、家族は「介護者」から「家族」本来の立場に戻れるため、穏やかな関係性を取り戻すケースも珍しくありません。
罪悪感に囚われず、本人と家族全体の幸せを考えた最善の選択が大切です。
「いいケアネット」では家族全体の生活の質が向上するよう、さまざまな老人ホームを紹介しています。介護施設への入所を検討し始めたら、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:親を施設に入れる罪悪感がある方必見!葛藤や後悔を払拭する方法を解説
介護から解放された後の自分の時間を大切にしよう【まとめ】

介護から解放された後に感じる虚無感や無気力は、あなただけが経験している特別なケースではありません。
介護から解放された後のうつ病や介護ロス症候群は、多くの元介護者が直面する課題です。
専門家への相談、地域活動への参加、趣味の再開、新たな学びへの挑戦、就労の再開など、小さな一歩から始めることが大切です。
焦らず、自分のペースで前に進んでいきましょう。
高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。