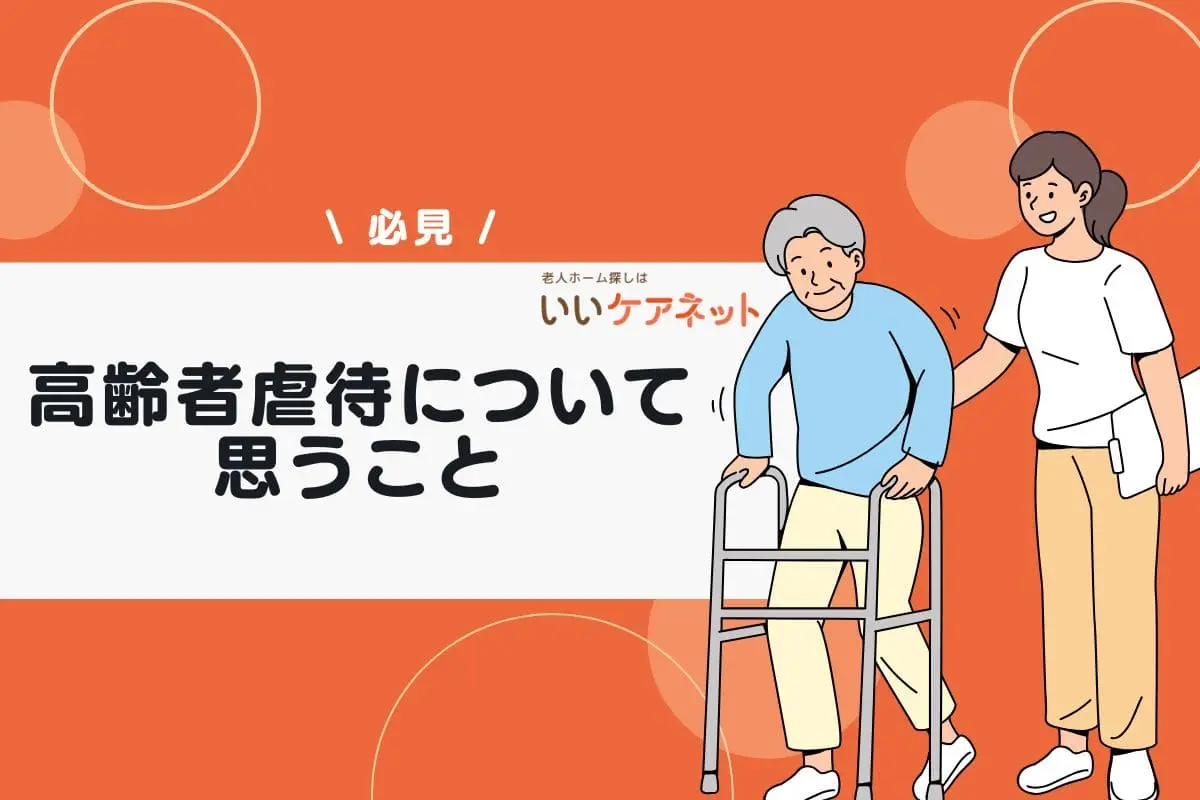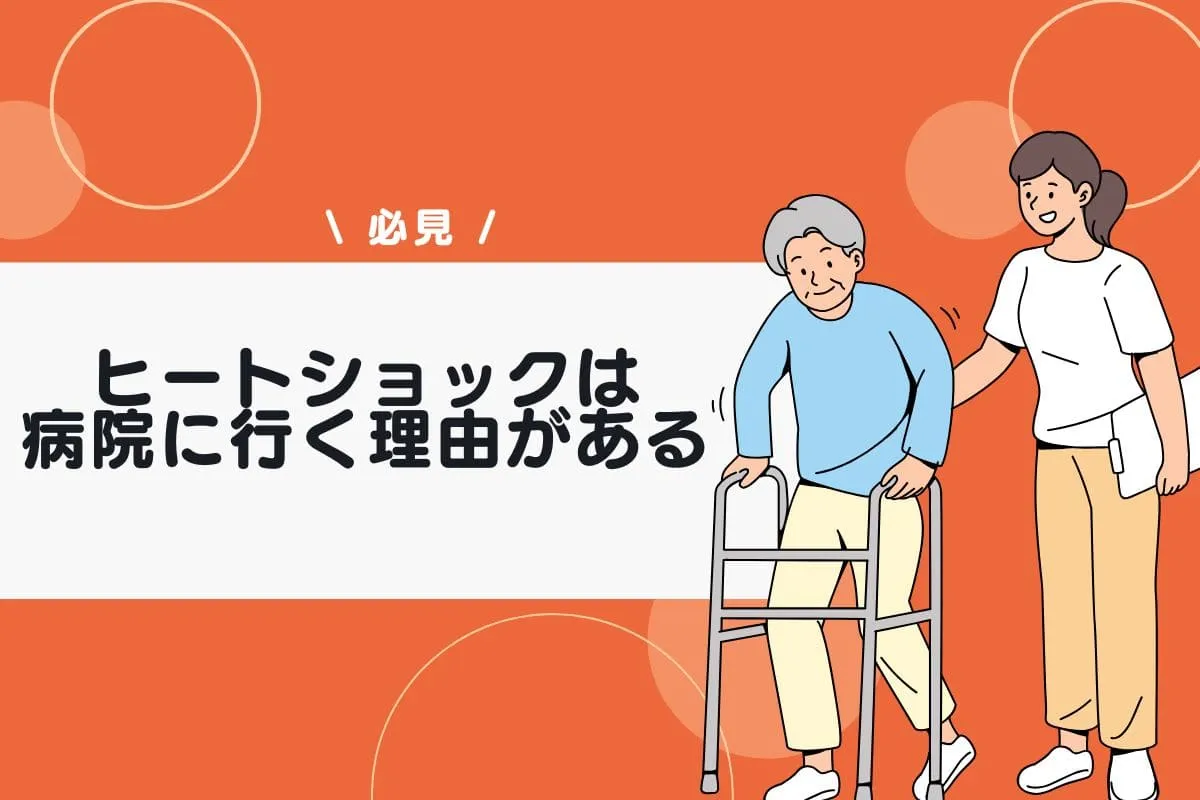「母が“家に帰りたい”と毎日言うようになり、施設に迷惑をかけていないか心配です。」
「帰宅願望が続くと、退去させられたりしないでしょうか…?」
認知症を患う高齢者に多く見られる「帰宅願望」は、本人の不安や混乱の表れであり、決して珍しいものではありません。とはいえ、毎日のように「家に帰る」と訴えられると、施設にいづらくなったり、退去を迫られるのではと感じたりしてしまうのも無理はないでしょう。
結論から言うと、帰宅願望が理由で施設から退去させられることは基本的にありません。施設側も認知症の特性を理解したうえで、適切な対応をおこなっています。
ただし、本人の不安や環境への不適応が長引くと、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。だからこそ、帰宅願望の背景を正しく理解し、適切な対処を知っておきましょう。
本記事では、帰宅願望が起こる原因や、本人が「退去したい」と訴えたときの対応方法を詳しく解説します。親の帰宅願望への対応に困っている方は、参考にしてみてください。
帰宅願望があっても退去させられることはない

帰宅願望が強いと退去させられるのではと不安になってしまいますが、強く訴えたとしても基本的に退去させられることはありません。とはいえ、施設側から退去勧告される可能性はあります。
施設ごとに退去勧告する基準は異なりますが、一般的に以下の5つは退去勧告される可能性が高いです。
- 経済状況が悪化し利用料が支払えない場合
- 医療対応のレベルが上がり、施設で対応できない場合
- 長期間の入院が必要になった場合
- ほかの利用者への迷惑行為が多い場合
- 自傷行為など問題行為が増えた場合
問題行為や具体的な問題が怒らない限り、家に帰りたい本人の気持ちだけで退去させられることはありません。
関連記事:認知症グループホームから追い出される理由とは|確認事項・やるべき事項まとめ
帰宅願望は認知症の代表的な症状

あまりにも家に帰りたいと言われると「施設選びを間違えたのでは」「自宅介護のほうが良かったのか」など考えてしまいますが、認知症の症状により帰宅願望が強まっているケースが多いです。
認知症の症状にBPSDという帰宅願望があり、自宅にいても帰りたいと訴える高齢者もいます。
記憶障害や見当識障害により自分の状況が理解できず、安心できる場所である家に帰りたい気持ちが強く表れることがあります。帰宅願望は、わがままではありません。
家は現在の住まいだけでなく、幼少期を過ごした実家など、過去の思い出と結びついた場所です。帰宅願望が満たされないと、徘徊や興奮などの行動に発展し、介護する側にとって対応の難しさにつながることもあります。
関連事:物忘れと認知症の境界線|見逃せないサインと家族ができること
帰宅願望が生じる5つの原因

認知症の症状である帰宅願望は、精神的な不安や焦燥感を抱いたり、孤立感を感じたりした際に現れやすいと言われています。
どのようなときに帰宅願望が生じるのでしょうか。主な原因は以下の5つです。
- 自分が置かれている状況を理解できない
- 環境の変化に対応できていない
- 介護されている現実を受け入れられない
- 夕暮れ時の不安感が強い
- 入所している施設が意向に合わない
帰宅願望の原因がわかれば本人の気持ちに寄り添ってあげられるので、適切な対応をとれるようになります。なぜ帰宅願望が生じるのか、原因を1つずつ解説していきます。
自分が置かれている状況を理解できない
認知症の初期症状に現在の状況を理解しにくい記憶障害と、日付や場所、現在どこにいるのか理解できない見当識障害があります。
そのため、老人ホームにいるにもかかわらず、以下のように訴えてくることがあります。
- 家で家族が待っているから帰りたい
- 会社に行かなければいけない
- 犬の散歩に行かなければいけない
本人の記憶の中にある「当たり前の日常」が強く残っていることに加え、自分が置かれている状況を理解できない戸惑いや不安感からくる発言です。
混乱した気持ちのなかで安心できる「自宅」に戻りたい思いが強まり、帰宅願望につながっていきます。
環境の変化に対応できていない
慣れ親しんだ自宅から生活拠点が変わり急激な変化に対応できず、その場から逃げ出したい気持ちから帰宅願望が出現するケースもあります。
とくに周囲の環境や人間関係になじめない場合、そのストレスが強く表れやすくなります。
たとえば部屋で快適に過ごせなかったり、ほかの入居者との関係が希薄で孤独感を感じたりすると、今の生活に対する不満が蓄積され、家に帰りたい気持ちがさらに募ってしまいます。
環境の変化に対応できず戸惑うのは、認知症に限った話ではありません。転校や転勤、引っ越しなど生活が大きく変わると、誰でも起こることです。
一時的な感情によるものか、継続的に訴えるのかによって必要な対応は異なります。本人の状態や言動をよく観察し、しっかりと見極めることが大切です。
介護されている現実を受け入れられない
高齢になると着替えや食事など今まで自分でできていたことも、誰かの介助がなければできないことも増えてきます。
父親としての自分や会社員の自分、今まで人を指導するはずだったのにと、老いや介護されている自分を否定する人は少なくありません。
介護されている現実を受け入れられない人には、以下のような特徴があります。
- プライドが高い
- 自分1人でやろうとする気持ちが強い
- 生活や気持ちに余裕がなく将来への不安感が強い
「自分はまだ若い」「何でもできる」と思っている人ほど、本来の場所へ帰りたい気持ちにつながってしまいます。
夕暮れ症候群とは暮れ時の不安感が強い
帰宅願望の1つに夕暮れ症候群というものがあり、薄暗くなる夕方になると落ち着かず帰宅願望が強まってしまいます。夕暮れは子ども達や会社員が帰宅したり、夕飯を作り始める時間です。
認知症により、以下のような状態が見られます。
- 薄暗くなると不安や混乱、興奮状態になってしまう
- 現在と過去の出来事が混同してしまう
- 家族団らんの場所へ帰りたがる
長年の習慣から「仕事が終わり家族で過ごす」「夕飯を作り家族で食べる」といった日常の記憶が呼び起こされ、ご本人はそこに帰る場所があると強く思い込んでしまいます。
自分自身で切実な帰宅願望をコントロールすることはできません。
入所している施設が意向に合わない
入居している施設の環境がご本人に合っていないことが、帰宅願望として現れている場合もあります。認知症の症状と一括りにせず、環境要因にも目を向けてみましょう。
無理に我慢を続けることは、心身の不調につながる恐れがあります。まずは、施設長やスタッフと状況を共有し、改善の余地があるか相談してみることが大切です。
すべての要望がそのまま受け入れられるわけではありませんが、対話を通じて解決策が見つかることも多くあります。
たとえ人生の最終的な住まいとして選んだ老人ホームであっても、ご本人やご家族の生活スタイルに馴染めない場合は、別の施設へ移ることも検討してみてください。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。無料で利用できるので、登録してどんな施設があるかチェックしてみてください。
帰宅願望で退去を訴えてくるときの対処法

帰宅願望は本人にとっては切実な訴えであり、不安や混乱から帰りたいと伝えてきます。無理に否定や説得をせず受け止めることで、安心感を得られるようになります。
帰宅願望を訴えてくるときは、以下の対処法を試してみてください。
- 本人の気持ちを否定せず受け止める
- 嘘をつかず真摯な対応を心がける
- 落ち着ける空間を作る
- 今すぐ帰宅はできないと説明する
帰宅願望が強いときは、本人を安心させ居心地の良い空間を整えることが重要です。どうすれば安心してもらえるのか、対処法を1つずつ解説していきます。
本人の気持ちを否定せず受け止める
仕事へ行く、ご飯を作るなど、何かしらの理由があり帰宅したいと訴えています。帰りたい気持ちを受け入れ、否定せずに声がけをすると帰宅願望が和らぎます。
以下のように、否定せずに対応しましょう。
- 仕事に行く
「今日会社はお休みです」 - ご飯を作りに行く
「外食すると言ってました」 - 犬の散歩に行く
「今日は息子さんが行く日です」
認知症の方に間違いを指摘すると、混乱が強くなるため逆効果です。完全に否定せず、安心できる声がけをしてあげてください。
関連記事:まだらボケ(認知症)の接し方は?主な症状や家族の対応について解説
嘘をつかず真摯な対応を心がける
不安感が帰宅願望を募らせる大きな要因となるため、ごまかしの言葉を使うのは避けましょう。また、本人の訴えをただ聞き流し、落ち着くのを待つだけでは、信頼関係を損ねてしまいます。
「家に帰りたい」と切実な思いを抱える方に対し、明らかな嘘や不明確な返答は、不必要な不安をあおり事態を悪化させるリスクがあります。
以下のように、気持ちに寄り添い安心感を与えましょう。
- 家に帰りたい
何か心配事でもありますか? - ここに居たくない
何か嫌なことでもありましたか?
真摯な対応を続けることで信頼関係を構築し、結果として帰宅願望の訴えが減っていく可能性があります。
落ち着ける空間を作る
認知症の方の帰宅願望を和らげるには、心安らぐ居場所を整えることが非常に重要です。安心感や自分らしさを感じられる環境が、気持ちを穏やかにしてくれます。
たとえば、以下のような工夫が効果的です。
- 家族写真や家具、大切にしているものを配置する
- 観葉植物や花を飾る
- なるべく家と近い環境を整える
家にいたときと同じようにリラックスできれば、帰宅願望が徐々に薄れていくでしょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、介護に関する疑問や施設にまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
今すぐ帰宅はできないと説明する
施設に入居している場合、本人の希望だけで帰るのは難しいです。しかし、帰宅できないと伝えると不安感が増してしまうため、あくまでも「今は」帰宅できないと説明し安心させてあげましょう。
以下のように、帰ること自体は否定せず伝えるのが効果的です。
- 今は難しいけど体調が良くなったら帰れるよ
- 今度の日曜日に外出許可が出てから一緒に帰ろう
認知症の程度にもよりますが、気持ちが落ち着くと帰りたいと言っていたことすら忘れてしまう場合もあります。
本人の気持ちに寄り添った上で、今は帰れない、少し待とうなど声掛けしましょう。
帰宅願望で退去を訴える本人の気持ちに耳を傾けよう【まとめ】

帰宅願望は不安の表れなので、否定せず、本人の気持ちに耳を傾けてあげることが重要です。しっかり寄り添うことで「自分の話を聞いてくれる人がいる」と安心感を得られます。
また、しっかり耳を傾けることで表面的な訴えだけでなく、本当の訴えや不安がわかり、本人に寄り添ったサポートができます。
まれに施設の環境が合わずに帰りたいと訴えるケースもあるため、認知症だからと決めつけず耳を傾けてあげましょう。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です!親の介護にお悩みの方は、気になる記事をチェックしてみてください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。