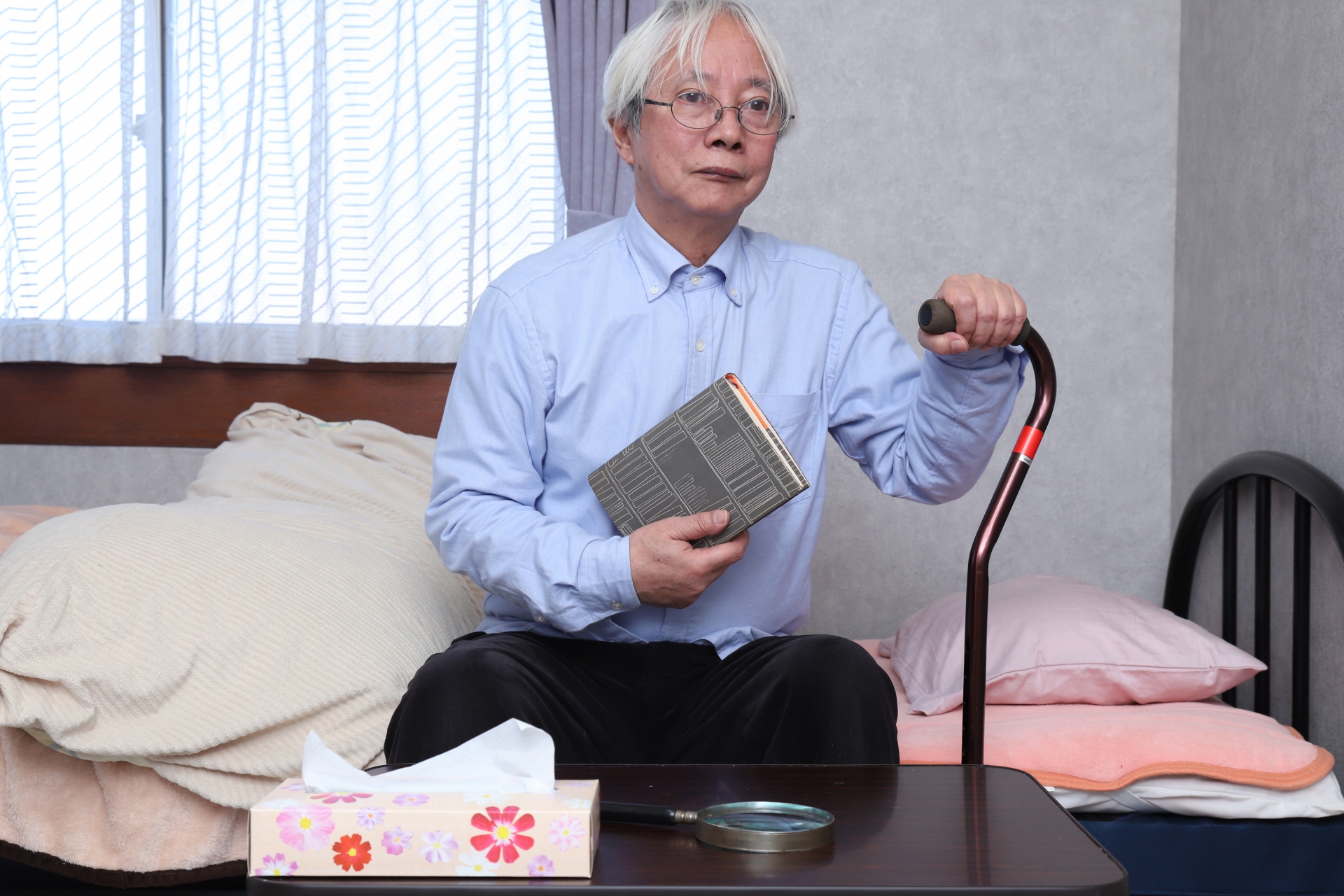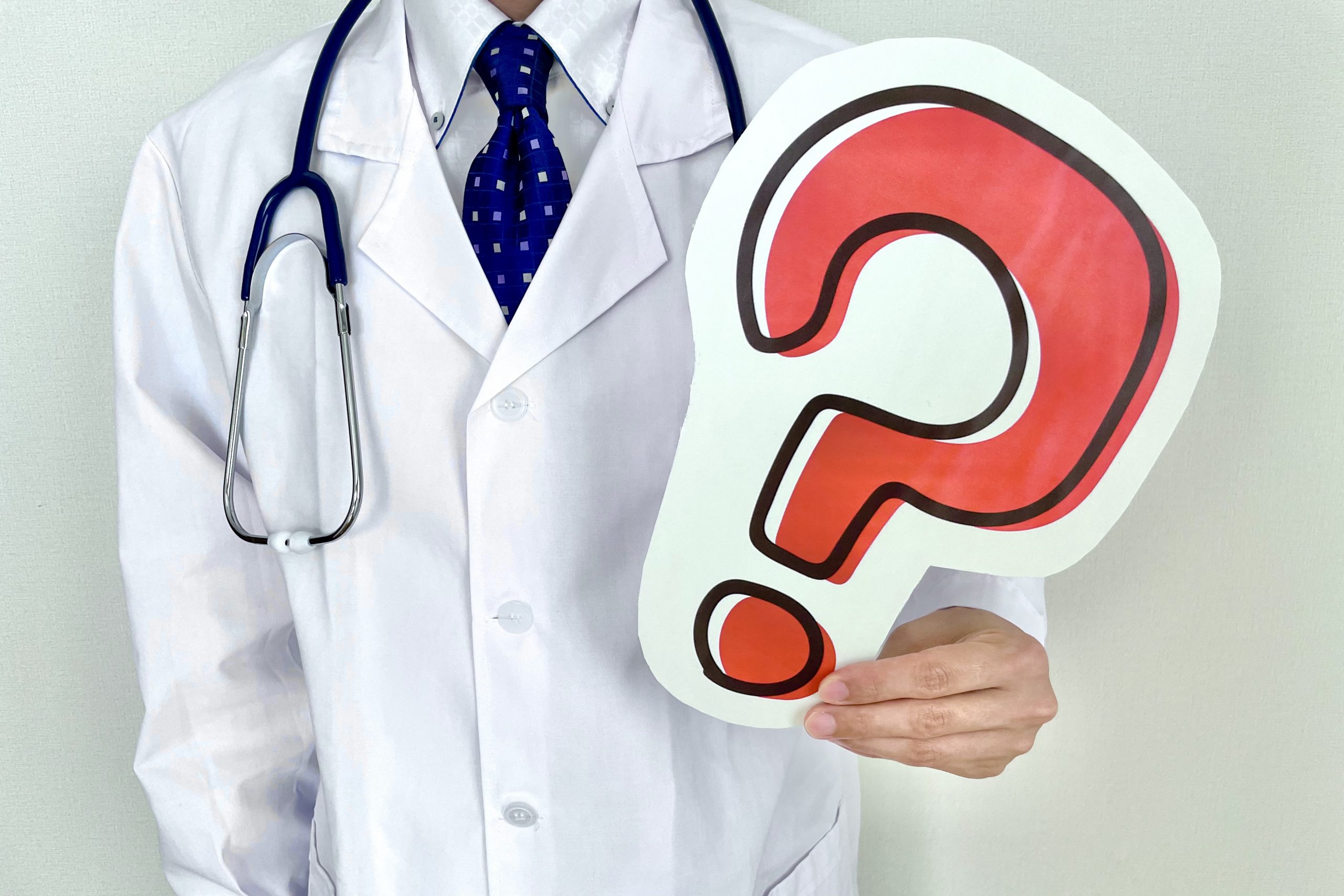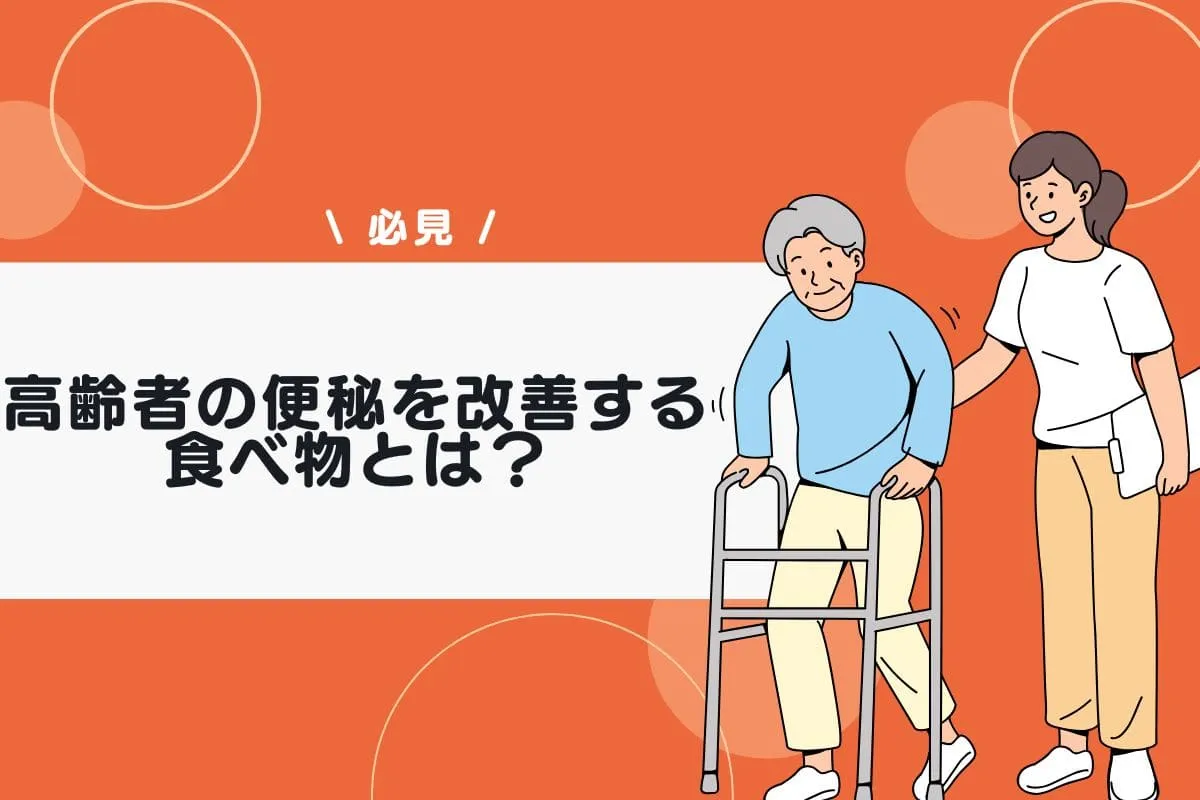介護が必要になったら、どこから始めれば良いのかと悩んでいる方は少なくありません。
突然の状況変化に直面したとき、適切な情報や支援を受けられるかが重要なポイントになるためです。
本記事では、介護が必要になったら最初におこなうべきステップや、利用可能な介護保険制度、具体的な介護サービス内容について詳しく解説します。
介護が必要になったら、何から手をつけるべきか、不安や心配を抱える方に向け、具体的かつ実用的な解決策を提供します。
多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
介護が必要になったらやるべきこと

介護が必要になったら、冷静に対応するためにも適切な順番を把握しておく必要があります。
介護が必要になったら必要な相談先や申請などの流れは、以下の通りです。
- 介護保険被保険者証が届いているか確認する
- 自治体や地域包括支援センターに相談する
- 要介護認定を申請する
- 要介護認定の判定や認定を受ける
- ケアマネジャーを決める
- ケアプランを作成してもらう
- サービスの利用を開始する
ステップごとに詳しく解説しているので、状況に応じて振り返れるよう、ぜひ参考にしてください。
STEP1:介護保険被保険者証が届いているか確認する
介護が必要になったら、まずは「介護保険被保険者証」が手元に届いているかを確認しましょう。
介護保険被保険者証とは、介護保険制度を利用するための基本的な証明書であり、要支援・要介護認定を受ける際のスタート地点となります。
通常、65歳以上の方には市区町村から自動的に送付されますが、住所変更や転居があった場合には届いていない可能性もありますので注意が必要です。
介護保険被保険者証が届いていない方や紛失してしまった方は、速やかに市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせて再発行を依頼しましょう。
介護保険被保険者証を受け取った後は、内容に誤りがないかを確認し、必要に応じて訂正手続きをおこないます。
とくに、氏名や住所、被保険者番号などの情報に誤りがあると、介護サービスの利用手続きに支障をきたす可能性があるため注意しましょう。
STEP2:自治体や地域包括支援センターに相談する
介護が必要になったら、次は自治体や地域包括支援センターに相談しましょう。
自治体や地域包括支援センターは、地域における介護サービスの情報提供や、適切な支援策の提案をおこなっています。
とくに地域包括支援センターは、介護が必要な高齢者を支えるための地域の窓口として、介護保険の申請やサービス利用のアドバイスをおこなう重要な役割を担っています。
また、介護のプロフェッショナルであるケアマネージャーと連携し、個々の状況に応じたケアプランの作成をサポートしてくれるのが特徴です。
相談を通じて、どのような介護サービスが利用できるのか、費用負担はどの程度か、具体的に把握できます。
さらに、地域独自の支援策や助成制度についても情報を得られるため、介護に関する不安や疑問を解消する大きな助けとなります。
STEP3:要介護認定を申請する
要介護認定の申請は、介護が必要になったら受けられる介護サービスを利用するための重要なステップです。
要介護認定とは「介護が必要」である点を認めてもらうための手続きです。要介護認定は、自治体や地域包括支援センターに問い合わせて、申請書を入手します。
申請には、自治体によって異なるものの、基本的には以下が必要になります。
- 要介護または要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(顔写真があるマイナンバーカードなど)
担当のケアマネジャーがいれば、委任状を用意すれば代行申請も可能です。
申請直後に認定が受けられるわけではないため、なるべく介護サービスに精通している専門家に相談するのがおすすめです。
STEP4:要介護認定の判定や認定を受ける
要介護認定を受けられるかどうかは、認定基準を満たしているかのチェックがおこなわれます。
要介護認定の申請を受け取った各市区町村が専門の調査員を派遣し、訪問調査が実施されます。
麻痺の有無や寝返りの状況などの聞き取り調査をするのも、客観的に介護が必要かどうかを判断するためです。
その後、主治医の意見書を受け取り、コンピュータによる一次判定と要介護認定審査会における二次判定がおこなわれます。
認定結果は、通常は申請から30日以内に通知されますが、自治体によっては多少の遅れが生じるケースもあります。
注意点として要介護認定は、定期的に見直されるため、状況が変わった場合には再申請が必要です。
関連記事:要介護認定を受けるには何が必要?申請先や具体的な方法を詳しく解説
STEP5:ケアマネジャーを決める
ケアマネジャーの選定は、介護サービスをスムーズに利用するための重要なステップです。
ケアマネジャーは、介護が必要な方の生活状況や健康状態を総合的に把握し、最適なケアプランを作成してくれます。
ケアマネジャーが身近にいない方は、各市区町村に「ケアマネジャーを探している」旨、伝えるとケアプランセンターの一覧表を渡してもらえます。
ケアマネジャーは、単に介護サービスを手配するだけではなく、利用者やその家族とのコミュニケーションを通じて、心身の健康を支える立場です。
介護が必要になったら頼るケアマネジャーを選ぶ際、相談しやすく柔軟に対応してくれる方を選びましょう。
関連記事:ケアマネージャーは変更できる!変更方法や注意点について解説
STEP6:ケアプランを作成してもらう
ケアプランは、介護サービスを受けるにあたっての具体的な計画書であり、利用者の個別のニーズに応じて作成されます。
ケアプランを作成する際、ケアマネジャーと相談しながら、本人の健康状態や生活環境、希望する介護サービスを詳しく話し合います。
話し合いのもとケアマネジャーは、情報をまとめながら、最適な介護サービスの組み合わせを提案し、ケアプランを作成する流れです。
たとえば、デイサービスの利用回数や訪問介護の時間帯、リハビリテーションの必要性などが含まれます。
完成したケアプランは「原案」として介護サービスを提供する事業者を交えての「サービス担当者会議」がおこなわれます。
STEP7:サービスの利用を開始する
ケアプランの作成が終わり、利用する介護サービスの事業者との契約が済んだらサービス開始になります。
サービス開始にあたっては、サービスの内容や料金体系、提供頻度について詳しく確認し、不明点があればその場で質問するのが大切です。
また、サービス開始後も定期的にケアマネジャーと連絡を取り、状況に応じてプランの見直しをするのがおすすめです。
とくに介護サービスの事業者や施設と問題が発生した場合、すぐにケアマネジャーに相談し、必要に応じてプランやサービスの見直しをおこないましょう。
しかし、ケアマネジャーに頼りすぎるのではなく、自分でも必ず契約書面の内容を見ておき、トラブル防止に努めましょう。
多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
関連記事:介護保険申請のベストなタイミングはいつ?流れや必要なものを紹介
介護が必要になったときに利用できる介護保険制度とは

介護が必要になったら利用できる介護保険制度とは、高齢化社会において介護が必要となった方を支援するために設けられた公的な制度です。
ここからは、介護保険制度の仕組みや、公的・民間の介護保険における違いについて深掘りしていきます。
介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、介護が必要な高齢者や障がい者が安心して適切な介護サービスを受けるための仕組みを提供しています。
制度の基本的な仕組みとしては、40歳以上の国民が介護保険料を支払い、介護が必要になったらサービスを受けられる仕組みです。
介護保険制度において、市町村と特別区である東京23区が保険者となり、被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)の2つに分類されます。
- 第1号被保険者:要介護(または要支援)認定を受けられれば利用可能
- 第2号被保険者:特定疾病(※)によって介護が必要と判断された場合に利用可能
※特定疾病とは、がんや関節リウマチなど、介護が必要となる可能性が高い16の疾病を指す
利用者の自己負担は、原則として介護サービス費用の1割から3割です。
自己負担額を抑えながら介護サービスを利用できるため、要介護認定を受けた方は介護保険制度があるのを忘れないようにしましょう。
関連記事:介護保険制度とは?~仕組みやサービスの種類・制度の最新情報まで解説~
公的と民間の介護保険の違い
公的介護保険と民間介護保険は、どちらも介護が必要な方々を支援するための制度ですが、その内容や目的には大きな違いがあります。
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |
| 提供者 | 日本政府 | 民間保険会社 |
| 対象 | 65歳以上または特定条件を満たす40歳以上 | 任意加入 |
| 目的 | 低コストでの介護サービス提供 | 公的保険でカバーされない部分の補填 |
| 保険料 | 所得に応じて異なる | 商品によって異なる |
| 自己負担 | あり(一定限度額あり) | 商品によって異なる |
| 加入条件 | 全国民加入義務 | 商品によって異なる |
公的と民間保険それぞれの特徴を踏まえ、自分の生活スタイルや将来的な介護のニーズに合った選択をするのが重要です。
介護が必要になったら利用できる主なサービス

ここからは、介護が必要になったら利用できる介護サービスについて、以下の観点からそれぞれ紹介します。
- 自宅で生活しながら利用できるサービス
- 住み慣れた地域にいながら利用できるサービス
- 施設に入所するサービス
ニーズにあわせて利用できる介護サービスを選ぶ際に、ぜひ役立ててください。
自宅で生活しながら利用できるサービス
自宅で生活しながら利用できる介護サービスである「居宅サービス」は、利用者が住み慣れた環境で快適に暮らし続けるための重要なサポートを提供します。
訪問介護(ホームヘルプ)はその一例で、ヘルパーが自宅を訪れ、食事の準備や掃除、入浴介助など日常生活の支援をおこないます。
居宅サービスにより、家族の負担を軽減し、利用者の自立した生活を支援できるのが特徴です。
訪問介護は、食事や入浴、看護など、幅広い選択肢があるため、在宅介護をしている方にとって、ニーズにあわせた介護サービスが利用できます。
住み慣れた地域にいながら利用できるサービス
住み慣れた地域で安心して介護サービスを受けられる「地域密着型サービス」は、家族にとっても本人にとってもおすすめの介護サービスです。
地域密着型のサービスは、利用者がこれまで慣れ親しんだ環境で生活を続けながら、必要な支援を受けられる点が大きなメリットです。
たとえばデイサービスでは、日中の時間を施設で過ごし、食事や入浴の支援を受けられます。
夜間徘徊を防止するために、夜間対応型訪問介護もあります。
また、住み慣れた地域からは離れずに入所できる有料老人ホームや軽費老人ホームも選択肢になるのが地域密着型サービスです。
施設に入所するサービス
施設に入所するサービス(施設サービス)は、在宅介護が難しくなった際頼りになる選択肢です。
24時間体制で専門的な介護を提供する施設に入所し、日常生活全般の支援を受けられるため、利用者とその家族にとって大きな安心をもたらします。
たとえば、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの種類があり、それぞれの施設は異なるサービス内容や介護度に対応しています。
施設選びの際には、利用者の身体状況や希望、家族の意向を十分に考慮するのが重要です。また、施設によっては入所待機期間があるため、早めの情報収集と手続きが求められます。
見学や相談を通じて最適な施設を選び、利用者の快適な生活を支える第一歩となります。
どの介護サービスを利用すべきかお悩みの方はいいケアネットへお任せください!【まとめ】

介護が必要になったら、どこから始めれば良いのか、多くの人が不安や戸惑いを感じるでしょう。
まずは、介護保険制度を理解し、必要なサービスを選ぶのが重要です。
地域包括支援センターやケアマネージャーに相談し、本人や家族に合った支援を受けられるよう関係を構築していきましょう。
また、介護サービスには訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、状況に応じた選択が可能です。
介護する側もされる側も、負担を軽減しながら生活の質を向上できるかに注目しましょう
なお、いいケアネットでは「入居無料相談」を受け付けております。
「介護が必要になったら何をすれば良いのか話し合いながら進めたい」方も含め、気軽にご相談ください。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。