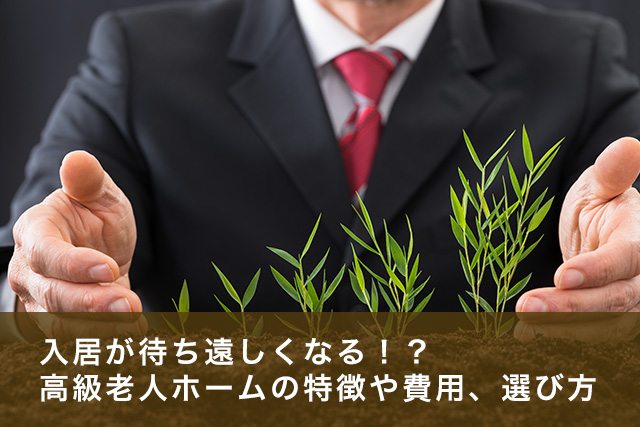「ケア・コミュニケーション検定を受けようと思うんだけど合格率はどれぐらい?」
「そもそもケア・コミュニケーション検定ってどんなメリットはあるの?」
このようにお悩みの方もいるでしょう。
ケア・コミュニケーション検定の合格率は8割を超えており、取得することでコミュニケーション能力のアップや認定証をもらえるなどのメリットがあります。
本記事では、ケア・コミュニケーション検定の合格率や概要、日程について解説します。取得するメリットや受験の流れ、勉強方法についても紹介するので、将来の介護に備えてコミュニケーションスキルを習得したい方は参考にしてください。
高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です!介護にお悩みの方は、気になる記事をチェックしてみてください。
ケア・コミュニケーション検定の合格率は80%以上

ケア・コミュニケーション検定は、個人・団体受検ともに合格率が80%を超え、計画的な学習で十分に合格を狙える資格です。
検定の合格ラインは合計得点の65%以上で、2024年度の個人受検における平均合格率は82.4%でした。
企業などが申し込む団体受検でも、2023年度の平均合格率は81.5%と高い水準にあり、しっかり対策すれば突破できる基準といえるでしょう。
この検定に合格すると、ケア・コミュニケーションの専門的な能力が証明されます。証明されるのは、基本的な考え方を深く理解し、目的や状況に応じて的確に表現する語彙力と知識です。
さらに、看護や介護の現場で、利用者や家族と円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力も含まれます。
ケア・コミュニケーション検定とは

ケア・コミュニケーション検定とは、株式会社サーティファイが実施する民間資格です。ケア・コミュニケーションは、看護や介護のケア・支援を受ける人とサポートする人とのコミュニケーションをいいます。
家族が介護状態になった場合、コミュニケーションがうまくとれず悩むケースも少なくありません。ケア・コミュニケーション検定では、介護の現場において要介護者と円滑なコミュニケーションをとれる知識を習得できます。
適切なコミュニケーションが取れると、適切なケアが可能になるため、介護によるストレス緩和にもつながるでしょう。
要介護者とのコミュニケーションに関する知識を得たい場合に、ケア・コミュニケーション検定はおすすめです。
介護が必要になった場合にはじめることについては、以下で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:介護が必要になったら何から始めるべき?受けられるサービス内容とは?
ケア・コミュニケーション検定を取得するメリット

ケア・コミュニケーション検定の取得は、介護をするうえで良い効果をもたらします。主なメリットは、以下の3つです。
- 要介護者との円滑なコミュニケーションがとれる
- オープンバッジとで認定証をもらえる
- 履歴書に書ける
以下で、詳しく解説します。
要介護者との円滑なコミュニケーションがとれる
ケア・コミュニケーション検定を取得すると、介護や看護などの現場で円滑なコミュニケーションがとれます。介護の現場では、相手が求めていることを理解し、寄り添う姿勢が重要です。
介護状態は一人ひとり異なるため、都度対応を変える必要があります。ケア・コミュニケーション検定では、ケア・コミュニケーションの基本的な心構えや良好な関係を築くためのコミュニケーション力などに関する知識を身につけられます。
そのため、要介護者と円滑なコミュニケーションを図れるため、要介護者が求めていることを理解し、適切な対応が可能です。将来、家族が要介護状態になったときの備えになる点が、ケア・コミュニケーション検定を取得するメリットになります。
現代ならではのコミュニケーション方法や、介護拒否の場合のコミュニケーションについて以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:
高齢者とテレビ電話でコミュニケーションを楽しもう!おすすめなアプリも紹介
介護を拒否する親への接し方|拒否する理由や対応例も解説
オープンバッジとで認定証をもらえる
サーティファイが主催するケア・コミュニケーション認定試験に合格すると、オープンバッチと呼ばれる認定証が交付されます。オープンバッチは、ICT活用教育分野における国際的な技術標準規格「IMS Global Learning Consortium」に準拠したデジタル証明です。
オープンバッチの取得には、次のメリットがあります。
- 専用の「オープンバッチウォレット」で認定履歴を一元管理できる
- ブロックチェーン技術を取り入れているた偽造・改ざんが防止できる
- オープンバッチはSNSやメールなど幅広いシーンで共有できる
また、ケア・コミュニケーション検定に合格するとオープンバッチだけでなく、デジタル認定証明書が交付されます。デジタルデータとして保存できるのはもちろん、印刷も可能となるため、活用シーンにあわせて利用できる点がメリットです。
履歴書に書ける
ケア・コミュニケーション検定は履歴書にも書けるため、介護の現場だけでなく仕事でも活かせます。高度なコミュニケーション能力がある証明として、ケア・コミュニケーションは効果的です。
コミュニケーション能力は、就職の現場でも重視されています。厚生労働省の「中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究」によると、採用評価項目においてコミュニケーション能力は管理職や総合職で特に求められていることがわかります。
実際に、コミュニケーション能力は総合職の採用において79.5%と、もっとも高い結果です。ケア・コミュニケーションは医療や介護、福祉で活かせます。強みとしてアピールできる点も、ケア・コミュニケーション検定を取得するメリットです。
参考:厚生労働省|中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究
ケア・コミュニケーション検定の試験概要
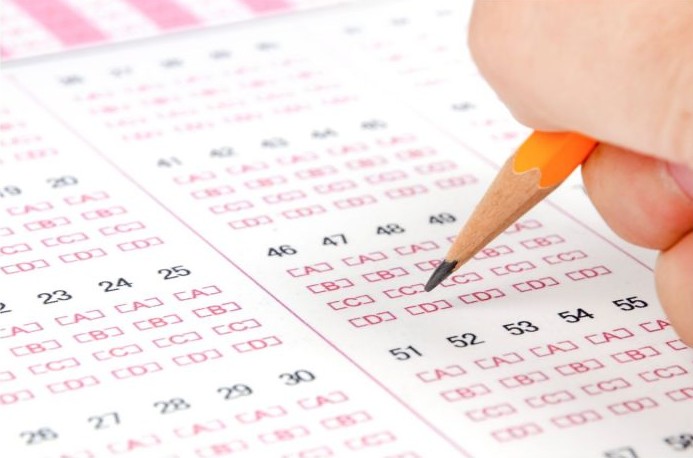
ここでは、ケア・コミュニケーション検定を個人が受講する際の試験概要について解説します。
- 受講資格
- 試験日程
- 試験形式
- 出題内容
- 合格点と合格率
介護におけるコミュニケーション能力向上へ向けて、受講を検討している方は、参考にしてください。
受講資格
ケア・コミュニケーション検定には、受講資格はありません。学歴や年齢などに制限がないため、どなたでも受講可能です。
また、ケア・コミュニケーション検定は介護や医療業務が未経験でも受験できます。受講資格不問のため、将来の介護の備えとして知識を習得しておくのにおすすめです。
試験日程
ケア・コミュニケーション検定の試験日程は、個人と企業で異なります。個人の受講は実施団体で任意に試験日程を設定できる企業と異なり、試験日程が決められており、年2回ほどです。
2025年〜2026年の試験日程は、以下のとおりです。※
| 試験日 | 申込期間 | 結果発表 |
| 2025年3月9日(日) | 2024年12月10日~2025年3月2日 | 2025年3月26日 |
| 2025年6月15日(日) | 2025年4月1日~2025年6月8日 | 2025年7月2日 |
| 2026年3月18日(日) | 2025年12月23日~2026年3月1日 | 2026年3月25日 |
ケア・コミュニケーション検定は、3月と6月に試験が開催される傾向にあります。試験日の1週間前まで申し込みが可能なため、学習の進捗状況に応じて検討するとよいでしょう。
※2025年5月時点の情報となります
試験形式
ケア・コミュニケーション検定の試験は、リモートWebテストによる在宅受験形式です。10時〜12時までの時間内であれば、好きなタイミングで受験をはじめられます。
そのため、たとえば、10時30分から試験をはじめても問題ありません。また、試験時間は60分なので、10時30分からはじめた場合は11時30分で試験が終了となります。
リモートWebテストは、2つのカメラと7つのAIによる不正監視機能を搭載しているため、在宅でも公平かつ公正な試験を受講できます。また、以下の条件が揃っていれば、国内外問わず受験が可能です。
- インターネット接続環境
- パソコンやタブレットなど受験用端末
- スマートフォン
- スマートフォンスタンド
- 静かな個室
受験用端末は、外付けのカメラとマイクが必要になります。
出題内容
ケア・コミュニケーション検定の問題数は40問で、主題形式の内容は以下の5つです。
- ケア・コミュニケーションの基本的な心構え
- 被援助者と良好な関係を築くためのコミュニケーション力
- 被援助者を受け入れ・支えるためのコミュニケーション力
- 職場におけるチームワークとコミュニケーション力
- 被援助者の症状に応じたコミュニケーション力
5つの分野から、多岐選択式問題にクリックで解答していく形式となります。なお、ケア・コミュニケーション検定を実施している株式会社サーティファイの公式サイトによると、「ケア・コミュニケーション」テキストを使用した場合の学習時間の平均は30時間です。
知識や実務経験の有無によって学習時間は異なりますが、目安として進めていくとよいでしょう。
ケア・コミュニケーション検定に関する受験の流れ

ケア・コミュニケーション検定を個人で受験する際の流れは、以下のとおりです。
- 試験内容を確認する
- 公式サイトから受験を申込む
- 申込時に「資格受付ONLINE」アカウントを作成する
- 資格受付ONLINEから「Webテスト受験方法」ページを読み込み、リモートWebテストの受験準備をする
- 資格受付ONLINEにログインして受講する
- 試験1ヶ月後に合否通知メールが届く
- 資格受付ONLINEから合否を確認する
ケア・コミュニケーション検定を申込む際は、資格受付ONLINEと呼ばれるアカウントを作成する必要があります。資格受付ONLINEとは、株式会社サーティファイの受験者向けポータルサイトです。
登録したアカウントは、株式会社サーティファイが主催する試験に共通で利用できるため、今後の資格取得にも活用できます。
ケア・コミュニケーション検定の勉強方法

ケア・コミュニケーション検定の勉強法には、教材の活用がおすすめです。合格へ向けた勉強方法には、次のものがあります。
- テキストを活用する
- 過去問を解く
それぞれ紹介するので、自身に合った方法で学習を進めていきましょう。
テキストを活用する
ケア・コミュニケーション検定には、公式テキストが用意されています。公式テキストは、主題範囲を学習内容に沿って解説しています。
また、各分野で理解度チェックや演習問題などがあるため、理解度を確認しながら進められる点が特徴です。テーマ別の練習問題と、模擬試験問題が掲載されているケア・コミュニケーション問題集とあわせて学習を進めていくと、理解度を深められるでしょう。
過去問を解く
ケア・コミュニケーション検定の勉強には、過去問を解く方法もあります。株式会社サーティファイの公式サイトには、検定試験の問題がPDF形式で用意されているため、試験対策として活用するのもおすすめです。
問題文は試験と同じで、制限時間60分40問となっています。マークシート形式になっているため、印刷して模擬試験として活用するのも効果的です。
ケア・コミュニケーション検定を取得してケアの質を上げよう【まとめ】

ケア・コミュニケーション検定では、介護の現場において要介護者と適切なコミュニケーションを図るために必要なスキルを身につけられます。試験の合格率は82.4%のため、計画的に学習を進めていくと資格取得を目指せるでしょう。
介護では、要介護者とのコミュニケーションが重要です。コミュニケーションをとり、適切な対応をとることで、良好な関係を築けます。コミュニケーションスキルを高め、ケアの質をあげるためにも、ケア・コミュニケーション検定の受講を検討しましょう。
なお、高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です!介護にお悩みの方は、気になる記事をチェックしてみてください。
ケア・コミュニケーション検定に関してよくある質問
サーティファイのコミュニケーション検定との違いはなんですか?
コミュニケーション検定とケア・コミュニケーション検定は、どちらも「サーティファイコミュニケーション能力認定委員会」が主催しています。
コミュニケーション検定とケア・コミュニケーション検定の主な違いは以下の表のとおりです。
| ケア・コミュニケーション検定 | コミュニケーション検定 | |
| 目的 | 医療・福祉・介護の現場で、患者・利用者・家族との信頼関係を築き、ホスピタリティとチームワークを高めるコミュニケーション能力を可視化・認定する。 | 対面で「話す・聴く」場面において、状況を正しく把握し、目的や場面に応じた適切な表現で自分の意思をわかりやすく伝える力(基礎知識+実践対応力)を測定・認定する。 |
| 主な対象者 | ・医療・福祉・介護スタッフ ・これらの分野を学ぶ学生 ・施設職員の研修・教育用 |
・就職・転職でコミュ力を証明したい学生・社会人 ・接客・営業・人事・管理職など対人対応が多い職種 ・研修講師・マナー講師 |
| 出題内容 | 1.基本的な心構え 2.被援助者と良好な関係を築く力(非言語・言語・敬意) 3.受容・共感/苦情対応/説明と同意確認 4.チームワークと職場内コミュニケーション 5.症状別コミュニケーション |
Part 1 基礎知識編 ・来客・電話応対 ・アポイント・訪問・挨拶 ・情報共有・質問・返答 ・チームコミュニケーション ・非対面(チャット等) Part 2 実践編 ・接客・営業・クレーム対応 ・会議・ヒアリング・ファシリテーション ほか |
| 試験内容 | ・60分/40問 ・多肢選択式(マークシートまたはリモートWeb) ・級区分なし(1レベル) ・合格基準:得点率65%以上 |
・初級:50分/30問 ・上級:60分/40問+面接3分 ・多肢選択+(上級のみ)個別面接評価 ・合格基準:知識65%以上(上級は面接3以上) |
このように、2つの試験は目的や対象者などが異なります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的や仕事内容に合った検定を受けましょう。
コミュニケーション検定に初級や上級はありますか?
初級と上級の級区分が設けられているのは、ケア・コミュニケーション検定ではなく「コミュニケーション検定」の方です。ケア・コミュニケーション検定には級の区分はありません。
コミュニケーション検定の初級では、主に社会人として必要とされる基本的なビジネスマナーや人間関係を築くための基礎知識が問われます。
一方上級では、より実践的で応用的なコミュニケーション能力が求められ、さまざまな場面で適切な判断や対応ができるかを測定します。自分のレベルに合わせて受験する級を選択しましょう。