高齢者虐待とは、高齢者が他者から不適切な扱いをされることによって、生命や健康、権利が侵害される状態になることをいいます。
虐待される環境を望んでいる人はいませんし、虐待しようと思ってしている人も少ないでしょう。
ではなぜ高齢者虐待が起こってしまうのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、どのような行為が高齢者虐待にあたるのか、虐待を防ぐためにはどうすれば良いのかを解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
高齢者虐待の数は増加傾向にある

厚生労働省が行なった調査によると、令和5年度は介護従事者による高齢者虐待は1,123件、家族などの養護者による虐待は17,100件に及びます。介護従事者による虐待は年々増加傾向にあり、養護者による虐待件数は横ばいではあるものの、相談件数は毎年増加しています。
出典:令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(厚生労働省)
なかには高齢者本人のためを思っての行為が、虐待と認定される場合もあります。介護者に虐待している自覚がない場合、周囲が気付かないうちに高齢者が危険な状態に陥っていることも多いのです。
高齢者虐待の種類
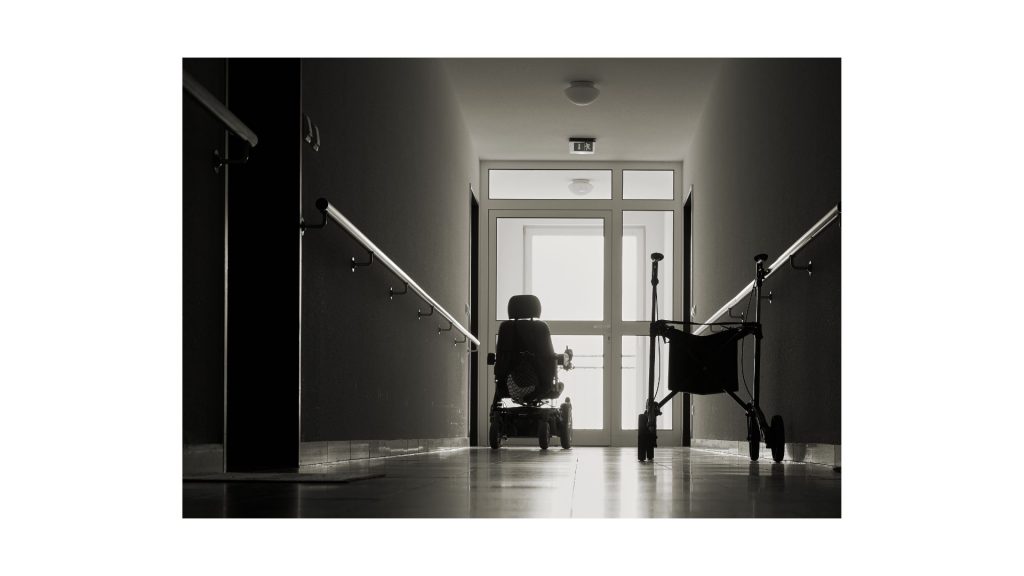
高齢者虐待は、高齢者を痛めつけようとする目的でなされるものだけではありません。高齢者に対し、悪意なく行なわれた行為も、虐待と判定されることがあるのです。
ここでは、高齢者虐待に認定される行動の種類を見ていきましょう。
身体的虐待
つねる・叩くといった、体に危害を与える行為は、身体的虐待に分類されます。また、意図的に外部との接触を制限したり、食事を無理矢理口に入れたりといった行為も身体的虐待にあたります。
移動しないようベッドに体を固定したり、ミトン型手袋を着用させたりといった身体拘束も身体的虐待として問題視されています。
身体拘束は、本人や周囲に怪我が及びそうなどの緊迫性や必要性が認められた場合のみ、一時的に認められるものです。「いうことを聞いてくれないから」「介護の手間が少なくなるから」といった本人の言動を抑制するためだけの理由では認められません。
介護・世話の放棄・放任
意図にかかわらず、介護や世話を放棄して高齢者の生活状態を悪化させる行為も、虐待にあたります。
たとえば、入浴させない、爪を伸ばしたままにさせているといった不衛生な状況に置くこと。食事や水分を十分に与えず、脱水や栄養失調の状態にさせることなどです。
同居しているにもかかわらず、心身の衰えから家事のできない高齢者を放置していると、高齢者虐待のひとつである介護放棄とみなされる可能性があります。
必要な介護を怠ったり、高齢者の生活や心身の状態を悪化させたりすることを、ネグレクトとも呼びます。
高齢者のネグレクトについては、以下の記事で詳しく解説しています。
高齢者のネグレクトとは?高齢者虐待や事例・対応策などを解説!
心理的虐待
虐待は身体だけでなく、精神的に苦痛を与えるものもあります。高齢者に対し威圧的な態度を取ったり、嫌がらせをしたりすることは、心理的虐待と見なされます。
高齢者が話しかけているのに意図的に無視したり、嫌がっているのに異性に介助させたりといった対応も心理的虐待の一種です。
ほかにも、本人の意向を無視した介護者の行為は、心理的虐待に認定される傾向があります。
たとえば、本人がトイレに行きたいと言っているのに、オムツの使用を強制する。自分で食べられるのに、早く片付けるために食事を全介助する、といった場合です。
高齢者を馬鹿にして「○○ちゃん」と呼んだり、幼児語を使ったりして子どもを相手にするように接するのも、心理的虐待に認定される可能性があります。
性的虐待
抵抗する力が弱く、認知症などで人に相談できない高齢者を狙い、わいせつな行為が行なわれることもあります。合意のない状態での性的な行為やその強要は性的虐待にあたります。
性的虐待はキスを迫ったり、不必要に性器へ接触したりといった直接的な行為ばかりではありません。プライバシーへの配慮を怠ったまま、更衣や入浴、排泄の介助を行なうことも性的虐待です。
虐待する意図がなくても、排泄介助中に下半身を裸のまま長時間放置する行為も、性的虐待に認定されます。
経済的虐待
心身に危害を加えなくても、経済的に損害を負わせることで虐待と認定される場合があります。
たとえば、本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人が希望しているのに、金銭の使用を理由もなく制限したりといった行為は経済的虐待にあたります。
過去には、本人に代わって財産を管理していた親族が、本人に必要な生活費を渡さなかったり、無断で自宅を売却・処分したりといった行為が経済的虐待に認定されました。
また、認知症など高齢者が正常な判断ができないことを利用し、金銭の贈与を受ける行為も経済的虐待に該当します。
家庭内で高齢者虐待が起こるおもな原因

高齢者虐待はさまざまな要因が重なって発生するものです。小さなわだかまりが少しずつ積み重なった結果、手が出てしまったということもあるでしょう。
虐待という行為にのみとらわれず、その背景には何があったのかを把握し、状況を正確に捉えることが大切です。
ここからは、介護施設に比べ虐待の相談件数が多い家庭内で、高齢者虐待が起こる原因を見ていきましょう。
介護疲れやストレス
介護中は自分の生活に加え、高齢者のサポートも必要となります。だんだんとできないことが増えていく高齢者を見て、「いつまでこの状況が続くんだろう」といった不安やいらだちが生じることもあるでしょう。
また、介護生活が長年にわたると、世間から取り残されてしまったような孤独感や報われない状況に追い詰められ、虐待に至るケースもあります。
とくに家族間での介護は、主たる介護者ひとりにかかる負担が大きくなっています。「なぜ私ばかりが」といった不満が、高齢者に向かってしまうことも多いようです。
認知症への無理解
認知症について正しい理解ができていないと、高齢者の言動に振り回され、いらだちから暴力が発展してしまう場合があります。
認知症は脳の機能が低下している状態です。発症した本人には対処のしようがなく、日によってできることとできないことが異なります。突然暴言を吐かれたり、泥棒扱いされたりすることもあるでしょう。
高齢者の言動は病気によるものだとわかっていても、回数が重なると負担は増します。「なぜわかってくれないのか」「何をされても覚えていないのではないか」という悲しみやいらだちから、虐待につながってしまう場合もあります。
性格や人間関係の不和
介護は人と人が深くかかわるもののため、お互いの相性が悪いこともあるでしょう。
介護者が細かいことは気にならない性質だった場合、高齢者のケアが行き届かないことも考えられます。
たとえば、高齢者が更衣や入浴の介助を希望しても、介助人が「まだ必要ない」と判断と判断し、生活環境を悪化させることもあるでしょう。
ほかにも、介護以前から介護者と高齢者の仲が悪い場合、意図せず介護が雑になってしまうことも考えられます。高齢者も介護してもらっている以上、「介護の不備を指摘したら、見放されてしまう」という不安から、誰にも相談できず状態が悪化してしまうケースもあります。
経済的な不安
要介護度が上がるにつれ、介護者の負担も大きくなります。なかには介護のために離職や転職を余儀なくされる人もいるでしょう。介護に時間を費やすことで、収入を得る機会が減り、経済的な不安から虐待につながることもあります。
自身の生活と高齢者の介護をしていれば、仕事にかけられる時間は少なくなります。介護によるキャリアの断絶や、将来を悲観して「介護さえなければ」という思考に陥りがちです。
とくに在宅介護は、閉鎖的な環境によって不安や不満をひとりで抱え込みやすい傾向があります。事態が悪化する前に、手を打つことが大切です。
高齢者虐待を引き起こさないための対策

虐待は一度起こってしまうと歯止めが外れ、二度三度と繰り返される可能性が高いものです。一度でも虐待が起こってしまうと、高齢者に手をあげたり、ケアを放棄したりする選択肢が介護者のなかに存在するようになります。
そのため、まず虐待を起こさせないことが大切です。ここからは、高齢者虐待を引き起こさせないための対策を紹介します。
家族で協力して介護する
在宅介護の場合、主たる介護者に負担が集中しがちです。ひとりにかかる負担を減らすためにも、「介護は〇〇の仕事」と決めつけず、家族で協力できる体制を作ることが大切です。
たとえば、介護者が介護から解放される時間や曜日を決め、生活が介護一色にならないよう心がけます。その際、介護のやり方を共有して、対応する人によってケア内容が変わらないようにすると、介護される高齢者の負担も減るでしょう。
大切なのは、介護者を孤立させないようにし、すぐに相談しあえる環境を作ることです。
相手を尊重する意識を持つ
高齢者は「不満を言ったら、世話してもらえなくなるかもしれない」といった不安から、嫌なことを我慢しがちです。
高齢者のなかにネガティブな感情が溜まっていくと、精神的な不安から本来できることもできなくなったり、不安を紛らわすために粗暴な言動が見られたりします。
介護を受けている高齢者も、ひとりの人間だという意識を持ち、落ち着いて話を聞く体制を持つことが大切です。介護の際はむやみに怒ったり、否定したりせず、相手を思いやる意識を大切にしましょう。
介護サービスを利用する
家族で介護すると決めていても、それぞれの生活があることから、介護者にかかる負担は大きなものです。介護の負担が大きいと感じたら、介護サービスを利用しましょう。
デイサービスやデイケアを利用して、一時的に介護から解放され、休息や気分転換の時間を持つことが大切です。
介護施設への入居も視野に入れましょう。虐待によってお互いが不幸になるよりも、介護のプロにケアを任せ、距離を取ることも虐待を予防する方法のひとつです。
さまざまな介護サービスを利用して、介護者の生活の負担を減らすことが虐待防止につながります。
親が施設への入居を嫌がっている場合の対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
嫌がる親を施設に入れる手順を解説!入居手順や在宅介護を続けるリスクも紹介
まとめ|高齢者虐待は防げる!周囲に頼ることから始めよう

介護者が良かれと思ってやっていることが高齢者にとって虐待になっていることもあります。虐待はいけないという認識があっても、何が虐待にあたるのかを認識していない限り、虐待は防げません。
介護にかかる負担を減らし、相手を尊重する気持ちがあれば、多くの虐待は防げます。現在高齢者を介護している人は、「自分は大丈夫」と過信せず、介護の状態を見直すことも大切です。
少しでも、介護生活に負担を感じている人は、介護サービスを上手に利用して負担の軽減を図ってみてはいかがでしょうか。
「いいケアネット」では、大阪を中心に全国の老人ホームの情報を掲載しています。無料相談も受け付けているため、介護に負担を感じる方はぜひご相談ください。
高齢者虐待についてよくある質問
誰から虐待を受ける可能性が高いですか?
厚生労働省の行なった令和5年度の調査では、高齢者から見た虐待者の続柄は息子38.7% 22.8%、娘18.9%です。(文献1)
虐待の半数以上が、男性の介護者によるものです。
これは、仕事一辺倒だった男性が慣れない家事や介護にストレスを感じ、虐待に発展していると考えられます。
高齢者虐待として多いものは何ですか?
厚生労働省が行なった調査では、高齢者虐待では、身体的虐待、精神的虐待、介護放棄の順に多く報告されています。
とくに在宅介護の場合は、閉鎖的な環境になりやすいため、虐待が発覚しにくいものです。
また、重度の認知症を患っている場合、介護放棄と経済的虐待を受ける割合が高くなっています。被介護者は何もわからないだろうと、世話をしなくなるケースが多いようです。(文献1)
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。











