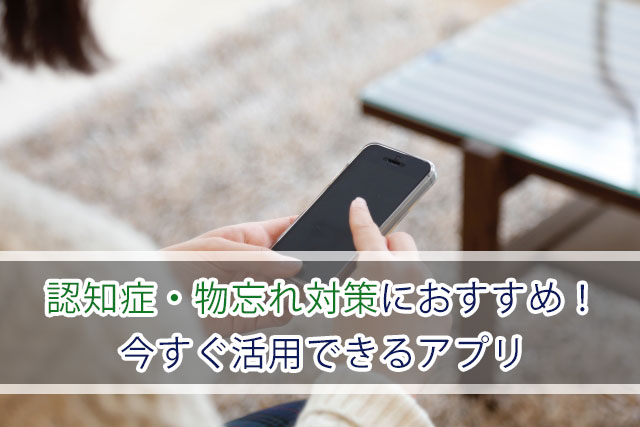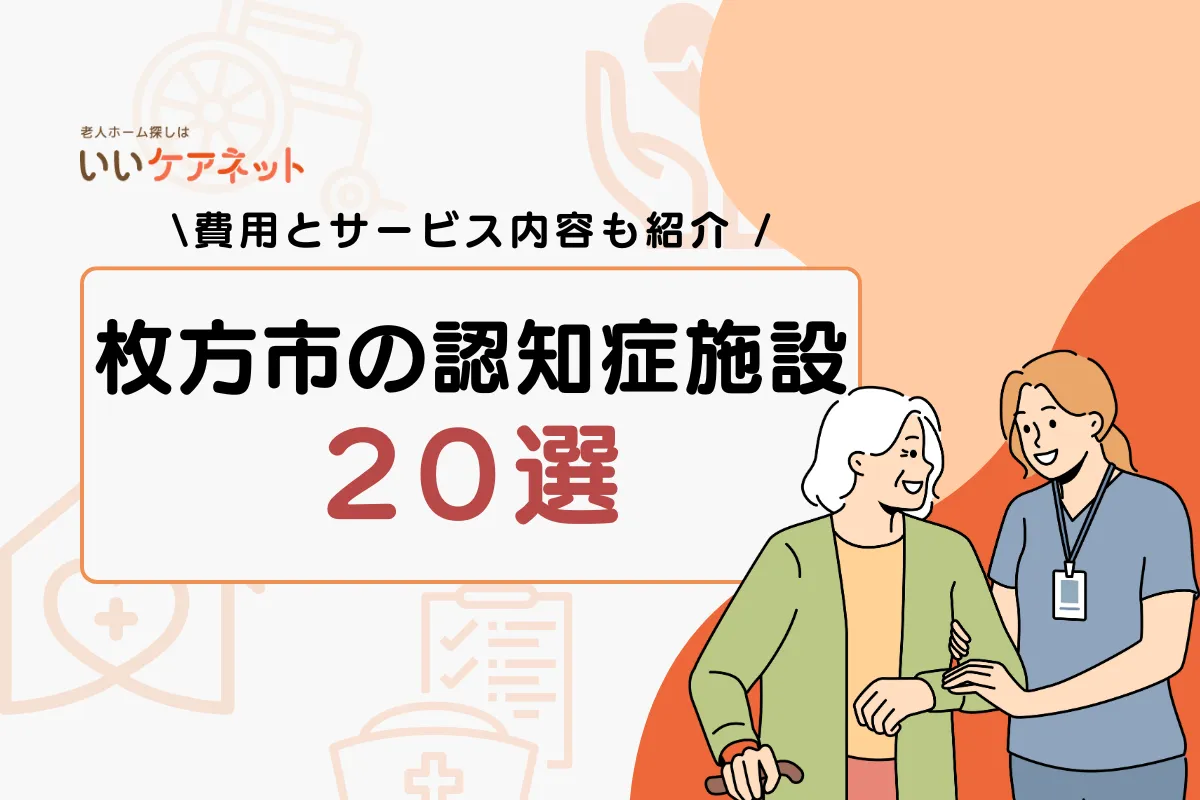「要介護5でもらえる給付金はどのようなものがあるか」
「施設入所も考えた方が良いか」
ご家族が要介護5と認定されたとき、このように思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、要介護5という重度の状態になると、経済的な不安が大きくなるものです。
そこで本記事では、要介護5で受けられる給付金やサービスについて詳しく解説します。経済的な負担を軽減するための介護保険制度や自治体独自の助成金についてお伝えします。
要介護5で利用できる給付金の種類や金額、申請方法まで理解でき、今後の計画を考える上での参考にもなるため、ぜひ最後までご覧ください。
要介護5とは日常生活全般で介護が必要な状態

要介護5は、介護保険制度における要介護認定のなかで最も重度の状態です。食事や排泄、入浴、着替えなど、日常生活のほぼすべての動作に全面的な介助を必要とします。
多くの場合、寝たきりの状態であり、自力で寝返りをうつことも困難です。意思疎通も難しく、認知症が進行しているケースも少なくありません。経管栄養や褥瘡ケアなど、医療的なケアが必要となることもあります。
要介護4との違いは必要な介護の量
要介護4と要介護5は、どちらも重度の介護を必要とする状態ですが、必要な介護の量に違いがあります。要介護4でも日常生活の多くの場面で介助が必要ですが、一部自力で行える動作が残っている場合があります。
一方、要介護5では、ほぼすべての動作に介助が必要です。介護認定の基準となる「要介護認定等基準時間」では、要介護4が「90分以上110分未満」、要介護5は「110分以上」とされています(文献1)。
要介護5でもらえる給付金と申請方法

ここでは、要介護5の方がもらえる6つの給付金と申請方法について解説します。
なお、在宅介護でもらえるお金に関する詳しい説明は、別記事『家族の介護でもらえるお金は?ジャンル別に9つの制度を解説』を参照してください。
1.介護保険の区分支給限度額
区分支給限度額とは、要介護度ごとに設定された、介護保険から給付される1カ月あたりの上限額で、要介護5の場合は362,170円です。この範囲内でサービスを利用した場合、自己負担は1~3割になります。
ただし、居宅療養管理指導や施設サービスなど、一部のサービスは限度額の対象外となります。また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となるため注意が必要です。
区分支給限度額は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて自動的に適用されるため、特別な申請は不要です。
2.高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1カ月の介護サービス自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。介護保険適用サービスが対象ですが、福祉用具購入費や住宅改修費などは対象外です。
サービス利用月の約3カ月後に自治体から申請書が届くので、必要事項を記載して返送します。2回目以降は自動で支給されるため申請は不要です。
申請期限はサービスを受けた月の翌月1日から2年間です。上限額は所得によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
高額介護サービス費に関しては、別記事『高額介護サービス費とは?わかりやすく対象サービスや申請方法を解説』でも詳しく解説しているのでご参照ください。
3.高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額合計が、所得に応じた限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。医療と介護の両方の負担が大きい世帯の経済的負担を軽減します。
申請には通常、自治体から届く申請書が必要です。要介護5の方は、医療や介護にかかる費用が高額になる傾向があります。詳細は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
4.福祉用具のレンタル、購入にかかる費用の給付
介護保険では、要介護者の生活を助ける福祉用具のレンタルや購入費が給付されます。レンタルは、車いすや介護ベッドなど幅広い品目が対象で、自己負担1~3割で利用できます。
ポータブルトイレや入浴補助用具など、レンタルにそぐわない特定の品目はレンタルではなく購入の対象です。年間10万円を上限に、自己負担1~3割で購入費が支給されます。どちらも、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談して、ご本人の状態に合った福祉用具を選ぶことが大切です。
なお、福祉用具貸与に関する詳しい解説は、別記事『介護保険で貸与(レンタル)できる福祉用具13種目』も参考にしてください。
5.医療費控除・障害者控除
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税から控除される制度です。要介護5の方も対象で、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅管理指導のように、看護師や保健師等により行われる居宅サービスが控除対象となります。
控除を受けるには確定申告が必要で、上限額は200万円です。また、障害者控除は、要介護5の方が「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、確定申告をすることで受けられます。控除額は通常27万円ですが、寝たきりなどの場合は特別障害者として40万円となる場合もあります(文献2)。
6.自治体独自の給付金
要介護5の方が受けられる給付金には、国で決められているものだけではなく、以下のように、自治体独自に設定しているものもあります。
| 給付金の種類 | 内容 |
| 紙おむつの支給や購入費用の助成 |
|
| 家族介護慰労金 |
|
| 介護休業給付金 |
|
給付の金額や要件、申請方法などは自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に確認してください。
要介護5で受けられるサービス

要介護5の認定を受けると、以下のようなさまざまな介護サービスを受けられます(文献3)。
【在宅でのサービス】
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 食事・入浴・排せつなどの介護、掃除・洗濯などの生活支援 |
| 訪問入浴介護 | 自宅での入浴が困難な方への入浴介護 |
| 訪問看護 | 健康状態の観察や医療ケアなどの看護サービス |
| 訪問リハビリテーション | 身体機能の維持・向上に向けたリハビリ |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯のホームヘルパー訪問 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回訪問と随時対応 |
【通所によるサービス】
| 通所介護(デイサービス) | 施設での日帰り介護 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 心身機能の維持回復のためのリハビリ |
| 地域密着型通所介護 | 19名未満の小規模デイサービス |
| 療養通所介護 | 難病や重度の脳血管疾患の後遺症、がん疾患などの疾患を持つ利用者向けの通所介護 |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方向けの通所介護 |
【その他のサービス】
| ショートステイ | 3日、1週間など、あらかじめ日数を決めて短期間施設へ入所 |
| 施設への入所 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などへの入所 |
| 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | ・利用者の心身の状況や生活環境に応じて適切な福祉用具を貸与
・貸与にはなじまない、排泄や入浴で用いる福祉用具の販売 |
| 住宅改修費の支給 | 手すりやスロープの設置など、自宅の改修にかかった費用のうち、支給限度基準額(20万円)の9 割(18万円)を上限に支給(文献4) |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護などへの入所 |
要介護5の状態では、在宅での介護が困難なケースも多いため、施設入所も視野に入れたサービス選択が重要になります。
まとめ:現金の給付は少ないが多くの制度を利用できる

要介護5でもらえる給付金は、直接的な現金給付については限られていますが、介護保険サービスの区分支給限度額や各種控除、自治体独自の支援制度など、さまざまな経済的支援を受けられます。介護保険の区分支給限度額の範囲内でサービスを利用することで、自己負担を1割(所得によっては2割または3割)に抑えられます。
とはいえ、これらの経済的な支援を十分に活用しても、要介護5の方の在宅介護は、ご家族にとって大きな負担となることも事実です。
いいケアネットでは、要介護5の方でも利用できる施設の紹介が可能です。無料で利用できるので、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
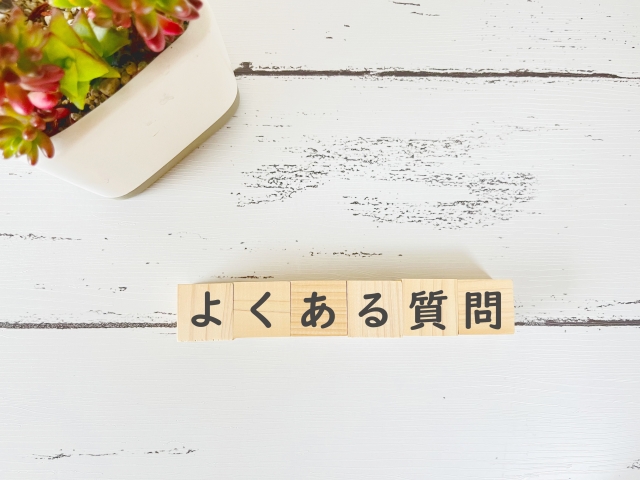
ここでは、要介護5の方の在宅介護についてよくある質問をまとめています。
要介護5で在宅介護を続けるのは難しいですか?
要介護5の方は基本的に寝たきりの方や認知症の症状が重い方が多く、ほぼ24時間体制の介護を必要とします。介護者の状況によりますが、要介護5の方の介護を一人で行うのは非常に難しいと言えます。在宅介護を継続するには、デイサービスやショートステイなどの介護保険サービスを積極的に活用し、介護者の負担を軽減することが重要です。また、状況によっては施設入所も検討する必要があるでしょう。
施設入所を検討する際は、別記事『老人ホーム探しはいつからが良い?』で解説しているのでご参照ください。
要介護5の認定を受けた場合、介護保険料は高くなりますか?
介護保険料は所得に応じて決まるため、要介護度によって変わることはありません。ただし、実際の負担額はサービスの利用量によっても変わるため、介護サービスを多く利用すると、自己負担額が増える可能性があります。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。