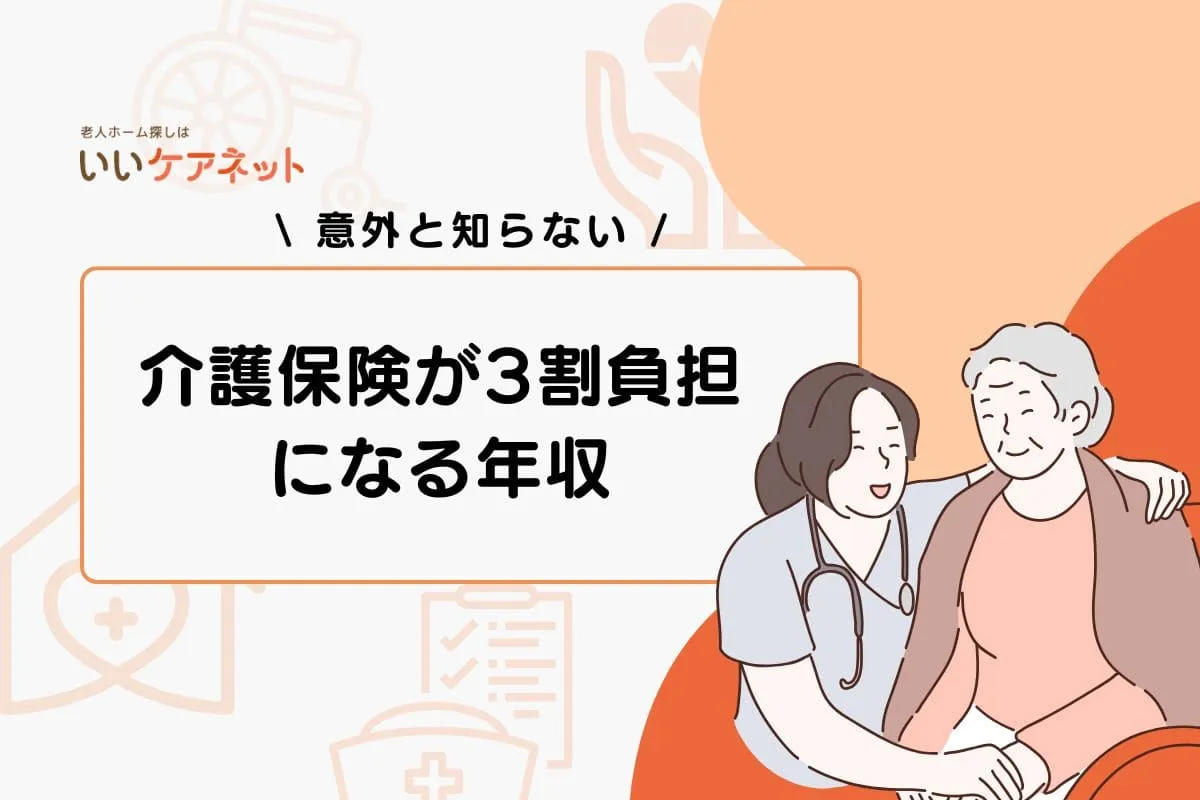「介護保険サービスを利用するときには医師の意見書が必要と聞いた」
「医師の意見書ってどんな書類なの?」
「意見書のもらい方がわからない」
このような疑問を持たれた方も多いことでしょう。
結論から申し上げますと、医師の意見書をもらう際には、市区町村役場の介護保険窓口に出向く必要があります。
本記事では、医師の意見書のもらい方やその必要性、困ったときの対処法についても解説します。
介護保険サービス利用を検討しているご家族や、施設入所を希望しているご家族にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
医師の意見書をもらうための方法

医師の意見書をもらうためには、要介護認定を申請する必要があります。意見書は、要介護認定に欠かせない書類であるためです。申請先は、市区町村役場の介護保険窓口です。
要介護認定とは、どのくらい介護を必要とするかを判断するもので、介護保険サービスをどの程度利用できるかの指標でもあります。
要介護認定申請を受け付けた担当者は、医師に意見書作成を依頼します。依頼された医師が、意見書に必要事項を記入して、役所に提出する仕組みです。
要介護認定申請書には主治医の名前やかかりつけ医療機関名を書く欄があるため、申請時にはそれらがわかるものを持っていきましょう。診察券やおくすり手帳などがあると便利です。
要介護認定を受けるための具体的な方法は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:要介護認定を受けるには何が必要?申請先や具体的な方法を詳しく解説
医師の意見書は要介護認定において必要な書類

医師の意見書は、正式名称「主治医意見書」であり、要介護認定を受けるために必要な書類です。(文献1)
意見書には、要介護者に関する医学的な情報および医師の意見が記載されています。(文献2)意見書に書かれた情報が、介護を必要とする度合い、いわゆる要介護度を決める材料の1つといえます。
要介護認定の流れや申請に関する詳しい情報は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:介護保険申請のベストなタイミングはいつ?流れや必要なものを紹介
医師の意見書に記載される内容
医師の意見書に記載される内容は、主に以下のとおりです。
- 申請者の身体状況
- 日常生活動作の状況
- 過去14日以内に受けた特別な医療
- 認知症の症状
- 病気の症状が安定しているかどうかの所見
この他にも、介護サービス提供時に留意すべき医学的な所見、介護サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しなどが記載されます。(文献2)
要介護者が第二号被保険者と呼ばれる40歳から64歳までである場合、特定疾病に該当しているかどうかも、意見書に記載されます。(文献3)
医師の意見書にかかる料金
主治医意見書作成にあたって、申請者の自己負担額は0円です。(文献1)
医師の意見書作成料は、要介護認定にかかる事務費として市区町村が負担するためです。
主治医がいない場合の対処法

主治医がいない場合として、2つのケースが考えられます。
- 申請時点で医療機関受診歴がない
- 複数の医療機関を受診しており、主治医が誰かを特定できない
それぞれについて対処法を解説します。
市区町村が指定する医師の診察を受ける
要介護認定を申請した時点で、申請者が医療機関を受診しておらず、主治医がいない場合の第一選択肢は、市区町村が指定する医療機関への受診です。(文献1)
市区町村が地域の医師会に要請し、医師会で適切な医師を紹介する流れが望ましいとされています。(文献4)
本人の状況を詳しく理解している医師の診察を受ける
内科や外科、呼吸器科など、複数の医療機関を受診している場合の選択肢は、申請者の状況を詳しく理解している医師の診察を受けることです。
具体的には、一番受診頻度が高い医師や、要介護認定申請の原因となった病気やケガを診察している医師などがあげられます。
なお、主治医意見書は本人の現状を記載するものであるため、少なくとも3カ月以内に診察を受けていることが望ましいとされています。
医師が主治医意見書を書いてくれない場合

基本的に、医師の意見書をもらえないケースはほとんどありません。
しかし、医師が正当な理由で意見書作成を断る場合もあります。具体例としては、以下のとおりです。
- 申請者が長期間受診していない
- 申請者が複数の医療機関を受診しており、他の医師の方が申請者の状況を把握している
意見書作成を断った医師は、他の医師を紹介することが望ましいとされています。(文献4)
もし、医師の意見書をもらえなかった場合は、別の医療機関を受診しましょう。どの医療機関を受診すると良いかわからない場合は、介護保険担当者に相談することも1つの方法です。
まとめ|医師の意見書のもらい方を理解した上で要介護認定を申請しよう

医師の意見書は要介護認定を受けるために必要な書類の1つです。要介護認定を申請した際に、市区町村役場の介護保険窓口が、医師に意見書作成を依頼します。
主治医がいない、複数の医療機関を受診している、医師から意見書をもらえなかったなど、意見書に関する困りごとがあるときは、介護保険担当者に相談しましょう。
要介護認定を申請すると、要支援1から要介護5までのいずれかに認定されます。支援や介護を必要としない状況であれば、非該当と認定されます。
要支援や要介護の認定を受けたあと、施設入所を考える場合は、ぜひいいケアネットにご相談ください。ご本人やご家族の希望に合った施設を、全国各地からお探しいただけます。
介護に関するさまざまな情報を知りたい方は、いいケアジャーナルをご覧ください。
医師の意見書のもらい方に関するよくある質問
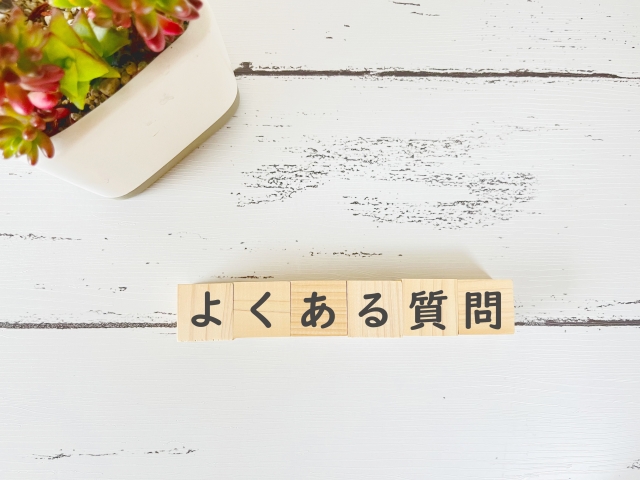
ここでは、医師の意見書のもらい方に関するよくある質問を2つ紹介します。
医師の意見書と診断書の違いは何ですか?
主治医意見書は、申請者の病気および治療状況、身体状況、介護保険サービス利用に関する医学的観点からの留意事項などを記載するもので、様式は全国一律です。(文献2)
これに対し診断書は、患者の病名や症状、治療内容などを記載した書類を指します。診断書の様式は、医療機関によって異なります。
医師の意見書は何に使われますか?
医師の意見書は要介護認定において使われる重要な資料です。それ以外にも、以下のような役割があります。(文献5)
- 介護サービス計画の原案作成にあたっての医学的情報、意見を提供する
- 介護サービス利用にあたっての医学的な注意点を示す
- おむつに係る費用の医療費控除の証明として使われる
- 特別養護老人ホームにおける特例入所者の判定や優先入所対象者の判定資料となる
介護が必要な状況および、介護保険サービス利用を希望する状況で使われるものと理解しておくと良いでしょう。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。