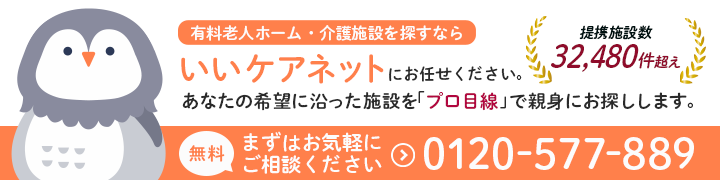家族がレビー小体型認知症を発症し「この症状はいつまで続くのか」「一人で介護を続けられるのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
レビー小体型認知症の介護は、認知機能障害や幻視などの症状への対応が必要となります。そのため、介護者の心身への負担が大きくなってしまい、一人で介護を続けるのが難しくなるのです。
本記事では、レビー小体型認知症の介護が大変な理由から、レビー小体型認知症に対する付き合い方まで幅広く解説します。
本記事を読むことで、レビー小体型認知症の介護における問題の理解が深まり、具体的な解決策を見つけられます。
レビー小体型認知症の介護が大変な5つの理由
レビー小体型認知症の介護は多くの困難を伴います。介護者の負担が大きい理由は以下の5つです。
- 症状に大きな波がある
- 幻視により不穏状態になる
- 転倒リスクが高い
- 睡眠時に異常な行動を取ることがある
- 昼夜逆転生活になりやすい
なぜレビー小体型認知症の介護が大変なのか、理由を明らかにしていきましょう。
症状に大きな波がある
レビー小体型認知症における症状の大きな波は、介護者に大きな負担をもたらします。この認知症の特性として、症状が非常に不安定であり、日々あるいは1日の中でさえも変動があるとされています。
朝は普通に会話ができても、午後には急に混乱して意思疎通が難しくなるケースもあるほどです。認知症の方は、夕方から夜にかけて症状が悪化する「夕暮れ症候群」を起こしやすいとされています。
症状の激しい変動により、介護者は認知症の方の状態を注意深く観察し、不測の事態にも柔軟に対応する能力が求められます。
幻視により不穏状態になる
レビー小体型認知症の方は、実際にはいない人や存在しないものが見える「幻視」の症状が現れます。この幻視が不穏状態を引き起こす要因です。
たとえば「知らない人が家の中にいる」「小動物が這い回っている」ように見え、本人にとってはリアルに感じられます。強い不安や恐怖を感じて興奮状態になったり、幻視の対象から逃げ出そうとしたりするケースがあるのです。
認知症の方は幻視によって突然不安定になるため、介護者は常に気を配る必要があり、精神的な負担が大きくなります。
転倒リスクが高い
レビー小体型認知症では、体が思うように動かない「パーキンソン症状」が現れるため、転びやすい危険性があります。
筋肉が硬くなったり手足が震えたりすると、日常生活での動作が難しくなるのです。とくにトイレや入浴などの場面では服を着脱する動作があるため、転びやすくなります。
レビー小体型認知症の方は転倒リスクが高く、転倒が原因で寝たきりになる可能性があります。そのため、介護者は常に見守りが必要になり、心身の負担が大きくなるのです。
睡眠時に異常な行動を取ることがある
レビー小体型認知症の方には、睡眠障害がしばしば見られます。中でもレム睡眠行動障害が顕著で、夢で見ている事象に対して無意識のうちに身体を動かしてしまいます。具体的な行動は以下のとおりです。
- 走っているように足を動かす
- 殴ったり蹴ったりする
- 大声で叫ぶ
レビー小体型認知症の方は夢の中と現実の行動が連動しやすいため、介護者は夜間も目が離せません。その結果、睡眠時間を十分に確保できなくなるのです。
参考:厚生労働省『レム睡眠行動障害』
昼夜逆転生活になりやすい
レビー小体型認知症は睡眠のリズムが乱れやすいのも特徴です。日中に強い眠気が現れて活動的に過ごせず、夜になると逆に目が覚めて活動的になってしまうケースがあります。
また、夜間に目が覚めて徘徊する恐れもあるため、介護者は十分に休めず心身ともに疲労が溜まりやすい状況に陥ってしまいます。
認知症の方が昼夜逆転してしまうと、介護者にも深刻な影響を及ぼすため、在宅での介護が難しくなります。
レビー小体型認知症とは
レビー小体型認知症は「三大認知症」の一つで、アルツハイマー型認知症に次いで発生率が高いとされています。独自の特徴と症状があり、早期診断と対処が重要です。
以下では、レビー小体型認知症の症状と進行速度について詳しく解説します。
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症の症状はさまざまで、以下のような特徴があります。
- 認知機能の変動:記憶力や判断力が低下し、同じことを何度も聞いたり、計算が苦手になったりします。
- 幻視:実際には存在しないものが見える症状です。たとえば「知らない人が部屋にいる」「小さな虫や動物が這い回っている」ように感じられます。
- パーキンソン症状:手足の震えや動きの遅れなど、パーキンソン病と似た症状が現れます。
- 睡眠時の異常行動:寝ている間に突然叫んだり、体を動かしたりします。
- 抑うつ症状:持続的な気分の沈みや意欲の低下を経験します。
- 自律神経症状:立ち上がった瞬間にめまいを感じる「起立性低血圧」が発生する場合もあるため、日常生活における動作や移動にも支障をきたしてしまいます。
レビー小体型認知症の介護では、特有の症状を理解するのも大切です。
参考:公益財団法人長寿科学振興財団『レビー小体型認知症』
レビー小体型認知症の進行速度
レビー小体型認知症の進行速度には個人差がありますが、一般的に診断を受けてから亡くなるまでの期間は約5〜8年とされています。
症状は徐々に進行していきますが、その速さは一定ではありません。初期は症状が緩やかに進行し、中期から後期にかけて症状が重くなる傾向があります。また、日によって症状の程度が大きく変動するのも特徴です。
レビー小体型認知症に対する付き合い方
レビー小体型認知症の介護は確かに大変ですが、次の5つのポイントをおさえれば負担を軽くできます。
- 症状が悪化する周期を知る
- 幻視を理解してコミュニケーションをとる
- 居住環境を工夫する
- リフレッシュできる時間をつくる
- 介護サービスを活用する
それぞれの付き合い方のポイントを解説します。
症状が悪化する周期を知る
認知症の症状が悪化する周期の理解とは、適切なケアと対応に必須です。周期を知ることで、認知症の方の状態が不安定になりやすい時間帯や状況に備えられます。
たとえば日が暮れる頃になると、不安や混乱が強まる「夕暮れ症候群」が起こりやすくなります。夕方になると気分が不安定になる場合、その時間帯に特別なケアを施す準備をしておくと良いです。具体的には、以下の内容が挙げられます。
- 夕方にリラックスできる音楽を流す
- 家族が一緒に過ごして見守る
- 趣味をして気を紛らわせる
以上のように症状の悪化を和らげる工夫ができます。
症状の周期を把握しておくことで、必要なときに適切な介護ができ、認知症の方も介護者も穏やかに過ごせます。
参考:水上勝義『認知症患者の夜間にみられる精神症状および行動症状』
幻視を理解してコミュニケーションをとる
レビー小体型認知症の方が経験する幻視を理解したコミュニケーションをとりましょう。幻視は認知症の方にとって非常にリアルな体験であるため、否定したり怒ったりすると、本人の不安や混乱をかえって強めてしまいます。
たとえば、幻視により認知症の方が「誰かが部屋にいる」と感じたら「私には誰も見えませんが、それは不安ですね。一緒に部屋を見てみましょう」と対話してみましょう。
幻視に対する理解を姿勢で示せば、認知症の方にとって心強いです。
参考:新潟市医師会『レビー小体型認知症の幻視体験』
関連記事:【認知症の正しい接し方】間違った接し方は症状を悪化させることも
居住環境を工夫する
転倒リスクの高いレビー小体型認知症の介護では、居住環境の工夫が非常に重要です。高齢者が転倒すると、ケガの度合いにより、その後の生活にも大きな影響を与える可能性があります。具体的には、次のような対策をしましょう。
- 動線を考慮して家具を配置する
- 通路を広めに確保する
- 滑りにくい床材を選ぶ
- 手すりや滑り止めマットを設置する
さらに、家全体にある段差の解消、トイレや浴室の改修のような大掛かりな工事も、介護保険の活用によりコストを抑えて実現できます。
認知症の方が穏やかに暮らせる環境は、介護者にとっても同じ環境といえます。可能な限りリスクを排除した環境整備を進めましょう。
リフレッシュできる時間をつくる
介護を続けるためには、介護者が気分をリフレッシュできる時間をつくることが大切です。
介護は長期間にわたるため、介護者が疲弊してしまうと提供できるケアの質も低下してしまいます。
心身の健康を維持するためには、次の方法を参考にしてみてください。
- 美味しい食事を食べに行く
- 映画を観る
- ショッピングを楽しむ
介護者自身のケアを意識的におこなうことは、介護を継続するために必要な取り組みとなるのです。
介護サービスを活用する
介護の負担が大きくなってきたと感じたら、介護サービスを上手に活用するのも大切です。
レビー小体型認知症の方は、夜間に突然大声を出したり、暴力的な行動を取ったりする可能性もあります。そのような状況下でのケアは、介護者自体の心身にも大きな負担をかけます。
このような場合、夜間の訪問介護サービスやショートステイの利用、老人ホームへの入所などを考えましょう。夜間の訪問介護では、専門の介護スタッフが自宅に訪れてケアを提供してくれます。また、老人ホームは長期的なケアが必要な場合に有用です。
ケアマネージャーに相談しながら、その方に合った介護サービスを見つけていきましょう。
レビー小体型認知症の介護が大変になる前に相談しよう
レビー小体型認知症の介護は、症状に波があることや幻視による不穏状態など、さまざまな困難を伴います。
介護の負担を少なくするためには、症状が悪化する時間帯を把握したり、幻視を理解したコミュニケーションをとったりしましょう。介護者自身がリフレッシュする時間をつくって、気分転換するのも大切です。
また、一人で抱え込まず、ショートステイや老人ホームなどの介護サービスを活用するのもひとつの手です。早めに専門家に相談しサポートを受けることで、より良い介護生活を送る一歩を踏み出しましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 日本介護福祉教育学会 城田 忠
大阪青山大学介護福祉別科准教授。介護教育と介護留学を専門とし、外国人留学生の介護福祉士国家試験の合格率向上や日本語教育に関する研究を行い、介護福祉業界の発展に貢献。