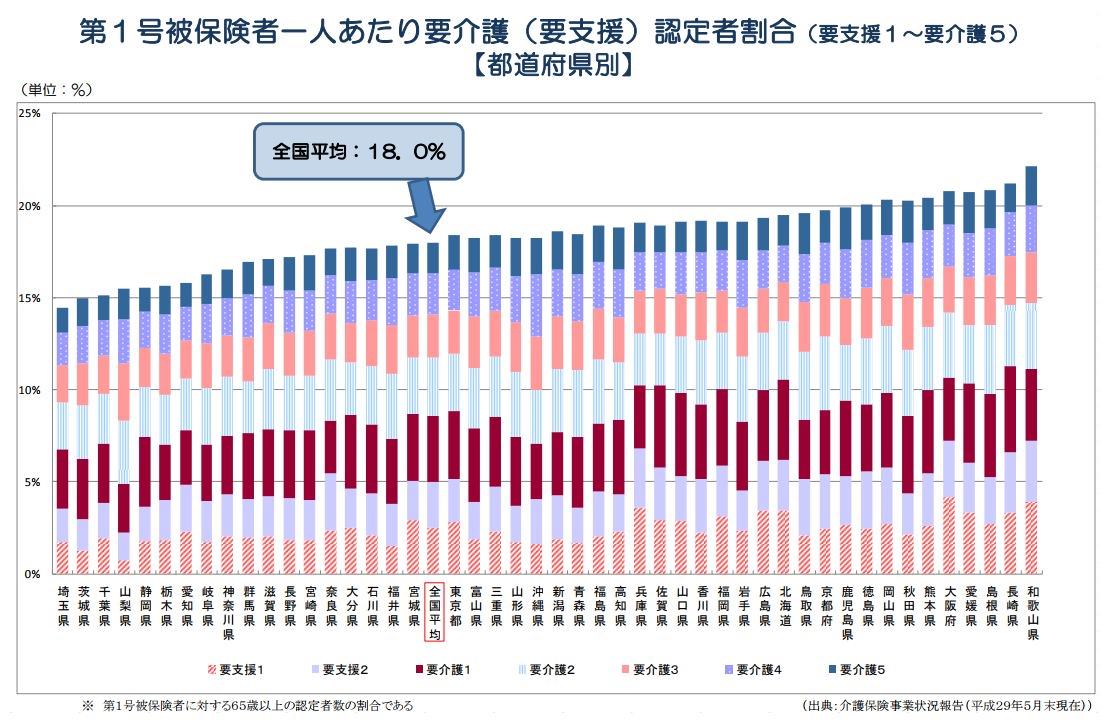高齢化が進む日本において、「認認介護」の問題があることをご存じでしょうか。
認認介護とは、認知症を患っている高齢者が互いに介護している状態を意味する言葉です。認認介護は決して珍しいわけではありませんが、実態や問題点などはあまり理解されていないのが現状です。
今回は、認認介護とは何か、日本社会における実態と問題点を解説します。認認介護のリスクを回避するための方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
認認介護とは

認認介護とは認知症を患っている高齢者同士が互いに介護している状態を意味します。認知症の主な症状は、物忘れや判断力の低下、意思疎通の難しさなどです。本来、介護を受けるべき立場の人が介護する立場になり、生活の維持や安全の確保が難しくなります。
認認介護と老老介護の違い
認認介護と老老介護の違いは、介護する人が認知症を患っているかどうかです。
老老介護とは、65歳以上の高齢者が同じく65歳以上の高齢者を介護している状態を意味します。親子や夫婦、兄弟間での介護においてよく見られるケースです。老老介護の場合、介護する側の高齢者は比較的健康であるケースも少なくありません。
認認介護は、前述の通り、介護する側・される側の両者が認知症を患っている状況です。高齢化が進む日本において、認認介護と老老介護はどちらも大きな社会問題となっています。
老老介護の原因や問題点について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
関連記事:老老介護とは?知っておくべき原因や問題点、解決策について
認認介護の現状

ここでは、次の2つの視点から、日本における認認介護の現状を見ていきましょう。
- 介護が必要になった主な原因
- 要介護者の年齢別の割合
以下で、それぞれ詳しく解説します。
介護が必要になった主な要因
厚生労働省の「2022年国民生活基礎調査の概要」によると、要介護状態になった主な原因として以下の病気があげられています。
| 要介護度 | 第1位 | 第2位 |
| 要介護1 | 認知症(26.4%) | 脳血管疾患/脳卒中(14.5%) |
| 要介護2 | 認知症(23.6%) | 脳血管疾患/脳卒中(17.5%) |
| 要介護3 | 認知症(25.3%) | 脳血管疾患/脳卒中(19.6%) |
| 要介護4 | 脳血管疾患/脳卒中(28.0%) | 骨折・転倒(18.7.4%) |
| 要介護5 | 脳血管疾患/脳卒中(26.3%) | 認知症(23.1%) |
介護が必要になった原因として、認知症は要介護者全体で23.6%と最も多い結果でした。要介護者の4人に1人が認知症を患っていることがわかります。
要介護者の年齢別割合
厚生労働省の「2022年国民生活基礎調査の概要」によると、要介護者の年齢別の割合は以下の通りです。
| 年齢階級 | 構成割合 |
| 40〜64歳 | 2.6% |
| 65~69歳 | 3.4% |
| 70~74歳 | 7.1% |
| 75~79歳 | 12.9% |
| 80~84歳 | 20.9% |
| 85~89歳 | 27.1% |
| 90歳~ | 26.2% |
要介護者が最も多い年代は「85歳~89歳」、2番目に多いのは「90歳以上」、3番目に多いのは「80歳〜84歳」となっています。以上のことから、80歳以上の方の4〜5人に1人が介護を必要としている人であるとわかります。
また、高齢者夫婦だけではなく、高齢者の親子が共に認知症であるケースの認認介護も珍しくありません。今後も認知症の方の数は増え続けていくと予想されます。
認認介護における7つの問題点

認認介護においては、介護する側も認知症の症状を抱えているため、さまざまな問題が発生します。認認介護の問題は、介護する側と介護される高齢者のどちらにも大きな影響を及ぼします。
以下で、具体的な問題点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.食事や栄養管理ができない
認知症を患っている高齢者は、以下のような理由から食事や栄養管理が難しくなります。
- 料理する意欲を失う
- 料理の手順を忘れる
- 食事の時間を忘れる
- 食事への興味・関心が薄れる
認知症になると、偏った食事や食べないことによる栄養不足のリスクが高まります。食事や栄養管理が行き届かなくなると、体力や免疫力の低下を引き起こし、健康に悪影響を与えかねません。加えて、食事の準備が難しくなり、家計に負担がかかる懸念もあります。
2.服薬や通院の管理ができない
服薬や通院の管理が難しい点も、認認介護の問題点の一つです。薬の名前や服用時間を覚えられずに間違って服用するなど、認知症患者が薬を管理するのは簡単ではありません。なかには、服用を忘れたまま気づかないうちに病状が悪化し、認知症の進行を早めてしまうケースもあります。
また、通院の日時を忘れたり、必要性を理解できなかったりして、医師の診察を受けられず、適切な治療が遅れるケースも少なくありません。認認介護の場合は、医療面での管理が不十分になるため注意が必要です。
3.お金の管理ができない
認認介護における問題点として、お金の管理ができなくなる点があげられます。認知症が進行すると、買い物や支払いといった日常的な支出、重要な書類の管理が難しくなります。その結果、無駄な支出が増えるだけではなく、詐欺に巻き込まれるリスクも高まるため注意が必要です。
実際に、認知症の高齢者は、認知機能の低下によって、詐欺の被害に遭いやすいといわれています。認認介護によってお金の管理が行き届かなくなると、生活基盤が不安定になる可能性があります。
4.適切な介護ができない
認認介護における大きな問題点は、介護する側も認知症を抱えており、相手のケアが十分にできない点です。認知症の症状によって、相手の状態を理解し、適切な対処をするのが難しくなります。そのため、相手が食事を摂らない、薬を服用しないといった状態でも、介護する側が必要性を認識できずに、対応が遅れてしまいます。
また、認認介護の場合、当事者同士でコミュニケーションがうまく取れなくなるケースも珍しくありません。介護する側が強いストレスを感じるようになると、共倒れしてしまうリスクもあるため注意が必要です。
5.交通事故や行方不明のリスクがある
認知症の高齢者は、記憶障害や見当識障害などにより、外出中に迷子になりやすくなります。用事のために家を出ても、認知症の症状によって時間の感覚や場所の認識が曖昧になり、行き先を見失ってしまう場合があります。
とくに、認認介護においては、介護する側が相手の外出を制限することが難しくなるため、思わぬ事故につながりかねません。また、外出したまま迷子になってしまっても、気づくのが遅くなり、行方不明になるリスクが高まります。
認知症の症状や徘徊について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:認知症による徘徊の理由とは?認知症の症状から対策まで解説!
6.火の不始末が原因で火災が発生する可能性がある
認認介護においては、火の扱いに注意が必要です。認知症の高齢患者が火を使う場合、物忘れや注意力の低下によって、火災リスクが高まります。火の不始末が起こりやすいのは、以下のような状況です。
- コンロの消し忘れ
- タバコの火の不始末
- こたつや暖房器具の使用
火災リスクを低減するためには、調理器具の見直しや、着衣着火の安全対策が必要です。
認知症は進行性の病気であるため、自宅での生活における火災リスクは月日とともに高まります。そのため、事故や火災を起こす前に、早めに介護施設への入居を検討するようにしてください。
7.同居孤独死のリスクがある
認認介護においては、同居孤独死のリスクもあります。同居孤独死とは、同居人がいるのにもかかわらず、死に気づかず放置されてしまうことです。
認認介護における問題は、気づかないうちに深刻化する場合がほとんどです。とくに、家族や親戚と疎遠になっている場合には、緊急時に外部に助けを求められないケースも少なくありません。
孤独死を未然に防ぐための対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
認認介護になる原因

認認介護になる原因には、人によってさまざまな背景があります。なかでも、経済的な余裕がない場合や、周囲に相談できずにいる場合は、認認介護に陥りやすくなります。
以下で、認認介護になる原因をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
経済的な余裕がない
認認介護になる一因として、経済的な問題があります。高齢者同士で介護する場合は、収入が限られているケースがほとんどです。
介護サービスの利用には費用がかかるため、経済的に余裕がない場合は外部への依頼が難しくなります。そのため、自宅でできる範囲でケアをせざるを得なくなり、認認介護の状態に陥るきっかけになりかねません。とくに、年金生活で収入が限られる場合や、介護保険制度を利用できない場合には、家族が介護の負担をすべて負うことになり、認認介護の問題が深刻化します。
周囲に相談できずにいる
周囲に相談できないといった孤立した状態も、認認介護の原因の一つです。認知症の症状が進行すると、自己管理ができなくなるため、介護する側が適切な判断を下すことが難しくなります。そのため、結果として周囲に相談できずに、自分たちだけですべて抱え込んでしまいがちです。
介護に関しては、「相談できる人がいない」「誰かに頼んで迷惑をかけたくない」など、さまざまな理由から相談を避ける人も少なくありません。結果として、周囲からの支援を得られず、認認介護の状態が続くことになります。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。認認介護における問題解決の選択肢として老人ホームへの入居を検討している方は、ぜひ気軽にご相談ください。
認認介護のリスクを回避するための解決策

認認介護にはさまざまな問題があります。そのため、年を重ねてもできるだけ自立して過ごせるよう、健康的な生活を心がける必要があります。また、周囲と定期的に連絡を取り、地域コミュニティと関わりを持つようにしておくと、ちょっとした異変に気づいてもらいやすくなるでしょう。
以下で、認認介護のリスクを回避するための解決策を解説するので、ぜひ参考にしてください。
健康的な生活を心がける
認認介護のリスクを回避するためには、年を重ねても自立した生活を送れるよう、健康維持に努めることが大切です。
野菜や果物、魚、タンパク質など、栄養バランスの良い食事を心がけ、塩分や糖分を控えるのがポイントです。健康的な食事は、認知機能の低下や体力の衰えを防ぎます。
また、健康を維持するために、日常生活に定期的な運動を取り入れましょう。無理のない範囲でウォーキングや軽いストレッチなどを習慣化できると、体力や身体の柔軟性を保ち、転倒や怪我のリスクを減らせます。
夫婦で老人ホームを利用したいと考えている方は、以下の記事もチェックしてみてください。
関連記事:夫婦で老人ホームを利用したい!利用可否や費用、入居タイミングについて
家族や友人と連絡を定期的に取る
認認介護のリスクを回避するためには、周囲と定期的に連絡を取ることも大切です。定期的に家族や友人と連絡を取ることで、ちょっとした体調の変化や認知症の進行にいち早く気づいてもらえる可能性が高まります。
また、突然連絡が取れなくなった場合には、心配して駆けつけてもらえるケースも珍しくありません。普段から家族や友人と連絡を取り、周囲に頼れる環境を整えておくと、孤独を防ぐことにもつながります。緊急時には迅速な対応が可能になるため、安心感を得られます。
地域コミュニティとの関わりを持つ
地域コミュニティとの関わりも、認認介護のリスクを回避する上で重要なポイントです。地域の人々と交流を深めておくと、困ったときに助けてもらいやすくなります。「遠くの親類よりも近くの他人」という言葉があるように、遠方に住んでいる親類よりも近隣の人のほうが迅速に支援してくれるケースも少なくありません。
厚生労働省の過去の調査結果によると、友達付き合いや家事などを普段からしている方は、していない方より健康状態が良いと思っている割合が高いといった結果が出ています。
日頃から地域コミュニティに参加し、つながりを深めることは、認認介護のリスクを回避するのに役立ちます。
参考:厚生労働省『第13回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況』
公的サービスを積極的に活用する
認認介護によって共倒れしないよう、積極的に公的サービスを活用しましょう。家族が介護状態になったら、できるだけ早めに介護保険をはじめとするさまざまな公的サービスを利用し、認認介護の問題が大きくなる前にサポートを受けるようにしてください。
介護支援サービスには、定期的な訪問介護やデイサービス、リハビリ支援などがあり、日常生活において必要なサポートを受けられます。
また、地域包括支援センターや市区町村の相談窓口、かかりつけ医などに介護の相談をすると、状況に応じた最適な解決策を提案してもらえます。専門的な立場からのアドバイスをもらうことで、今後の介護計画を立てやすくなり、介護負担の軽減も可能です。
なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。介護保険を利用して老人ホームへの入居を検討している方は、ぜひ気軽にご相談ください。
▼ 介護保険を申請するタイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:夫婦で老人ホームを利用したい!利用可否や費用、入居タイミングについて
認認介護のリスクを理解して周囲との連携体制を整えよう【まとめ】

介護が必要になった場合、自分たちだけで出来ることには限界があります。また、「自分は大丈夫だ」と思い込んで自宅での介護を続けていても、気付かぬうちに自分が認知症になってしまう可能性もゼロではありません。
2000年に介護保険制度ができ、自宅で受けられる介護支援にはさまざまなサービスがあります。また、昔と比べて老人ホームの数も増え、入居もしやすくなっています。
認認介護における問題やリスクは決して少なくありません。今回紹介した内容を参考に、周囲との連携を深めるところから始めましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。