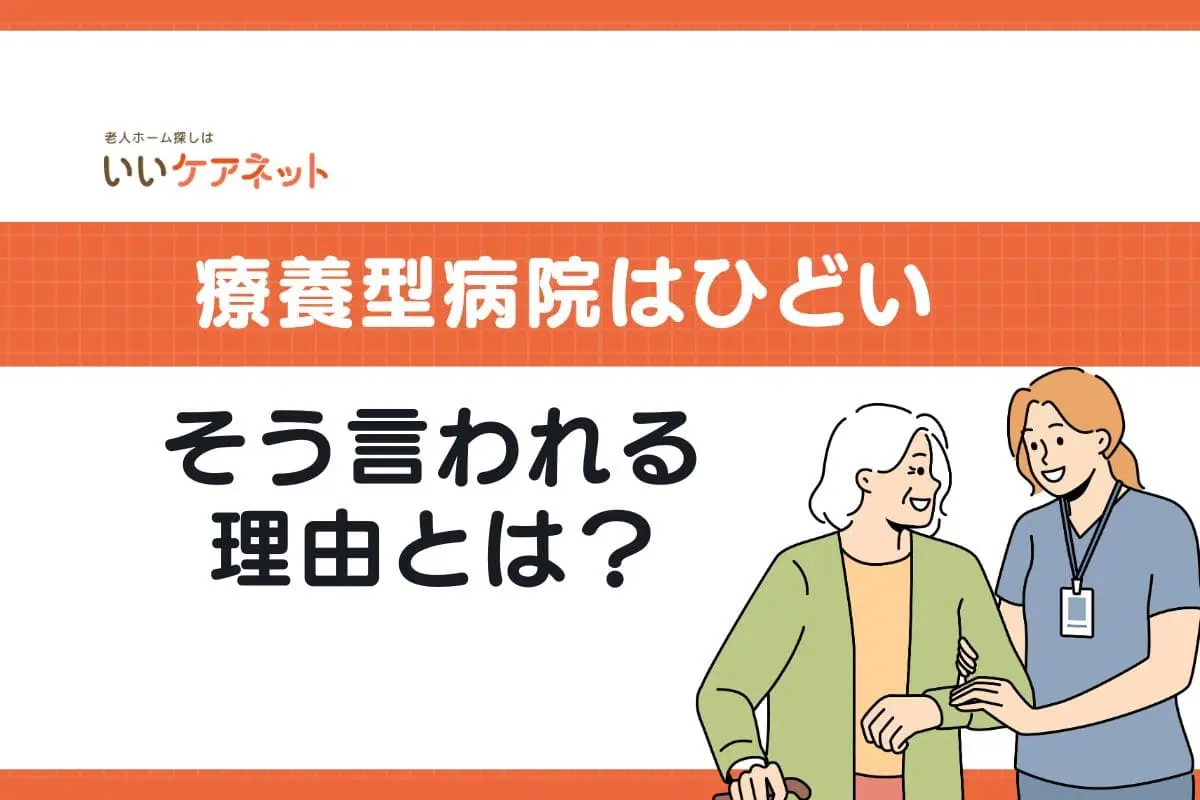「多発性硬化症の患者さんには、どんな看護や生活支援が必要なの?」
「進行性の病気って聞いたけど、家族としてどう関わればいいのかわからない…」
このような悩みはありませんか?
多発性硬化症は自己免疫疾患の1つで、脳や脊髄などに炎症が起こり、再発と寛解を繰り返す特徴があります。症状は人によって異なり、身体的なサポートだけでなく、心理的・社会的な支援も欠かせません。
本記事では、多発性硬化症に必要な看護や介護、医療費助成や介護保険サービスについて詳しく解説していきます。難病の方が入れる介護施設も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
多発性硬化症とは何か

多発性硬化症とは、免疫細胞が脳や脊髄などの中枢神経や視神経に炎症を起こし、神経組織を障害する自己免疫疾患です。
本来であれば免疫細胞は、自分の体を守るためにあります。しかし、免疫に異常が起き、自分の体を敵とみなし攻撃することで病気が発症するのです。
多発性硬化症という名前の由来は、脳や脊髄に炎症が起きたあとに傷ついた部分が時間とともに固くなることから名付けられました。
ここからは、以下4つの観点から多発性硬化症を詳しく解説します。
- 日本における多発性硬化症の患者数
- 多発性硬化症の症状
- 多発性硬化症の原因
- 多発性硬化症の治療法
順番に見ていきましょう。
日本における多発性硬化症の患者数
難病情報センターの発表によると、2023年度末時点で多発性硬化症の患者数は約24万人と報告されています。多発性硬化症は20代以降に発症することが多く、年齢層は以下のとおりです。
|
年齢 |
総数 |
| 0~9歳 | 1人 |
| 10~19歳 | 83人 |
| 20~29歳 | 1,304人 |
| 30~39歳 | 3,190人 |
| 40~49歳 | 5,900人 |
| 50~59歳 | 5,629人 |
| 60~69歳 | 3,735人 |
| 70~74歳 | 1,416人 |
| 75歳以上 | 1,847人 |
出典:難病情報センター「特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,年齢階級・対象疾患別」
全体の患者数は限られており、国内では比較的まれな病気であることがわかります。
多発性硬化症の症状
多発性硬化症は神経のいろいろな場所に障害が起こるため、人によって症状はさまざまです。
以下は、多発性硬化症の症状の一例です。
- ものが二重に見える
- 手足に力が入らず、ふらつく
- 手足のしびれや痛み
- 疲れやすい
- 物忘れが多くなる
また、体温が上がると一時的に症状が悪化する「ウートフ現象」という特徴的な症状があり、体温が下がると元に戻ります。
多発性硬化症の原因
多発性硬化症の原因は、まだ解明されていません。近年の研究では、免疫の働きが自分の体を誤って攻撃してしまう「自己免疫反応」が関わっていると考えられています。
わかっているのは、神経を包み守っている髄鞘(ずいしょう)という部分が免疫の異常によって傷つき、神経の信号がうまく伝わらなくなるということです。
以下の複数の要因が絡み合い、影響している可能性があります。
- 遺伝的な体質
- ウイルス感染
- ビタミンD不足
- 住んでいる地域などの環境
多発性硬化症はAQP4抗体(アクアポリン4抗体)という特定のたんぱく質にできる抗体が、脳や脊髄を支える細胞を攻撃してしまうことが知られています。
視神経脊髄炎は抗体が関係する病気であると理解されつつあります。
多発性硬化症の治療法
多発性硬化症の治療は、大きく分けて以下の3つです。
- 急性期の治療
- 再発防止や進行を遅らせる治療
- 症状を和らげる治療とリハビリテーション
症状が出たときはステロイドの点滴を用い、さらに症状が重い場合には血液中の異常な成分を取り除く血液浄化療法が行われることもあります。
症状が落ち着いたあとの慢性期には、後遺症の軽減や生活の質を保つため、対症療法やリハビリテーションが進められます。
多発性硬化症患者に必要な看護と生活支援

多発性硬化症(MS)は再発と寛解を繰り返す病気で、継続的な医療と生活支援が必要です。訪問診療医と脳神経内科医の連携による体制が理想とされ、在宅療養では多職種が関わるサポートが求められます。
患者の生活の質を向上させるため、以下のような看護ケアが必要です。
|
支援内容 |
対応例 |
| 食事介助 | 姿勢保持、嚥下機能の確認 |
| 投薬管理 | 服薬スケジュールの把握 |
| 感染予防 | 免疫低下に配慮した衛生管理 |
| 移動・排泄介助 | 杖・歩行器の活用、排泄支援 |
退院後も、日によって体調が変わることがあるため、体調の波を理解しながら無理のない生活を送れるような総合的な支援が必要です。
また、自宅での生活を支える家族は医療や介護制度をうまく活用し、本人の想いを踏まえサービスを活用していきましょう。
高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
多発性硬化症患者が利用できる制度やサービス

多発性硬化症は長期的な治療や生活支援が必要となるため、医療費や介護に関する制度の利用は必須です。
負担を減らし安心して暮らすためにも、以下のサービスの活用がおすすめです。
- 医療費助成
- 介護保険サービス
- 難病の方が入れる介護施設
どのような支援制度があるのか知っておくことは、経済的・精神的な負担軽減につながります。
それぞれの制度やサービスの特徴を詳しく見ていきましょう。
医療費助成
医療費の助成を受けるにはあらかじめ「特定医療費(指定難病)受給者証」という証明書をもらっておく必要があります。医療費助成の対象者となるのは、病状の程度が一定以上、または3カ月以上にわたり月額の医療費が33,000円を超える場合です。
申請から受給者証の交付の流れは、以下のとおりです。
- 都道府県・指定都市の窓口で申請する
- 審査後に医療費受給者証が交付される
- 受給者証を医療機関に見せ、受診や治療を行う
自己負担額は所得によって異なり、上限が設定されています。詳しくは自治体の窓口や公式サイトで確認しましょう。
介護保険サービス
通常、介護サービスは65歳以上で要介護認定を受けた方が対象となりますが、40〜64歳の方も、特定疾病が原因で介護が必要と認定された場合は利用可能です。
多発性硬化症は厚生労働省が定める19疾病等に該当するため、介護保険サービスを受けられます。
介護サービスの概要は、以下のとおりです。
|
内容 |
|
| 対象者 | 以下すべてを満たす方
・ 日常生活に支障あり |
| サービス内容 | ・ホームヘルプ(介護・家事) ・短期入所(原則7日以内) ・ 用具給付(車いす、吸引器など17品目) |
| 実施主体 | 市町村 |
出典:厚生労働省「難病患者等に対する介護サービス」
介護や生活の負担を軽くするためにも、早めにお住いの自治体に相談し申請しましょう。
関連記事:介護保険申請のベストなタイミングはいつ?流れや必要なものを紹介
難病の方が入れる介護施設
難病のある方でも、状態や制度に応じて介護施設を利用できます。ただし、すべての施設が受け入れているわけではなく、受け入れには条件があります。
難病の方のおもな受け入れ先は、以下の介護施設です。
|
施設名 |
対象者・特徴 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護が必要な高齢者が対象(原則65歳以上・要介護3以上) |
| 介護老人保健施設(老健) | 医療やリハビリを受けながら、在宅復帰を目指す施設で、比較的医療対応が可能 |
| 障がい者支援施設 | 年齢を問わず、障害福祉サービスの対象となる難病患者も利用可能 |
入所を希望する場合は、事前に病状や医療ニーズを伝え、対応可能か確認してください。医療対応が必要な場合は、看護師常駐や医療機関との連携がある施設を選びましょう。
関連記事:難病の方を受け入れる介護施設は?老人ホームや医療施設を4つ紹介
高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護施設関連の情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
多発性硬化症の看護と支援を理解し適切なケアにつなげよう

多発性硬化症は寛容と再発を繰り返す慢性疾患で、身体的だけでなく心理的・社会的な支援も必要とする病気です。神経のさまざまな場所に障害が起こり症状も人それぞれなので、患者に合わせた看護とケアが求められます。
医療費助成や介護保険サービス、介護施設などを上手に活用し、本人と家族の負担を減らしながら、安心して暮らせる環境づくりを進めていきましょう。
また、難病の介護は心身ともに大きな負担を伴うため、早めに専門機関や自治体に相談することも大切です。
高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスに関する情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。