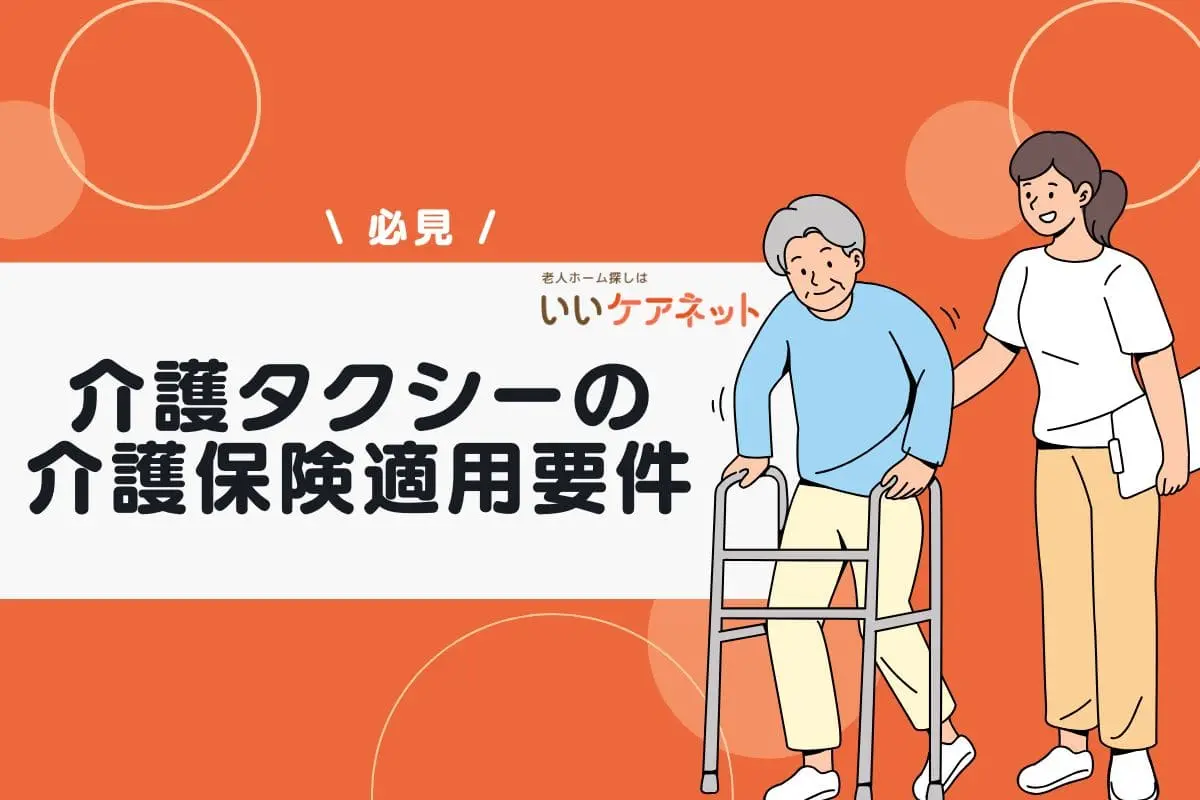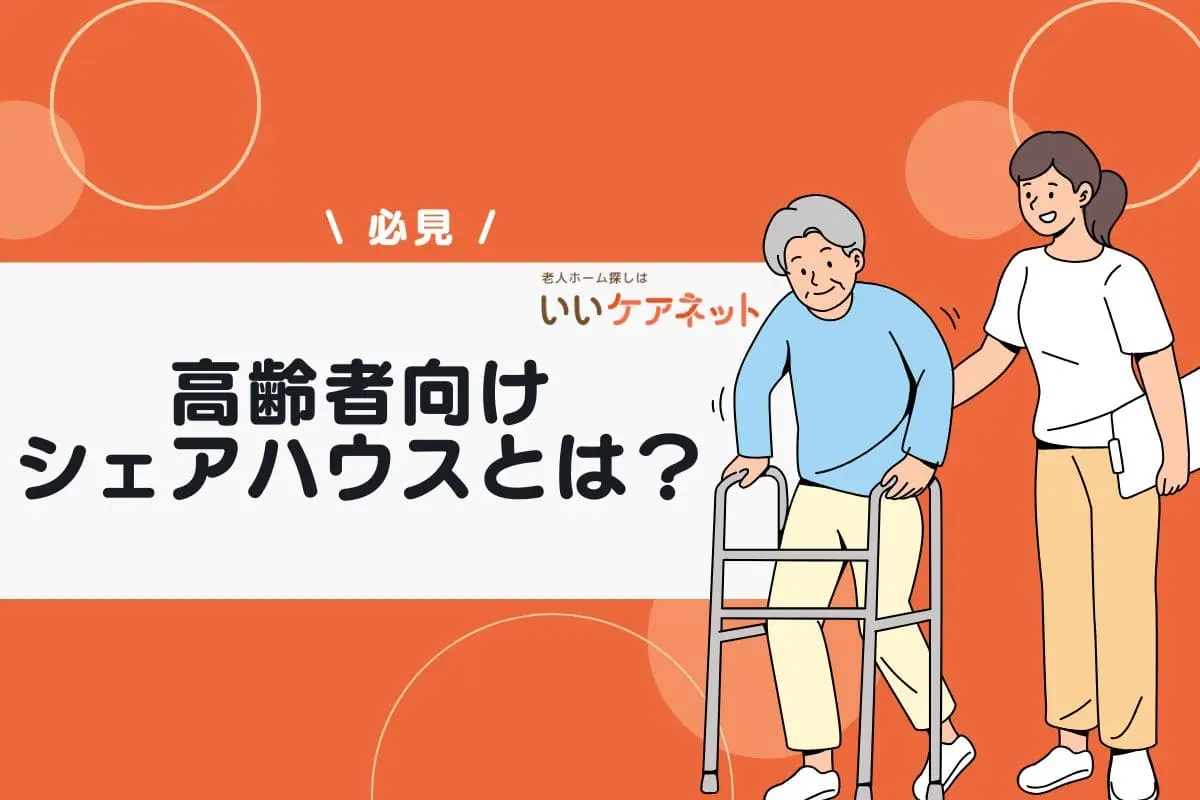訪問看護を受ける際の訪問回数は一律ではないことをご存じですか?訪問看護は、疾患や状態、適用される保険によって訪問回数が異なります。
週に何回訪問看護を受けられるかは、これからサービスを受ける方にとって重要です。
今回は、訪問看護に適用される「別表7」と「別表8」による訪問回数と特定疾病の違いを解説します。介護保険と医療保険のどちらが適用されるかも解説するので参考にしてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
訪問看護の「別表7」と「別表8」の違いは?

訪問看護では、疾病や本人の状態によって「別表7」と「別表8」に分けられます。ここでは、「別表7」と「別表8」それぞれに該当する条件と違いを解説します。
訪問看護の「別表7」とは
訪問看護の別表7は、特定疾病に該当する方が対象になります。特定疾病は、65歳以上が比較的発症しやすい以下の疾病のことです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
別表7は疾病なので、該当すると医療保険が適用されます。
訪問看護の「別表8」とは
訪問看護の別表8は、厚生労働大臣が定める以下の特掲診療料施設基準等別表第八のことです。
- 一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 二 在宅自己腹膜流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 三 人工 肛こう門又は人工 膀胱を設置している状態にある者
- 四 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
別表8は上記のような特別な管理が必要な状態の方が該当します。別表8のみに該当する場合、原則として介護保険が適用されます。
「別表7」と「別表8」の違い
訪問看護の別表7と別表8は、該当する条件が異なります。別表7が疾病を指しているのに対して、別表8は状態を指します。
また、別表7では医療保険が適用されますが、別表8のみに該当する場合は介護保険が適用されるのです。
訪問看護を受ける際は、上記のどちらに該当しているか把握することが大切です。
訪問看護で「別表7」「別表8」に該当した場合の特例の違い

別表7と別表8に該当した場合、以下のような特例があります。
| 別表7 | 別表8 | |
| 適用保険 | 医療保険 | 原則介護保険 |
| 訪問看護ステーション数 | 最大3カ所まで利用可能 | 2か所以上の訪問看護事業所を利用可能 |
| 1日の利用上限 | 1日に複数回の訪問看護を利用可能 | 1日に複数回の訪問看護を利用可能 |
| その他の特例 | ・複数名訪問看護加算を算定
・医療機関からの外泊時、訪問看護基本療養の算定が可能 ・退院日に訪問看護に加入できる |
・複数名の看護師からケアを受けられる
・必要に応じ通常より長時間の訪問看護が利用可能 ・入院中の外泊時にも訪問看護を2回まで利用可能 ・退院日当日から訪問看護を利用可能 |
別表7と別表8では、利用できる訪問看護ステーションの数や医療機関から外泊時のサービスの有無が異なります。
とくに、別表8は特別なケアが必要になることが多いため、長時間の訪問看護を利用できるのが特徴です。
訪問看護では「別表7」「別表8」に該当すると訪問回数の上限が変わる

訪問看護では、別表7と別表8に該当すると訪問回数の上限が変わります。通常の訪問看護とどう変わるのかを解説します。
「別表7」「別表8」の訪問回数
一般的な医療保険を使う際、訪問看護の回数は原則1日1回、週3回が上限です。
しかし、別表7と別表8に該当する場合、週4日以上の訪問が可能です。看護師によるこまめなケアが受けられるため、利用者は安全で快適な生活を送りやすくなります。
「特別訪問看護指示書」が交付された場合も訪問回数が変わる
別表7と別表8以外に、「特別訪問看護指示書」が交付された場合も週4日以上の訪問看護を受けられます。
特定看護指示書とは、医師が退院直後や急変の可能性があり、特別な看護が必要だと判断した際に交付される書類です。特別訪問看護指示書は、以下のようなケースで交付されます。
- 退院直後
- 感染症等の急性増悪時
- 終末期(末期の悪性腫瘍等除く)
特別訪問看護指示書は疾患や状態などの条件がありません。医師が週4日の看護が必要な状態と判断すると適用されます。
介護保険では訪問回数に上限がない
介護保険で訪問看護を受ける際、訪問回数に上限はありません。
1回あたり20~90分利用できます。継続的なリハビリが必要な場合は、作業療法士や理学療法士を90分以上利用するケースもあります。
介護保険は要介護度によって限度額が異なるため、限度額を超えた分は全額自己負担になる点に注意しましょう。
また、介護保険で訪問看護を受ける際は、前の訪問から2時間空けなければいけません。2時間経たずに再度利用してしまうと、前回の利用時間と合算されてしまいます。
緊急時や訪問リハビリが必要な際は特例になることもあるため、相談員に確認してみることをおすすめします。
訪問看護で利用できる介護保険と医療保険の違い

訪問看護では、疾病や状態によって介護保険と医療保険どちらが適用されるか決まります。それぞれの保険にどのような違いがあるか気になる方のために、保険の特徴を解説します。
介護保険の適用条件
介護保険は、介護が必要な方が適切なサポートを受けられるように費用を給付します。
訪問看護で介護保険を適用するための条件は、以下のとおりです。
- 医師から「訪問看護指示書」の交付がある方
- 要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の方
- 要介護や要支援の認定を受けた40歳以上65歳未満で別表7に該当する方
上記の方が訪問看護を受ける際は、原則介護保険が優先されます。
医療保険の適用条件
医療保険は、病気やケガをした際の治療費をカバーしてくれるものです。訪問看護で医療保険を適用するための条件は、以下のとおりです。
- 40歳未満の方
- 65歳以上で別表7に該当する方
- 65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方
65歳以上でも別表7の疾病に該当する方は、介護保険ではなく医療保険が適用されます。
訪問看護では原則介護保険が優先される
訪問看護では、医療保険と介護保険を同時に使えません。要介護や要支援認定を受けている場合は、原則として介護保険が適用されます。
医療保険と介護保険は自分では選べません。利用者の年齢や疾病、状態をもとに判断されます。
訪問看護は「別表8」になると訪問回数が変わる【まとめ】

今回は訪問看護に欠かせない別表7と別表8の違いを解説しました。訪問看護を受けると自宅で安心して生活できます。
訪問看護を利用しても不便がある方は、介護施設の利用も検討してみてください。
いいケアネットでは、老人ホーム探しのための入居無料相談を受け付けています。日常生活が困難な親が安心して利用できる施設を紹介しているので、お気軽にご相談ください。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。