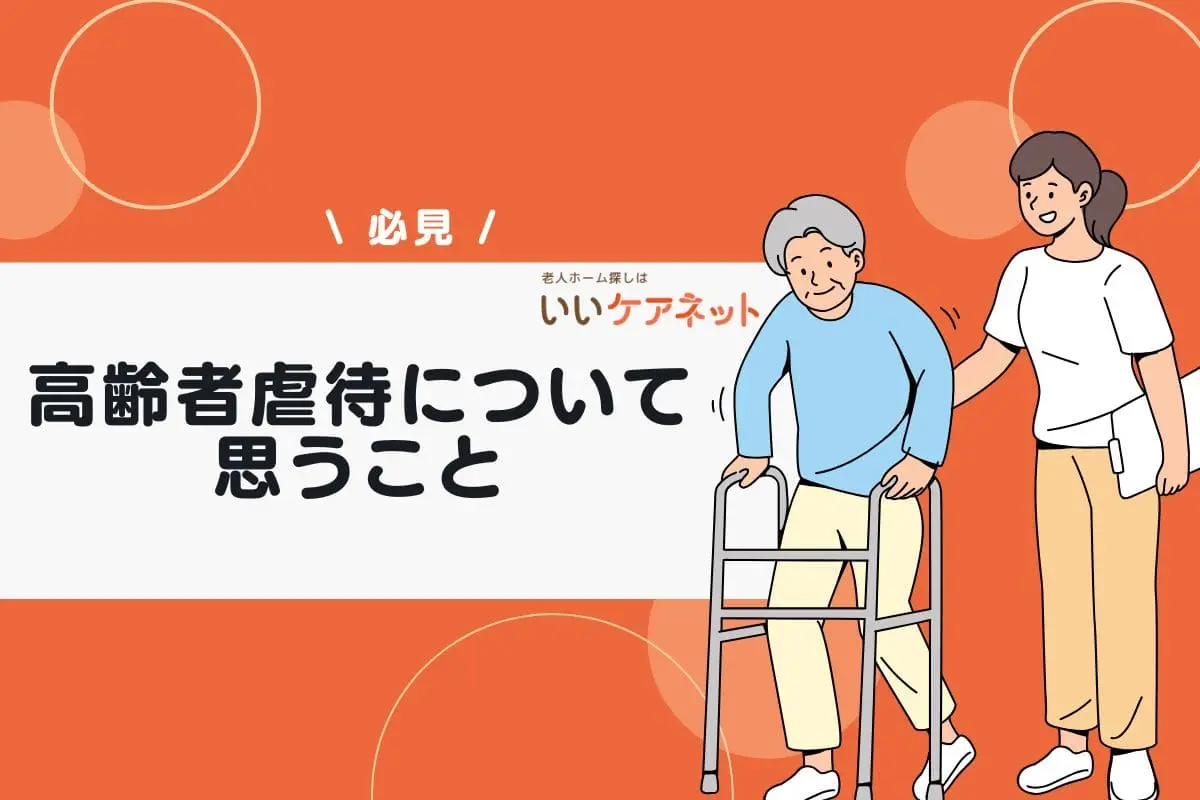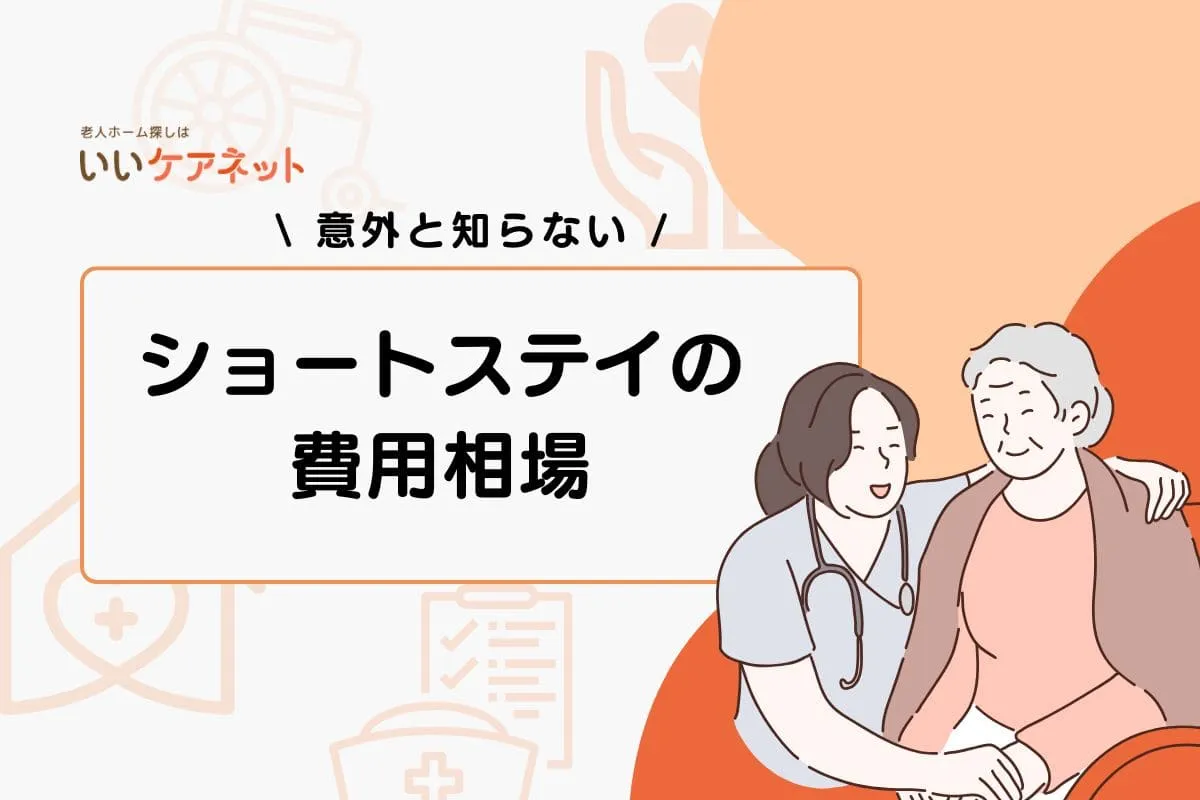「高齢者に多い病気には何がある?」「歳を重ねても健康でいるためのポイントが知りたい」との悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論として、高齢者がかかりやすい病気のトップ5は以下のとおりです。
- 認知症
- 脳卒中
- 骨折・転倒
- 高齢による衰弱
- 関節疾患
本記事では、高齢者が病気にかかりやすい理由とともに、健康的な生活を送るためのポイントも解説しています。見逃しがちな病気のサインも紹介するので、早期に予防したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
大阪を中心に、多数の高齢者向け施設情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中。
高齢者に多い病気ランキングTOP5

まずは、高齢者がかかってしまうと介護が必要となる病気を5つ、ランキング形式で紹介します。厚生労働省が2022年に発表した『国民生活基礎調査』の結果は以下のとおりです。
- 認知症
- 脳卒中
- 骨折・転倒
- 高齢による衰弱
- 関節疾患
それぞれの特徴について解説します。
1位:認知症
認知症は、脳の病気や障害などによって起こり、認知機能の低下が主な症状となる疾患です。認知症には複数の種類がありますが、中でも代表的なのがアルツハイマー型認知症であり、この病気が介護のきっかけになったと回答する方が多くいます。
また、65歳以上が認知症になる割合は、年々増加傾向にあり、2025年には5人に1人が認知症になるとの推計もあるほどです。
引用:3 高齢者の健康・福祉|平成29年版高齢社会白書(概要版) – 内閣府
認知症について詳しく解説!【PART2】~認知症の種類・症状について~ | シニアライフアドバイザー監修 介護Q&A【いいケアネット】公式
2位:脳卒中
脳の血管が破れたり詰まることで、脳に血液が届かなくなり、脳の神経細胞が障害される病気の総称が脳卒中です。代表的なものには次のようなものがあります。
| 脳卒中の例 | 原因・症状 |
| 脳梗塞 | 血栓によって血管が詰まる |
| 脳出血 | 脳の血管が破裂する |
| くも膜下出血 | 動脈中が破れて硬膜と軟骨の間にあるくも膜に出血が見られる |
厚生労働省の『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』によれば、どの年代においても、女性よりも男性の方が患者数は多い傾向にあります。
引用:脳卒中に関する留意事項
脳梗塞になると、半身が痺れたり、身体を思うように動かせずフラフラしたりするのが原因で、高齢者であれば介護が必要になるケースが多いです。
また、脳卒中については下記のリペアセルクリニックの記事も参考になりますので、合わせてご確認ください。
脳卒中の前兆とは?見逃してはいけない5つのサインとチェックリストを紹介
3位:骨折・転倒
高齢になるにつれ、骨折・転倒しやすくなります。元気であっても、骨折・転倒が原因で介護が必要になるケースも少なくありません。高齢者の骨折・転倒が起こりやすい理由は次のとおりです。
- 骨粗鬆症による骨の強度の低下
- 関節機能の衰え
- 加齢に伴う四肢の筋力低下
骨折や転倒をしてしまうと、どれだけしっかりしていても、身体を十分に動かせません。結果として、認知症の進行をはじめ、他の疾患の症状が悪くなるケースがあります。
4位:高齢による衰弱
高齢による衰弱は、フレイルとも呼ばれます。フレイルは加齢とともに認知機能などが低下し、生活機能障害や要介護状態、死亡するリスクが高くなった状態です。
一般的に、加齢に伴い、以下のような症状が現れます。
- 食欲不振
- 社会交流の減少
- 筋力・認知機能の低下
- 多くの病気を患っている
また、65歳以上の地域在住高齢者を対象におこなったフレイルの調査では、全体の有症率は11.5%との結果も出ています。加齢に伴って生じるフレイルは、介護が必要になるケースが多いです。
参考:後期高齢者の健康
5位:関節疾患
関節疾患は身体の関節に異常をきたす疾患の総称です。膝関節や股関節に多くの症状がみられます。とくに多い疾患としては、変形性膝関節症が挙げられ、膝の軟骨に負担がかかるのが原因です。
なお、変形性膝関節症の患者の半数が女性です。60歳以上では、男性の約1.5〜2倍の有病率になる旨もわかっています。変形性股関節症になると、膝の曲げ伸ばしが難しくなったり、足が地面に引っかかったりするのが特徴です。
高齢者がなりやすいランキング外の病気

ここからは、高齢者がなりやすいランキング外の病気を解説します。具体的には以下の6つです。
- 心疾患(心臓病)
- パーキンソン病
- 呼吸器疾患
- がん(悪性新生物)
- 糖尿病
- 脊髄損傷
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
心疾患(心臓病)
心疾患にはいくつもの種類がありますが、代表的なものは「心筋梗塞」と「狭心症」です。主な原因はどちらも加齢による血管の老化、いわゆる動脈硬化であるといわれています。その他にも次のような生活習慣が原因で発症する場合もあります。
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 肥満
心疾患は日本人の死因第2位で、突然死や要介護に至るケースの多い疾患です。
パーキンソン病
パーキンソン病は、脳の異常のために体の動きに障害が現れる病気です。症状には次のようなものが挙げられます。
- 筋固縮
- 手足が震える
- 動作が遅い・小さい・少ない
- バランスがとれない
また、幻覚や抑うつの症状を伴う場合があり、高齢になって症状が進むと認知症を発症するケースもあります。パーキンソン病になる人の割合は、一般的には1,000人に約1〜2人ほどですが、65歳以上になると100人に約1人と、高齢になるにつれて発症しやすいのも特徴です。
パーキンソン病の家族を施設に入れる最適なタイミングとは?施設選びのポイントまで解説 | シニアライフアドバイザー監修 介護Q&A【いいケアネット】公式
呼吸器疾患
高齢になると、呼吸器疾患になるリスクが高くなります。体力が衰えることで、買い物や散歩に出かけてもすぐに疲れたり、息切れを起こしたりして、外出を控えるようになるためです。次第に呼吸する力までも衰えてしまう場合があります。
呼吸器疾患の代表的な例は、以下のとおりです。
- 肺炎
- 肺気腫
- 慢性気管支炎
- 慢性閉塞性肺疾患
適度な運動をおこない、体力や呼吸機能の低下の予防が欠かせません。
がん(悪性腫瘍)
がんは別名「悪性腫瘍」と呼ばれます。エラーにより細胞が異常に増殖してしまい、その増殖が止まらないために「悪性」と呼ばれ、人を死に至らしめます。
年齢を重ねる内に、細胞単位でのエラーが多くなったり、修復能力が下がったりするため、高齢者のほとんどは若年者と比べて癌になりやすい状態といえます。2020年に発表された『高齢者がん医療 Q&A 総論』によると、65歳以上高齢者の1980年時点での罹患率は50.3%だったのに対し、2014年には72.1%と高齢者の割合が大幅に増加しています。
しかし最近では、がんは必ずしも不治の病ではなく、検査や治療の精度が上がったことで、延命できるケースが増えています。入院期間も短くなり、在宅で療養・介護をおこなうことも少なくありません。
糖尿病
糖尿病は、インスリンが十分に機能しなくなり、血中の糖のレベルが高い状態が続く慢性的な疾患です。高齢者がかかる糖尿病は「2型糖尿病」であり、運動不足や不健康な食事が原因で発症します。
初期症状がほとんどないため、頻尿や喉の渇き、手足の痺れなどの自覚症状が出てくるころには、病気は非常に進行しているといえます。
また、糖尿病になった後に血糖値が高いままだと、血管がもろくなり血液が詰まりやすくなります。脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こし、突然死のリスクが高まることも否めません。
万が一、助かったとしても要介護となるケースも少なくないです。
脊髄損傷
高齢になると骨がもろくなるため、転倒などで骨折のリスクが高まることはよく知られています。ただし、65歳以上の脊髄損傷者の60~70%は骨折や脱臼を伴わない、非骨傷性脊髄損傷が多いとされています。
脊髄損傷の進行は以下のとおりです。
- 加齢変化により頚椎症が起こる
- 神経の通り道である脊柱管が狭くなる
- 手足の痺れなどの症状が出始める
以上まで進行した状態を「頸椎症性脊髄症」といいます。少しの外傷が加わるだけで非骨傷性脊髄損傷となり、損傷した部位によっては以下のような障害も患います。
- 四肢の運動障害
- 感覚障害
- 排便・排尿障害
高齢者が病気になりやすい理由は免疫機能の低下

ここまで、高齢者がかかりやすい病気について解説してきました。しかし、なぜ高齢者は病気になりやすいのか疑問に思われる方もいるかもしれません。結論として、高齢者が病気になりやすい理由は、免疫機能の低下にあります。どれだけ健康であったとしても、加齢とともに、免疫機能は下がってきます。
免疫には、自然免疫と獲得免疫の2つがあり、獲得免疫の能力は20代の頃がピークです。40代に入ると、ピーク時の半分ほどだともいわれています。感染源である微生物への攻撃力が弱まってしまい、感染症にかかりやすくなるのも一例です。
高齢者の病気のサイン

高齢者が病気になるにあたって、いくつか見逃せないサインがあります。ここでは、代表的な3つのサインについて解説します。
- いつもより元気がない
- 痛みや熱がある
- 物忘れが多くなった
身近な家族が該当していないかをチェックし、万が一、心当たりがあれば、医療機関を受診するようにしましょう。
いつもより元気がない
1つ目のサインはいつもより元気がないことです。疲れやだるさは、高齢者でも休めば回復します。しかし、食欲がなかったり水分を摂っていなかったりして、元気がない状態が続く場合は病気が原因かもしれません。元気がないときに考えられる病気は、以下のとおりです。
- 心筋梗塞
- 心不全
- 感染症
- 貧血
- 脱水症状
また、飲んでいる薬が原因で元気がない場合もあります。何か少しでもいつもと様子が違うと感じたら、かかりつけ医に相談するか医療機関を受診しましょう。
痛みや熱がある
2つ目のサインは痛みを訴えたり、熱があったりする場合です。突然の頭痛や発熱でも、重大な病気が隠れている可能性があります。
気をつけるべき症状は次のとおりです。
- これまでに経験したことがないくらい強い痛みがある
- 身体を動かしていると痛みがひどくなる
- 痛みが長く続いており、体重も減ってきている
- 言っていることが支離滅裂である
以上のケースでは、がんや重い感染症などの前兆であるかもしれません。
また、高齢者は体温が低い傾向にあるため、37℃ほどの微熱であっても注意が必要です。かかりつけ医に相談するか救急車を呼び、救急外来を受診しましょう。
物忘れが多くなった
3つ目のサインは物忘れが多くなったことです。物忘れが多くなる理由のひとつに、認知症の初期症状が考えられます。
たとえば、以下のような症状は、認知症の初期症状として注意すべきポイントです。
- 同じことを何回も聞く
- 今日の日付がわからない
- 怒りっぽくなる
- 約束が守れない
- 物をなくす
認知症は、早期治療により進行を遅くできるため、なるべく早めに医療機関に受診しましょう。
高齢者が健康的な生活を送るために意識すべきポイント

最後に、高齢者が健康的な生活を送るために意識すべきポイントを3つ紹介します。
- 食生活に気を配る
- 適切に運動する
- 健康診断を受ける
順番に見ていきましょう。
食生活に気を配る
高齢者が健康的な生活を送るためには、食生活に気を配りましょう。100歳以上の高齢者の食生活には、以下のような特徴があります。
- 1日3回規則正しく食事する
- 腹八分目を心掛ける
- 緑黄色野菜を食べる
- 魚や肉、卵なども積極的に食べる
健康的な生活を送るためには、適切な食生活が重要です。
適切に運動する
健康的な生活を送る上で、運動も必要不可欠です。人それぞれ個人差があるので、量や強度を調整しつつ、無理のない範囲で運動に取り組んでみてください。
厚生労働省の『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023』によれば、高齢者の運動は以下が推奨されています。
- 筋力・バランス・柔軟性などを考慮した運動を週3日以上おこなう
- 筋力トレーニングを週2〜3日おこなう
- 毎日6,000歩以上歩く
ただし、運動する際は安全に配慮し、転倒のような事故に気をつけて実施しましょう。
健康診断を受ける
定期的な健康診断を受けるのを忘れないようにしましょう。健康診断を受ければ、生活習慣病をはじめとしたさまざまな病気や疾患を見つけるきっかけとなるためです。また、40歳以上75歳未満であれば、「特定健診・特定保健指導」も受けられます。受診するメリットは以下のとおりです。
- 自分の健康状態を知れる
- 結果をもとに自分の健康状態へのアドバイスがもらえる
- 疾病予防をして、ずっと健康で暮らせる
生活習慣病はがんや心疾患につながる可能性もあるため、早期発見が重要です。自覚症状がないまま、症状が悪化しているケースもゼロではありません。生活習慣病の早期発見のために、定期的に健康診断を受けるようにしましょう。
高齢者がかかりやすい病気に注意して健康的な生活を送ろう

高齢者は免疫機能の低下により、がんや脳卒中、認知症などの重大な疾患にかかる可能性が高いです。症状によっては、これまでの生活に戻るのが難しく、介護が必要になるかもしれません。
ただし、定期的に健康診断を受けたり、適切な運動を続けたりすれば、病気の予防や早期発見、病気の進行を防げるようになります。一気にすべての予防法を試すのではなく、できそうなものから少しずつでも毎日始めてみるのが大切です。
大阪を中心に、多数の高齢者向け施設情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。