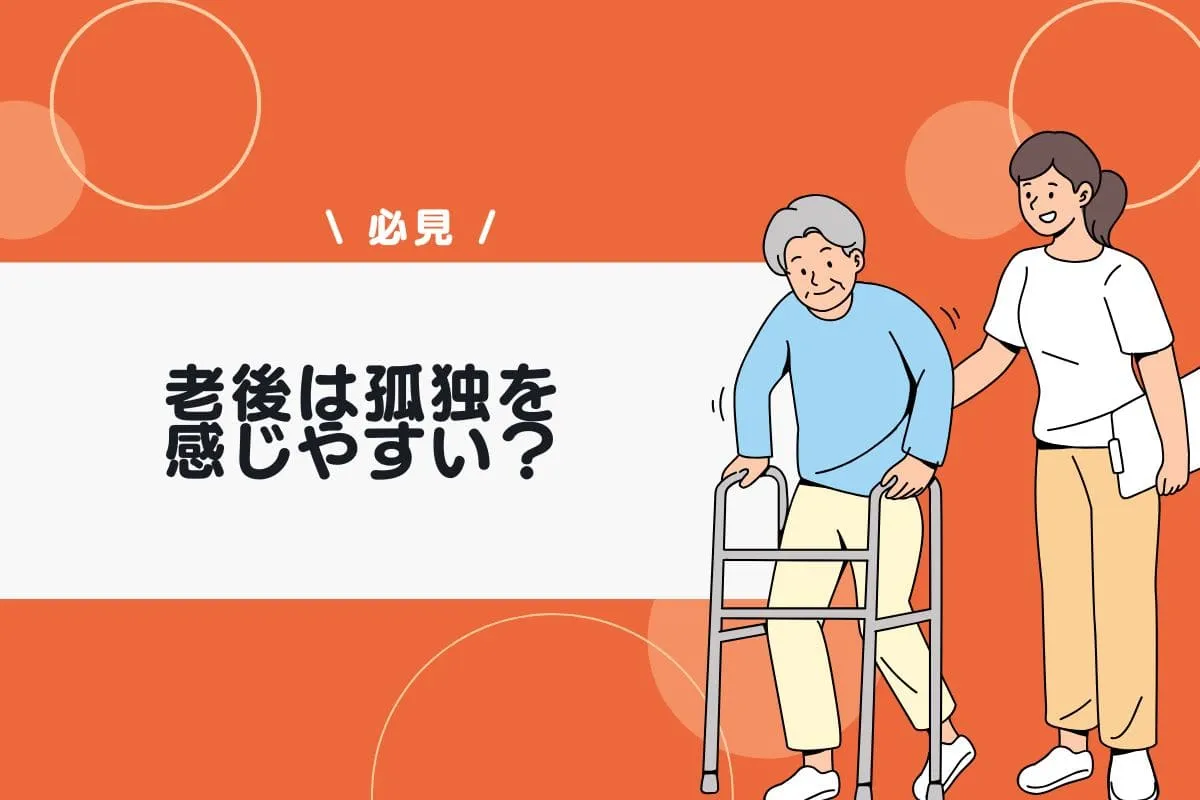レビー小体型認知症の方が一人暮らしをする際には、多くのリスクが伴うのが実情です。
たとえば、適切な薬物療法が難しい点や転倒による怪我のリスク、金銭的なトラブルに巻き込まれる可能性が高いためです。
そもそもレビー小体型認知症は、家族や介護者にとっても症状や進行が大きな悩みの種となります。
しかし、仕事の関係から離れた場所で生活しなければならず、レビー小体型認知症の家族に一人暮らしで生活してもらう必要もあるでしょう。
そこで本記事では、レビー小体型認知症が一人暮らしをする上で見逃せないリスクや症状、治療法などを解説します。
一人暮らしを続けるのは困難と感じないための支援策や、おすすめの介護施設についてもまとめました。
レビー小体型認知症の方への不安を少しでも軽減したいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
【結論】レビー小体型認知症の方が一人暮らしするのはリスクが伴う

レビー小体型認知症の方が一人暮らしをするには、以下のリスクが伴います。
- 適切な薬物療法が難しい
- 転倒による怪我のリスクが高い
- 金銭的なトラブルに巻き込まれやすい
レビー小体型認知症の方が家族にいる方に向け、具体的なリスクを解説していきます。
適切な薬物療法が難しい
レビー小体型認知症における薬物療法の難しさは、その病態の複雑さに起因しています。
レビー小体型認知症は、認知機能の低下だけでなく、幻覚やパーキンソン病様の運動症状、自律神経機能の障害などが伴います。
単一の治療薬ですべての症状を管理するのは難しく、抗精神病薬の使用には慎重にならなければいけません。
またレビー小体型認知症の方は、従来の抗精神病薬に対して過敏であり、副作用として症状が悪化するリスクもあります。
薬物療法の効果が個人差により大きく異なるため、医師と患者家族との緊密な連携が欠かせません。
たとえ市販の薬であっても飲み合わせや誤った服用方法につながるリスクがあるため、一人暮らしを促すには慎重さが大切です。
転倒による怪我のリスクが高い
レビー小体型認知症の方が一人暮らしをする際、転倒による怪我のリスクも考えなければいけません。
転倒によるリスクは、レビー小体型認知症に特有の運動障害が原因となるケースがよくみられます。
たとえばバランス感覚や筋力の低下により、日常生活の中で簡単に転倒してしまう恐れがあるのです。
レビー小体型認知症は、全身の筋肉が硬直する「パーキンソン病」の症状がみられるケースが多いためです。
レビー小体型認知症の方は、幻視や注意力の低下も併発する可能性もあり、転倒のリスクをさらに高める要因となります。
一人暮らしの場合、転倒のリスクは本人が注意しなければいけません。しかし、筋肉の硬直や注意力の低下が併発すると、本人では予防策を講じられない可能性が高まります。
レビー小体型認知症の方や家族にとって、少しでも安心した生活を続けるためにも、バリアフリー化や証明、家具などの整理をしておくのがおすすめです(詳しくは後述します)。
金銭的なトラブルに巻き込まれやすい
レビー小体型認知症の方が一人暮らしをする際、金銭的なトラブルに巻き込まれやすいリスクが伴います。
認知症の特性上、金銭の管理が難しくなる場合が多く、詐欺や不正利用の被害につながる可能性があります。
2023年に警察庁が公表した調査結果によると、高齢者の詐欺被害を認知した件数は、年間で14,895件発生していると発表されました。
レビー小体型認知症を含めた認知症の方は、判断力が低下するため、押し売りにも不信感を抱きにくくなってしまうリスクもあります。
記憶力の低下に伴い、財布や通帳を保管した場所を忘れるケースも考えられます。
つまり、レビー小体型認知症の方が一人暮らしをすると、金銭的な管理が不十分になり、法的なトラブルに発展するリスクがあげられるのです。
参考:警察庁「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」
そもそもレビー小体型認知症とは
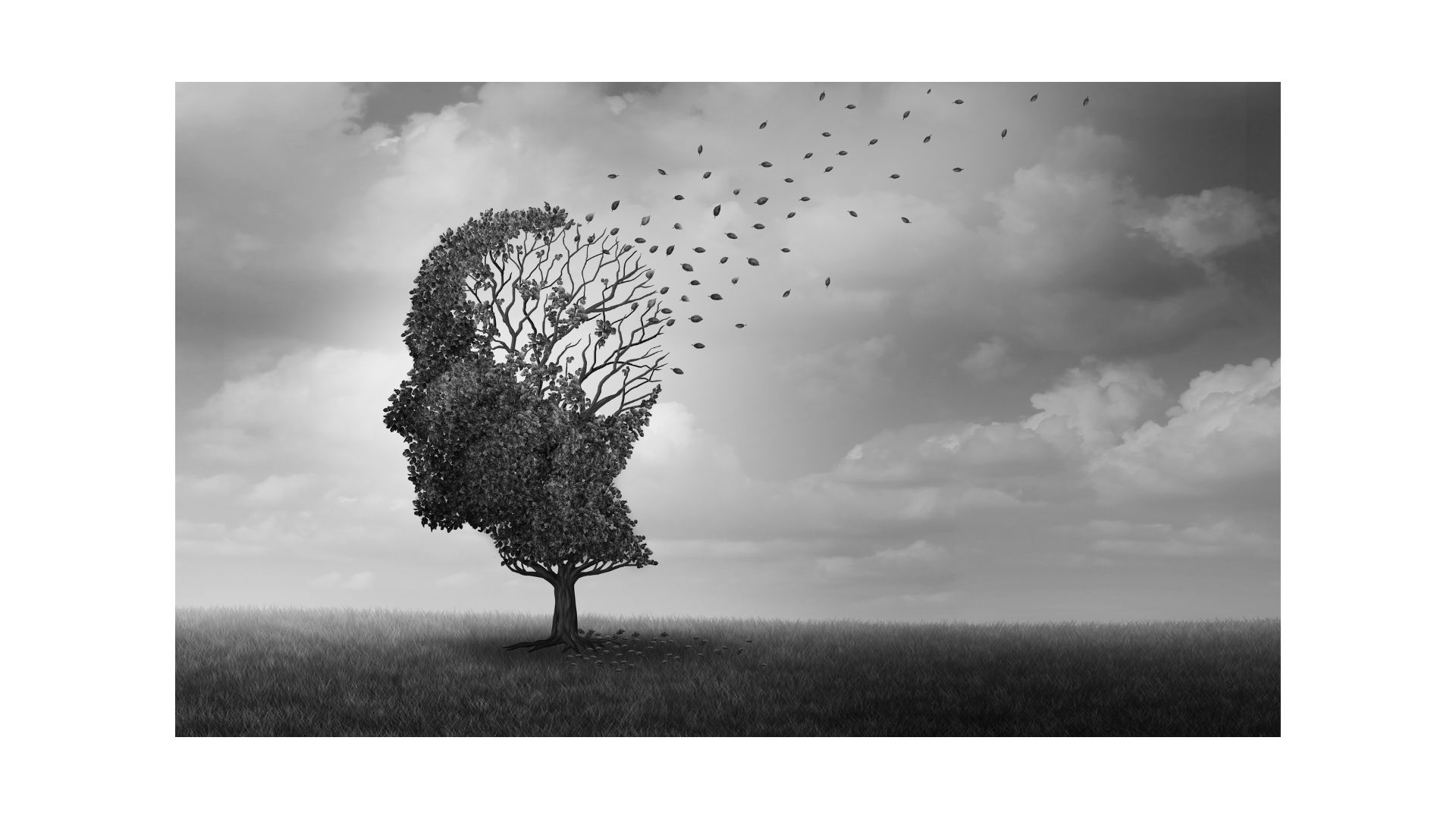
レビー小体型認知症とは、アルツハイマー型認知症やパーキンソン病と並ぶ、代表的な認知症の1つです。
レビー小体型認知症は、脳内にレビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質の塊が蓄積して発症します。
とくに高齢者に多く見られ、進行性の病気であるため、時間の経過とともに症状が悪化する傾向があります。
ここからはレビー小体型認知症の症状や進行、治療法について詳しく解説していきます。
主な症状
レビー小体型認知症の主な症状は、認知機能障害やパーキンソン病などがあげられます。
発生初期から「知らない人がいる」「壁に虫が這っている」など、幻覚症状もあり、気分の浮き沈みも激しいのがレビー小体型認知症の特徴です。
それぞれの症状や特徴は以下の通りです。
| 症状名 | 特徴 |
| 認知機能障害 | 判断力・注意力の低下、健常な状態と変動する障害。数分間〜数カ月の変動。 |
| パーキンソン病 | 手足の筋肉がこわばり、震え、動作が緩やか。嚥下(えんげ)障害や誤嚥(ごえん)性肺炎の原因。 |
| 幻視・幻聴 | 実際には存在しない人物・虫・動物が見える。発症初期からみられる。 |
| レム睡眠行動異常症(RBD) | 怖い夢を見て異常行動をとる。 |
| 自律神経症状 | 便秘・尿失禁、嗅覚異常、異常な発汗、起立性低血圧。無気力やうつ症状など。 |
症状の進行
レビー小体型認知症の症状は、時間の経過とともに徐々に進行し、一人暮らし生活においても大きな影響を与えます。
レビー小体型認知症の症状は、以下のような段階に応じて進行します。
| 症状の進行 | 具体的な症状 |
| 初期段階 | 注意力や集中力の低下、記憶力の障害 |
| 中期段階 | 空間認識能力の低下、運動機能の障害、幻視や錯覚、妄想 |
| 後期段階 | 自立性の著しい損失、日常生活全般に支援が必要 |
レビー小体型認知症の症状を遅らせるためにも、早期の発見と治療が大切です。レビー小体型認知症は、医療や福祉の専門家と連携をしながら、適切な支援を受けていきましょう。
主な治療法
レビー小体型認知症の治療法は、根本的な改善を促す方法は現在明らかになっていません。
しかし、レビー小体型認知症の進行を遅らせ、生活の質を向上させるのを目的に治療をしています。主な治療法としてあげられるのが薬物療法や理学療法があげられます。
レビー小体型認知症の方が一人暮らしをしながら治療する場合、正しく服用されないリスクは見逃せません。
レビー小体型認知症を含めた認知症の方は、孤独感から症状を悪化するケースもあるため、転倒防止を目的にした理学療法がおすすめの選択肢になります。
また、幻視や幻聴の症状がみられる方に対し、寄り添ったコミュニケーションが求められます。
つまり、薬物療法に頼らず生活を送る上での環境を整えるのが、レビー小体型認知症の進行を遅らせるのに効果的な支援策になるのです。
レビー小体型認知症とほかの認知症との違い

レビー小体型認知症を含めた認知症には、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症の「三大認知症」の違いを把握しておく必要があります。
それぞれの違いは以下の通りです。
| 認知症の種類 | 性別差 | 主な症状 |
| アルツハイマー型認知症 | 女性に多い | 記憶障害、思考能力の低下、妄想、徘徊、睡眠障害 |
| 脳血管性認知症 | 男性に多い | 記憶障害、突然の症状の現れ、まだら認知、手足の麻痺 |
| レビー小体型認知症 | 男性が女性の2倍発症しやすい | 幻覚、パーキンソン病様症状、気分や態度の変動 |
なお、以下の記事では認知症の初期症状を早期に発見するために、具体的な症状について解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:認知症について詳しく解説!【PART1】~認知症と物忘れの違い・初期症状チェックリスト~
レビー小体型認知症の方が一人暮らしするための支援策

レビー小体型認知症の方が家族にいて、仕事の関係から一人暮らしをしてもらう必要がある場合、両者が安心できる環境が不可欠です。
離れた場所で一人暮らしをしていて「レビー小体型認知症の家族が心配」と感じる方に向け、具体的な支援策を解説します。
バリアフリーな家に改修する
レビー小体型認知症の方が安全に一人暮らしを続けるためには、住環境をバリアフリー化するのがおすすめです。
バリアフリー化とは、物理的な障壁を取り除き、移動や日常生活の動作をスムーズにするための工夫を施す方法です。
具体的には、以下の工夫があげられます。
- 段差をなくす
- 滑りにくい床材を使用する(主に浴室)
- 手すりを設置する
上記のような工夫をすると、転倒や怪我のリスクを大幅に減少する可能性が高まります。
また、ドアや廊下の幅を広げると、歩行器や車いすの使用が容易になり、移動の自由度が増すのもバリアフリーの魅力です。
なお、一軒家をまるごとバリアフリーにする場合の費用は、施工会社によっても異なりますが、数百万〜1,000万円が相場です。
全額が自己負担になるのではなく、助成金や補助金の制度を受けられるケースもあります。地域の自治体や施工会社に相談しながらバリアフリー化を実現させましょう。
照明の改善や大型家具を減らす
レビー小体型認知症の方が安全に一人暮らしを続けるためには、生活環境のシンプル化が重要です。
とくに照明や大型家具の扱いは注意が必要です
照明は、視覚的な錯覚や幻覚を引き起こしやすいレビー小体型認知症の特性を考慮し、柔らかい自然光に近い照明を選びましょう。
また直接光を避け、間接照明を利用すると、落ち着いた環境を作れるだけでなく、夜間のトイレや移動の際に安全に歩けるよう、足元を照らす照明も役立ちます。
大型家具を減らすのも、転倒や怪我を防ぐため、部屋の動線を確保し、必要最低限に抑えましょう。
動線を妨げる位置に家具を配置しないようにし、頻繁に使用する物は手の届きやすい場所に置くのがおすすめです。
さらに、照明や大型家具の整理は、認知症の進行度にあわせて定期的に見直すのが重要です。
進行に応じて即座に対応できるよう、医療や介護の専門家と連携しながら、レビー小体型認知症の方にとっての生活を支援していきましょう。
多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
関連記事:レビー小体型認知症の介護が大変な理由や付き合い方のポイントを解説
レビー小体型認知症の一人暮らしに限界を感じたときにおすすめの介護施設
レビー小体型認知症の方が一人暮らしで生活を送るのが限界に感じた場合、以下の介護施設への入居が選択肢にあげられます。
- 特別養護老人施設
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 有料老人ホーム
介護施設ごとの特徴を順番に解説していきます。
特別養護老人施設
特別養護老人施設(特養)は、24時間体制で介護が必要な高齢者に手厚いケアを提供する施設です。
レビー小体型認知症の方が一人暮らしに限界を感じた場合、特別養護老人施設は安全で安心できる選択肢となります。
特別養護老人施設では、介護スタッフが食事、入浴、排泄などの日常生活の支援を行い、認知症の症状に応じた個別のケアプランを作成します。
また特別養護老人施設は、医療機関との連携が充実している点も魅力です。
医師や看護師が定期的に訪問し、健康状態のチェックや薬の管理を行うため、持病のある方や薬物療法が必要な方も安心して生活できます。
施設内でのリハビリテーションやレクリエーション活動も充実しており、身体機能の維持や社会的交流の促進が図られるのも特徴です。
関連記事:養護老人ホームとは?特養との違いや入所条件、費用負担について解説
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者が安心して暮らせるように設計された住まいです。
レビー小体型認知症の方にとっても、食事の準備や掃除、洗濯など日々の生活がサポートされる環境が整っているため、安心感を得られるでしょう。
日常生活の支援が提供されるだけでなく、医療や介護の専門スタッフが常駐している施設もあります。
施設内には共用スペースが設けられており、アクティビティを通じて、心身の健康を維持も可能です。
さらに、希望に応じて個別のケアプランが作成されるため、各人の状態やニーズにあわせたケアを受けられるのも特徴です。
関連記事:サービス付き高齢者向け住宅の問題点とは?失敗しない選び方も解説
認知症グループホーム
認知症グループホームは、認知症の症状がある方が少人数で共同生活を送る施設です。
認知症グループホームでは、専門のスタッフが24時間体制でサポートし、日常生活の支援を行います。利用者一人ひとりの状態やニーズに応じたケアプランを作成し、個別対応を心がけているのが特徴です。
また我が家で生活しているような居心地を提供するために、居住者は少人数のグループで生活するため、家庭での生活に近い方式でおこなわれます。
たとえば日々の活動だけでなく、レクリエーションを通じて、認知機能の維持や向上を目的にしています。
食事や入浴、排泄の介助などはもちろん、個別のサポートが受けられるだけでなく、認知症に特化した知識を持ったスタッフが適切に対応する介護施設です。
関連記事:グループホームとは?入居条件や老人ホームとの違いを簡単に解説
有料老人ホーム
有料老人ホームは、介護や医療のサポートが必要な高齢者の方に、日常生活を安心して過ごせる環境を提供する介護施設です。
大きく分けると「介護付き」「健康型」「住宅型」3タイプがあるため、ニーズにあわせた福祉サービスを受けられます。
有料老人ホームには、看護師や介護スタッフが24時間常駐しており、薬の管理や体調の急変に迅速に対応できる体制が整っています。
また有料老人ホームは、通常の居住環境とは異なり、認知症の症状が進行しても安心して生活できるように設計されているのが特徴です。
認知症の進行している方には「介護付き」、まだ自立している方には「住宅型」のように、選択の幅があるため、ケアマネジャーと相談しながら決めていきましょう。
関連記事:住宅型有料老人ホームとは?主なサービス内容や必要な料金をわかりやすく解説!
レビー小体型認知症の方に一人暮らししてもらうべき?お悩みの方はいいケアネットへ!【まとめ】

レビー小体型認知症の方が一人暮らしを続けることには多くの課題があります。
症状の進行に伴い、日常生活の中での安全性や健康管理が難しくなるためです。
一人暮らしでも安心した生活が送れるよう、バリアフリー化に改修したり照明の改善など、生活環境を整えるのもおすすめの支援策です。
レビー小体型認知症の症状が進行し、一人暮らしが困難と感じた場合、介護施設の利用も視野に入れましょう。
家族や専門家と相談しながら地域の支援サービスや介護施設の情報を集めていくのが大切です。
まずは、信頼できる相談窓口や地域包括支援センターなどに問い合わせて、必要なサポートを受けましょう。
なお、いいケアネットではレビー小体型認知症の方が一人暮らしをするのが限界に感じる前でも「入居無料相談」を受け付けております。
レビー小体型認知症の進行に応じた適切な介護施設を把握したい方も含め、気軽にご相談ください。
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。