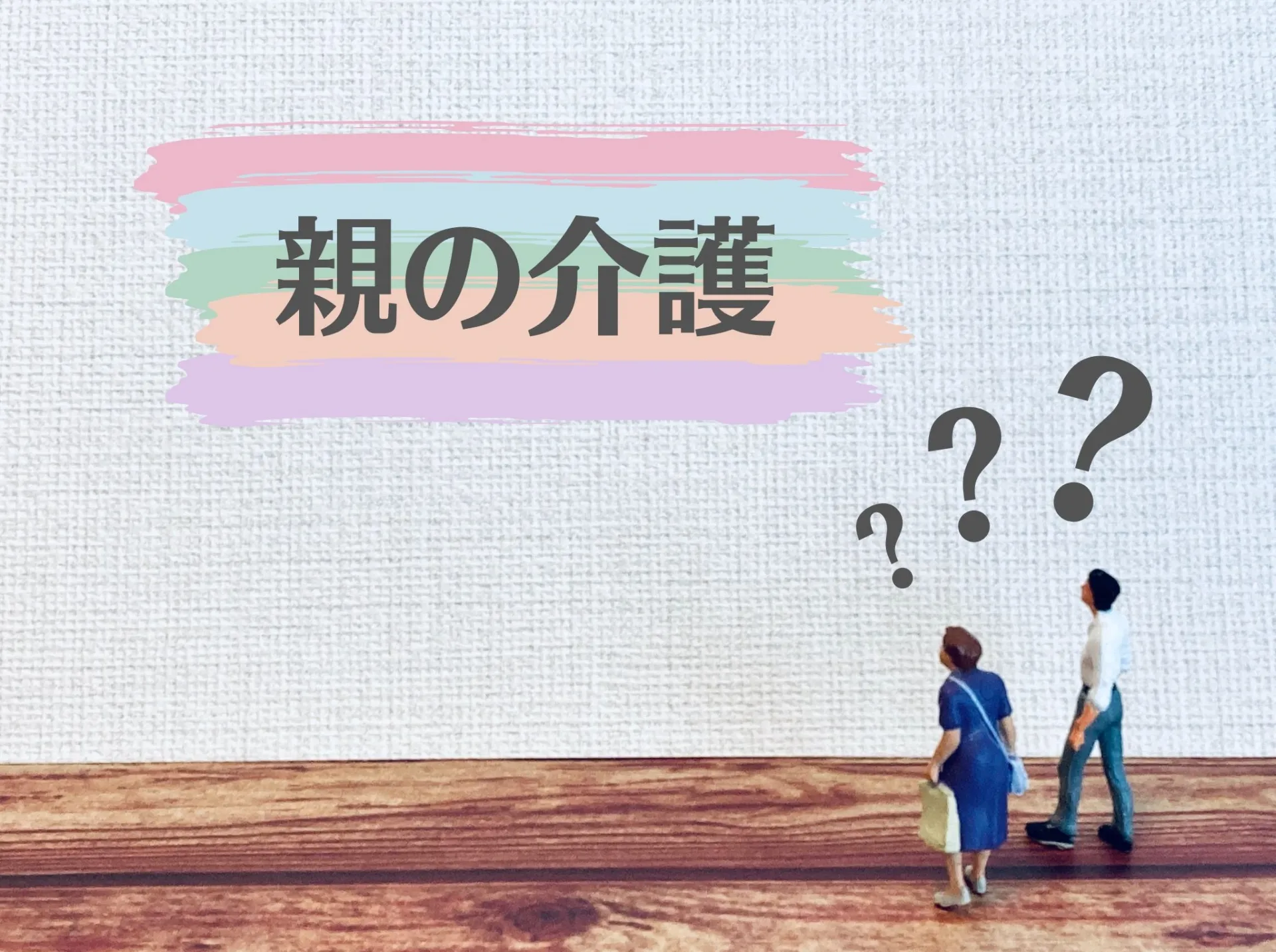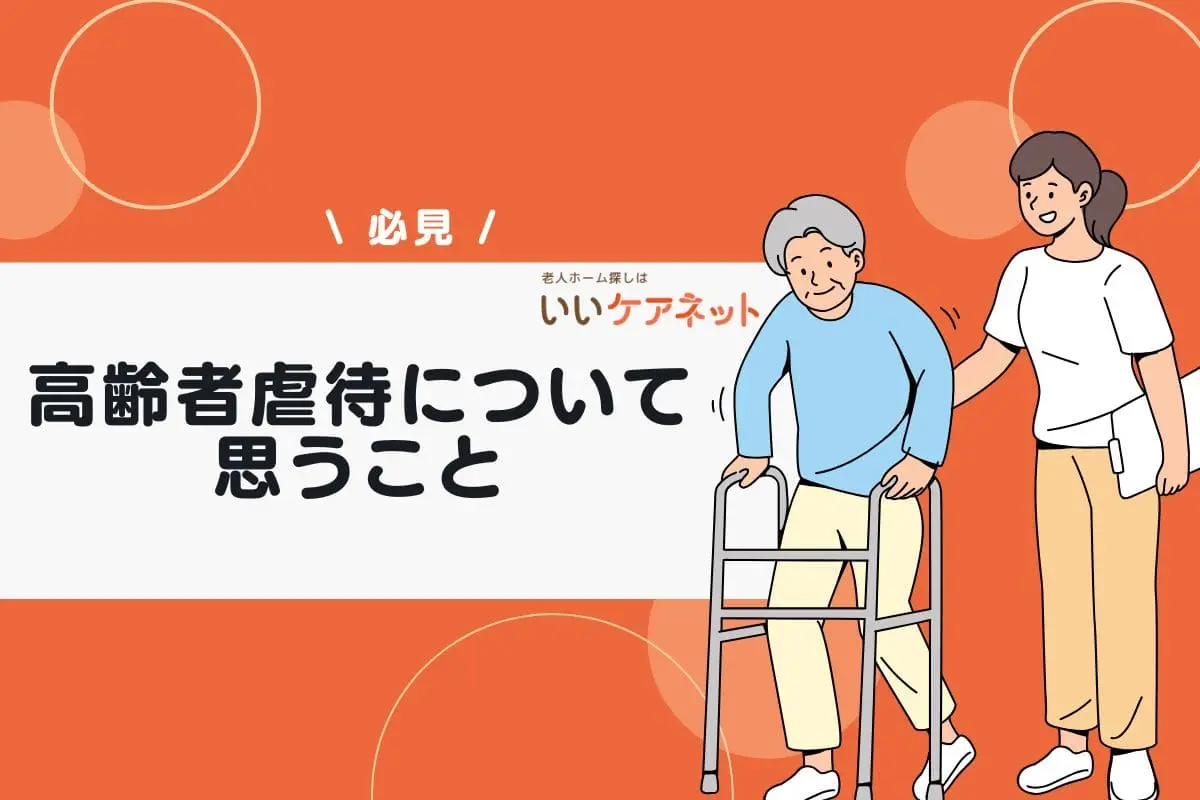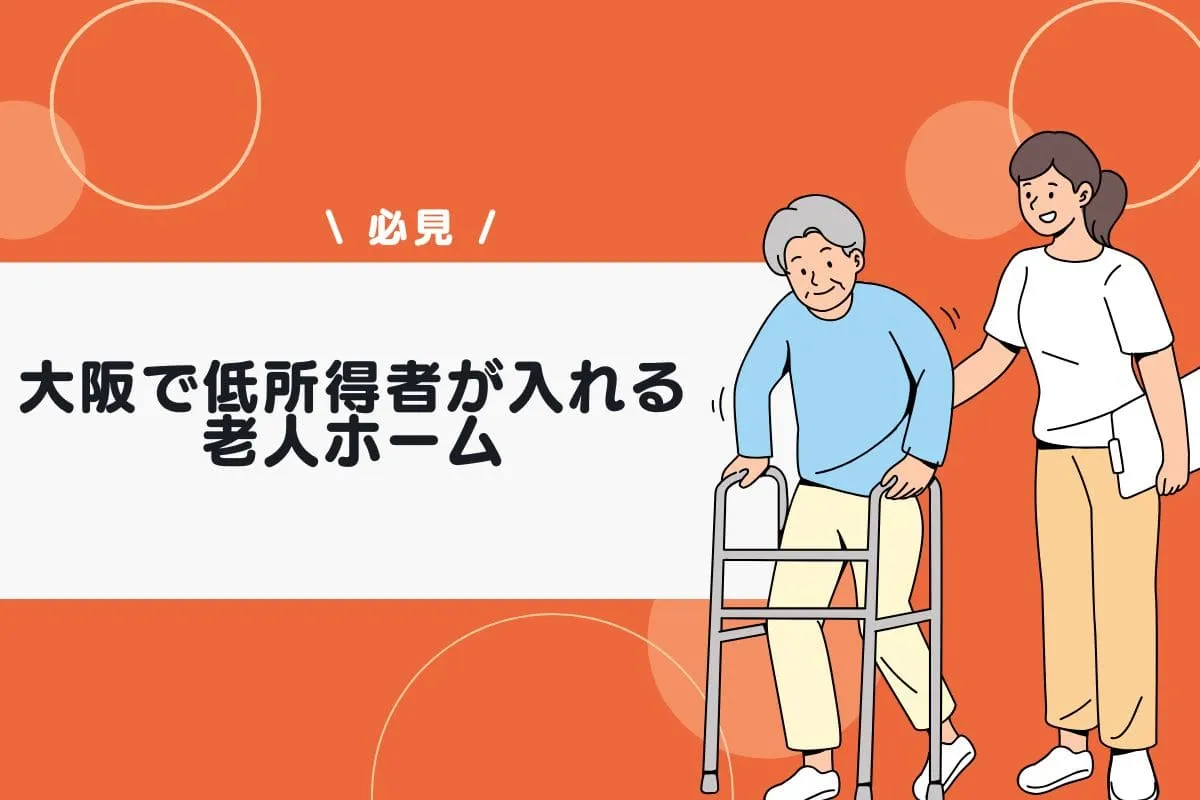「親が食事中にむせる回数が増えた」
「在宅介護なので何か予防策が知りたい……」など、悩んでいませんか。
高齢者がむせるのを予防するには、食事の工夫や姿勢の改善などの方法があげられます。
そこで本記事では、高齢者がむせるのを予防する方法を網羅的に解説します。
高齢者の在宅介護をしている方に注目してもらいたい「嚥下障害」について、発症の原因や症状も取り上げているので、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
高齢者がむせるのを予防する方法

高齢者がむせるのを予防するには、以下の方法を講じるのがおすすめです。
- 飲み込みにくい食品の提供を避ける
- 飲み込みやすい食事を提供する
- むせにくい姿勢で食事をしてもらう
- ゆっくり食べてもらう
- 食事前の体操をしてもらう
すべての予防策を講じなくても、いずれかを実施できるよう試してみてください。
予防策1.飲み込みにくい食品の提供を避ける
高齢者がむせるのを予防するためには、飲み込みにくい食品の提供を避けるのが重要です。
飲み込みにくい食品とは、硬いものや粘り気のあるもの、細かい粒状のものなど、喉に詰まりやすい特性を持つ食品です。
具体的には以下の食品が一例になります。
- ステーキのような硬い肉
- パンの耳
- ナッツ類
- クラッカー
- ドライフルーツなど
高齢者の多くは、加齢に伴って嚥下(えんげ)機能が低下するため、上記のような食品を避けると、むせるリスクを大幅に減少できます。
また調理法の工夫として、硬い肉は薄くスライスするか柔らかく煮込む、もしくは細かい粒状の食品にとろみをつけるなども試してみてください。
予防策2.飲み込みやすい食事を提供する
高齢者がむせることなく安全に食事を楽しむためには、飲み込みやすい食事の提供も重要です。
飲み込みやすい食事とは、柔らかく調理された食材やペースト状にした食事が該当します。
たとえば以下の調理方法があげられます。
- 野菜は煮込んで柔らかくする
- 肉は細かく刻むかミンチにする
- 魚は骨を取り除き柔らかく焼く
- 食材にとろみをつける
上記を含め、嚥下機能に問題があると感じる場合は、専門家に相談し、適切な食事形態を聞いてみましょう。
予防策3.むせにくい姿勢で食事をしてもらう
高齢者が食事中にむせるのを予防するためには、正しい姿勢を保つのも重要です。
とくに背筋を伸ばし、椅子に深く腰掛ける姿勢を心がけましょう。
むせにくい姿勢は、気道と食道の流れを良くし、食べ物が喉をスムーズに通過するのを助けます。
また、食事中に頭を少し前に傾けると、食べ物が重力によって自然に喉の方向に流れるのを助け、気管に入るのを予防できます。
家族や介護者が食事を手伝う場合は、高齢者の表情や動きをよく観察し、姿勢が崩れていないかを確認するのが大切です。
予防策4.ゆっくり食べてもらう
高齢者が食事中にむせるのを予防するためには、食事をゆっくりと摂ってもらうのも重要です。
速く食べると、無意識に大きな口で食べ物を取り込み、噛む回数が減った結果、飲み込みが不十分になるのです。
高齢者には食事中に十分な時間をかけて、一口ごとにしっかりと噛んでから飲み込むよう促しましょう。
少量ずつ口に運び、次の一口を口に入れる前に完全に飲み込む習慣をつけるのも効果的です。
また、高齢者が食事をする環境にも注目しましょう。テレビやラジオなどの音があると集中力が削がれやすく、急いで食べてしまう可能性があります。
さらに、食事中の会話も大切ですが、話すのに夢中になりすぎると、食べ物が喉に詰まりやすくなります。
家族や介護者が食事のペースを見守り、適切なタイミングで声をかけると、むせるリスクを抑えられるので意識してみましょう。
予防策5.食事前の体操をしてもらう
食事前に「嚥下体操」とも呼ばれている体操をすると、高齢者がむせるのを予防する有効な方法の1つになります。
高齢者がむせるのを予防する嚥下体操の一例は、以下の通りです。
| 運動名 | 方法 |
| 首の運動 | ・首を左右に3回ずつ傾ける。
・左右に大きく一回ずつ回す。 ・腹式呼吸とともに行う。 |
| 肩の運動 | ・両肩を上げて一度止め、力を抜いて落とす。
・上記の動作を3回繰り返す。 ・肩を上げるときに息を吸い、落とすときに吐く。 |
| 上体の運動 | ・上半身の力を抜き、左右に大きくゆっくり倒す。
・左右各3回行う。 |
| 口の運動 | ・唇を閉じ、ほっぺたを膨らませる。
・その後、すぼめる。 ・上記の動作を2〜3回繰り返す。 |
| 舌の運動 | ・口を横に大きく開け、舌を出して引っ込める。
・上記の動作を2〜3回繰り返す。 ・舌を左右の口角に2〜3回ずつつける。 |
| 声の運動 | ・「パパパ、タタタ、ラララ」と大きな声で発声する。
・その後、ゆっくりと腹式呼吸を行う。 |
上記の嚥下体操を「首の運動」から「声の運動」までをステップ式で実施してから水をコップ一杯分飲むのが、おすすめの方法です。
以下の記事では、動画付きで嚥下訓練の1つ「パタカラ体操」について解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:嚥下訓練のパタカラ体操とは?効果や目的・具体的なやり方を解説
【高齢者向け】むせるのを予防するトレーニング法一覧
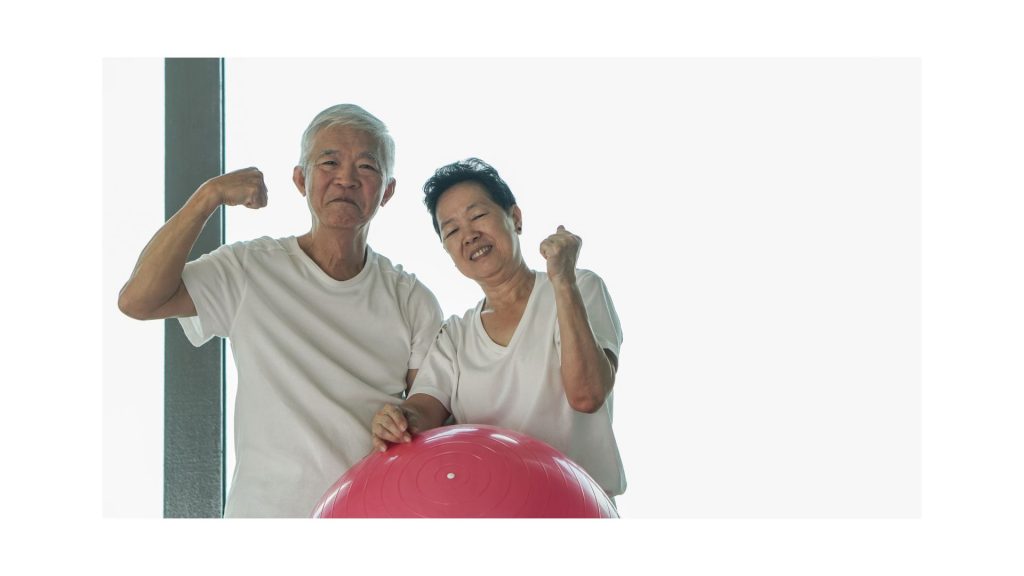
高齢者がむせるのを事前に対策するためには、嚥下機能を強化するトレーニングを実施するのがおすすめです。
以下に、効果的なトレーニング法をいくつか紹介します。
| 練習方法 | 説明 |
| 嚥下体操 | 首や喉を柔らかくし、飲み込みをスムーズにする体操。首のストレッチや口の開閉運動を取り入れる。 |
| 声を出す練習 | 喉の筋力を鍛えるために「アー」「イー」「ウー」など母音を発音し、飲み込み力を強化する。 |
| 嚥下反射の練習 | 少量の水を飲み込み、嚥下反射を鍛える。徐々に量を増やしていく。 |
| ガーグリング(うがい) | うがいで喉の筋肉を刺激する。唾液分泌を促し、口を清潔に保つ。 |
| 呼吸法のトレーニング | 深呼吸や腹式呼吸で喉と横隔膜を鍛え、呼吸と飲み込みの調和を図る。 |
上記のトレーニングを日常生活に取り入れると、高齢者がむせる状態を予防でき、食事を楽しめるようになります。
家族や介護者も一緒に無理なく、毎日少しずつ行うのが大切です。
そもそも高齢者がむせる原因とは

高齢者がむせる原因は、主に加齢による身体機能の低下が原因です。
加齢とともに、喉や食道の筋肉が弱くなり、食べ物や飲み物がスムーズに喉を通過しにくくなります。
さらに、高齢者は口腔内の感覚が鈍くなるケースもあり、飲み込みのタイミングが判断しにくくなるため、むせる事態になるのです。
また、唾液の分泌量が減少する原因の1つです。
唾液は食べ物を滑らかにする役割を果たしており、唾液の分泌が減ると食べ物が喉を通過しにくくなるため、むせる可能性が高まります。
関連記事:高齢者が食べられないときに食欲を回復する方法!食欲不振の原因や対策法を解説
むせる高齢者が把握しておきたい嚥下障害とは
高齢者がむせる際に注意しておきたい「嚥下機能」が低下すると「嚥下障害」の状態を指すようになります。
食事を摂ろうとすると、むせるため食事の楽しみが減るだけでなく、十分に栄養補給ができなくなってしまうのです。
高齢者がむせるのを予防するだけでなく、嚥下障害につながる事態にならないよう、具体的な発症の原因と症状を解説していきます。
嚥下障害が発症する原因
高齢者における嚥下障害は咽頭や食道の筋肉が弱くなり、飲み込み動作が円滑におこなわれにくくなるのが主な原因です。
また、脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患も原因で、嚥下機能を制御する神経に影響を及ぼし、嚥下障害を引き起こす可能性があります。
さらに、心理的要因や食事の環境も考慮すべきです。
ストレスや不安は、嚥下機能に影響を与えるケースがあり、食事中の不適切な姿勢や急いだ食事も嚥下障害を悪化させる可能性があります。
つまり、嚥下障害の予防や対策には、上記の原因を総合的に理解し適切なケアをおこなうのが重要になるのです。
嚥下障害の症状
嚥下障害の症状は、本記事で題材にしている「食事中にむせること」が主な症状です。
嚥下障害は食べ物や飲み物が誤って気管に入り、咳反射を引き起こします。
むせるのが頻繁になると、食事の際に恐怖感や不安を感じてしまい、食事を避ける原因にもなります。
また、嚥下障害のある方は、食事を摂るのが苦痛になり、食欲の低下や体重減少につながる場合もあるため注意が必要です。
嚥下障害の初期症状を見逃さず、早期に専門医の診断を受けましょう。適切な診断と治療により、嚥下障害の症状を管理し、生活の質を高められます。
高齢者がむせるのを予防するには家族の支援が不可欠!【まとめ】

高齢者がむせるのを予防するには、飲み込みにくい食品を避け、飲み込みやすい食事を提供、食事時の姿勢を意識するのがポイントです。
また、食事をゆっくり楽しんだり食事前の簡単な体操を取り入れたりするのも効果的です。仮に今、高齢者がむせる症状が続く場合、専門医に相談するのをおすすめします。
健康的で楽しい食生活を目指し、一緒にサポートしていきましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
高齢者がむせるのを予防する上でよくある質問
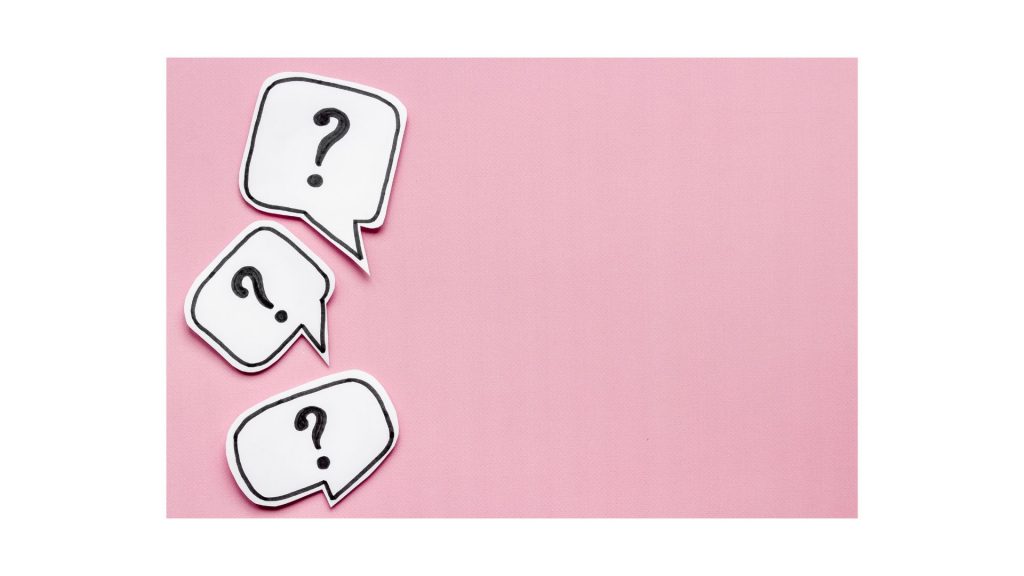
むせにくい食事を作るには何を意識すれば良いの?
むせにくい食事を作るためには、食材の選び方や調理法に工夫が重要です。
まず、固い食材や大きな塊のままの食品は喉に引っかかりやすいため、そのまま提供するのは避けましょう。
食材は細かく刻んだり、柔らかく煮込んだりして、口の中で簡単に崩れるように調理するのがおすすめです。
また、乾燥した食品は喉に引っかかりやすいため、水分を適度に含ませたり、スープやソースを添えたりするのも1つの方法です。
さらに、食事の温度にも注意を払い、熱すぎたり冷たすぎたりしないように心がけましょう。
むせにくい食事を作るためには、食材の選定、調理法、提供の仕方などの側面からの配慮が大切です。
以下の記事では、咀しゃくしやすい介護食を作る方法や考え方について触れているので、あわせてご覧ください。
関連記事:咀しゃくしやすい介護食を作るには?考え方のポイントと基本の作り方
むせるだけでなく食べこぼしも起きるのはなぜ?
高齢者がむせるだけでなく、食べこぼしも起きる背景には、嚥下機能の低下が大きく関与しています。
嚥下機能が低下すると、食べ物や飲み物をうまく飲み込むのが難しく、結果として口から食べ物がこぼれ出る回数が増えるのです。
むせるのを予防するのと同様、食事中の姿勢だけでなく、使用する食器にも注意しましょう。
高齢者は手の力が弱まり、手先の器用さも低下する傾向にあります。
長年使っている食器であっても、食器が重いと食べこぼしが起きる可能性が高まるので注意してください。
関連記事:大人の食べこぼしの原因は?嚥下(えんげ)障害の症状や対処法も解説
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。