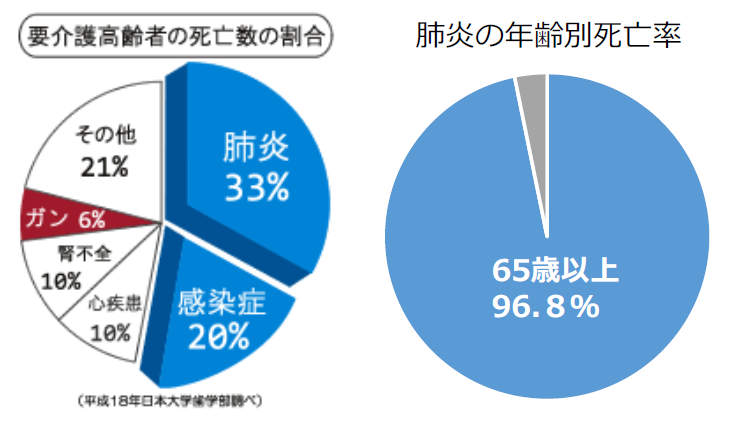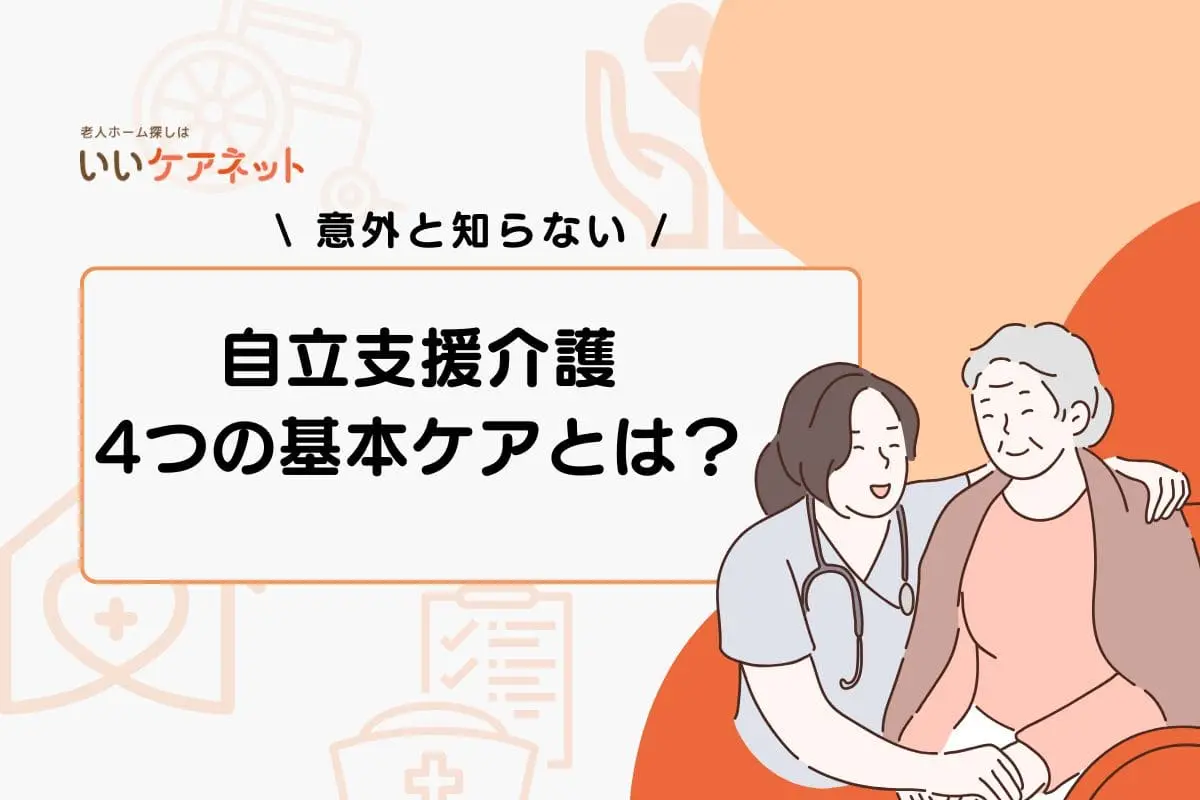「母が近所で徘徊して…」
「何度注意しても、他人の家に入ってしまう…」
認知症の家族がいる方なら、このような近隣トラブルに心を痛めた経験があるのではないでしょうか。
認知症の症状は進行すると、本人に悪意がなくても近隣に迷惑をかける場合があります。
注意しても繰り返されるため、家族は孤立感や罪悪感に苦しみがちです。
この記事では、認知症による近所トラブルの具体例と効果的な対処法を解説します。
対策から専門機関の活用まで、バランスの取れた支援方法を知ることで、一人で抱え込まずにトラブルを未然に防げます。
あなたと大切な家族が穏やかに暮らせるよう、一緒に対応策を考えていきましょう。
認知症で近所に迷惑をかけるトラブル例
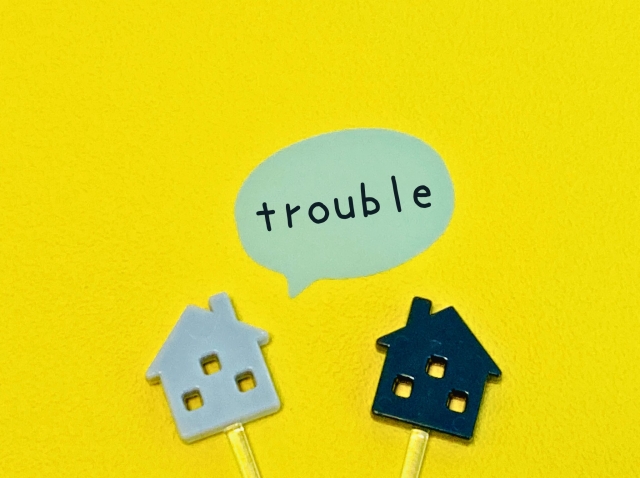
認知症が進行すると、本人に悪意がなくても近隣の方々に迷惑をかけてしまうケースがあります。
トラブル例は以下の5つです。
- 地域行事の予定を忘れる
- 近所を徘徊する
- 間違って他の人の家に入る
- 被害妄想や作り話で攻撃的な態度をとる
- 警察に通報される
事前に理解を深め、トラブルを未然に防ぐために役立てましょう。
関連記事:数分前のことを忘れるのは認知症の初期症状?チェック項目や対処法を解説
地域行事の予定を忘れる
認知症による記憶障害で、町内会や老人会などの地域行事の予定を忘れてしまうケースがあります。
カレンダーに予定を書いておいても見落としたり、待ち合わせに遅れたり、欠席したりすることで周囲に迷惑をかけてしまいます。
繰り返し同じことを忘れると「約束を守れない人」という印象を与えかねません。
認知症の症状を理解していない地域の方々からすれば、単なる無責任な行動と映ることもあります。
家族の方は、本人の状態を周囲に伝え、理解を求めることが大切です。
近所を徘徊する
認知症の方には、目的なく歩き回る「徘徊」の症状が見られる場合があります。
これは脳の見当識障害により「家に帰りたい」と思って外出しても道に迷ったり、昔の家を探し回ったりするためです。
徘徊によって発生する問題は、以下のとおりです。
- 深夜の徘徊が近隣住民に不安を与える
- 大声を出す、歌を歌うなどの騒音トラブルになる
- 不適切な服装で外出し、通報されることがある
- 交通事故に巻き込まれる危険性がある
本人には理由があっても、周囲には理解されにくく、家族が責任を問われるケースもあるでしょう。
徘徊の兆候に早めに気づき、地域や専門機関と連携しながら見守る体制を整える必要があります。
関連記事:認知症による徘徊を放置するとどうなる?理由や対策ポイントを解説!
間違って他の人の家に入る
認知症による見当識障害が進むと、自分がどこにいるのか分からなくなり、他人の家を自分の家と間違えて入ってしまうケースがあります。
昔住んでいた家や親の家と思い込んで入ろうとするケースも少なくありません。
また「この土地は自分のものだ」という思い込みから、隣家とトラブルになるケースもあります。
本人には侵入する意識はなく、単に「自分の家に帰る」という当然の行動をしているのですが、第三者からすれば不法侵入と変わりません。
このような行動が見られたら、一人で抱え込まず専門機関に相談しましょう。
被害妄想や作り話で攻撃的な態度をとる
実際にはない出来事を事実と思い込む「被害妄想」は、認知症の代表的な症状の1つです。
「財布を盗まれた」「悪口を言われている」など、近隣の方を疑う内容が多く、本人にとっては真実であるため強く主張します。
被害妄想などは本人の不安や孤独感、自尊心の低下から生じているケースが多く、近隣の方にとっては心理的な負担となります。
暴言がひどくなりそうな場合は、ケアマネジャーや医師に早めに相談するとよいでしょう。
警察に通報される
認知症が進行すると、徘徊や妄想により警察に通報されるケースがあります。
通報される内容は以下のとおりです。
- 徘徊中に道に迷い、行方不明者として通報される
- 他人の敷地や家に誤って入り、不審者として通報される
- 被害妄想から「財布を盗まれた」と騒ぎ、警察に通報される
警察が介入すると、本人も家族も大きなストレスになるでしょう。
認知症の方は理解できない状況に置かれることで混乱し、さらに症状が悪化する可能性もあります。
地域や警察と情報を共有しておくことが、誤解や通報による混乱を防ぐポイントです。
認知症で近所迷惑をかけないための対応策

認知症の症状による近隣トラブルを防ぐには、適切な対策が必要です。
以下では、近隣トラブルを防ぐための対策5つを紹介します。
- 玄関や門扉に鍵やセンサーを設置する
- 近所の人に事情を伝える
- 専門家や行政に相談する
- 介護サービスを利用する
- 施設入居を検討する
対策と支援のバランスを意識して、地域と連携しながら取り組んでいきましょう。
玄関や門扉に鍵やセンサーを設置する
認知症の方の徘徊による近隣トラブルを防ぐには、以下のような住環境の工夫が効果的です。
| 項目 | 効果 | 特徴 |
| 玄関ドア開閉センサー | ドアの開閉を検知し、スマホに通知を送ることで外出時の対応を可能にする | ・家族に通知が届く ・外出の事前対応が可能 ・高齢者や認知症患者の見守りに役立つ |
| 複雑な鍵 | 本人が開けるのが難しい構造の鍵に変更することで、外出を防止できる | ・セキュリティ向上 ・認知症患者の徘徊防止に効果的 |
| GPS内蔵靴 | 靴にGPS機能を搭載し、外出時に履くことで居場所を把握できる | ・外出時に必ず履くため効果 ・違和感なく使用可能 ・居場所を迅速に確認可能 |
| GPSキーホルダー型グッズ | 小型で携帯しやすいGPS機能付きキーホルダーで、位置情報を把握する | ・コンパクトで持ち運びやすい ・ 違和感なく使用可能 ・紛失防止にも役立つ |
ただし、設備や道具による対策だけでは、不安や怒りを引き起こす場合があります。
定期的な外出の機会を設けるなど、環境づくりもバランスよく取り入れましょう。
近所の人に事情を伝える
認知症の方と良好に暮らすためにも、近隣の方々に正直に事情を伝えましょう。
認知症と知っていれば行動への理解が得やすく、徘徊時に連絡してもらえる可能性が高まります。
伝え方としては、日頃から付き合いのある近隣の方に、認知症の症状や対応方法について具体的に説明するのが効果的です。
近隣の商店や本人がよく立ち寄る場所にも事情を説明しておくと、外出時のトラブルを未然に防げます。
認知症は誰にでも起こりうる病気であることを伝え、協力を得られる関係づくりを目指しましょう。
専門家や行政に相談する
近隣トラブルが増えてきたら、一人で抱え込まず専門家や行政のサポートを活用しましょう。
専門家や行政サポートの内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 地域包括支援センター | ・認知症を含む高齢者に関する総合相談窓口 ・介護保険の申請や各種サービスの紹介を行う |
| 認知症地域支援推進員 | ・認知症の人と家族を支援する専門職 ・医療機関や介護サービスとの連携を図り、適切な支援を提供する |
地域包括支援センターは認知症に関する総合相談窓口で、介護保険の申請から各種サービスの紹介まで幅広い支援が受けられます。
認知症地域支援推進員は、認知症の人と家族を支援するための専門職で全市町村に配置されています。
医療機関や介護サービスとの連携を図り、適切な支援につなげてくれる心強い味方です。
介護サービスを利用する
認知症の症状による近隣トラブルを防ぐには、介護保険サービスの活用が効果的です。
たとえば、デイサービスを利用すれば、以下のような効果があります。
- 日中の見守りを確保できる
- 運動や他者との交流できる
- 生活リズムが整い、徘徊の減少が期待できる
家族が仕事で日中不在になる場合は、訪問介護サービスを組み合わせることで、一日を通した見守り体制が構築できます。
専門スタッフの定期的な訪問は、本人の状態変化の早期発見にもつながります。
ケアマネジャーと相談し、本人と家族の状況に合わせた最適なケアプランを作成し、無理のない在宅生活を継続できる環境を整えましょう。
施設入居を検討する
在宅での対応が難しくなってきたら、施設入居という選択肢も視野に入れましょう。
近隣とのトラブルが頻発したり、家族の疲労が限界に達したりした場合は、お互いのためにも環境の変化を検討する時期かもしれません。
認知症の方が入居できる施設は以下のとおりです。
- グループホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 特別養護老人ホーム
認知症の症状や介護度によって最適な施設は異なるため、早めに情報収集が大切です。
施設入居はすぐに決断しなくても、将来の選択肢として準備しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
可能であれば症状が軽いうちに本人の意向を確認し、施設見学に一緒に行くなどして、将来の備えをしておくとよいでしょう。
将来の選択肢として施設入居を検討する際は、早めの情報収集が大切です。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設を多数掲載している「いいケアネット」では、ご本人の状態や希望に合った施設を無料で探せます。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:認知症で施設に入居するタイミングは?利用できる施設や選び方も解説
認知症による近所迷惑のトラブル例を知って対策しよう【まとめ】

認知症による近隣トラブルは、本人に悪意がなくても起こりうる現象です。
記憶障害による地域行事の予定忘れや見当識障害からくる徘徊・他人の家への侵入など、警察に通報されるケースもあります。
これらの問題に対処するには、環境整備と地域の理解が欠かせません。
センサーやGPS機器の活用が効果的ですが、近隣の方々に事前に状況を説明し協力を求めることも不可欠です。
また、地域包括支援センターなどの専門機関への相談や、デイサービスなどの介護保険サービスの利用も検討しましょう。状況によっては施設入居という選択肢も視野に入れる必要があります。
介護施設を多数掲載している「いいケアネット」では、無料で認知症の方に適した施設を探せます。早めの情報収集と対策で、本人と家族双方の負担を軽減し、地域との良好な関係を維持しましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。