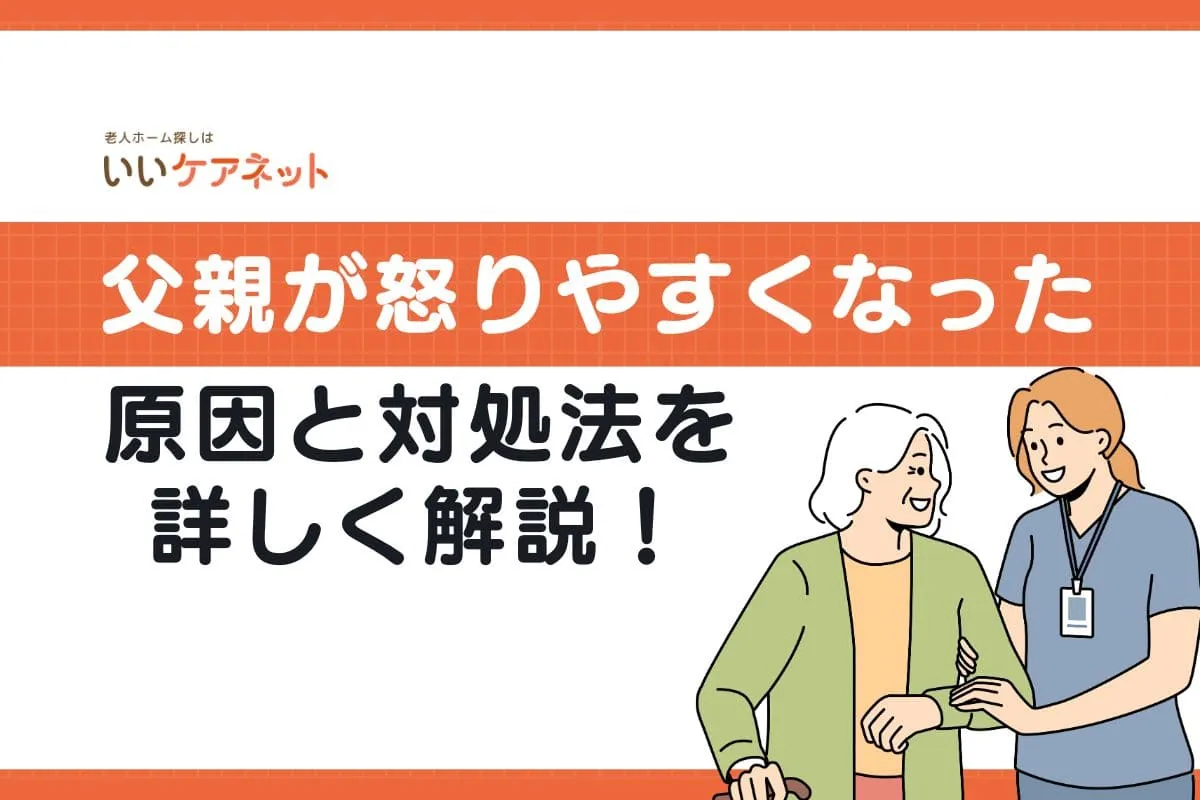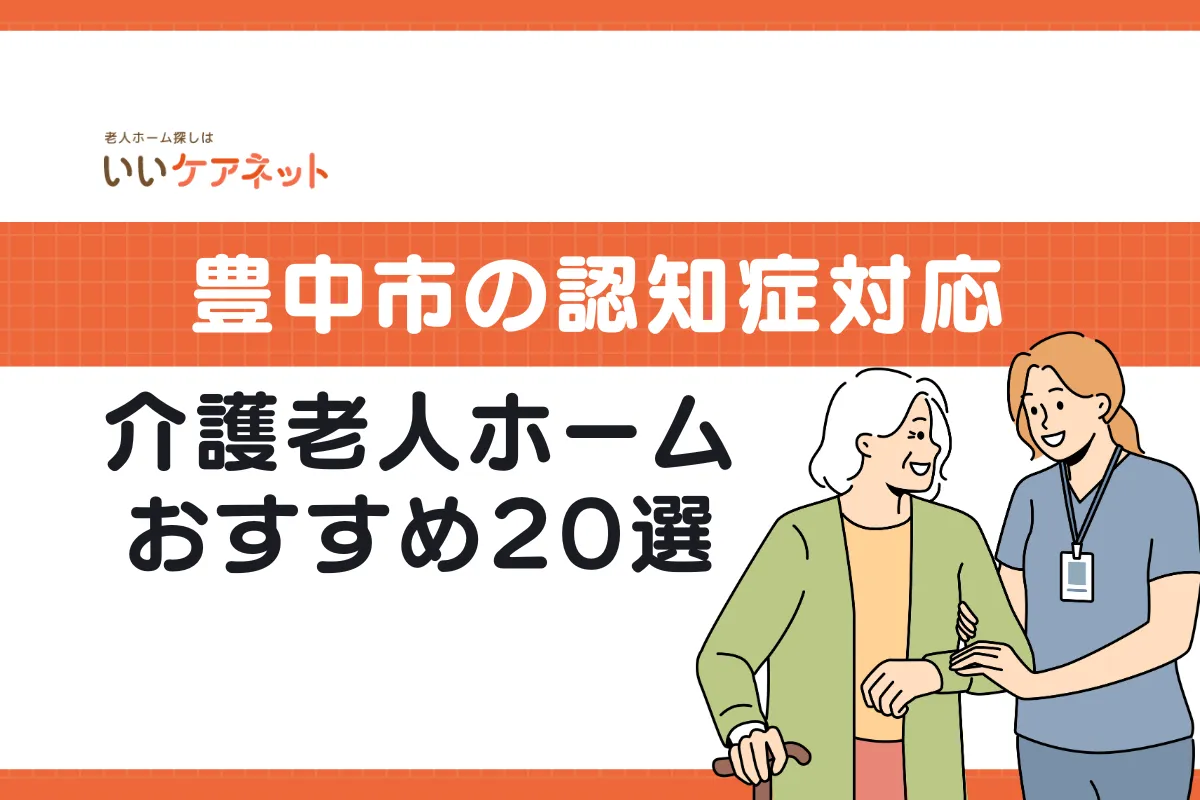介護サービスを利用するうえでは、欠かせないのが「ケアプラン」です。
ですが「そもそもケアプランって何?」「どうやって作るの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
ケアプランは、本人や家族の希望に沿って、必要なサービスを無理なく、効果的に使えるようにするための計画です。
きちんと理解して活用すれば、より快適で安心な介護生活につながります。
本記事では、ケアプランの基本から活用のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。
ケアプランとはわかりやすく言うと「介護サービスの利用計画」のこと

ケアプランとは、要介護または要支援認定を受けた人が、介護保険サービスを効果的に利用するために作成する計画書です。
要介護や要支援の認定を受けた人が、自分に合った介護保険サービスを上手に利用できるように作ります。
利用者一人ひとりの心身状態や生活環境、家族の状況などを考慮し、心身状態にあった介護サービスを適切に組み込む点が特徴です。
ケアプランは、生活の質を上げるための“設計図”のような役割も果たします。
サービスを並べるだけではなく「その人らしい暮らし」ができるよう、工夫されているのがポイントです。
なお、介護施設を利用する際にはケアプラン作成が義務化されています。
要介護度が上がるほど必要なサービス内容が多岐にわたるため、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談するか、地域包括支援センターなどに依頼して作成を進めるのが重要です。
関連記事:介護保険制度とは?~仕組みやサービスの種類・制度の最新情報まで解説~
ケアプラン作成による3つのメリット

ケアプランを作成すると、3つのメリットが発生します。
- 介護保険サービスが効率的に利用できる
- 体調や介護状況に応じた見直し・変更ができる
- 本人や家族の不安が軽減される
それぞれ、どのようなメリットなのかを解説していきます。
介護保険サービスが効率的に利用できる
ケアプランを作っておくと「どのサービスを、どれくらい使うか」が、はっきりわかるようになります。とくに重複や抜け漏れが減り、各専門職と連携しやすい状況になります。
利用者と家族の安心感にもつながり、手続き面でも負担が軽減されるケースは多くなるでしょう。
一方で、ケアプランを作成していない場合は、介護サービスの利用費をいったん全額支払わなければいけません。事務手続きも複雑になるため、利用のハードルが高くなります。
ケアプランをあらかじめ作成しておけば、サービス利用時の自己負担は原則として1〜3割です。経済的な負担が軽くなり、安心してサービスを利用できます。
体調や介護状況に応じた見直し・変更ができる
ケアプランは、一度作って終わりではありません。人の体調や生活環境は、日々変わるため、ケアマネジャーが定期的にモニタリングをおこない、状況に応じてプランを見直します。
症状が良くなればサービスを減らしたり、悪化した場合は必要なサービスを増やしたりできます。
こうした柔軟な対応ができるのは、ケアプランがあるからこそです。現在の状態に合ったサービスが受けられるため、生活の質を保ちやすくなります。
関連記事:地域密着型サービス9種類とは?サービス一覧と利用までの流れを解説
本人や家族の不安が軽減される
ケアプランには「誰が」「何を」「いつ」「どのように」支援してくれるのかが、はっきりと書かれています。
利用者や家族にとって介護支援の全体像がわかると、先が見えやすくなり、不安も軽くなるのが、ケアプラン作成ならではのメリットです。
困ったときは、ケアマネジャーに相談できる体制が整っているため、安心して介護に向き合えます。
関連記事:介護が辛い時どうする?【PART3】~介護疲れを軽減させるためには~
ケアプラン作成5ステップ

ケアプランは「アセスメント(事前の聞き取り・情報収集)」から始まり「評価と見直し」までの5ステップを踏む必要があります。
一連の流れを通して、利用者にとって最適なケアプランが作られるように、仕組み化されているのが特徴です。
作成には、次の5つのステップがあります。
- ステップ1:アセスメント(課題分析)
- ステップ2:ケアプラン原案の作成
- ステップ3:会議にてプランの検証
- ステップ4:サービス利用開始とモニタリング
- ステップ5:モニタリング結果の評価と見直し
ステップ1:アセスメント(課題分析)
アセスメントとは、利用者の現状をふまえて、今どのような環境にあるのかを把握し、困りごとや解決すべき課題を明らかにする段階です。
アセスメントは、利用者の多くの個人情報(プライバシー)に関わるため、介護サービスの申請が受理されたあとにおこなわれます。
ケアマネジャーなどが利用者の家を訪問し、ご本人やご家族と面談するのが通例です。
生活や体の状態に関する情報を集めて分析・評価し、日常生活の中で解決すべき課題(ニーズ)をはっきりさせていきます。
ステップ2:ケアプラン原案の作成
続いては、アセスメント結果にもとづき、必要なサービスを検討します。長期目標と短期目標を設定しながら、利用頻度やサービスの種類を組み合わせます。原案作成の際には、利用者はもちろん、家族とも十分な話し合いが重要です。
ステップ3:サービス担当者会議にてプランの検証
サービス担当者会議とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が開く会議です。
この会議では、利用者の状況に関する情報を、ケアプランの原案に関わるサービス担当者たちと共有します。
会議をおこなうのは、ケアプラン原案について各担当者から専門的なフィードバックにともなう改善が目的です。
参加者は利用者本人や家族、主治医、ケアプランに関わるサービス事業者の担当者のほか、必要に応じて近隣の住民やボランティアなども含まれる場合があります。
サービス担当者会議は、新たに介護サービスを利用する場合や、要介護度の更新時、要介護状態が変わったときなどには必ず開かれるくらい重要度が高いステップです。
また、会議の中で出された意見をもとに、ケアプラン原案が修正されるケースもあります。修正後のプランは、利用者の同意を得た時点で正式に確定します。
ステップ4:サービス利用開始とモニタリング
決定したケアプランに沿って、サービスの利用がスタートします。ケアマネジャーは定期的に状況を確認し、自立支援が進んでいるかを把握し、問題が発生した際には、再調整が可能です。
ステップ5:モニタリング結果の評価と見直し
一定期間経過後に、サービスの効果や目標達成度を評価し、必要に応じてアセスメントからやり直し、新しい目標を設定します。こうした継続的な見直しによって、サービス利用者の生活の質を高めるのがモニタリングの目的です。
ケアプランで押さえるべき3つのポイント

ケアプランを知るうえでは、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
- ケアプランは状況に応じて3パターンから作られる
- ケアプランでは長期・短期の目標を設定して生活を支援する
- ケアプランはセルフでも作れる
それぞれ、具体的にどのような意味合いなのかを解説します。
状況に応じて3パターンから作られる
ケアプランは大きく3つの種類に分かれます。
- 在宅介護向けの居宅サービス計画書:自宅で暮らしながら、自宅を拠点に介護サービスを利用するために作成されるケアプラン
- 介護施設入所向けの施設サービス計画書:介護施設に入所し、介護サービスを受けるために作成されるケアプラン
- 要支援認定1・2の方向け介護予防サービス計画書:要支援の状態から要介護へ進行するのを防ぐため、介護予防サービスを利用する要支援認定1・2の方を対象としたケアプラン
介護予防サービス計画書は要支援認定1・2の方を対象としていますが、居宅サービス計画書と施設サービス計画書は要介護度を問わず利用可能です。
長期目標と短期目標を定めて生活を支援する
ケアプランでは、必ず長期目標と短期目標を設定します。
長期目標は「いつまでに、どの程度まで生活課題を解決するか」を示すもので、短期目標は長期目標達成に向けた段階的な目標です。
期間は原則として開始時期と終了時期を記載し、定期的に達成状況を評価して必要に応じて見直しをおこなわなければいけません。また、期間を設定する際は、要介護認定の有効期間も考慮します。
セルフでケアプランを作成できる
「居宅サービス計画(ケアプラン)」は、ケアマネジャーに作成を依頼すれば作成してもらえます。ただし、希望すれば利用者本人や家族でも作成可能です。
ケアマネージャーに依頼せず自分たちだけで作る場合は、以下のような手間がかかるため、ケアプランの作成依頼をするのが一般的です。
- 自治体関係部署への書類の提出
- サービス事業所との連絡・調整など
- すべての手続きを利用者や家族が自分でおこなわなければならない
専門家であるケアマネジャーのサポートを受け、利用者の状態や希望に合った、より的確で使いやすいプランを立てやすくなります。
安心して介護サービスを利用するためにも、プロの力を借りると大きな助けになります。
ケアプランをうまく活用してスムーズに介護サービスを利用しよう【まとめ】

ケアプランは、要介護・要支援の方が、自分に合った介護サービスを無理なく、効果的に使うための計画書です。
利用者の状態や希望に応じて内容が柔軟に調整され、生活の質を保つサポートをしてくれます。
定期的な見直しや目標設定も含まれており、安心してサービスを継続するための大切な仕組みです。
家族が介護サービスを利用するようになったら、ケアプランや専門家の助言をうまく活用して介護サービスを適切に利用しましょう。
ケアプランに関してよくある質問

最後に、ケアプランに関してよくある質問に回答します。
ケアプラン作成で大切なことは何ですか?
利用者本位の視点が大切です。利用者の意思や人格を尊重し、最適なサービスを選択する必要があります。
複数の事業者やサービス内容を提示し、選定理由を丁寧に説明して同意を得るステップも重要です。最終的には利用者の立場に立った計画になっているかを確認しましょう。
介護計画書とケアプランの違いは何ですか?
ケアプランは、要介護者が適切な介護保険サービスを受けられるよう、ケアマネジャーが作成する全体的な利用方針です。
心身の状態や希望に基づいて、複数のサービスを総合的に調整します。
一方、介護計画書はそのケアプランに基づき、各事業者が実際のサービス内容を具体的にまとめた個別の実施計画です。
たとえば「週○回の訪問介護」とケアプランにあれば、訪問介護事業所がその内容に沿った計画書を作成し、サービスを提供します。
ケアプランを作成しないとどうなる?
ケアプランを作成しないと、介護施設への入所ができません。
さらに、ケアプランなしでサービスを利用すると、費用が全額自己負担になり大きな経済的負担が発生します。手続きも煩雑になるため、早めの作成が得策です。
ケアプラン料は自己負担ですか?
ケアプランの作成にかかる費用は、すべて介護保険でまかなわれます。そのため、利用者の自己負担はありません。
ケアマネジャーへの相談や作成サポートも無料で受けられます。利用者自身がセルフケアプランを作成する場合でも、同様に作成費用は発生しません。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。