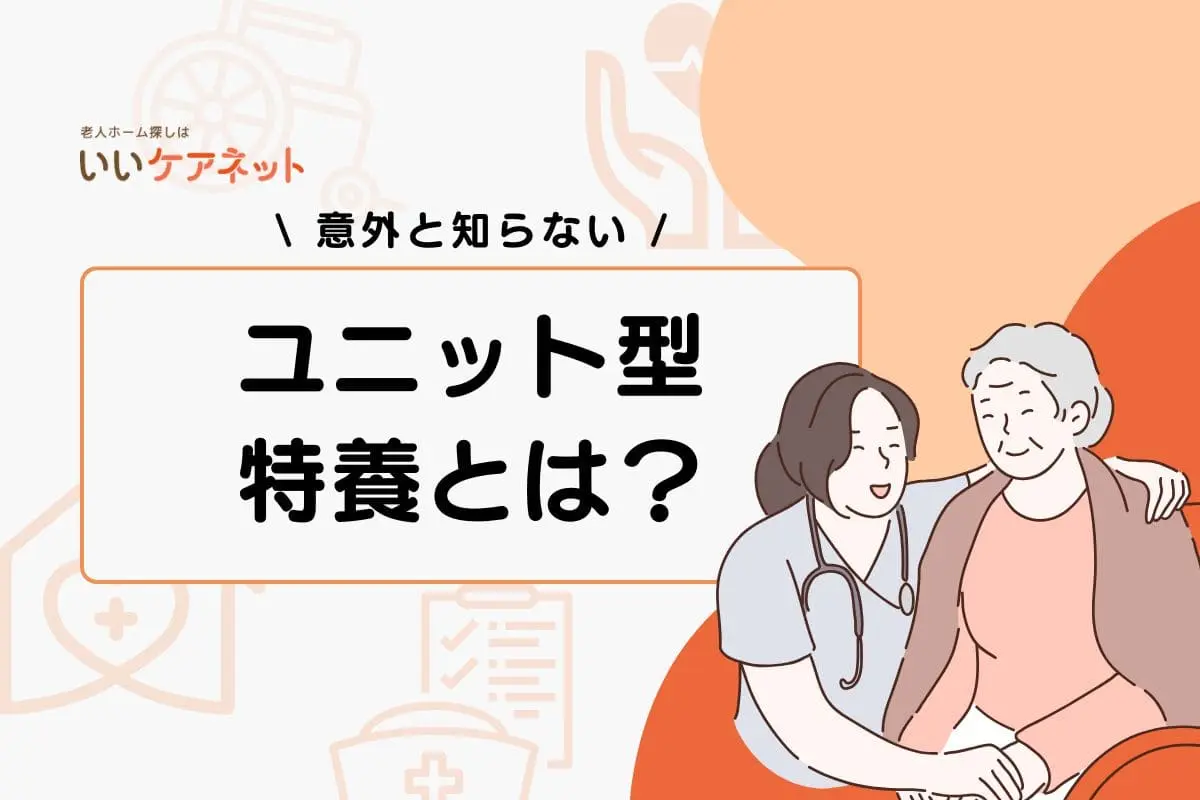「まだら認知症」とは、日や時間帯によって症状の現れ方に波がある状態を指す言葉です。これは正式な病名ではなく、主に脳血管性認知症に見られる特徴的な症状の出方を表現する通称として用いられています。
その原因は脳梗塞や脳出血といった脳の血管障害にあり、脳の損傷部位によってできることとできないことが混在するため、「まだら」な状態が生まれます。
「まだら認知症」は正式な病名ではない?その意味を解説

「まだら認知症」という名称は、正式な医学用語や病名ではありません。認知症の一つの種類である「脳血管性認知症」において、症状が変動しやすい特徴を指して使われる通称です。
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害によって脳の神経細胞が壊れ、認知機能が低下する病気です。脳の損傷を受けていない部分は正常に機能するため、できることとできないことが混在し、日によって状態が変わる「まだら」な症状が見られます。この特徴的な症状の現れ方から、まだら認知症と呼ばれるようになりました。
まだら認知症で現れる代表的な症状

まだら認知症、すなわち脳血管性認知症では、認知機能の低下だけでなく、感情のコントロールや身体機能にも様々な症状が現れます。初期段階から症状に波が見られるのが特徴で、できる時とできない時の差がはっきりしています。
記憶障害は部分的に起こり、判断力や計画を立てる能力の低下、感情の起伏が激しくなる感情失禁、手足の麻痺などが代表的な症状です。また、意識が混濁する「せん妄」が夜間に見られることもあります。
判断力や計画を立てる能力が低下する
まだら認知症では、物事を順序立てて考え、計画的に実行する能力が低下することがあります。これは実行機能障害と呼ばれ、例えば料理の手順が分からなくなったり、効率よく家事をこなせなくなったりする形で現れます。
なぜこのような症状が起こるかというと、脳の中でも思考や判断、行動のコントロールを担う前頭葉が、脳血管障害によって損傷を受けるためです。以前は当たり前にできていた作業に時間がかかったり、途中で投げ出してしまったりする変化は、日常生活の中で周囲が気づきやすい症状の一つと言えるでしょう。
感情の起伏が激しくなり、抑えられなくなる
脳血管性認知症の症状として、感情のコントロールが難しくなる「感情失禁」が見られることがあります。これは、本人の意思とは関係なく、ささいなきっかけで急に泣き出したり、怒り出したり、大笑いしたりする状態を指します。
感情の起伏が非常に激しく、周囲から見ると些細なことに過剰に反応しているように映ります。
この症状は、脳の感情を司る神経回路が脳血管障害によってダメージを受けることで生じます。人格が変わってしまったように感じられるかもしれませんが、病気による症状の一つとして理解することが重要です。
身体に麻痺やしびれといった障害が起こる
まだら認知症の原因となる脳血管障害は、脳の運動機能を司る部分にも影響を及ぼすため、身体的な症状を伴うことが少なくありません。具体的には、片方の手足に麻痺やしびれが起きる、歩行が不安定になり転びやすくなる、呂律が回りにくくなる、食べ物がうまく飲み込めなくなる嚥下障害などが現れます。
これらの運動障害は、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の初期にはあまり見られない特徴です。そのため、認知機能の低下とともに身体症状がある場合は、脳血管性認知症が疑われ、頭部CTやMRIなどの画像検査による詳しい診断が必要となります。
記憶障害が部分的に見られる
まだら認知症における記憶障害は、体験したこと全体を忘れてしまうアルツハイマー型認知症とは異なり、覚えていることと忘れていることが混在する「まだら」な状態が特徴です。例えば、昨日の出来事は覚えていないのに、数日前のことは鮮明に記憶しているといったことが起こります。
このため、介護する側からは「わざと忘れたふりをしているのではないか」と誤解されやすいですが、これも脳の損傷部位による症状の一つです。物忘れを指摘したり問い詰めたりするのではなく、病気の症状として理解し、本人の自尊心を傷つけない対応が求められます。
なぜ症状に「まだら」な状態が生まれるのか?

日によってできることとできないことが変わる「まだら」な状態は、本人だけでなく、介護する家族にとっても戸戸惑いの原因となります。しかし、この症状の波には、脳の損傷状態や血流の変化といった医学的な理由が存在します。
なぜ症状がまだらに現れるのか、そのメカニズムを理解することは、本人の状態を正しく把握し、適切な介護を行う上で非常に重要です。主に「脳の損傷部位が限定的であること」と「日々の脳血流量の変化」という二つの要因が関わっています。
脳の損傷部位が限定的であるため
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血によって脳の一部の神経細胞が壊れることで発症します。このとき、ダメージを受けた脳の部位が担っていた機能は失われますが、損傷を免れた他の部分は正常に働き続けます。
そのため、失われた機能と保たれている機能が混在し、できることとできないことがはっきりと分かれる「まだら」な状態が生じるのです。例えば、言語機能は保たれているのに注意力が著しく低下する、といったケースが見られます。
脳血管障害が再発し、新たに別の部位が損傷すると、症状は段階的に進行していきます。
日々の脳血流量が変化するため
人の脳の血流量は、体調や時間帯、活動内容などによって常に変動しています。
脳血管性認知症の方は、動脈硬化などによって脳の血管が狭くなったり詰まったりしているため、健常な人よりも脳血流量の変化による影響を受けやすい状態にあります。
血流が比較的安定している時は脳の働きも良く、症状が落ち着いて見えますが、血圧の変動などで血流が低下すると、脳の機能が一時的に落ち込み、症状が悪化したように感じられます。この日内変動も、症状に波が生じる「まだら」な状態の大きな原因の一つであり、脳血流を安定させる治療が重要となります。
まだら認知症と脳血管性認知症の密接な関係

これまで述べてきたように、「まだら認知症」は正式な病名ではなく、脳血管性認知症に見られる特徴的な症状の現れ方を指す通称です。したがって、この二つは別の病気ではなく、表裏一体の関係にあります。
脳梗塞や脳出血といった脳血管障害が原因となって発症するのが「脳血管性認知症」であり、その結果として、記憶や能力が部分的に保たれ、日によって症状が変動する「まだら」な状態が見られるのです。
そのため、まだら認知症へのアプローチは、すなわち脳血管性認知症の治療やケアを指します。具体的には、原因となる脳血管障害の再発予防を目的とした薬物治療や、残された機能の維持・向上を目指すリハビリなどが中心となります。
アルツハイマー型認知症との見分け方

まだら認知症(脳血管性認知症)とアルツハイマー型認知症は、症状の現れ方や進行の仕方に違いがあります。脳血管性認知症は、脳卒中などをきっかけに急に発症し、再発を繰り返すことで段階的に症状が進行します。
一方、アルツハイマー型は発症時期が特定できず、ゆっくりと進行するのが特徴です。記憶障害においても、脳血管性は「まだら」な物忘れであるのに対し、アルツハイマー型は体験全体を忘れてしまいます。
また、脳血管性認知症は男性に多く、比較的若い年齢でも発症しやすい傾向があり、初期から手足の麻痺などの身体症状を伴うことが多い点も鑑別のポイントです。
まだら認知症の方と向き合うための3つのポイント

日や時間帯によって症状が大きく変動するまだら認知症(脳血管性認知症)の方への対応は、周囲の家族を戸惑わせることがあります。
「昨日できたことが今日はできない」という状況に、苛立ちや不安を感じるかもしれません。
しかし、こうした症状の波は病気によるものであり、本人が最もつらく、混乱していることを理解する必要があります。本人と穏やかに向き合い、適切なサポートを提供するために、いくつかのポイントを押さえておくことが助けとなります。
症状に波があることを前提に接する
まだら認知症の方と接する上で最も重要なのは、「症状に波があるのが当たり前」と理解することです。
昨日までできていたことが急にできなくなっても、それは本人が怠けているわけでも、わざとやらないわけでもありません。病気の症状として受け止め、できないことを責めたり、無理強いしたりするのは避けましょう。
その時々の本人の状態をよく観察し、できることは本人に任せて自尊心を尊重し、難しいようであればさりげなく手助けをするなど、柔軟な対応が求められます。症状の変動を前提とすることで、介護する側の精神的な負担も軽減されます。
日々の様子を観察し記録をつける
症状の変動パターンを把握するために、日々の様子を具体的に記録することは非常に有効です。いつ、どのような状況で症状が良くなるのか、あるいは悪化するのかを書き留めておくと、本人の状態を客観的に理解しやすくなります。
例えば、時間帯、体調、睡眠時間、食事内容、その日の出来事などを記録することで、症状の変動に関わる要因が見えてくることがあります。また、この記録は、医師やケアマネージャーに本人の状態を正確に伝えるための貴重な情報源となり、より適切な治療方針やケアプランの立案に役立ちます。
介護サービスなどを活用し環境を整備する
介護は家族だけで抱え込まず、専門家や社会資源を積極的に活用することが大切です。
デイサービスや訪問介護といった介護保険サービスを利用することで、本人は専門的なケアを受けながら他者と交流する機会を持つことができます。これは、残された機能の維持や社会的な孤立の防止につながります。
同時に、介護する家族が休息を取る時間(レスパイト)を確保でき、心身の負担軽減にもなります。また、麻痺や歩行障害がある場合は、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修を行い、本人が安全に過ごせる環境を整備することも重要です。
症状の進行を緩やかにするための治療アプローチ

まだら認知症、すなわち脳血管性認知症の治療は、一度失われた脳細胞を元に戻すことではなく、残された脳の機能を最大限に維持し、症状の悪化を防ぐことを目的とします。そのためには、新たな脳血管障害の発生を防ぐことが最も重要です。
治療の柱となるのは、脳血管障害の危険因子を管理する「薬物治療」と、心身の機能維持を目指す「リハビリテーション」であり、この二つを並行して進めていくことが症状の安定と進行の抑制につながります。
脳血管障害の再発を防ぐ薬物治療
脳血管性認知症の進行を抑える上で最も重要なのは、原因である脳梗塞や脳出血の再発を防ぐことです。
そのために、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のコントロールが不可欠となります。医師の診断に基づき、血圧を下げる降圧薬、血液を固まりにくくする抗血小板薬や抗凝固薬などが処方されます。
これらの薬を継続的に服用し、血圧や血糖値などを適切な範囲に保つことが、新たな脳血管障害のリスクを低減させます。また、意欲の低下やうつ状態、興奮といった行動・心理症状(BPSD)に対しては、症状を緩和するための薬が用いられることもあります。
認知機能や身体機能の維持を目的としたリハビリ
薬物治療と並行して、リハビリテーションを行うことも症状の進行抑制に有効です。リハビリの目的は、残された機能を維持・向上させ、できるだけ自立した生活を長く続けることにあります。
理学療法士による歩行訓練や筋力トレーニング、作業療法士による着替えや入浴といった日常生活動作の訓練、言語聴覚士による会話や飲み込みの訓練など、専門家による多角的なアプローチが行われます。
また、計算ドリルやパズル、昔の出来事を思い出す回想法といった認知リハビリテーションは、認知機能の低下を緩やかにする効果が期待されます。
まだら認知症を予防するために今日からできる生活習慣

まだら認知症、すなわち脳血管性認知症を予防するためには、その原因となる脳梗塞や脳出血といった脳血管障害のリスクを減らすことが最も重要です。これは、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を予防・管理することとほぼ同じ意味を持ちます。
特別なことを始める必要はなく、日々の食事や運動といった生活習慣を見直し、改善していくことが、脳の健康を守るための最も効果的な方法です。今日からでも始められる具体的な予防策を実践しましょう。
高血圧をコントロールする
高血圧は、脳血管障害の最大の危険因子です。血圧が高い状態が続くと、血管の壁に常に強い圧力がかかり、血管が硬くもろくなる動脈硬化が進行します。
動脈硬化が進んだ血管は、詰まって脳梗塞を引き起こしたり、破れて脳出血を起こしたりするリスクが非常に高くなります。そのため、血圧を正常な範囲に保つことは、脳血管性認知症の予防において極めて重要です。
家庭で定期的に血圧を測定する習慣をつけ、塩分を控えた食事や適度な運動を心がけましょう。それでも血圧が高い場合は、医師に相談し、必要に応じて降圧薬による治療を受けることが大切です。
塩分や脂肪分を控えた食生活を心がける
食生活の改善は、生活習慣病予防の基本です。特に、塩分の過剰摂取は血圧を上昇させる大きな原因となるため、減塩を意識することが重要です。
漬物や干物、加工食品、麺類の汁などは塩分が多い傾向にあるため、摂取量に注意しましょう。だしや香辛料、香味野菜などをうまく利用すると、薄味でも美味しく食べられます。
また、肉の脂身やバターといった動物性脂肪の摂りすぎは、血液中の悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を促進します。野菜や果物、青魚などをバランス良く取り入れた食生活が、健康な血管の維持につながります。
ウォーキングなど適度な運動を続ける
定期的な運動は、血行を促進し、血圧や血糖値、コレステロール値を改善する効果があります。特に、ウォーキングや軽いジョギング、水泳といった有酸素運動は、無理なく続けやすく、生活習慣病の予防に効果的です。
運動をすることで、肥満の解消や血管の弾力性を保つことにもつながります。まずは「1日30分」「週に3日」など、自分に合った目標を立てて始めてみましょう。
運動は身体的な健康だけでなく、ストレス解消や気分のリフレッシュにも役立ち、総合的な健康増進に貢献します。継続することが最も重要なので、楽しみながら続けられる運動を見つけることがポイントです。
まとめ

「まだら認知症」とは、脳血管性認知症にみられる症状の変動性を表す通称であり、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害が原因で発症します。その特徴は、脳の損傷部位に応じて機能が部分的に保たれるため、できることとできないことが混在し、日々の脳血流量の変化によって症状に波が生じる点にあります。
主な症状には、まだらな記憶障害のほか、実行機能障害、感情失禁、身体の麻痺などが挙げられます。
治療の基本は、高血圧などの生活習慣病を管理し、脳血管障害の再発を防ぐことです。同様に、予防においても塩分や脂肪分を控えた食事、適度な運動といった健康的な生活習慣が鍵となります。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。