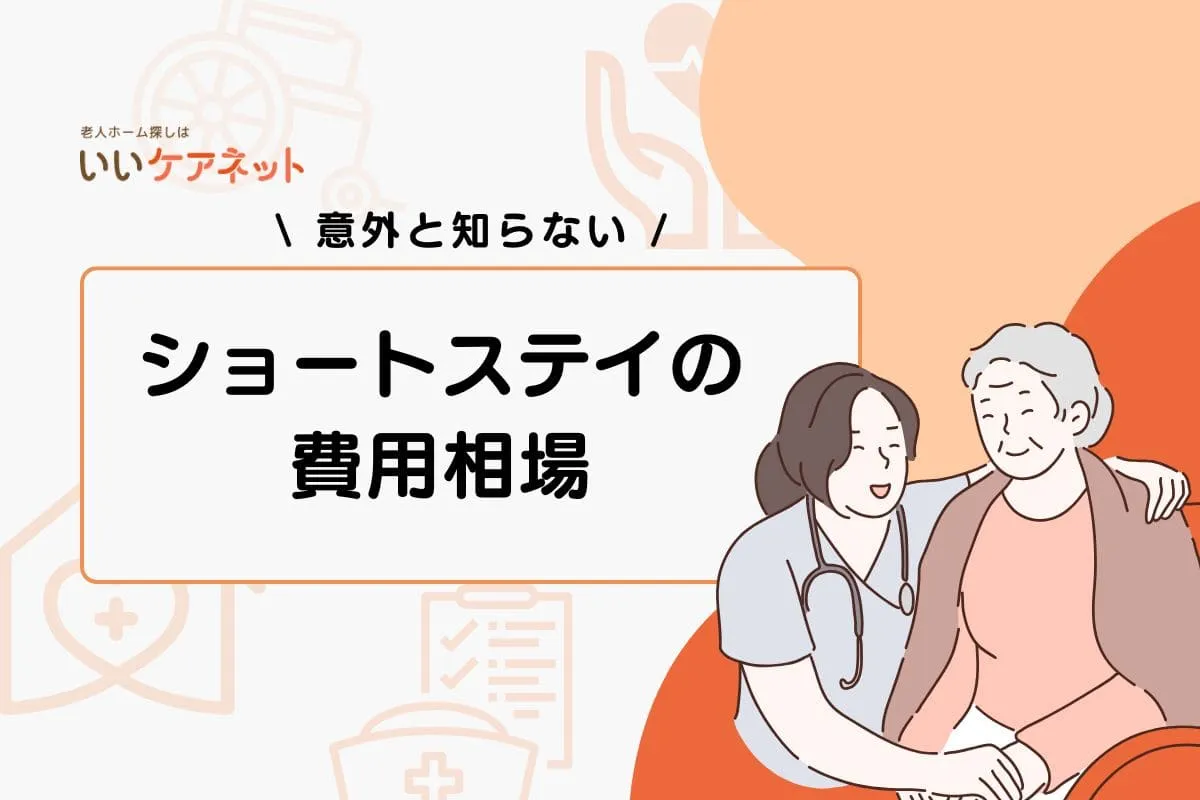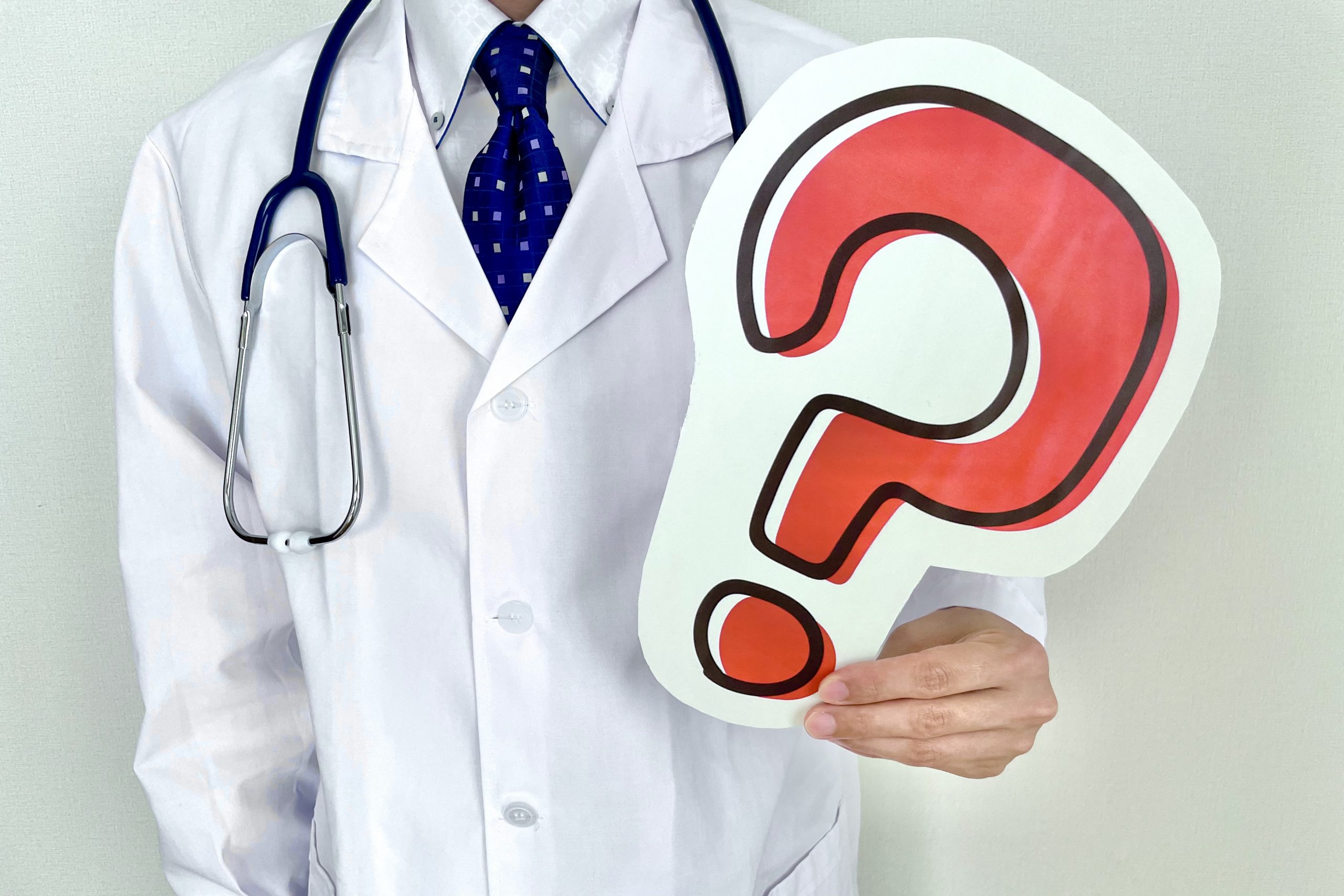ヒートショックは、寒い季節に多発する健康リスクであり、高齢者や生活習慣病を持つ人にとっては深刻な問題です。
本記事では、ヒートショックが起こるメカニズムや症状、なりやすい人の特徴を詳しく解説します。
また、ヒートショックを防ぐための対策や、病院に行くべき症状についても具体的に紹介します。
ヒートショックによる健康被害について深掘りしているので、ぜひ最後までご覧ください。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
ヒートショックとは
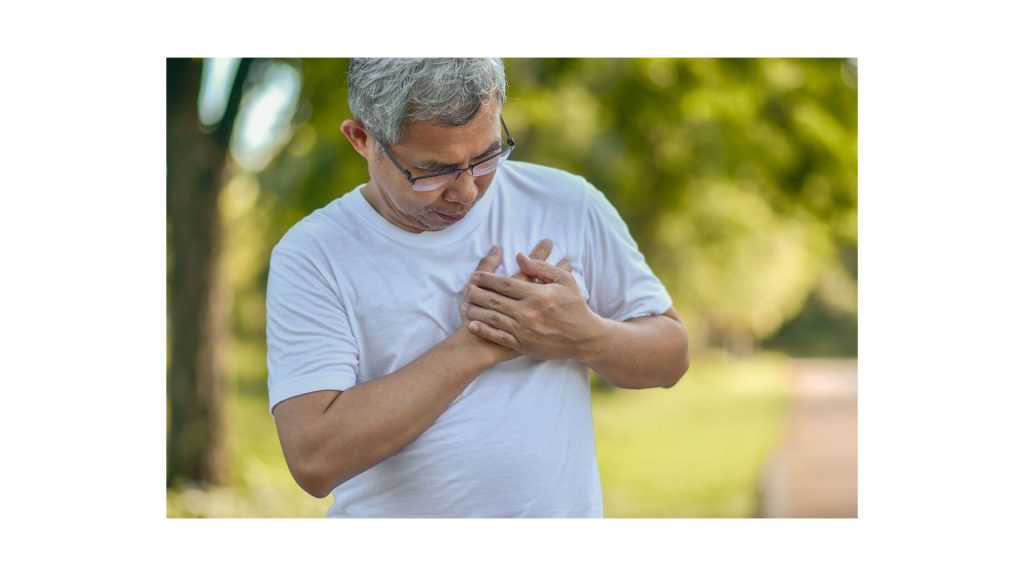
ヒートショックとは、急激かつ過剰な温度変化により体内の血圧が急激に変動し、健康に影響を及ぼす現象を指します。
とくに高齢者に多く見られ、家庭内での事故の一因ともなっているのが実情です。
実際に東京都健康長寿医療センターの研究でも、家庭内で起きる死亡事故の溺死や病死にヒートショックが含まれると推測しました。
東京都健康長寿医療センターでは、2011年内で約17,000人がヒートショックで死亡し、そのうち14,000人が高齢者であると考えたのです。
住宅内での温度管理が不十分である場合や、入浴時の温度差が大きい環境での発生が多いのが特徴です。
参考:東京都健康長寿医療センター「冬場の住居内の温度管理と健康について」
ヒートショックが起こるメカニズム
ヒートショックは血圧の低下後、熱い湯に浸かると体温がさらに上昇し、血圧が急激に上昇すると起こる現象です。
たとえば、寒い部屋から暖かい浴室に移動すると、急激な温度上昇により血管が急速に拡張し、一時的に血圧が低下します。
血圧の急上昇と急降下が、心臓や血管に大きな負担をかけ、場合によっては心筋梗塞や脳卒中を引き起こす原因となります。
とくに高齢者や心血管系に疾患を持つ人は、急激な血圧変化に対する適応力が低いため、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるのです。
ヒートショックの症状
ヒートショックは入浴時に多く見られ、主な症状があります。
- めまい
- 立ちくらみ
- ふらつき
- 動悸
- 息切れ
- 心筋梗塞
- 脳卒中
上記の症状は、脳への血流が一時的に不足するのが原因で、高齢者や持病を持つ人にとっては要注意です。
また、軽度な症状を放置しすぎると、心筋梗塞や脳卒中など重大な疾患を誘発する可能性もあります。
一見軽く見られがちなヒートショックですが、背後には深刻な健康リスクが潜んでいると把握しておきましょう。
ヒートショックになりやすい人の特徴

ここからはヒートショックになりやすい人の特徴について解説していきます。
日常生活を送る上で、注意すべき対象となるのかを詳しく見ていきましょう。
特徴1.高齢者に該当する人
高齢者は加齢に伴い、体温調節機能が低下するため、ヒートショックになりやすい特徴があります。
若い頃には無意識に対応できた温度変化や血管の収縮・拡張が、年齢を重ねるにつれ、スムーズにできなくなります。
とくに、浴室の急激な温度変化が発生しやすい場所では、血圧の急上昇や急降下が起こりやすいのです。
また、高齢者は自宅で1人の時間が長くなる傾向があり、すぐに助けを求められない状況もリスクを増大させます。
家族や介護者は、日常的に高齢者の体調や入浴習慣に注意を払う必要があります。
特徴2.生活習慣病持ちな人
生活習慣病を持つ人は、ヒートショックに対して注意が必要です。
高血圧や糖尿病、脂質異常症などの疾患を持つ人は、血管の健康に影響を与え、血流の制御がうまくいかなくなる可能性があるためです。
たとえば高血圧の人は、急激な温度変化により血圧が大きく変動しやすい特徴があります。
また、糖尿病の人は神経障害を伴うケースが多く、体温調節機能が低下している場合があるため、温度変化に対する反応が鈍くなります。
つまり生活習慣病を持つ人は、急激な温度変化に対する警戒反応が遅れ、ヒートショックの危険性が増すのです。
特徴3.一番風呂に入る人
単身世帯を含め、一番風呂に入る日が多い人もヒートショックになりやすい特徴として挙げられます。
一番風呂に入るのは、湯船の温度が最も高く、浴室全体がまだ温まっていないため、温度差が大きくなる特徴があります。
温度差の大きさが、ヒートショックを引き起こしやすい状況を作り出しているのです。
とくに冬場は、暖房が効いていない浴室内と外の冷たい空気の間で急激な温度変化が生じ、血圧が急上昇または急下降するリスクが高まります。
結果として心臓や血管に負担をかけ、場合によっては心筋梗塞や脳卒中の引き金となるのです。
一番風呂によるリスクを軽減するためには、入浴前に浴室を暖めておいたりシャワーで体を温めてから湯船に入ったりしましょう。
特徴4.サウナや熱い風呂が好きな人
サウナや熱い風呂が好きな人は、高温環境による血圧の変化が心臓や血管に大きな負担をかけ、ヒートショックを引き起こしやすいリスクがあります。
高温の環境に長時間いると、体は血管を拡張して体温を下げようとする一方で、冷たい空気に触れると急に収縮し、血圧が急上昇します。
とくに、サウナの後に冷水を浴びる習慣や、熱い風呂から急に出て寒い部屋に移動するのは、体に負担をかけてしまうのです。
急な温度変化は、心臓に負担がかかり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが増加するので注意しましょう。
特徴5.飲酒後に入浴する人
飲酒後に入浴するのは、アルコールは血管を拡張させる作用があるだけでなく、入浴も体温上昇により血管を拡張させるため注意が必要です。
血管の拡張が頻繁に起こる状態は、心臓や血管に大きな負担がかかり、寒暖差の激しい環境ではヒートショックを引き起こしやすくなるのです。
飲酒後は判断力も鈍るため、適切な水分補給や入浴時間の調整が難しく、さらなるリスクにつながります。
とくに高齢者や心臓に持病のある人は、意識障害や重篤な健康被害のリスクが高まります。
どうしても入浴が必要な場合は、入浴前には必ず十分な水分を摂り、ぬるめに温度を調整し、短時間で済ませるのがおすすめです。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
ヒートショックで病院に行くべき理由

ヒートショックは一時的な症状が多いため、一見すると軽く見られがちですが、病院に行くべき理由があります。
- 意識障害や脳卒中などのリスクがあるから
- 高齢者の死亡事故が多発しているから
上記の観点からヒートショックでも病院に行くべき理由があるため、少しでも気になる症状を感じた経験がある方は、ぜひ参考にしてください。
意識障害や脳卒中などのリスクがあるから
ヒートショックは、急激な温度変化が体に与える影響により、健康リスクを引き起こす可能性があります。
中でも注意が必要なのが、意識障害や脳卒中などの深刻な症状です。
急激な血圧の変動により、脳への血流が途絶えると、脳卒中を引き起こすリスクが高まるため、迅速な医療対応が求められます。
また意識障害は、脳への酸素供給が不十分になったときに発生するケースが多く、放置すると後遺症を残す可能性もあります。
とくに高齢者や生活習慣病を抱える人は、血管が脆弱になっているため、リスクがさらに高まるのです。
意識障害や脳卒中の症状が現れた場合、速やかに救急車を呼び、専門医による診断と治療を受けるのが不可欠です。
ヒートショックが疑われるケースでは、迷わず医療機関を受診するのをおすすめします。
高齢者の死亡事故が多発しているから
高齢者の死亡事故が多発している背景には、ヒートショックによる健康への影響が大きいのが実情です。
消費者庁の統計を見ても、65歳以上の人が溺死または溺水による事故のうち約8割が浴槽内の事故で、その約9割が家や居住施設内で起きています。
年齢による人数によると死亡者数5,072人中、4,750人が65歳以上の高齢者が浴室内で事故につながっているのです。
また、東京消防庁の調査結果でも、11月〜2月にかけての冬場に救急搬送された発生人数が多いのも明らかにしています。
夏場の8月と冬場の1月と比較すると約11倍もの差があるため、ヒートショックにかかわらず冬場には最善の注意が必要です。
ヒートショックを防ぐには対策が必須
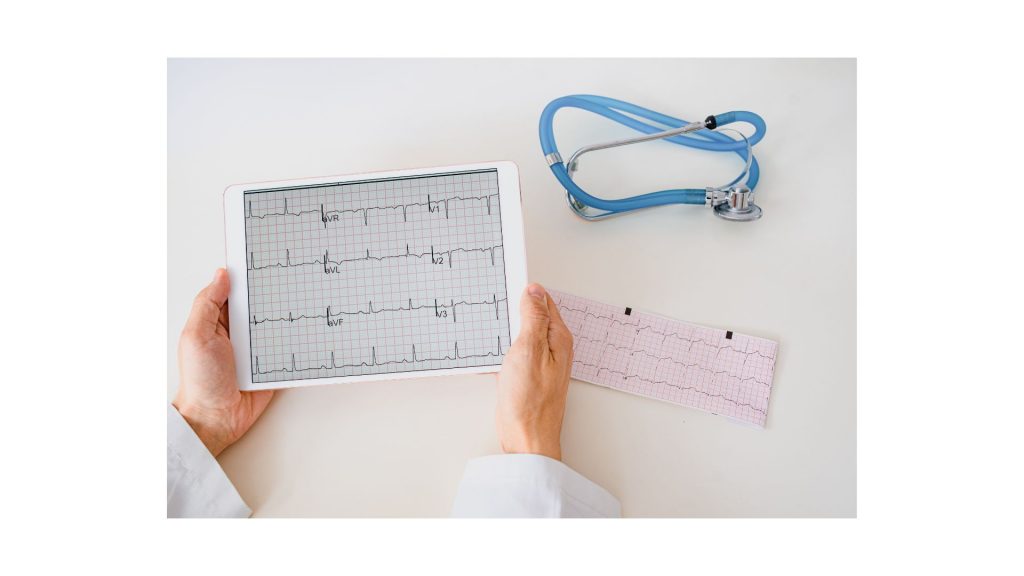
ヒートショックを防ぐためには、以下のような適切な対策が必須となります。
| 対策項目 | 説明 |
| 温度差の管理 | 浴室と脱衣所の温度差を小さくし、ヒーターや暖房器具で脱衣所を温める。 |
| 湯温の管理 | 浴槽の湯温を41℃以下に保つ。 |
| 入浴のタイミング | 一番風呂を避ける、もしくはシャワーで浴室内を温める。 |
| 水分補給 | 入浴前後に十分な水分補給をする。 |
| 高齢者への配慮 | 血圧変動に対する耐性が低い高齢者は家族と一緒に入浴するなどの配慮をする。 |
| 知識の共有 | ヒートショックに対する知識を深め、家族全員で防止策を共有する。 |
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
【症状別】ヒートショックが起きたらどうするのか
ここからは「ヒートショックが起きたらどうするのか」気になる人に向け、症状別の対処法を解説します。
緊急事態に陥った際、焦らず対処できるよう、全体像を見ていきましょう。
意識がある軽度の場合
ヒートショックで、めまいや立ちくらみのように、意識がある軽度な症状の場合、以下の流れで対処していきましょう。
- ゆっくりとその場に座る
- 座るのがつらければ横になる
- 症状が治まるまで静かに過ごす
- 症状が落ち着いたら、ゆっくりした動作で立ち上がる(立ち上がるのが不安な場合は四つん這いで移動)
- 周囲に家族や介助者がいる場合は移動を手伝ってもらう。
- 移動後は快適な温度の部屋で安静にして様子を見る。
上記の流れで対処し、解決すれば病院に行くべき症状ではない可能性があります。
しかし、ヒートショックの症状が治らない場合、脳卒中のような症状を疑いましょう。
また、軽度のヒートショックであっても、定期的な血圧測定をもとに、異常が見られた場合は、すぐに専門医の指示を仰ぐのをおすすめします。
意識がない場合はすぐ病院に行くべき症状
ヒートショックが原因で意識がない場合は、脳や心臓に重大な影響が及んでいる可能性があり、早急な医療介入が必要です。
意識を失うほどのヒートショックは、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。
とくに高齢者や持病を持つ人は、血圧の急激な変動によって脳や心臓に負担がかかりやすいため、より一層注意が必要です。
意識を失った場合、周囲の人はすぐに救急車を呼び、患者を安全な体勢に移し、呼吸や脈拍を確認しながら医療スタッフの到着を待つのが重要です。
また、可能であれば患者の体を温かく保ち、転倒などによる二次的な怪我を防ぐため、周りを片付けるのもおすすめします。
関連記事:救急車で運ばれた後に家族ができることは?利用できる制度やサービスも解説
病院に行くべき事態を防ぐ環境を整えよう!【まとめ】

ヒートショックは、寒暖差が原因で体に大きな負担をかける現象で、とくに高齢者や持病を持つ人にとっては命にかかわる可能性があります。
症状が軽くても油断せず、めまいや立ちくらみをしたり、倒れてしまったりした場合は病院に行くべき症状が隠れているリスクも挙げられます。
早めの対応が深刻な健康被害を防げるため、入浴前に部屋を暖めたり急激な温度変化を避けたりしてリスクを減らしていきましょう。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。