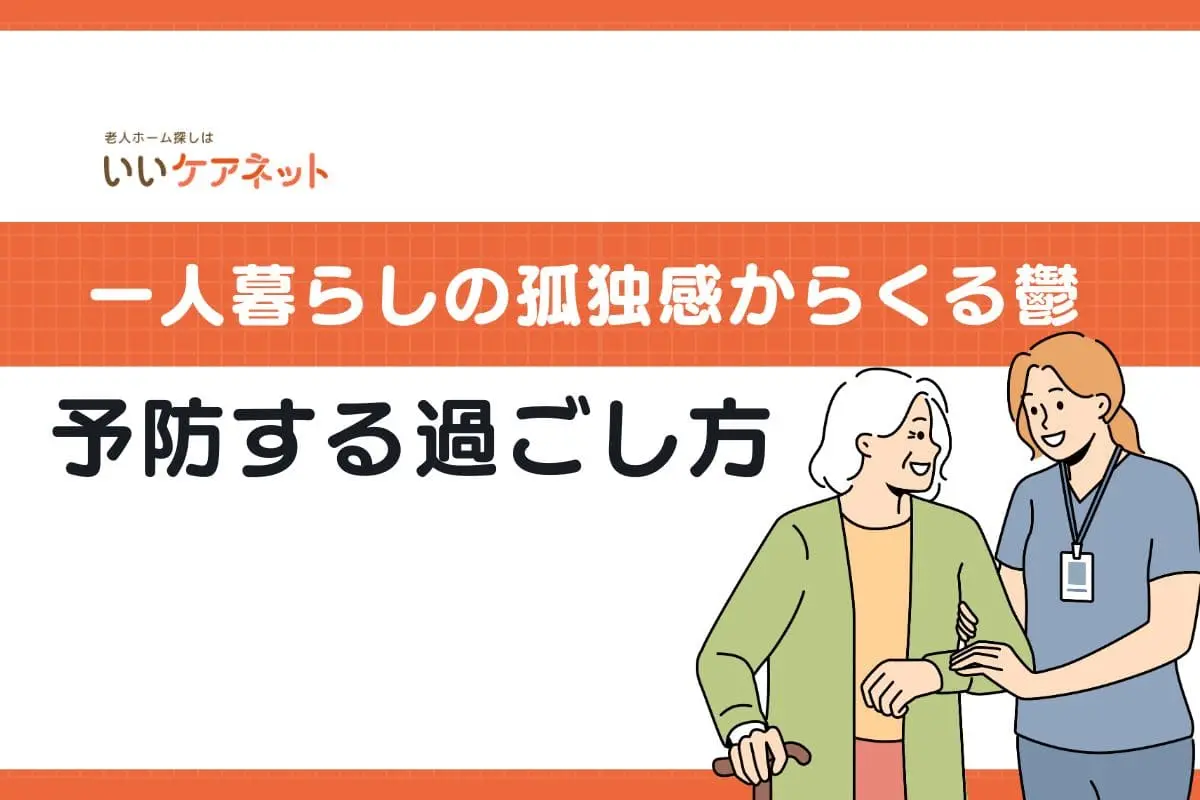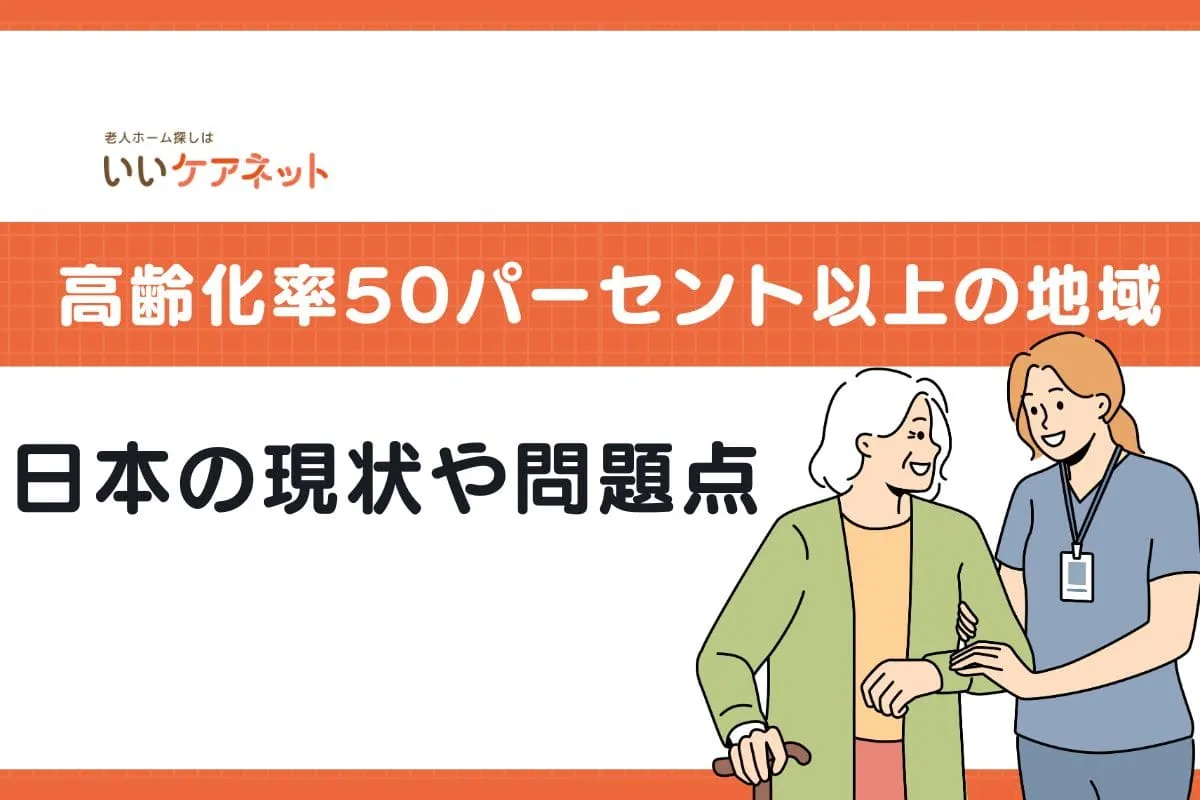ホスピスの利用を検討する際、費用がいくらかかるのかは最も気になる点の一つです。ホスピスの料金は、病院に入院するのか、介護施設に入居するのかといったケアを受ける場所によって大きく異なり、その平均的な相場や内訳も変わります。
終末期を穏やかに過ごすためのホスピスケアですが、安心して利用するためには、費用の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。この記事では、ホスピスにかかる費用の内訳や、場所による料金の違い、利用できる公的制度について具体的に解説します。
ホスピスの費用はどこでケアを受けるかによって変わる

ホスピスケアにかかる費用は、ケアを受ける場所によって大きく異なります。日本国内では主に、病院に設置された「緩和ケア病棟」、ホスピスケアに対応した「介護施設」、そして住み慣れた自宅でケアを受ける「在宅ホスピス」の3つの選択肢があります。
費用体系はそれぞれ異なり、例えば東京や横浜、京都などの都市部では施設の選択肢が豊富な一方、立地によって家賃などの費用が高くなる傾向が見られます。どの場所でケアを受けるかによって、費用負担だけでなく受けられるサービス内容も変わるため、本人の希望や状態に合わせて慎重に選ぶ必要があります。
病院の緩和ケア病棟に入院する場合の費用内訳

病院の緩和ケア病棟に入院する場合、費用は医療保険が適用される部分と、全額自己負担となる部分で構成されます。入院費の総額はこれらの合計金額となり、内訳を理解することで、月々どの程度の支払いが必要になるか予測できます。保険適用の費用は高額療養費制度の対象となるため、所得に応じた上限額を超えた分は払い戻されます。
一方で、差額ベッド代や日用品費などは保険適用外となるため、事前にどのくらいの金額がかかるか確認しておくことが大切です。
医療保険が適用される入院基本料
緩和ケア病棟の入院基本料は、厚生労働省によって定められた定額制となっており、公的な医療保険が適用されます。そのため、窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じた自己負担割合(1〜3割)分となります。例えば、75歳以上の後期高齢者医療制度の対象者で1割負担の場合、1日あたりの自己負担額は数千円程度に収まる計算です。
この入院基本料には、検査や投薬、処置などの費用が包括されています。ただし、一部の高度な治療や手術などを行った場合は別途費用が発生することもあります。高額療養費制度を利用すれば、1ヶ月の医療費負担には上限が設けられるため、実際の支払額は所得区分に応じた限度額までとなります。
決められた金額を負担する食費
緩和ケア病棟に入院中にかかる食費は、医療費とは別で自己負担となり、公的医療保険の適用対象外です。この食費は標準負担額として国が定めた金額を支払うことになっており、原則として1食あたり460円(2024年時点)となっています。
ただし、住民税非課税世帯や指定難病患者など、所得や特定の条件によっては負担額が軽減される措置があります。例えば、住民税非課税世帯の場合、過去12ヶ月の入院日数に応じて1食あたり210円や160円に減額されます。食事は治療の一環でもあり、患者の状態に合わせた食事が提供されますが、その費用は定められた金額を支払う必要があります。
個室などを希望した場合にかかる差額ベッド代
緩和ケア病棟で個室や少人数の部屋を希望した場合、差額ベッド代(室料差額)が発生します。この費用は公的医療保険の適用外であり、全額が自己負担です。
差額ベッド代は病院によって設定金額が大きく異なり、1日あたり数千円から数万円と幅があります。プライバシーが確保され、家族が気兼ねなく付き添いできるといったメリットがある一方で、入院期間が長くなるほど負担は大きくなります。
差額ベッド代のかかる部屋への入室は患者側の同意が前提ですが、治療上の必要性から個室管理となる場合など、状況によっては費用が発生しないケースもあります。有料の個室を利用する際には、設備や広さとともに費用を事前に確認することが重要です。
おむつ代や雑費などの自己負担費用
入院基本料や食費、差額ベッド代以外にも、日常生活に関わる様々な費用が自己負担として発生します。その代表的なものがおむつ代で、これも医療保険の適用外です。その他、衣類やタオルのレンタル代、クリーニング代、テレビカードの購入費、電話代、新聞や雑誌の購読料といった雑費も実費で支払う必要があります。
これらの費用は個人の生活スタイルによって変動しますが、月々数千円から数万円程度かかることも珍しくありません。病院によっては、入院生活に必要な日用品をセットにした「アメニティセット」を有料で提供している場合もあります。何が自己負担になるのか、入院前に病院の窓口やパンフレットで確認しておきましょう。
介護施設でホスピスケアを受ける場合の費用内訳

近年、終末期ケアを提供する有料老人ホームなどの介護施設が増えています。病院とは異なり、「住まい」としての性格が強いため、費用体系も大きく異なります。介護施設(ホーム)でホスピスケアを受ける場合、主に「入居一時金」などの初期費用と、「月額利用料」がかかります。
月額利用料には家賃や管理費、食費が含まれ、これに加えて介護保険サービスの自己負担分や医療費、その他の実費が上乗せされるのが一般的です。病院の入院費とは異なり、居住に関わる費用が大きな割合を占めるのが特徴です。
入居時に必要な初期費用(入居一時金)
有料老人ホームなどの介護施設に入居する際には、初期費用として「入居一時金」が必要になる場合があります。この費用は、その施設を利用する権利を取得するためのもので、金額は施設によって大きく異なり、0円から数千万円以上と非常に高い設定のところまで様々です。一般的に、入居一時金は想定される居住期間に応じて月々の家賃の一部を前払いする性格を持ちます。
そのため、一定期間内に退去した場合には、未償却分が返還される仕組み(初期償却・償却期間)が設けられています。契約前には、入居一時金の意味合いや償却のルール、返還金の計算方法などを十分に確認し、納得した上で契約することが不可欠です。
月々支払う家賃や管理費
介護施設でホスピスケアを受ける場合、毎月の費用として家賃や管理費が発生します。これは月額利用料の主要な部分を占め、施設の立地、居室の広さや設備、共用施設の充実度などによって金額が変わります。家賃は文字通り居室の賃料であり、管理費は共用部分の維持管理費、水道光熱費、事務スタッフの人件費などに充てられる費用です。
これらの居住関連費用は全額自己負担となり、介護保険の適用はありません。一般的に、入居一時金が0円の施設は月額の家賃が高めに設定されている傾向があります。月々の支払い能力を考慮し、無理のない料金プランの施設を選ぶことが重要です。
施設で提供される食事の費用
介護施設における月額利用料には、1日3食の食事費用も含まれています。この食費は施設ごとに独自に設定されており、月額で4万円から6万円程度が一般的な相場です。
多くの施設では、管理栄養士が監修した栄養バランスの取れたメニューが提供されるのはもちろんのこと、入居者一人ひとりの健康状態や嚥下能力に合わせて、刻み食やミキサー食、塩分制限食といった個別対応も行っています。
ただし、特別な食事形態への対応に追加料金が発生する場合もあるため、事前に確認が必要です。また、外泊などで施設での食事を長期間取らない場合の返金規定についても、入居契約時に確認しておくとよいでしょう。
介護サービス利用料の自己負担分
介護施設で受ける介護サービスには、介護保険が適用されます。介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の場合、要介護度に応じて定められた月々の定額費用を支払います。この費用は「包括型」と呼ばれ、所得に応じた自己負担割合(1〜3割)を支払う仕組みです。
一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、外部の訪問介護やデイサービスなど、利用した分の介護サービス費用を支払う「出来高払い」が基本となります。どちらの形式が適しているかは、必要な介護の量や種類によって異なります。医療的ケアが必要な場合は、看護師の配置状況や提携医療機関のサポート体制も費用と合わせて確認すべき点です。
日用品や理美容代などその他の実費
月額利用料に含まれない費用として、日常生活で必要となる様々な実費があります。例えば、おむつや口腔ケア用品、個人の嗜好品、衣類などの購入費用は自己負担となります。また、施設内で提供される理美容サービス、レクリエーションの材料費、買い物代行といったオプションサービスを利用した場合にも、別途料金が発生します。
これらの費用は個人の希望や必要性に応じて変動するため、月々の支出にはある程度の余裕を見ておくことが大切です。入居を検討する際には、パンフレットに記載されている料金だけでなく、どのような追加費用がかかる可能性があるか、口コミを参考にしたり、施設に直接問い合わせたりして具体的に確認しておくと安心です。
ホスピスの費用負担を軽くする公的制度

ホスピスの利用には継続的な費用がかかりますが、その経済的負担を軽減するための公的な制度がいくつかあります。特に、医療保険が適用される費用については、自己負担額を抑える仕組みが整っています。
代表的なものとして、月の医療費の支払いが上限額を超えた場合に還付される「高額療養費制度」や、年間の医療費負担を確定申告で軽減できる「医療費控除」があります。これらの制度を正しく理解し、適切に活用することで、安心してホスピスケアを受けるための経済的な基盤を整えることにつながります。
高額療養費制度で医療費の自己負担を抑える
高額療養費制度は、1ヶ月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。緩和ケア病棟への入院にかかる医療保険適用の費用は、この制度の対象となります。
事前に加入している公的医療保険(健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示すれば、支払いを自己負担限度額までに抑えることが可能です。
これにより、一時的に高額な医療費を立て替える必要がなくなります。食費や差額ベッド代などは対象外ですが、医療費の負担を大きく軽減できる重要な制度です。
確定申告で活用できる医療費控除
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が一定額を超える場合に、確定申告をすることで所得税や住民税の負担が軽減される制度です。本人だけでなく、生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。
緩和ケア病棟の入院費や治療費、医師の処方に基づく薬代などが対象となります。おむつ代も、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば対象に含めることが可能です。
ただし、差額ベッド代や日用品費は原則として対象外です。医療費の領収書は必ず保管しておき、翌年の確定申告期間中に手続きを行うことで、税金の還付を受けられます。
生活保護受給者がホスピスを利用する場合
生活保護を受給している方も、ホスピスや緩和ケア病棟を利用できます。生活保護制度には、医療費の自己負担分を公費で賄う「医療扶助」と、介護サービス費の自己負担分を賄う「介護扶助」があります。
これにより、医療保険や介護保険が適用されるサービスについては、実質的に自己負担なしで利用することが可能です。つまり、入院基本料や介護サービス費は無料となります。
ただし、差額ベッド代や個人の日用品費、特別な食事など、扶助の対象とならない費用は自己負担となる場合があるため注意が必要です。ホスピスの利用を希望する場合は、まず担当のケースワーカーや病院のソーシャルワーカーに相談し、利用可能な施設や手続きについて確認することが大切です。
まとめ

ホスピスの費用は、ケアを受ける場所が病院か介護施設かによって、その内訳や価格が大きく異なります。病院の緩和ケア病棟では医療保険が中心となり、高額療養費制度の活用が負担軽減の鍵となります。
一方、介護施設では家賃や管理費といった居住費が費用の大部分を占め、介護保険サービス費が加わります。どちらの選択肢が適しているかは、本人の希望や必要な医療・介護の内容、そして経済的な状況によって変わってきます。後悔のない選択をするためには、候補となる施設から具体的な見積もりを取り、費用とサービス内容を十分に比較検討することが重要です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。